「ほら、あれだよ! あれ! 何つったかなぁ……ええい! ちくしょう、思い出せねえ」
カウンター席で右近龍二と酒造りの用語や道具の名前を挙げ連ねる火野銀平が、ド忘れしてしまった品物に頭を抱えている。
今夜のポンバル太郎は忙中閑ありで、龍二と銀平のほかには、そのやりとりをほくそ笑みつつ肴にしている平 仁兵衛と連れの白髪の男が冷酒を傾けているだけだった。
恰幅の良いその男を、平は銀平たちに紹介しなかったし、太郎も誰何しなかったが、龍二は老獪そうな男の顔に見覚えがあった。
大吟醸のグラスを舐めながら余裕を覗かせる龍二は銀平の喉まで出かかっている暖気樽(だきだる)を知っているのだが、したり顔をして教えない。その理由は、冷酒一杯を賭けたゲームなのである。
間違えたり、答えられない場合は、相手の好きな酒を奢るというルールだった。
「お前なぁ、人を選んでそのゲームをやれよ。お前が龍ちゃんに勝てるわけ、ねえだろ。それとも、もはや早期の認知症か?」
太郎は平たちが注文した鱧の落としを伊万里の平皿に丁寧に飾り盛りした後、ほっとした面持ちで銀平を冷やかした。
「う、うるせぇな。単なる、物忘れだよ! くそ、ダメだ、悔しいが一杯奢りだ!」
白旗を揚げた銀平は、勝った龍二の注文を聞こうともせず、記憶から消えている暖気樽を探そうとスマートフォンを取り出した。
すると、無言で連れの男と傍観していた平がグラスを飲み干し、おもむろに口を開いた。
「それだから、今の若い人たちは物忘れが多いんですよ。パソコンや携帯は便利だけど、頼りすぎは禁物です。我々の若い頃は、恩師や上司に『あれ、それ、と言ったら、何のことなのか、ピンとくるぐらい憶えてないとダメだ』とよく叱られたもんです。銀平さん、アナログな頭を失っちゃあ、いけませんよ」
おまけに“あれ”にもいろいろあって、どの“あれ”なのか即座に解らなければ出世できない時代だった。つまりITやネットワークなど存在せず、記憶力が良くて機転の効く奴が成功したんだと平はつけ足した。
「平先生、仕事ってのは教えてもらうんじゃなくて、盗んで憶えろって、確かに昔はよく言われました。おい銀平、魚匠なんてその典型だろうが?」
太郎が、スマートフォンにてこずっている銀平を皮肉った時、平の連れの男がつぶやいた。
「でもね、“あれ”とか“それ”じゃ、今の若い者には伝わりませんからなぁ。酒造りにも、職人ながらの隠語ちゅうのがありますが、それも今じゃめっきり減りました」
しかめっ面の銀平は男をしばらく凝視していたが、卒然として声を高めた。
「あっ! あんた、能登の有名な杜氏さんじゃないの?……ええっと名前は……ちくしょう! また、思い出せねぇや」
その言葉が終わらないうちに、隣席の龍二がゆっくりとした口調で訊ねた。
「矢口杜氏さん……ですよね?」
龍二の視線はその男と平だけでなく、厨房へも向けられた。太郎も男の正体を知っているはずだと、龍二の目は言っていた。
男は図星とばかりに破顔一笑すると、黙って見ていた太郎に足元の風呂敷包みを手渡してから、
「はい、そうです。でも、元・杜氏だから、そこを間違えないでもらいたい」
と龍二へ、はにかんだ。
思わず、やはり本人だったと顔を見合わせる龍二と銀平の前に、太郎が平然とした顔である物を差し出した。
たった今、矢口の風呂敷から取り出した、奇妙な形をした二つの杉桶だった。
「何だ、この丸っこい桶と三角みたいな楕円形の桶は?」
銀平が首を捻ると、平はようやく矢口のことを紹介した。
「矢口杜氏は、私が卒業した能登の高校の先輩でしてね。昨年、杜氏引退と同時に全国で講演をしながら日本酒の普及に尽力されている。ポンバル太郎のことをお話したら、お店のデコレーションにと、それを頂いたのですよ」
龍二が柿渋の浸み込んだ古めかしいその桶に、手を伸ばした。
「キツネとタヌキだ」
目を輝かせる龍二に、矢口は嬉しげな笑みを口元に浮かべた。
「よく知ってますな……これも酒造りの“あれ”“それ”を解りやすくした、典型的な道具なんですよ」
江口は血色の良い顔で、語り続けた。二つの桶は発酵が終わった酒のモロミを搾り袋に入れるために使うのだが、見た目の形で蔵人はキツネやタヌキと呼んでいた。キツネは注ぎ口が尖っていて、酒袋に注ぎやすい。タヌキは竹筒の注ぎ口を付けた円筒形、これも用途は同じである。昔の蔵元が使う桶は工程によって数十種類あり、使い方も千差万別だったので、誰もが親しみある名前で呼んだと解説した。
「なるほどね。言われてみりゃそうだな。でも、名前が安直過ぎねえか?」
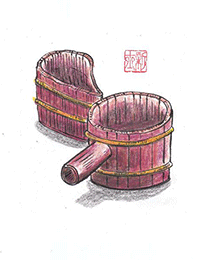
その銀平の批評に、龍二が反論した。
「安直だからこそ、酒造りがはかどったんじゃないでしょうか。キツネやタヌキなら、誰もが間違わないでしょう。さっき、銀平さんの答えられなかった暖気樽だって、“だき”って短く呼ぶのが、蔵人の常識です」
銀平と龍二のやり取りが、静かなポンバル太郎の店内に続いた。そのようすを厨房から見つめる太郎に、矢口が問わず語った。
「いい酒を造るためには、蔵人の誰もが解り合えること。高度な技術や複雑な理論に走るよりも、現場では阿吽の呼吸を共有できることが大事。それを日々積み重ねることで、誰にでも杜氏になるチャンスはあるんです。でもね、杜氏と蔵人ってのは、技を盗み合う敵同士でもありますから……いい意味で、キツネとタヌキの化かし合いですな」
その声も耳に入らないのか、酔い始めた銀平と龍二が、またもや蔵元ゲームに戻っていった。
今夜の二人の顔は、キツネとタヌキのように愛嬌があると太郎は思った。
