クリスマスソングが、渋谷のスクランブル交差点に流れている。忘年会シーズンと合わさって、夜のハチ公前では酔っ払いがはしゃいでいた。
ポンバル太郎も連日、予約客で満席になり、猫の手も借りたい状況に冬休みが始まった剣が動き回っている。酒が注文されるたび冷蔵ケースへ行ったり来たりする剣に、テーブル席の女性客は感心しきりだった。
カウンターの真ん中に座る平 仁兵衛も、見るたびに大きくなっている剣の背丈に赤い頬をゆるめている。
「おい、剣。あんまり張り切り過ぎると、一升瓶を落っことしちまうぜ」
平の隣の火野銀平が、両手で瓶の首を持つ剣をたしなめた。余計なお世話とばかり剣が身をひるがえした時、右手の一升瓶がスッポ抜けた。
「あっ! いけねえ!」
床に落ちる寸前、カウンター脇の男がしゃがんで、間一髪、瓶を抱きかかえた。素早い身のこなしに、客席からどよめきと拍手が巻き起こった。
白髪混じりの六十歳ぐらいの容姿に反して、動きは敏捷だった。
冷や汗をかいた剣が男に詫びると、太郎もカウンター越しに
「助かりました。ありがとうございます」
と頭を下げた。
「ああ……どうも」
生返事する男は、一升瓶のレッテルに見入っている。「碇(いかり)」の銘柄と、船の碇のロゴが描かれていた。
ふいに、剣の背中へ右近龍二の声が聞こえた。来たばかりらしく、玄関の鳴子は歓声に消されている。
「ご年配なのに、スゴイですね。何か、スポーツをやってらしたんですか?」
「いやいや、肉体労働をずっとやってたから。貨物船の船員でね。荷物の積み下ろし専門でした……まあ、それも今年で引退しましたがね」
男は我に返ると、はにかみながら答えた。それでも、酒の瓶を手放さない。
酒瓶を受け取ろうとする剣に、男は目尻の皺をほころばせて「この碇、一杯もらうよ」と注文した。函館港の近くにある蔵元の純米酒だった。
「へえ、船乗りかぁ。カッコイイじゃねえすか。港々に女あり、なんてね。俺は憧れちまうなぁ」
男の気取らない雰囲気が気に入った銀平は、酔った口で話しかけた。
剣が注ぐグラスの酒を見つめながら、男は言った。
「女よりも、俺は酒でしたよ。港々に、地酒ありでした。この酒も、その一つでね。偶然、私の苗字と同じ銘なんですよ」
平と龍二が、思わず目を丸めた。
「てことは、碇さんですか。珍しいお名前ですねぇ」
「しかも、船乗りにはピッタリだ!」
男が頷くと、平は名乗り、龍二と銀平もそれに続いた。
「函館の他にも、いろんな港に行ったんでしょ?」
剣が、興味ありげに碇へ訊ねた。生まれてこの方、数回しか船に乗ってない剣にとって、碇は異色の人物に思えた。
「そうだね。函館、酒田、新潟、舞鶴、長崎……50くらいの港を、毎年回ってね。鋼材とか燃料とか、あらゆる物を運んだよ。疲れた体を癒すのは、その土地の日本酒だった」
碇の話しに、いつしかテーブル席の女性たちも耳を傾けていた。
それぞれの港町には古めかしい酒場があり、情にもろい亭主や芯の強い女将がいて、常連客の多くは人見知りをした。
だから、よそ者の碇を受け入れるのに時間がかかった。
店主は話しかけてくれても、常連客の目は疑っていた。座席も彼らに遠慮をして、カウンターの一番端っこから始めなければいけない。もしかしたら、その椅子も誰かの定席かも知れない。だから新顔の頃は、落ち着いて飲めない。それでも半年ごとに寄港して顔を出し、5年もすると、一人また一人と口をきいてくれるようになった。
土地の訛りが分かりにくくても、難しい顔をしてはいけない。言葉の意味が分からなくても、とにかく笑顔を返すこと。そうする内に信用され、常連客に認められたら、ひと安心。いったん入り込めば家族のような仲になると、碇は懐かしげに酒瓶のレッテルを撫でた。
言いにくそうな顔の龍二が、口を開いた。
「僕も出張で、いろんな町の居酒屋へ行きます。碇さんと同じような、よそ者扱いを最近受けました。常連さんに声をかけてもらえるための秘訣って、なんですか?」
碇は一瞬ためらったが、隣りに置いた鞄から青い帽子を取り出して答えた。
「まずは、土地の酒を飲んで、褒めることじゃないかな。そうすると、いつかはこんな間柄になれる」
貨物船の名前が入った、色褪せた船員帽だった。そこに縫い込まれている碇のマークは、驚いたことに酒瓶のレッテルにあるロゴマークとソックリだった。
「えっ!? どうして、同じなの?」
二つの碇のマークを見比べる剣の頭に、碇が帽子を被せてほほ笑んだ。孫を見るような、柔和なまなざしだった。
「30年前に俺のことを、この蔵元が気に入ってくれてね。函館の港にある赤提灯の居酒屋に、蔵元の社長がいつも来ていた。根っからの函館人で、よそ者を嫌っていたよ。だけど、半年ごとに必ずやって来る俺が、その蔵元の酒を飲んで褒めると、社長は船乗りにピッタリの酒を造ってやると約束した。そして、レッテルに俺の苗字と帽子のマークを使ってくれたんだよ」
碇の話しに、店内の客たちは物珍しげに背伸びして、剣の手にする酒瓶を覗き込んだ。
今どき耳にしない船乗りの体験談に、太郎も包丁を止めていた。
「その酒は、最近になってレトロなレッテルと碇マークが珍しいのか、人気が出てきました。もちろん、味わいも上々。ドッシリとしたコクのある、男っぽい純米酒ですよ」
太郎が褒めると、あちこちから同じ酒をくれと注文が飛んで来た。碇がおもはゆい顔で客席に会釈をすると、銀平が羨んだ。
「いいねぇ。全国各地に自慢の酒と家族みてえな酒場があるなんて、碇さんは故郷をあちこちに持ってんだなぁ」
龍二と剣が、何度も相槌を打った。だが、碇は表情を曇らせて、長いため息を吐いた。
「そうじゃない。俺には、故郷なんてないさ。40年も海の上で暮らした風来坊だからね。でも、いざ陸に上がると船の上が恋しくなるもんだね。これからは、年金生活だ。もう遠くの港町には、行けなくなっちまったな」
しんみりとしたカウンターの空気が、店内にも広がった。碇の胸中を斟酌する銀平や龍二も言葉が出なかった。
すると、剣が冷蔵ケースから、次々と一升瓶を取り出し、碇の前に並べ始めた。
「おいおい、どうしようってんだよ?」
不審げな顔の銀平の横で、平はニンマリとして頷いている。
剣が胸を張って、答えた。
「どれも、港町に近い蔵元の酒だよ。だからさ、碇さんが全国に行けなくたって、馴染みだった地酒をここで飲んでもらえば、いいじゃんか!」
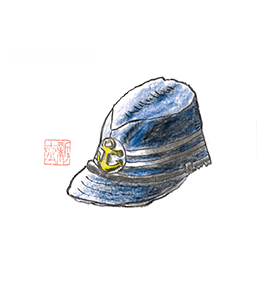
「なるほど! 簡単だよね。さすが、剣君。僕、単純なことを見落としてたよ」
感心する龍二が剣に親指を立てると、銀平も手を打った。
「ちげえねぇ! じゃあ、港町めぐりの酒旅をやっちゃいますかぁ」
カウンターへズラリと並んだ地酒のレッテルに、店内の客たちもスマホを手にして群がった。
平が碇の隣へ座り、つぶやいた。
「第二の人生、このポンバル太郎を故郷にしてはいかがですかねぇ。人見知りのないこの店なら、すぐに常連組になれますよ」
紅潮する碇の頭に、剣が帽子を戻して敬礼した。
「それじゃあ碇船長、出航しまぁす!」
カウンター席を見つめる太郎は、どこからか汽笛の聞こえる気がした。
