ドロリとぬかるんだ茶色い塊が、白磁の小皿を覆うように山盛りされている。
それを箸先で突っつきながら、ひと口舐めては、盃を傾けている二人の男がカウンター席で顔をほころばせていた。
テーブル席の客たちは、怪しげなその肴が気になるのか、首を伸ばしながら覗いていた。二人の男とは平と中之島で、愛知県の普通酒の一升瓶を前にしている。
「う~む、シンプル イズ ベスト。昔の尾張の人は、これをツマミに粗酌を楽しんでいたわけだ。ノスタルジーですねぇ」
陶然とした表情を浮かべる平に、大阪人の中之島がせわしなく何度も頷いた。
「そうでんな! この醤(ひしお)っちゅうのは、日本人の食のルーツでっせ。いまだにわしらが味噌をアテに飲めるちゅうのも、醤を食ってた頃から始まってる習慣やな。ところで太郎ちゃん、これ、どこで手に入れたんや?」
唇の端に残った醤をもったいなさそうに指先でぬぐう中之島へ、太郎がほくそ笑んで答えた。
「ある人の土産です。誰だか、当ててみてください。うちの常連さんですけど、先月、愛知県へ旅した時に八丁味噌の蔵元も訪れて、そこで手に入れた希少な大豆の穀醤(こくびしお)です」
大豆の醤は、いわゆる醤油の元になるモロミと同じで、古くは弘法大師が中国から持ち帰った発酵調味料と伝わっている。これが弘法大師の開いた和歌山県の高野山周辺で始まり、そこから愛知県や千葉県の銚子、香川県の小豆島など全国の醤油文化へ広まったと、太郎はその人物から聞いたことを付け加えた。
「なるほど、おもしろい……その話しを語るとなると、取材に行ったあすかちゃんか。この醤に愛知の酒を奨めるのも、彼女がこだわる地産地消でしょう?」
辛口派の平が気に入るだけあって、酒の裏ラベルには+7と日本酒度が表示してあった。それは、渋い辛さとコクのある大豆の醤に不思議なほどマッチした。
「いえ……あすかじゃないです」
太郎の答えに、中之島が小首を傾げる平の肩を叩きながら、声を高めた。
「ほんなら、龍ちゃんやで。あいつは、休日にあちこちの蔵元めぐりをしてるさかいな。名古屋の酒蔵に行ったついでに、味噌蔵も回ったんやろ」
しかし、太郎はしたり顔で首を横に振り、
「残念ながら、龍ちゃんでもありません。意外ですよ、これを持って来た奴は。ほら、呼ぶよりそしれだ。来た、来た!」
と薄暮の空を窓越しに覗かせている玄関扉へ、視線を向けた。
銀縁メガネで店内をうかがうようにノッソリと入って来たのは、トレーダーの菱田だった。その手には、小さな瓶を入れたビニール袋を提げている。
「……へぇ~、ほんまかいな? 意外どころか、大穴やがな。アメリカかぶれの菱田君が、何でまた、醤なんちゅう古典的な日本の調味料に興味を持ったんや?」
中之島が訝しげな顔で太郎に訊くと、平も傾けていた盃を止めて「まったくです」と相槌を打った。
太郎はその問いを読んでいたかのように、菱田に目で合図した。
菱田はいささか自信ありげな面持ちで中之島と平に近づくと、カウンターの上に瓶を置いた。
「いえいえ! 中之島の師匠、醤は今や海外でも日本酒に合う創作的な料理に応用されてるんです。特にイタリアンのシェフには人気で、それには理由があります。ちょっと、これを試してみませんか」
菱田が、赤褐色の液体が入った瓶を手にした。
その風変わりなラベルの文字は中之島に読めなかったが、かつて美術教師だった平は
「イタリア語でコラトゥーラ・ディ・アリーチ……つまりは、アンチョビを濾過した液か。これまた、おもしろそうですな。いやぁ、ワクワクしてきた」
と鼻の穴をヒクヒクさせ、ほろ酔いの髭面が赤くなった。
それに気を良くしたのか、菱田は自慢げに瓶の栓を開けた。
「カタクチイワシで仕込んだ、イタリアの醤なんです。日本にも秋田県の“しょっつる”や能登の“いしる”って魚醤があって、これと似ていますから、きっと日本酒にも合うはずです」
シチリア近海で捕れたイワシを塩漬けにして熟成させ、自然に染み出してきた液体を濾過して仕込む。醤油のような感覚でいろいろな地元料理の味付けに使われ、パスタや魚介料理に相性抜群と、菱田は太郎が用意した小皿にその液体を注いだ。
とたんに鼻腔を突くような発酵臭が立ち上がると、「むぅ」と平はつぶやき「おおう!」と中之島が目をみはった。
太郎はそれを味見すると、即座に冷蔵ケースの奥から一升瓶を取り出した。
「これには、やっぱり能登の辛口でしょ」
すると、しびれを切らしながら見つめていたテーブル席の客たちが、
「すみません! 俺たちにも、是非、それをもらえませんか!」
と舌なめずりをした。
ポンバル太郎の客のほとんどが、小皿を啜って魚醤を舐めた。
そして、異口同音に「日本酒に合う~!」と絶賛した瞬間、扉を開けっぱなして立っている龍二の姿が太郎の目に入った。
「この匂い、ひょっとして!?」
龍二は脇目も振らずにカウンターへ歩み寄ると、大豆の醤と魚醤を凝視した。
「奇遇ですね、いい所へ来ちゃいました。僕が持って来たこいつも、味を比べてみませんか。本当は、太郎さんの料理に使えるかと思ったんですが……」
鞄の中から出てきたのは、黄色がかった液体を入れたペットボトルだった。龍二はそれを全員の小皿に注いで回った。
「うむ。これ、私の好物の野沢菜の匂いだ」
と平は目をつむりながら、嗅覚を研ぎ澄ませていた。
「平先生、正解です。これも醤の一つ、菜醤(なびしお)です。どっちかと言えば、大豆の醤と同じく、そもそもは農村や山国の調味料。魚が獲れない土地では、野菜を塩漬けにして発酵させて、その汁を調味料に使った。つまり、漬物の残り汁って具合です」
むろん、太郎が選んだ三番目の酒は長野県の純米酒だった。スッキリとしながらも大らかな旨味が、口中で淡白な塩味の菜醤を包み込んだ。
三種類の醤に客たちは感嘆を洩らすと、口々に自分たちの出身地の醤油や漬物の話しを思い出したかのように始めた。そして機会があればお国自慢の品を入手するから、一度、ポンバル太郎のツマミに使ってもらいたいと言う者までいた。
「日本の食の美味しさは、ある意味、三つの醤に育てられたのかも知れんなぁ」
中之島が目を細めると、太郎が冷酒グラスに酒を注ぎながら答えた。
「山国の人たちは、濃厚な穀醤で川や沼で獲った魚の生臭さを消したのでしょう。だから、その地酒も濃厚で辛い物が多い。海の国は塩が豊富だから、まろやかな魚醤が造れた。それで食べる新鮮な海の魚や干物には、淡麗な地酒が合う……そんな昔ながらのDNAを、今も僕たちはそれぞれの中に受け継いでるんでしょうね」
太郎の言葉に、平が心地よさげに頷いた。
「私の若い頃は“醤油臭い日本人”なんて外国で卑下されましたが、今頃ブームになるとは……菱田さん、あなたツイッターやフェイスブックやってるんでしょ。だったらハンドルネームを“ソイソースマン(醤油男)”とかにして、今夜のことや醤の話しを海外に発信してみたらいかがですか」
「へっ? 先生、SNSをやってんですか?」
いきなり平の口から飛び出したネットワーク用語に、菱田だけでなく、太郎も呆気に取られた。
「そりゃあ、私の焼き物にだってファンがいますから、SNSをやるに越したことはないでしょ。ボケ防止にも、なりますしね」
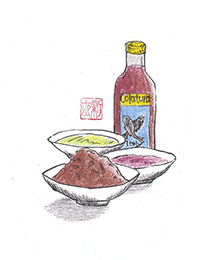
平は笑いながら、ジーンズの尻ポケットからスマートフォンを取り出した。
すると、旧タイプの携帯電話を手にしてうろたえる中之島が真顔で言った。
「お、おっし! わしも負けてられへんわ。菱田君、そのSNSちゅうもんのやり方を教えてくれるか。ちなみに、“S”は醤油の頭文字か? SNS……“醤油なんでも相談”ってことかいな?」
その大ボケに、酔いの回ってきた店内の客たちが吹き出した。
「師匠って、穀醤みたいですねぇ。それって、天然の関西モンですよ」
龍二のツッコミに、どことなく生真面目な雰囲気だった今夜のポンバル太郎で爆笑が巻き起こった。
