卯の花くたしどころか、連日のうなぎのぼりの暑さに辟易とする男たちが、居酒屋の店先に積んだピー箱卓で生ビールに喉を鳴らしている。
それを一瞥しながら涼しい顔でポンバル太郎へ向かう久留米絣の女性に、汗を拭いてすれちがう男たちは二度三度と振り返った。
女のえりあしから漂うかすかな白檀の香りにも、彼らは束の間のやすらぎを憶えた。
剃り上げた頭にタオルを巻いたままやって来た火野銀平も、目に入った汗をぬぐいながら、女のきなり色に朱色を浮かせた蚊絣の上品さに見惚れた。
「あっ、あれ? 真知子さんじゃないすか?」
「あら、火野屋さん。暑いわねぇ、この格好、私もう限界だわ。やせ我慢が折れちゃいそう」
銀平が目を凝らすと、ほほ笑む真知子の鼻梁には小さな汗粒が浮いていた。その上に並ぶ切れ長の瞳に銀平は塩を吹いている自分の黒いTシャツを見つめられ、はにかみながら胸元をはたいた。
「へへっ、これから塩分補給と水分補給! ポンバル太郎で、しこたま食って飲みますよ」
「私も久しぶりに、太郎さんの顔を覗きに来たの。じゃあ、このお土産、銀平さんにもごちそうしちゃおう」
うす紫の風呂敷包みを手にする真知子がポンバル太郎の扉を開けると、満席で騒がしい店内が、一瞬、水を打ったように静まった。テーブル席もカウンター席も、客たちの酒を持つ手が止まり、その視線は和装の真知子に釘付けになった。
真知子を見つけた剣はいっこうに料理が来ないとぼやく客へ気もそぞろに詫びると、満面の笑みに変わった。剣は真知子に会うたび、亡き母のハルコが使っていたハンドクリームの匂いを思い出すのだった。
そんな剣の表情を真知子が受け止めた途端
「おいっ、何をチンタラやってんだ。早くしろ! こんなガキを手伝いに使いやがって、客をなめてんのか!」
とテーブル席から太い声が飛んで来た。
真知子に向いていた視線が、いっせいに声の主に集まった。いかにも難癖をつけそうな、横柄な態度の太った男がテーブル席に腰かけていた。
強面の男にまわりの若い客たちは口をつぐみ、気圧された剣もビビッてしまっている。
「やれやれ、しばらくこの手のお客さんはいなかったんだけど、あっちこっち料理が遅れてちゃ、謝るしか手はねえな」
真知子のこめかみに筋が浮くのを察した銀平は、そうつぶやいて男の席へ歩み寄ると深くお辞儀した。
「お客さん、すみませんね。今日のところは、俺に免じて許してもらえませんか。今から俺が手伝うから。こう見えても築地で魚屋やってっから、手は早えすよ」
へりくだる銀平を、顔なじみの客たちが驚いた表情で見つめた。不穏な空気の中、斜に構えて座る男は、あぐら鼻の先で銀平の言葉を嘲った。
「それじゃあよ、三分だけ待ってやるから、うまいツマミを出せよ。その間、あんたは詫びついでに酌をしてくれねえか。こいつの連れなんだろ?」
増長する男は真知子に向かって、隣の席へ座れとばかりに鬚の濃い二重顎をふった。
「おう、ちょっと待ちなよ。この人は関係ねえんだ! それによ! もう五分ぐらい、待てねえのかよ」
「あれ、今さっき俺に頭下げたのは、どこのどいつだっけな?」
男が臆面もなく嫌がらせを始めると、業を煮やした銀平の顔色が火照ってきた。そのようすに、厨房でようやく料理を仕上げた太郎が店内へ向かおうとした時、真知子が男の前の席へ静かに腰を下ろした。背筋の伸びた凛とした姿勢に、どこからか、ため息が聞こえた。
「おっ、物分かりがいいねえ。じゃあ、酌を頼むわ。できるだけ色っぽく、しなを作ってな」
鼻息を荒げる銀平を、太郎は後ろ手にしてつかんでいた。そして、動揺する剣を諭すような視線を投げながら、真知子のようすを見守った。
真知子は男のお銚子には手を出さず、風呂敷包みを開くや、太郎に背を向けたまま言った。
「太郎さん、てん突きと包丁をちょうだいな!」
「な、何だってぇ? てん突きだぁ? ふざけんじゃねえぞ、この野郎」
男が罵声を浴びせるやいなや、真知子も店の空気を震わせるほどの啖呵を切った。
「ふざけてなんか、いないさ。私は今夜、ここの主人に日本一のところてんを持って来たんだよ。大阪の高槻って町に、たった一軒だけ今もそれを作っている農家があるんだ。あんた、知らないだろうから教えてあげるよ。ところてんの素の寒天は海のテングサで作るんだけど、実は、山間部の農家にとっては、冬をしのぐ大切な出稼ぎ仕事だったんだよ」
高槻は淀川水運に近く、朝晩の寒暖差がある場所で、市場の京都や伏見、大坂の中間点だったことなど好条件が揃っていたため、寒天造りが栄えたと真知子は続けた。
太郎は中之島 哲男からその話を聴いた記憶を思い出しながらも、真知子の度胸の良さに感心した。
真知子が開いた風呂敷の中から、大きなタッパーが現れた。
蓋を開けると普通のところてんの三倍近くもありそうな塊りだった。真知子は太郎から受け取った菜切り包丁でそれを素早く切り分けると、てん突きに入れ、軽快な音を立てて押し出した。
「はいよっ! つきだし、お待ちどう!」
あっけにとられている男の前へ太郎が酢醤油を置いてやりながら、笑いを噛み殺して言った。
「なるほど、これぞ、本当の“つきだし”だな。その昔、江戸の町の居酒屋は気の短けえ大工とかが多くってな。あんたみたいに辛抱ができねえ客のために、ところてんをツマミに出したんだ。だから、今でも先付けのツマミを“つきだし”って呼ぶんだよ。さて、じゃあそれを食ったら、御代はいらねえからとっとと帰ってくれ」
「おい、俺は客だぞ! 出るとこへ、出てもいいんだぜ!」
しかし、あれほど凄んでいた男の声音が下がっている。それは、徐々に周囲の客たちを真知子と太郎の呼吸が引き寄せ、男への恐怖感が薄れ、帰れコールを始めたためだった。
「どうぞ、ご勝手に。というか、早く出てった方がいいんじゃないかしら。このお店、おまわりさんも常連さんだしねぇ」
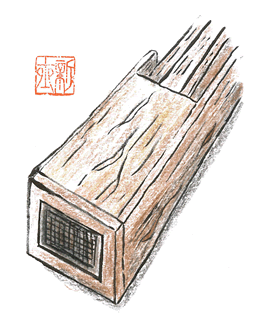
真知子が聞こえよがしに、声をそびやかした途端、
「くそっ、二度と来てやるか!」
と男は捨て台詞をして出て行った。
玄関の鳴子の木枡が鳴り響くと、客たちが勝鬨を上げるかのように、いっせいに拍手した。
泣きそうになるのを堪えていた剣がどっと息を吐き出した時、銀平が玄関に塩を撒きながら叫んだ。
「ただいまの決まり手は、突き出し、突き出して真知子の勝ち~!」
行司を気取る銀平のしぐさに、ポンバル太郎の店内に笑い声と歓声があふれた。
真知子も酌を始めるようすに、太郎は剣の両肩へ手を置いて言った。
「なあ、剣……日本一単純な魚屋の旦那や、日本一気風のいい居酒屋の女将が仲間にいて、俺は、日本一の幸せ者だ」
