通りの水たまりに、小さな波紋が広がっては消えていた。
音もない小ぬか雨の中を、傘も差さずに松村が歩いて来る。いつもの軽やかな足取りとちがい、立ち止まっては横っ腹を押さえ、しかめっ面を見せていた。
マチコの玄関前に立った松村は一瞬ためらうように肩で息をすると「ま、いいや」と一人ごちて、格子戸を引いた。
「こんばんは……」
力ない松村の声に、真知子は、いったい誰が来たのかというような顔を厨房から覗かせた。
「何だ、和也君か。あら、どうしたの? 何だか、つらそうね?」
いきなり返された真知子の言葉に松村はほっと顔を和ませ、「分かる? どうもここんとこ、胃の調子が悪くってさぁ」とカウンター席にくずおれた。
「そのようすじゃ、さっさと帰った方がよさげじゃない。あんた最近、飲みすぎてない? 顔色も茶色いし、肝臓が弱ってるんじゃないの?」
「えっ、お、脅かさないでよ。でも、そんなに茶色い~?」
じっとこちらを見つめる真知子に、松村はどぎまぎとしながら両手で頬を確かめるように触った。
「ねえ、樋口さん。どう思う?」
真知子が、カウンター席の奥に向かって声をかけた。
「えっ? 誰かいるの?」
松村が真知子の視線をたどると、そこにグレーの制服姿の男が座っていた。
歳は松村と同じぐらいか、少し上の三十代半ばといったところだった。
腹の痛みに気持ちがいってたことと、あまりにも男が静かだったため、松村は彼の存在に気づいていなかった。
「そうだね。たぶん、胃のもたれからくる消耗性疾患だと思うけど、でも肝機能も弱っているかも。あの……よかったら、これを飲んでみて下さい」
樋口は、越中薬仙堂と書かれた手提げ袋から、白い小箱を取り出した。
「うちの会社が江戸時代から作っている、肝心丹という薬です。手前味噌ですけど、よく効くと評判なんですよ」
「えっ! 薬屋さんなの?」
松村の表情が、どこか安心したようにほころんだ。
「樋口さんね、置き薬の会社の営業マンなの。昔、私がOLをしてた会社で同期だったんだけど、3年前にそこを辞めて郷里の富山に帰ったの。それで、置き薬の会社に入ってさ。私のところにも手紙が届いて、それじゃあってことでお薬を頼んでるわけ。今日は東京泊まりだから、一杯飲んでってもらってるの」
真知子が紹介すると、樋口は少し赤らんだ顔で松村に会釈した。
「へえ~、置き薬かぁ。僕、滋賀県の彦根で生まれ育ったんだけど、子どもの頃、毎月一度は富山の薬売りのおじさんが来ててね。家には赤い厚紙で作った大きな薬箱があって、中にいろんな種類の薬が入ってた。おじさんは、うちの家族が使った分だけを勘定して、減った薬を足して帰ってくんだけど、いつも富山の飴をくれてさあ。おじさんがやって来ると、ばあちゃんやじいちゃんと茶飲み話が始まって、気がついたらみんなの具合が、それだけで良くなってた。僕もその飴をなめてると、いつの間にか気分が良くなってさ」
松村は樋口の横に移ると、何の変哲もない白い箱に書かれた肝心丹の字を指でなぞった。
「そうですか。その飴、おじさんが持って来てくれたのには、理由があるんですよ。富山の飴は、苦い薬を飲みやすくするため、昔から練り合わせるのに使われてたんです。だから、薬り売りと飴は縁が深いんですよ」
「そうなの! それって、日本人の智恵だね~。何だかこの肝心丹って、すっごく効きそう」
樋口との会話に、松村の顔はしだいにゆるんでいた。
「和也君って、樋口さんと話した途端、お腹が痛いの消えちゃってない?」
と真知子が訊くと、「あれ、本当だ! 不思議だねぇ」と松村は目をしばたたかせた。
「私も、最初にそうなったの。ねえ、樋口さん。そんなことをいつも言われない? 何か秘訣でもあるの?」
「あはは、みんな薬売りの前では素直になるからストレスが消えちゃうんだよ。医院に行けば、誰だって自分の健康状態は包み隠さずしゃべるだろ。置き薬売りと話しをする時は、それと同じなんですよ。それに自分の家まで来てくれるから、緊張もしないしリラックスできる。でもって、あれこれ世間話もしてる内に、気持ちが楽になる。だから“病は気から”って言うの」
「そうか! 僕もマチコが家みたいなもんだから、治っちゃったんだね~。じゃ、さっそく飲ませてもらいますよ」
松村は、真知子がカウンターに置いた水で肝心丹を喉に流し込んだ。
そのようすをおだやかな笑みで見つめる樋口に、真知子は訊ねた。
「置き薬屋さんって、素敵な仕事ね。でも、IT派だった樋口さんがまさかと思ったわ」
「……技術主義に走るほど、大事なものを失くしている気がしたんだ。例えば、この帳面。懸場帳と言うんだけど、これにはお客様の住所、名前、置いてる薬の種類と数、毎月の訪問日、前回までの薬の使用量などを書いてある。懸場帳はただお客様との取り引きに使うのでなく、体の状態やかかりやすい病気の傾向などを記録し、健康作りのアドバイスをしてあげるものなんだ。ノートパソコンとエクセルファイルが今の時代だろうけど、うちの社員はみんなこれ。手肌の温もりと心を込めて書き留めることで、その人を思う気持ちが1冊の帳面の中に生き続ける。そんな気持ちが、お客様に伝わっているのかも」
樋口が開いた分厚い帳面は、ぎっしりと手書きの文字や表で埋まっていた。
「これ、す、すげえや!」と、松村が帳面を手に取ろうとした。すると帳面の間から、一輪の押し花がカウンターへこぼれ落ちた。
「まあ、可愛い。れんげの押し花ね」
真知子がその花を手にすると、樋口はさも大事そうに受け取って、ノートの中へ綴じ直した。
「……多摩に住んでる小学生の女の子から、この春にもらってね。両親とも事故で亡くしてる子でさ。俺が薬を置いている祖父母と、一緒に暮らしてんだ。その子、待ってるんだよ、いつも俺のことを。3年間、これで良かったのか悩んでた。あの会社を辞めて、東京を離れて良かったのか、ずっとわだかまってた。でも、これが俺の欲しかった答えだったんだ」
ひと息ついた樋口が盃を飲み干すと、松村がさりげなく徳利を傾けた。
「そういう大切な心……僕も、つい忘れそうになっちゃうんですよ」
「でも、ここに来れば大丈夫だよね。真知子の料理とうまい酒、それに彼女の優しさは、何よりもの薬だろうから」
樋口の言葉に、真知子が「あら、お世辞も昔より上手になったのね」とはにかんだ。
その時、格子戸がガラリと開いて、見慣れた津田の髭面が現われた。
しかし、いつもの「毎度、こんばんは!」の声は聞こえず、うつむきかげんで入って来た。
「ふうっ……真っちゃん、すまんが、お白湯を一杯くれへんか? おおっ、和也君、元気か。わしゃ、ちょっと腹を冷やしてなあ」
津田は背広の内ポケットをまさぐりながら、カウンターの端っこに座った。
「あらあら! またも、病人のご登場なのね?」
真知子が温い湯を出すと、「ちゅうと? 和也君もかいな?」と津田は苦しそうな顔で訊いた。
「ええ、さっきまでね。けど、これで治りました~」
自慢げに松村が肝心丹の箱を手にしたのと、津田が懐から白い箱を出したのは同時だった。
「えっ!?」「おっ!?」と二人の声が交差すると、真知子の声がそれに続いた。
「どっちも越中薬仙堂! これまた、奇遇よねえ」
驚く真知子に樋口を紹介された津田は、気を良くして、痛みを忘れたようにしゃべり始めた。
「おっほん! 越中薬仙堂はんにとって、わしは上得意先や。ここの妙薬を使うて、人生60年。そもそも富山の薬売りは、富山の飴とともに栄えてな」
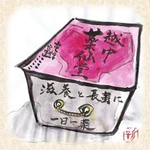 「うへっ! それはもう聞いたから、いいっすよ」
「うへっ! それはもう聞いたから、いいっすよ」
浪曲士のような津田の声に、思わず松村は耳をふさいだ。
「あほう! 何べんも“聞く”方が、薬だけによう“効く”ねん!」
「う~む……これは、ちょっと寒いかな~」
今度は、真知子がつぶやいた。
「はい! 寒い時には温灸湯って、いい薬がございます」
薬袋からタイミング良く赤い小箱を取り出した樋口に、4人の笑いが巻き起こった。
