ヒグラシの賑やかな声が、公園の林を揺さぶっていた。
それに追い立てられるように、真知子は玄関を開けると「ふう~!やれやれね」と大きく息をついた。
4日ぶりの店内には、ムッとした空気と醤油の匂いが満ちている。
松村からは「遅くなるかも知れないけど、Uターンで東京に戻ったら、その足で家族を連れてマチコに行くから」と留守電が入っていた。
一刻も早く窓を開けたい真知子は、両手に提げていた紙袋を、思わず手荒に床へ置いた。すると、「ようこそ、宮崎へ!」の言葉と人気者の宮崎県知事の顔イラストを描いた袋から、2つ、3つと、緑色のイチジクが転がった。
いびつな形で、独特の臭いが強かった。
イチジクは、その時店内を覗うように入って来た宮部の足元で止まった。
「お帰りなさい、真知子さん。宮崎のお盆は、どうでした?久しぶりに、お父さんに甘えて来た?」
額の汗を拭った宮部は、イチジクを珍しそうに拾い上げ、日焼けた顔で笑った。その後ろでは、宮部と同じ社服を汗だくにした青年が、冷酒ケースをおぼつかない手つきで抱えている。
配達係らしいが見かけない顔で、「あら?新人さん?」と真知子はおしぼりを手渡しながら、宮部に訊いた。
「アルバイトの子でね。今年は盆明け早々、ビールと冷酒の注文が集中しちゃって」
勝手の分かっていない新人バイトに付き合って、昼から外回りをしている宮部の背中も、大きな汗のシミを作っている。
「田尾君、そこの冷蔵ケースに酒を入れるんだ」
宮部に指図される垢抜けしない容貌の青年は、ちらとイチジクを一瞥して、「あっ、はい」と生返事した。
宮部が真知子に出された麦茶を口にしつつ、田舎話に聴き入っている間、田尾は、冷酒をケースに並べてはポリポリと口元を掻いていた。その所作があまりに遅いので、宮部が怪訝な顔で覗き込もうとした時、真知子の声がした。
「田尾君って、イチジクをよく食べたでしょ?」
「えっ……ええ」
戸惑いを見せる田尾の右手が、また口元を掻いた。
「ふ~ん……私は、イチジクを食べたことないんだけど。どうして分かるの、真知子さん?」
カウンターの笊に盛られたイチジクをつつきながら、宮部が訊いた。
裂けかけた実から甘酸っぱい香りがして、玄関からの夕風がそれを漂わせた。
「田尾君が口元を掻くしぐさは、たぶん癖ね。イチジクを食べると、痒くなるの。でも、食べてもないのに反応しちゃってるのは、条件反射みたいなものね」
ほほ笑む真知子に、田尾は唖然としてつぶやいた。
「おふくろが亡くなって、もう十年だけど、イチジク食ってなかったです。でも、無意識に癖が出ちゃいました。お盆やお彼岸になると、おふくろがイチジクをよく食べてました。俺も、やたらと食わされました……今さっき、その顔が、ふっとよぎっちゃって……そしたら、痒みが起こってきて。不思議なんですよ」
はにかみながら、田尾は口元を掻いた。
「ほんなら、君のお母はんも、そうやって親指で掻くのが癖やったやろ?」
ふいに玄関から聞こえた声に、三人ともが振り向いた。
津田が、汗を浮かせた顔をパナマ帽であおいでいた。
「はっ!……そ、そうです」
驚く田尾の横に、津田はそのまま腰を下ろした。そして、真知子の差し出すおしぼりを左手で受け取りながら、右手でイチジクをつまんだ。
「ほんでも、真っちゃん。このイチジクは、まだ若いがな。ちょっと酸っぱいんちゃうか?」
冷えたおしぼりで髭まわりを拭いた津田は、ほっと息をついて、イチジクの匂いをかいだ。
「私の母は、実家の庭にイチジクが実ってくると、ちょっとだけ早くもいでたの。酸っぱくて、少し堅いぐらいが、夏バテした体にいいって。だから、私は今でも、そんなイチジクが好き。これも、癖よね」
酸っぱさを思い出したのか、真知子のえくぼが、一瞬キュッと締まった。
「なるほどなぁ……ええ話や。今どきの子どもは、イチジクなんぞ食べんやろ。若いお母ちゃんは、皮を剥くこともでけへんやろうし」
津田の嘆きに、宮部が同調するように続けた。
「スーパーでも、見かけませんしね。都会の子どもは、ますますおふくろの味や故郷の味覚を、持たなくなっちゃうんですかねえ」
「そう考えれば……私も田尾君も、恵まれてるね。いつか、自分の子どもにも、教えてあげなきゃね」
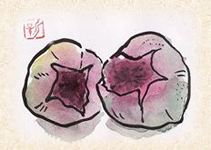 真知子のイチジクを剥く小さな音が、カウンターに漂った。
真知子のイチジクを剥く小さな音が、カウンターに漂った。
「あの、宮部さん……イチジク、一つもらっていいすか?」
田尾が、遠慮気味につぶやいた。
「ああ、一つと言わず、どっさり食えばいいさ」
宮部は真知子と顔を見合わせ、うれしげに笑った。
「ほれほれ、田尾君。君の指、ま~た口元を掻いてるでぇ」
津田の冷やかしに、田尾もうれしそうに答えた。
「じゃあ、将来、俺の子どもには、これを癖にさせます」
イチジクの甘酸っぱい香りの中に、4人の笑い声がしみていった。
