3日続きの雨が、“本日臨時休業”の貼り紙を濡らしている。
店内では、トン…トン…と単調な音が響いていた。
真知子の見上げる天井からは等間隔で雨しずくが落ち、バケツの底を叩いていた。
昭和40年代の木造建築とはいえ、雨漏りなど真知子には思いもよらなかったが、長雨に妙な胸騒ぎがして昼一番に店へ出てみれば、カウンターの隅は水浸しの状態だった。
どうにか応急処置を済ませ溜め息をつく真知子の横で、配達のついでに番茶をご馳走になっている宮部が、ふっと笑った。
「でも、何となくオツなもんだ。ガキの頃、長屋住まいだったから、ウチもよく雨漏りしてさ。こうやって目をつぶると、お袋が鍋やバケツなんか置いてたのを思い出すよ」
もうすぐ53歳を迎える宮部にしてみれば、雨漏りのリズムが懐かしくもあるようだった。
「そうかもしれないけど……修理屋さん、遅いわねえ」
真知子がそうこぼした途端、玄関の格子戸がガラリと開いた。
「こんにちは、佐野工務店です。雨漏りの修理は、こちらさんで?」
菜っ葉色の作業服を着た老齢の男が、名刺を濡らしながら立っていた。頭には、やけに白いものが目立った。
「待ってました。あそこなんですが、なるべく早く直してもらえませんか」
真知子は雨漏りを指しつつそう言ったものの、佐野と名乗る男に少なからず不安を感じていた。
修理するためには天井裏を調べ、屋根瓦の点検もしなければならないはずだが、真知子と宮部の目に、佐野はあまりにも頼りなげだった。
しかし、彼は雨漏りの箇所を凝視したかと思うと、やにわに捻りハチマキを絞めた。そして、無言のまま軽トラックから脚立を運び、天板を手際良く外すと、懐中電灯を手に、軽々とした身のこなしで天井裏へ入って行った。
目を丸くしている真知子に「まるで、忍者だな。ありゃあ、叩き上げでこの道50年ってな感じだね」と、宮部は嬉しそうに顎を撫でながら言った。
10分もすると、佐野は埃と蜘蛛の巣にまみれたまま、ストンッと降りて来た。
「屋根瓦がズレちまって、隙間から雨が漏れてますね。すぐに直せますよ。あれはカラスのせいでしょう。ご近所で、増えてませんか?」
真知子から渡されるおしぼりを、佐野は帽子を取りながら受け取った。
「あっ、そう言えば」と、真知子はポンと手を打った。
近頃、マチコの界隈では生ゴミを漁るカラスの群れに、町内会で対策を立てたばかりだった。
「へぇー、カラスって力持ちなのね」
真知子は、佐野の小さな体を見つめながら、感心した。
「群れになって、瓦の上を一気に動いたり、飛んだりすると、その力でズレちまうんですよ。古い家は、最近の建物とちがって、屋根瓦を固定してませんからね。それにカラスは知能が高いんです。ひょっとしたら、こいつら、わざとやってんじゃないかって思うこともあります」
佐野は汚れた頬をおしぼりで拭うと、目尻の皺を増やして笑った。
「それにしても、佐野さんは身軽で……見た目より、ずいぶんお若いですな」
宮部は、空になった湯飲みを手にしたまま訊いた。
「いえいえ、私なんぞ、これしかできないもんでね。実は最近、足が縺れるようになっちまって、年寄りの冷水って孫に言われてます。そろそろ潮時とは思うんですが、息子はもっぱら経営者になっちまって、現場に出ないので。それに、雨漏りなんて若い衆には修繕できませんし……。昔からのお馴染みさんに頼まれるので、つい長引いてね」
「でも、あんな短い時間で雨漏りの原因をつきとめるのは、簡単じゃないでしょう」
「……嬉しいですねえ。そんな風におっしゃって下さるのは。私は、子どもの頃から天井裏が大好きなんですよ。あそこに入るとね、今でもワクワクするんです」
そう答える佐野は、番茶を出す真知子にチョコンと頭を下げて、問わず語りを始めた。
戦前生まれの佐野は、今年62歳。小さい頃は、大工の棟梁だった父親の仕事場まで弁当を届け、真新しい木の香に包まれる屋根裏へ上がることが楽しみだった。
佐野の父は「大工が金儲けに走っちゃいけねえぞ」と、生涯職人であるように諭した。青年になった佐野は教えどおりに、大工と鳶の修行に明け暮れた。
しかし、昭和50年以後の新建築ブームによって、本格木造建築は減り、佐野の仕事もしだいに減っていった。跡を継いだ息子は新建材住宅を手がけ、現場に立つことも止めた。
それでも幸いなことに、20歳になる孫が佐野の意志を継いで、大工の修行を始めているのだった。
「今じゃ、簡単にできてしまう家ばかり。大工の魂なんて薄れちまいました。寂しいかぎりですよ。いいかげんな仕事が多くて、釘一本、柱組み一つをとっても情けないです。スタッカーでパンパン釘打って、組み立てたボード部屋を繋いで“はい!一丁上がり”。そんな家とは会話ができないんです。私が雨漏りを直せるのは、屋根裏に入れば、『こっちだよ、ここがおかしいよ』って、家が教えてくれるからなんですよ」
佐野は、最近の建売家の手抜き工事を見れば、若い職人の腕が落ちていことが分かると付け加えた。
宮部は佐野の思い出話しに頷きながら、二杯目の番茶を飲み干した。その時、柱時計が4時の鐘を打った。
「おっ、もう4時ですか。こりゃ、いけねえ。瓦を直さなきゃ」
ドッコイショと腰を上げかけた佐野を、真知子の両手がやんわりと押し止めた。
佐野が「へっ?」と一言発して振り返ると、真知子の横に地下足袋を履いた華奢な体躯の青年が立っていた。
「お孫さん、心配で見に来たんだって。佐野さん、雨に濡れるとそれこそ冷や水だから、屋根の上は彼に上がってもらいましょうよ」
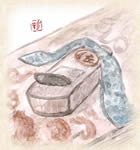 真知子がほほ笑むと、佐野は照れくさそうに頭を掻いた。そして「ほれっ!」とハチマキを解き、青年に渡した。
真知子がほほ笑むと、佐野は照れくさそうに頭を掻いた。そして「ほれっ!」とハチマキを解き、青年に渡した。
きりりとハチマキを絞めた佐野の孫は、真知子たちが見上げる中、脚立から屋根へ軽々と飛び移り、スルスルと登って行った。
「佐野さん、まだまだ若い人も捨てたもんじゃないですね」
真知子が、梅雨の晴れ間から覗いた太陽に手をかざしながら言った。
佐野の誇らしげな瞳に、ハチマキ姿の青年が生き生きと動いていた。
