春一番の訪れとともに、潮岬では桜が満開になったと渋谷の電光掲示板が知らせていた。
それでも三寒四温を繰り返す都内の夜は肌寒く、桜の蕾も足踏みするかのように縮こまっている。
ポンバル太郎のメニューには、早春を告げる瀬戸内のサワラやイカナゴといった関西の旬味も出始めていたが、カウンター席の火野銀平は不機嫌だった。
隣りの平 仁兵衛が純米酒を酌しても、舌打ちと鼻息はなかなか収まらない。
「まったく、ガキじゃあるまいし。いつまでも、ふてくされてんじゃねえぞ」
厨房から覗き見た太郎の声に、銀平はメニューの張り紙をにらみながら、ぬる燗の盃をあおった。
「いや、気に入らねえ! あれだけ約束しておきながら、よそに回しちまうなんてのは、築地に出入りする業者の面汚しだ」
毒づく銀平の視線の先には「静岡産桜海老」の品札が張られながらも、朱色の×印が付いていた。銀平の手配した桜海老だったが、納める当日になって、不漁を理由に火野屋へ断りが入った。
水揚げが極端に少ない上に、先約の魚屋がすべて買い占めたためだった。テーブル席の客から残念そうなため息がもれると、平が慰めるようにつぶやいた。
「まあまあ、お楽しみは後に取っておこうじゃありませんか」
「平先生、気が短けえ江戸っ子てのは、先物でなきゃダメなんでぇ!」
平自身、桜海老には目がないのを銀平は知っているだけに、また口惜しげに舌打ちをした。その時、カウンターの奥から荒っぽい声が聞こえた。
「てやんでぇ! 築地の者だからって、いつもかつも桜海老が手に入る保証はねえよ。桜海老漁は静岡の漁協が120隻に制限して獲ってんだ。それを均等に分けるから、どうしたって品薄な時もあらあ」
酔っているのか、声の主の中年男は頬がかなり赤らんでいる。ブルゾンの下の肩はたくましく盛り上がり、屈強そうな男を隣りの若い男が諌めた。
「信さん、よせよ。築地の人たちは、俺たちにとっちゃ、大事なお客さんじゃねえかよ」
「うるせぇ! 買う方が偉いって法は、俺には通用しねえ。こちとら男一匹、命がけで桜海老を獲ってんだ」
声高な男に店内の客たちがうんざりすると、太郎がようやくカウンターへ近寄った。
「お客さんは漁師みてえだが、ここは港じゃねえし、築地でもねえ。すまねえが、ほかのお客さんに迷惑はかけねえでくれ。銀平、おめえもいいかげんにしねえと帰ってもらうぜ」
太郎の声が、いつになくドスの効いた低音に変わった。
畏まる若者の横で男が鼻息を荒げると、平が仕込み水の瓶を手にして二人に近づいた。
「やわらぎ水です。あなた、ちょっと酔い過ぎてますねぇ……何か、やけっぱちな感じだ。この年寄りに、腹の中の物を吐き出してみませんか」
平が目尻に皺を刻むと、中年の男は気まずげにうつむいた。若い男が、代わりに応えた。
「すみません。俺たち、静岡から築地へお詫びに来たんです。俺は前川 誠。この人は磯田信吾で、俺の兄貴分の漁師です。確かに、そこのお客さんが言うように、桜海老の欠品を出して……謝りに来たんですが、あっちこっちでこき下ろされ、ヤケ酒になっちまって」
前川の言葉は先細って、消え入るようだった。それを平たちが耳にする間、磯田は目をつぶったまま右手で胸元を握っていた。苦しみを我慢するかのようなしぐさだった。
世間ずれしていない漁師だけに、真っ正直な気持ちが現れていると平は見て取った。
太郎が、おもむろに訊ねた。
「それだけが理由じゃあ、ないでしょう。磯田さん、あんた、何か辛いことを忘れたくてヤケ酒してませんか?」
前川が一瞬、体をビクつかせると、それに気づいた磯田が目を開いて言った。
「……だから、桜海老を築地の奴らに売るのが、嫌だってことよ」
「この野郎! 太郎さんが下手に出てるってのによ。てめえ、表に出やがれ!」
銀平が大声で啖呵を切った時、玄関から聞き慣れた声が飛んで来た。
「銀平さんのバ~カ! まったくもう、しばらく顔を見ないとロクなことがないわね。桜海老だって、そんな酔っ払いに食べられたかないわよ!」
張りつめた空気が、高野あすかのひと声でゆるむと、平が「いいタイミングですねぇ」とほほ笑んだ。だが、苦虫をつぶす銀平の向こうでは、磯田と前川が口をポカンと開けていた。
「そっちのお客さんも、新参者なら、もう少し遠慮したらいかが?」
腕ぐみしたまま顔をしかめる勝気なあすかに、磯田がつぶやいた。
「洋子だ……そっくりじゃねえか」
前川も、唖然とした表情で言った。
「うん、ビックリした。『桜海老だって、酔っ払いに食べられたくないわよ!』って、洋子さんの口癖だったじゃないか」
勘の働いた太郎が、胸に置いたままの磯田の右手を見つめながら訊いた。
「その手の中に握ってるのは、もしかして奥さんの写真ですか?」
銀平とあすかも、磯田の手元に目を細めた。はっとする磯田が前川と顔を見合わせると、太郎は言葉を続けた。
「いや、俺もカミさんを失くしてるんで、何となく、そんな気がしてね」
口ごもる磯田に、平がおだやかな表情で話しかけた。
「奥さんと、桜海老を一緒に獲ってらしたのでしょう。きっと、桜海老を大事に扱っておられたのでしょうねぇ。あなたのようすから、そう察しますよ」
開いた磯田の右手の中、銀色のチェーンの先に四角いペンダントが光っていた。磯田の日焼けた指がそれを開くと、小さな写真にあすかによく似たショートカットの女性がいた。
「あらっ! 本当に似てる! でも私より、ずっと美人ですよ」
それを覗き込むあすかに、磯田は本気で顔を赤くした。
「いいや、そんなことはねえ。もう10年前の写真だからよ、生きてれば45歳の年増女だ……だけど、女房と獲った桜海老が一番上等だったよ」
磯田は妻の洋子がいればこそ、桜海老の吟味を怠ることはなかったと言った。漁獲が制限されている中、大きさや形をそろえてトロ箱に詰めるのは面倒だが、洋子の叱咤激励があったから大ざっぱな自分でも、いい桜海老を出荷できた。そして漁が終ると、静岡の日本酒で洋子に酌をしてもらい、獲れたての桜海老を味わったと遠い目をして語った。
怒りの色を消して訥々と話す磯田の横で、前川も洋子の写真へ懐かしげに見入っていた。
しんみりとする店内に、あすかの声が響いた。
「じゃあ、私が一杯、お注ぎしましょうか。それでさ、次の桜海老は、必ず火野屋へ回してよね」
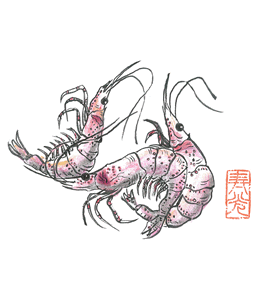
冷蔵ケースの中からあすかが静岡の純米酒を取り出すと、銀平がその瓶をつかんだ。
「おっと、そうはいかねえ。俺の許しがなきゃ、あすかに酌はさせらんねえな」
「何だよ、まだやろうってのかよ!」
またぞろ始めた銀平と磯田だったが、お互いの口元は笑っていた。
二人に一升瓶を傾けたあすかが、太郎におもねった。
「どっちにしても、私の胸が桜海老みたいに染まるのは、ちがう人なんだけどなぁ」
「へぇ、そいつぁ、誰なんだよ? 羨ましいじゃねえか」
太郎があすかに冷酒グラスを渡しながら訊くと、平がとぼけ顔でつぶやいた。
「ほっほっ、あすかちゃん。そろそろ、桜海老で鯛を釣っちゃいなさい!」
ほころんだ平の目尻が、太郎とあすかを見比べていた。
