桜の枝がすっかり新緑へ衣替えし、初夏の木漏れ日がアルファルトを暖めていた。外苑通りは、陽炎と人いきれにうつろっている。
ゴールデンウィークを間近にして、アベノミクス効果を謳う旅行業界は北陸新幹線ツアーのPRにかまびすしい。そのせいだろうか、ポンバル太郎の冷蔵ケースも、いつになく石川県の銘酒が肩を並べていた。
「ポンバル太郎でも、北陸キャンペーンをやってるの?」
目ざとく“加賀の菊酒”を見つけたテーブル席のグループ客が、太郎につっこんだ。
「先週末に二日間休みを取って、息子と金沢まで行ったんですよ。蔵元を回って酒も利いたもんで、いろいろ注文しました。それに、加賀野菜も手に入れましたよ」
太郎が目で指す杉壁に、“加賀蓮根まんじゅう”や“加賀太きゅうりのなます”といった献立が貼られていた。客たちは物欲しげに見上げたが、カウンター席に座る火野銀平は浮かない顔だった。
「太郎さん。平先生の具合はどうなんだよ? 春先の風邪っ引きかよ?」
「うむ……今日、精密検査らしいよ。とにかく、めまいが五日も続くってのは良くねえ」
太郎の答えを前のめりで聞く銀平のようすにも、平の体調の悪さが窺えた。
一週間姿を見せない平 仁兵衛の異変を知ったのは、常連客の菱田祥一からの電話だった。贈答用の酒器を注文していた菱田に、平から創作遅れの連絡が入ったのだ。
菱田から微熱とめまいが続いていると聞き、気になる太郎は平のアトリエを訪ねた。
妻に先立たれてからは「婚活でも、やってみますか」を口ぐせにする平だが、その日は冗談の一つも出なかった。曇り気味の表情に太郎が体調を訊くと、平は思いがけない答えを返した。
「太郎さん、お願いがあるのです。私の代わりに、金沢へ行ってもらえませんか。知人の息子さんのようすを調べて欲しいのです」
突然の依頼に続けて、平は問わず語りを始めた。狼狽する平を、太郎は初めて目の当たりにした。
かつて平が能登に暮らした少年時代、輪島塗の漆器職人だった父の元には金沢の料理人たちが足しげく通っていた。逸品の器を欲しがる板前の中に、藤王英夫という生意気な若い男がいた。藤王は、金沢市内の浅野川のほとりで割烹を始めたばかりだった。
彼は先輩料理人を差し置いて、平の父にうるさく注文をつけては値引きする始末。輪島の漆器職人の間では、鼻つまみ者と疎んじられた。
しかし、平の父は向こう意気の強い藤王を気に入った。自分が手作りする加賀野菜を土産に毎月やって来る藤王との関係は、爾来、三十年も続いた。
父親の跡を継がず美術教師となった平を、英夫はくさした。平は趣味で創っていた鉢や酒器をいくつか贈ったが、英夫は気に入らず、割って捨てたと皮肉られた。その後、能登から離れた平は藤王と疎遠になったが、父親は生涯にわたり漆器を創ってやった。
「そんな藤王さんが、八年前の能登地震で亡くなったのです。うちの実家へ、跡継ぎ息子の英太郎さんと車で向かっているさなかでした。崖崩れで車が埋まってしまい、息子さんだけ助かったのです。英夫さんは、助け出されてからひと月足らずで亡くなった……彼の命日が五日前でね、英夫さんが夢枕に立ったんですよ。それが、気になっちゃってね」
藤王は粗野な兄貴分だが、野卑ではなかったと平は語った。彼の息子と面識はないが、亡き父から
「腕は良いが、英夫に似て癇癖が災いする性格だ。まだ若僧だから、辛抱がきかないと先行きは不安だな」
と聞かされていた。
「恥ずかしながら英夫さんの事、忘れかけていたのです。でも、虫の知らせのようで……菱田さんの作品も手が付きません。太郎さん、後生だからお願いします」
両手を合わせる平に、むろん太郎の二の句はなかった。せっかくなら加賀の蔵元めぐりもと連れ出した剣は、北陸新幹線の興奮の余韻をいまだ引きずっている。
「で、どうだったんでぇ、その息子ってのは?」
銀平が太郎に答えをせかすと、加賀蓮根まんじゅうを待っているテーブル席の客が手持ち無沙汰な顔を向けた。太郎が気まずげに愛想笑いを返した時、銀平の後ろから声がした。
「銀平さんに似て、せっかちな人だったよ。食材にこだわるところも、同じだったけどね」
店を手伝おうと半被に着替えた剣が、土汚れた加賀蓮根を手にして立っていた。
「この蓮根は、英太郎さんから送ってもらったんだ。あの人、平先生のことを知ってたよ。英夫さんから、いつも聞かされてたんだって」
剣は厨房へ入る太郎へ蓮根をわたすと、銀平へ語り始めた。テーブル席の客たちも、加賀の菊酒を飲みながら剣に耳を傾けた。
震災後のいまわの際に、英夫は英太郎へつぶやいた。割烹・藤王の加賀料理は、これからは平 仁兵衛の陶器に盛りつけろ。そうすることが平一家への恩返しであり、加賀野菜に似合う器だと英太郎に語り、静かに逝った。だが、若い英太郎の目に、平の陶器はごく平凡な焼き物としか映らなかった。
「だけど九年経って、平先生の皿や鉢が見てみたくなったって。お父さんから受け継いだ畑で野菜を育てるうちに、優しい風合いの素朴な器こそ加賀野菜にふさわしいと分かったんだって。実は、平先生の若い頃の作品を、英夫さんは押入れにいくつか持ってた。それを偶然、英太郎さんが発見したんだ。僕と父ちゃんが、金沢へ行く一週間前だって……驚いたよ。きっと英夫さん、それを伝えたくて、平先生の夢に現れたんじゃないかな」
剣の話しが終りかけると、玄関の鳴子が小さな音を立てた。弱々しく杖をつく平の目元が、嬉しそうにほころんでいた。
「せ、先生! 無理しちゃ、いけねえよ」
「いや、加賀の菊酒と野菜の滋味を口にすれば、治ってしまいますよ」
銀平が平の肩を支えてカウンター席に座らせると、剣は加賀の菊酒を冷蔵ケースから取り出しグラスに注いだ。
「じゃあ今日は、百薬の長ってことで一杯だけですよ」
剣が笑顔で前置きすると、太郎はカウンターに小鉢を置いた。
「それと、こいつだ。お待たせしてるテーブル席のお客さんにも、サービスでお出ししろ」
加賀太きゅうりのなますが、鮮やかな彩りを映していた。小鉢の肌は、何の変哲もない土色の素焼きだった。
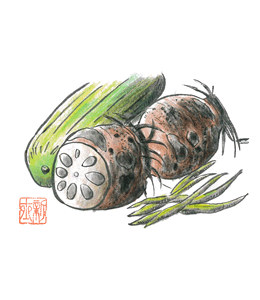
途端に、平が瞠目して言った。
「おっ、おお! これは、私が十九の時に創った小鉢です。まちがいない……どうして、ここに?」
「英太郎さんが、先生に加賀野菜を食べてもらうなら、それを使ってくれって。亡くなった英夫さんが、大事に隠してたらしいです。若かった平先生にもらった時、壊してなんかいなかったんです」
太郎が答えながら、カウンターの下から数枚の皿も取り出した。すべて、平が英夫に贈った作品だった。
平の目が潤んで、なますの上にしずくが一つ落ちた。その気持ちをいたわろうと、銀平と剣が口を開きかけた時、テーブル席からしみるような声が聞こえた。
「あの……私の蓮根饅頭、できれば、その皿で頂けませんか?」
平が客に振り返ってほほ笑むと、銀平が言った。
「平先生。藤王さん、きっと今、隣りにいるんじゃねえすか」
加賀蓮根を切る太郎の包丁の音が、相槌を打った。
