初夏の暖流に乗った黒マグロの大群が房総沖で獲れ、築地市場がにわかに活気づいているとニュースが報じていた。そのせいか、火野銀平はここ数日、ポンバル太郎へ顔を見せていない。
連日、赤身と中トロの入ったトロ箱が店へ届くのだが、納品伝票と一緒に「すまねえ、今日も忙しくって、行けそうにねえ」と走り書きした詫びのメモが付いていた。
杉板の壁に貼ったおすすめメニューには、赤身のタルタルステーキ、竜田揚げ、ヅケ丼など、特製のマグロ料理が書かれ、客たちに大好評である。
ただ、カウンターの隅に座る独酌の男は見向きもしなかった。くたびれたスーツ姿の男の後ろにはトランクが置かれ、出張で上京しているようだった。
銀平のメモを目にしたカウンター席の高野あすかが、隣りの中之島哲男へ回しながら訊ねた。手元には、土佐の純米酒と中トロの刺身が並んでいる。
「銀平さんには悪いけど、お蔭でしばらくはマグロが安く食べれそう。でも、マグロって、最近、養殖できるようになったらしいですね。大阪の大学が研究開発したんでしょ?」
「ああ、だいぶ長い間かけて試行錯誤しとった。最近は、養殖マグロの専門店もやってるで。けど、どないやろうな。餌の味によって、青魚の旨味は変わるからな。わしは、まだ食べてない」
実際、瀬戸内海のハマチや鯛の養殖物は、ひと口食べれば見分けがつくと中之島は答えた。特に、カツオ節のだしよりも昆布だしを大事にする関西の薄味では、養殖物の匂いがすぐに判るのだと答えた。
「ふ~ん、それは、どうしてなの?」
「関東の味つけは、カツオ節の一番だし、二番だしをぎょうさん使うのが基本や。カツオは青魚やから、その風味が養殖物の匂いを抑えてくれる。それに、東京の醤油も濃いよってなぁ」
常々、都内の立ち食い蕎麦やうどんのダシが大の苦手と顔をしかめる中之島は、醤油も銚子産ではなく、兵庫県の龍野醤油がお気に入りである。
「まあ、それが前々から話してる、心土不二(しんどふじ)ちゅうこっちゃ。けど、クロマグロは絶滅危惧種になったし、いずれ、わしの店でも養殖マグロを使わんならんやろ」
あすかに注がれた辛口純米酒を飲み干した中之島は、長いため息を吐いた。
カウンターの隅から、それと重なるため息が聞こえた。お銚子の手を止めたあすかは、独酌の男を見つめている。
「養殖魚に一番いいのは、あごだしですよ。トビウオもマグロと同じ青魚。安い下魚だけど、あごだしの旨味とコクは、匂いやクセを包んでしまいます。それに、この島根の酒にあごだしの料理はピッタリですよ……なのに、都会の料理店じゃ受け入れてくれない」
男の率直な物言いが、田舎育ちを感じさせた。冷酒グラスをあおった男は益田と名乗り、松江市で細々と海産物を扱う商店をやっているとあすかに言った。都内のデパートへ催事でやって来たが、予想に反して、主婦たちはあごだしを受け入れてくれなかったと腐した。
「どうして、あごだしはダメなんですか?」
益田は、テーブル席へヅケ丼を出している太郎へ食ってかかるように訊いた。テーブルの若い客たちが、ぶっきらぼうな益田に飽きれ顔を覗かせた。
益田の一本気な語気を背中で感じ取った太郎は、ちょっと待てと言うふうに人差し指を立て、冷蔵ケースへ向かった。
中之島が、肩に力の入った益田をたしなめた。
「ダメやないねん。ただ、あの匂いの強さは、家庭料理の味も変えてまう。あごだしをもっぱら使うのんは、山陰料理の専門店ぐらいやろ」
「はあ、それは分かってるんです。でも、専門店との縁やルートもありません。関西じゃ、あごだしは難しいし、東京で何とか活路を見出さないと。……地元の島根じゃ、少子高齢化のせいで需要が減って、廃業する料理店も増えてます」
益田の嘆きに取材記者のあすかも同感らしく、小さく頷いた。テーブルの客たちも、曇った顔で黙り込んでいる。
「益田さん、この酒を飲んでみなよ」
冷蔵ケースから太郎が取り出したのは、青森の純米酒と山形の本醸造だった。
「え、いや、私は山陰の日本酒でいいです。これが一番、口に合ってますから」
「まあ、いいから、試してみなって」
訝しげな益田に太郎が二つの酒を冷酒グラスへ注いでやると、テーブル席の客たちも気になるのか前のめりになった。酒を味わった途端、益田の目が見開かれた。
「こ、これは、旨さも香りも島根の酒によく似ています。あごだしに合いそうだ。東北と山陰じゃ、まったくちがうと思っていたのに……どうしてですか?」
「それは、俺よりも詳しい、東北育ちの記者さんに教えてもらおうか」
太郎が、うずうずしているあすかに答えを譲った。あすかの生まれ育った相馬地方も、あごだしに慣れているからだった
「私の故郷の相馬は、お正月の御雑煮もあごだしなの。あごだしって、山陰地方だけじゃなくて、青森、秋田、山形、新潟、能登とか、江戸時代には日本海側の各地で使われてた。北前船で上方へ運ばれた北海道の昆布は高級品だから、日本海側の人たちには手が出なかったの。だから今も、日本海側じゃ、あご料理やあごだしのラーメンが定番なの。益田さん、東京よりもそっちに新しいルートを作るって発想はどう。もちろん地元業者はあるけど、益田さんのあごだしが美味しければ、きっと大丈夫よ」
嬉々として語るあすかに、中之島が何度も満足げに頷いた。テーブル席の客たちは感心しきりだが、益田は自分の無知を責めるかのように、何度も酒の味を確かめていた。
「そうか。甘味が強くてコクのある地酒は、あごだしの風味と合うんだ。はっ! そ、それなら九州の酒も……」
益田がつぶやいた時、玄関の鳴子が賑やかに鳴った。
「あごを使う九州の店なら、あたしゃ、よう知っとると!」
銀座のクラブへ向かう途中の、手越マリだった。ふと、マリの故郷である熊本や博多も、あごだしが定番だと太郎は気づいた。しかも麦味噌や醤油は甘くて、あごだしに合う。
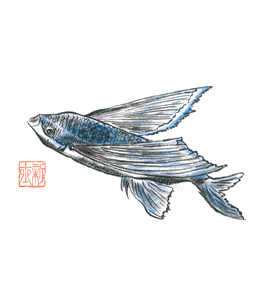
同じ考えの中之島が、益田の隣席へ移りながらマリに手招きをした。
「またまた、打ってつけの人が来よった。益田はん、これで全国制覇やで! まずは、あんさんの自慢のあご節、ここへ出しなはれ。お客さんの中には、あごだし育ちの人がいてるかも知れん。きっと、助っ人になってくれまっせ」
頬を紅潮させる益田がトランクから茶色いあご節を取り出すと、香ばしくて磯っぽい香りが漂った。
「あっ、懐かしい。これ、ぜったい上物のあごだしの匂いね。私、血がさわいじゃう」
思わずあご節を鼻先へつけるあすかを目にして、マリが負けじと頭からかぶりついた。
中之島が、あんぐりとして言った。
「あらら、色気より食い気やがな。こりゃ、大阪の食い倒れも降参やがな」
笑い声に満ちる店内に、あご節の濃厚な香りが満ちていた。
