隅田川の大花火を皮切りに、江戸川区や江東区の花火大会が夏の夜空を彩っていた。
屋形船やスカイツリーからの見物客もあいまって、都内のホテルは軒並み満室。ここ数日、高野あすかやジョージは、取材に駆け回っているらしく、ポンバル太郎に姿を見せていない。
外国人観光客へのクールジャパンPRも兼ねて、あちこちの花火見物の会場には、江戸の風情を偲ばせる立ち食い寿司や屋台蕎麦などかつての大川花火のオモテナシが登場し、そのせいで築地の火野屋は多忙を極めていた。
「太郎さん、すまねえ。お役所の仕事も、いいかげんなもんだぜ。蓋を開けてみりゃ、当初の話しの三倍も注文があってよ。仕入先にゃ無理言わなきゃなんねえし、マグロなんてどこも品薄になっちまってよ」
ポンバル太郎を訪れている花火の帰り客を横目に、カウンター席の火野銀平が愚痴った。だが、目元は口と裏腹に嬉しげである。ちょっとばかり遅れたボーナスになったのだろう。
しかし、ポンバル太郎には本マグロが五日も入っていない。太郎の柳刃は、代替えに仕入れた「ソマ」と呼ばれるソウダカツオを切っている。
「まあ、お江戸の文化を盛り上げるためなら我慢するぜ。けどよ、本マグロどころか、キハダも水揚げが減ってるらしいじゃねえか。先行き、このソマに取って変わられるんじゃねえか?」
ぶ厚く切ったソマの身は、クロマグロと見まがうほど赤い。
「じょ、冗談じゃねえ! 太郎さん、江戸前のマグロはクロかキハダじゃなきゃいけねえよ」
歯がゆげに銀平が吐き出した時、隣に座る右近龍二が純米吟醸にソマをつまみながら答えた。
「でも、ソマは意外にいけますよ。それにマグロって、江戸時代は高級魚じゃなかったんです。昔は“シビ”って呼ばれて、死日を思わせるから縁起が悪いとまで言われた。青魚で日持ちが悪く、赤身はすぐに黒ずんでしまったんですよ。それを醤油でズケにしたことから、にぎり寿司のネタになったわけです」
テーブル席の若い男たちも頷いていた。歳の頃は、二十代半ば。三人の男は揃えたような黒いスーツ姿で、表情はいささか暗かった。
銀平の鼻息がおさまると、玄関からしゃがれた声が聞こえた。
「なかなか、おもろい話をしてるやないか。やっさん、あんたを連れて来た甲斐があったなぁ」
久しぶりに現れた中之島哲男が、連れの大男の肩を叩いた。背丈は190㎝近くあろうか、赤銅色に焼けた顔の真ん中に鼻梁が黒光りしている。Tシャツの胸板は厚く、二の腕は丸太のようで銀平のふた回りも太かった。
「こちら、マグロ漁師の安本純平さんや。出身は和歌山の太地町やけど、宮城沖までの近海を回るはえ縄漁の船長をしてはる。わしの大阪の店には、やっさんの獲ったクロマグロを入れとる……実は、マグロ漁の人手不足で厚労省のIターンイベントに来てるんや」
中之島の言葉に銀平は「なるほど!」と頷くと、安本をカウンター席へいざなった。太郎が斟酌してソマを切る柳刃を止めると、安本は「気になさらずに」とつぶやいた。いかつい体躯とは対照的な目尻の皺が、海の男の純朴さを感じさせた。
中之島は和歌山の辛口本醸造をお銚子で頼み、安本とさしつさされつした。肴は、太郎が漬け込んでいた本マグロの角煮を選んだ。そして、安本は白い飯が欲しいとも言った。
「近海のはえ縄ってえと、キハダがご専門ですか? 近頃は、キハダも少ないって噂ですが」
丼ぶりに飯をよそう太郎の問いに、銀平が耳をそばだてた。
「ええ、カジキやメバチもやります。ただ、この数年は海流が変わったことや、サメやシャチに食われちまう被害も増えてましてね。はえ縄を揚げてもマグロの頭しか残ってないことが多い……漁師は年々稼ぎが減り、歳を食って陸に上がる連中が増えてるんですよ。このままじゃ、マグロよりも先に人手が不足します。少子化は、漁業にも堪えますよ」
はえ縄漁は、今の若者にとっては3Kの極みと安本は言った。近海の漁でも十時間は太平洋の上で、夕方に港へ入ると、しばし休息を得た後で午前0時から長い水揚げ作業を夜明けまで続ける。体の疲れが取れないまま四ヶ月の漁を繰り返すには、強い心身と薬代わりの酒が欠かせないと本醸造の盃を飲み干した。
「やっさんは、親子三代のマグロ漁師や。お祖父さんも親父さんも船頭やっただけに、断腸の思いで船を降りる古参の漁師を見送ってきた。けど、そないな年齢まで頑張れるのは、叩き上げの漁師だけやろ? 中途採用で、はえ縄漁師になんぞ簡単になれるんかいな」
安本は頷き、長いため息を吐いた。テーブル席の若者たちが、彼の広い背中を凝視していた。
「苦肉の策です。板子一枚下は地獄、誰だって最初は怖気づくと思います。それを奮い立たせるために、漁師は獲ったばかりの活きのいいマグロを必ず食べる。船上の飯は手早く済ませなきゃいかんので、丼ぶり飯にマグロの赤身と醤油をぶっかけ、そして、マヨネーズが馬力の元になるんですよ」
マヨネーズと聞いて、店内の客たちがあんぐりとした。ただ、龍二と太郎はニンマリと視線を交わした。
「マグロにマヨネーズ? ツナ缶じゃあるめえし、生の刺身に気持ち悪くねえのかい?」
眉をしかめる銀平に、安本がごもっともといった表情を向けた。
「一般人はね。でも、漁師はいつも醤油にワサビだと、マグロの味に飽きるんです。マヨネーズの酸味は、マグロの脂っこさと生臭さを包んでくれる。それに漁は体力を消耗するから、マヨネーズのカロリーが助けになる」
安本は太郎にマヨネーズを頼むと、マグロの角煮をどんぶり飯にぶっかけ、その上にしぼった。
「うへぇ! コッテコテじゃねえか」
ドン引きする銀平に、龍二がほくそ笑みながら言った。
「そうでも、なさげですよ。今どきの若者には……ほらね」
龍二が振り返ると、腰を浮かせたテーブルの客たちが物欲しげな顔で覗き込んでいた。彼らが手にしているパンフレットに、安本が思わず声を発した。
「おっ、おい! それ、和歌山県の漁連パンフレットじゃないか……てことは、ひょっとして、今日のイベントに来ていたの?」
三人の中の太った男が、丼ぶり飯に唾を呑みながら答えた。
「はい、僕たち全員、漁業のIターン希望者です。ベンチャーやブラックな企業に疲れちゃって。今日のイベントで偶然逢ったばかりですけど、意気投合してこの店へ入ったら、あなたがやって来て驚きました……あのう、はえなわ漁のこと、もう少し詳しく聞かせていただけませんか。それとマスター、僕たちにも角煮のどんぶり飯とマヨネーズをもらえませんか」
いきなりの展開に、銀平がポカンと口を開けている。
苦笑する太郎を、龍二が代弁した。
「コンビニ飯やファーストフード好きには、たまらんメニューかもなぁ」
安本は、色白な三人の男を見回し
「わかった。じゃあ、まずは出逢いに乾杯しようじゃないか。紀州漁師のマグロ酒だ」
と常温の本醸造をふるまった。
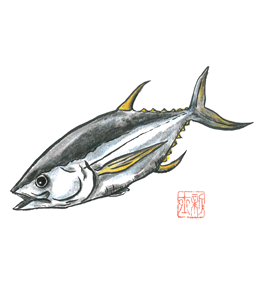
中之島が、飲み干した盃につぶやいた。
「確かに、この辛口でキレのええ和歌山の本醸造は、マヨネーズにも負けへん。そやからマグロ酒っちゅうわけか。こりゃ、いっぺんわしの店でもやってみるか」
「えっ! ええ~、中之島の師匠まで、おかしなマグロの食い方をやっちまうの?」
「そうや。わしも古参やからな、マヨネーズの力でパワーがつくなら、それもまたよしや!」
続いて中之島が丼ぶりを注文すると、マヨネーズを手にする太郎が銀平をいじっくった。
「銀平、お前も一緒にどうだ! まだまだ花火大会の注文で忙しいんだろ。パワーつけなきゃな。脂ののった禿げ頭も、マヨネーズのおかげでスッキリするじゃねえか」
「うへぇ、早いところ、花火はおしめえになってくれぇ」
銀平の嘆きに、客席から笑い声が起こった。
安本たちの乾杯を祝うかのように、打ち上げ花火の音が聞こえていた。
