東京のソメイヨシノが満開になった夜、スカイツリーのライトアップは桜色に変わっていた。夜気に漂う若葉の匂いも、本格的な春の訪れを花見客へ伝えていた。
右近龍二が歩くポンバル太郎の通りは、上野公園からどっと流れて来た二次会組が行き交っている。その中に、酔客が思わず振り向く和装の女性がいた。
落ち着いた銀鼠の正絹に、大正風のヒサシ髪の横顔が、円熟した女性の色香に満ちている。丸みを帯びた後ろ姿は、いかにも小料理屋の女将といった雰囲気だった。
「龍ちゃん、いつまで見惚れてんねん。おまはん、熟女派かいな?」
冷やかしたのは、ポンバル太郎の扉から顔を覗かせた中之島哲男だった。周囲の視線に赤面する龍二だったが、中之島の声に気づいた女性は真っすぐこちらへ振り向いた。ドギマギする龍二に、女性は「お久しぶりね、龍二さん」と思わせぶりな言葉をかけると、中之島に誘われて店内へ入った。右手には、小さなトロ箱を下げている。
狐につままれたような龍二へ、中之島と入れ替わりに玄関へ現れた火野銀平が
「驚れぇたろ! あれ、真知子さんだぜ。しばらく見ねえうちに、すこぶるつきな女将になってるぜぇ!」
と興奮して手招きをした。
「えっ! 真知子さんって、あんなにポッチャリしてたっけ!?」
龍二が赤提灯を目にしつつ居酒屋マチコで飲んだのは、かれこれ八ヶ月前だった。ご無沙汰とはいえ、別人と見まがう容姿である。
カウンター席の平 仁兵衛もドギマギした面持ちで、菱田祥一などは冷酒グラスが宙に浮いたまま。店内の客はため息も出ないほど、真知子に釘づけだった。
「なるほどねぇ。近頃じゃ、真知子さんの立ち姿も極上の肴だって評判だからなぁ。マチコで人気の“鰯の梅肉煮”みたいに客は骨抜きになるって噂は、本当らしいや」
たった一人、太郎だけは冗談めかして言った。今夜の真知子の訪れは、太郎との約束である。
「もう、太郎さんまで、人聞きの悪いこと言わないで。でも皆さん、本当に無沙汰いたしてます。お目にかかれて嬉しいわ」
ほころぶ目じりの皺も、いくらか深くなった。しかし、肌の色ツヤは光っている。
「こりゃ、脂ののったハマチやなぁ……それにしても、真知子さんが来るちゅうだけで、常連の男がほとんど揃うとはなぁ」
臆面もない中之島のつぶやきだったが、平も相槌を打った。うなじから控えめな微香をかがよわせる真知子に、男好きするいい女将になったと太郎も思った。
ところが、真知子はトロ箱をカウンターへ置くやいなや、顔つきを変えた。
「それじゃ、太郎さん。始めますか」
トロ箱から出てきたのは、ラップで巻いた褐色の塊だった。
「ええ、いいですよ。じゃあ、酒も出しましょう」
今度は太郎が、冷蔵ケースから北海道の地酒を取り出した。龍二たちが見たことのない銘柄で、レッテルの右肩には“日本最北の地酒”と表記されていた。
客たちが怪訝な顔を合わせる中、真知子がラップをほどくと、現れたのは魚の白身を巻いた昆布じめだった。
「おっ、そりゃあヒラメですかい。しかも、えらく太ぇエンガワだ。うちで扱う伊豆沖の天然物の、倍以上はありそうだぜ」
目を丸くする銀平に、テーブル席で傍観していた客たちが前のめりになった。
含み笑いを浮かべる真知子の昆布じめを太郎がそのまま柳葉包丁で切ろうとした途端、声を発した。
「うっ、うわ! なんだ、この粘っこさは!?」
柳葉包丁が、昆布から糸を引いていた。まるで、納豆並みの長さである。
「発酵してんのかいな……しかし、白身の色はどうっちゅことない。変な匂いも、せえへんで」
鼻先をひくつかせる中之島の横で、平が昆布じめの白身にくぼんだ目元を近づけた。50㎝を超えそうなエンガワだけに、ヒラメの図体はゆうに1mを超える大物と太郎も思った。
「残念、ヒラメじゃないの。魚匠の銀平さんなら、オヒョウって知ってるでしょ」
「オ、オヒョウ? ……ひょっとして、アラスカとかで獲れる、化け物みてえなヒラメかよ」
銀平は眉間に皺を寄せたが、平や龍二はさっぱり分からんといった面持ちである。だが、糸を引く分厚いエンガワに興味津々だった中之島は、銀平の答えに両手を打った。
「おお! オヒョウか! 漢字では大鮃(大きなヒラメ)と書くんや! でっかい奴は2m以上、体重も200kgを超えるっちゅう大物や……それに真知子さん、この昆布はガゴメやろ?」
昆布の端っこを中之島が箸で引っ張ると、ドロリとした粘りが出て、オヒョウの身を包んだ。まるで透明なソースである。
「さすが、中之島さんですね。利尻昆布や礼文昆布といったありきたりの昆布じめじゃ、ないんです。この日本最北端の地酒と合わせる肴として、考えました。イケるかどうか、太郎さんに試してもらいたくて、今夜はお邪魔したんです」
真知子は、親しいその蔵元がシアトルの日本食レストランへの輸出を始めたのをきっかけに、現地へ提案する肴を蔵元から頼まれたと語った。そこで、道北でも揚がるオヒョウのエンガワを使ったワイルドな昆布じめを、サプライズメニューにしようと考えた。シアトルではフライやムニエルでオヒョウを食べるが、昆布ジメは未知の料理である。しかも、ガゴメ昆布のネバネバは、見た目にも強烈なインパクトだ。
「がごめ昆布は、北海道でも貴重な昆布なの。ネバネバには、外国人シェフが今注目しているフコイダンやアルギン酸がいっぱいで、脂肪を吸収する効果もあるの。糖分の消化・吸収、血糖値の調整もするから、ダイエット志向のアメリカ人の酒の肴には、ピッタリだと思うの」
熱弁する真知子のうなじが血色を帯びて、さらに艶っぽく見えた。
粘ってはすべるエンガワを四苦八苦して切り分けた太郎は、味見すると
「こいつは凄いぜ! エンガワの甘みとガゴメ昆布の旨みが絶妙にからむぜ」と叫んだ。そして、キレのある地酒を口に流し込むと、至福の表情を浮かべた。
「しかし、切るのがめんどくさいのは、手先が不器用なアメリカ人の板前にしたら、かなわんやろうなぁ」
「大丈夫でしょう。あちらじゃ、トングを使って挟みながら切り分けますからねぇ。あのネバネバ、おっかなびっくりの顔で食べるシアトルのお客さんを見てみたいものですねぇ」
度肝を抜かれている中之島へ、平はおもしろがって言った。
「しかし……真知子さんのセンスって、おもしろいですね! 見た目の歳ほど、粘っこくないなぁ。あっ、失言!」
口をすべらせた龍二が赤面すると、銀平は「この、スットコドッコイが!」と頭をひっぱたいた。
「あら、だって私の彼はアメリカ人なの。ほら、そこに来たわ」
真知子の声に、店内の客たちがいっせいに振り向くと、玄関の鳴子とともに
「待ってました! オヒョウの昆布じめ~!」
とおかしなアクセントの声が響いた。
舌なめずりするジョージに常連たちが思わず顔を見合わせると、真知子が
「な~んてねぇ。実は、このマッチングはマチコへ取材に来たジョージさんにも協力してもらったの。アメリカ人だけど、やたら昆布ダシや旨み成分に詳しいし、打ってつけだった」
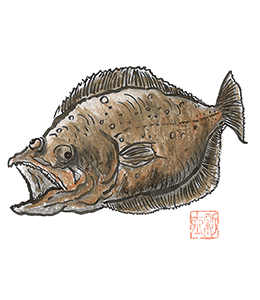
真知子の褒めそやしに、ジョージは地酒を注文しながら胸を張った。
銀平がエンガワの昆布じめを箸でつまみながら、ダジャレを口にした。
「オヒョウで意表を突くてえアイデアは、この変なヤンキーのせいかよ」
一瞬で店の空気はシラけたが、あまりの美味しさに銀平は絶句したままだった。
「あら! オヒョウの漁は突くんじゃないのよ、アメリカじゃ釣り上げるの。英語では“ハリバット”って名前ね。大きな鈎で釣り上げると、暴れないように頭をバットでぶん殴って気絶させるの。だからハリバット、なんてね!」
店内のムードにとどめを刺すような、真知子のオバサンジョークだった。
太郎が、固まっている龍二に耳打ちした。
「あのよ……真知子さんのセンスって、やっぱり年相応かもな」
それでもオヒョウの昆布じめだけは、ツヤツヤに光っていた。
