熱中症注意報が連日報じられ、浅草の目抜き通りでは、柄杓と手桶を使う打ち水に外国人観光客がスマホ撮影している。アメ横にはミストシャワーも登場し、行列をなす中国人客が大はしゃぎしていた。かまびすしい中国語が、なおさら暑苦しさを盛り上げている。
土用の丑の日まで一週間、気温はまさに鰻登りで、日暮れを迎えてもポンバル太郎の通りはまだ35℃を超えていた。
「まったくよう! この暑さ、どうなってやがる。葵屋の旦那がせっかく来てくだすったのに、これじゃ活きのいいノロもくたばっちまわぁ」
今しがたカウンター席に座った火野銀平が、したたる汗を首にかけた豆しぼりで拭った。その隣で、週に一度、ポンバル太郎へ通っている築地市場の元締め・葵 伝兵衛が上燗の本醸造をなめている。夏でも燗酒と腹巻きを欠かさないのが、伝兵衛の健康法だった。
銀平が口にした「ノロ」とは、魚匠が使う鰻の呼び名である。築地は、ここ数日、養殖鰻の取引が好調で、太郎も早々と、浜名湖産の鰻を蒲焼きにしていた。その上物が、今夜の伝兵衛のお目当である。
伝兵衛は白磁のお銚子を傾けながら、背開きした鰻に串を打つ太郎へ問わず語った。
「江戸は侍の町だったもんで、切腹は縁起が悪いてぇ理由で背開きなんだが、そもそもは、ぶつ切りなんだよ。それを串に刺して焼いた物が、蒲の穂に似てたから蒲焼きってんだ。だがよう、小骨が多くて食うのが面倒だった。今のように裂いた蒲焼きは、大坂からやって来た商人が屋台で売り出したんだよ。当初は醤油ダレが薄っ辛くて、まったく人気がなかったそうだ」
築地の白眉として聞こえた伝兵衛のウンチクにテーブル席の客たちは感心しつつ、蒲焼きのタレが焦げる匂いに鼻先をひくつかせた。
「へぇ、そうなんですか」
と感心する太郎が炭火の上で蒲焼きを返すと、香ばしい匂いはゆるりと玄関扉の方へ流れた。
「昔の上方では、白焼きが主流やったんや。軽く塩焼きしたマムシをワサビで食べる。あっさりとした味やから、伏見の酒と抜群に合うで」
クンクンと嬉しげに鼻を鳴らす中之島哲男が、古めかしい新聞包みの一升瓶を手にして入って来た。マムシは、関西ならではの鰻の呼び方だ。
見知った仲の中之島と伝兵衛は軽く会釈を交わしながら、横並んだ。むろん、中之島も蒲焼きには目がない。存在感のある二人に、店内が一瞬、静まった。
太郎がカウンターに置かれた一升瓶の包みを凝視すると、新聞の発行された日付は平成18年7月22日だった。
「……珍しいですね。中之島の師匠が、古酒を持って来るなんて。しかも10年物って、スゴイな」
酒のヴィンテージに、テーブル席の客が前のめりになった。そのようすに、中之島はまんざらでもなさげに口を開いた。
「これは、うちの割烹の床下で寝かせた酒や。ええ按配に、ひんやりした場所やさかいな。毎年、この時期になると10年前に貯蔵した酒を取り出して、土用酒に使うねん。太郎ちゃん作る蒲焼きとの相性はどうかと思うて、持って来たんや」
聞き慣れない土用酒に、焼き上がった蒲焼きへ伸びる銀平の箸が止まった。
「土用酒ってぇことは、ノロに合わせる酒ってことですかい? そんな酒が、あったんですかい?」
「昔、灘の蔵元が江戸向けに仕掛けた熟成酒や。味の濃い江戸の蒲焼きのタレには、春にしぼった酒が熟成して、ちょっとヒネて、甘みも増すからイケたんちゃうか。そもそも“夏バテには、土用の鰻”かて、夏に売れへんかった鰻をどうにかするために、江戸時代の奇人変人・平賀源内が考えたキャッチコピーやからな」
中之島の声に、店内の客たちは口々に「あの、エレキテルの平賀源内だよね?」と驚きを隠さなかった。もちろん、伝兵衛や銀平もである。
「ほう、そうなんですかい? 確かに、天然物のノロてぇのは、冬に脂がのってうめえんでさ。夏場はどっちかってえと、痩せてやす……てこたぁ、源内さんの土用の鰻にまんまと江戸っ子がはまったから、ついでに蒲焼きに合う酒も売っちまおうって腹だったわけか。まったく、昔から上方人は商魂たくましいこった……そういやぁ、昭和の半ば、葵屋の客に大阪から深川にやって来た「まむし屋」の赤井千治てぇのがいたんでさ。まむしは上方流の屋号で、ノロは腹開きだし、関東みてえに蒸さずに焼くんで客の人気は今ひとつだった。ところが、蒲焼きに合う酒を用意した途端、すこぶるつきに鰻がうまくなるって評判になったんでさ。その酒の秘密を教えてもらう約束が、新聞にまむし屋を紹介された翌日、心臓発作でおっ死んじまってね。ありゃ、今でも謎だねぇ」
板についた築地言葉で、伝兵衛は赤井の人となりを語った。東京の蒲焼きの多くは、銚子のヒゲ印醤油に黒糖のザラメ、本枯れ節のダシを使った味の濃いタレだが、赤井は頑として兵庫の龍野醤油にこだわり、砂糖は香川産の和三盆、ダシは関西の荒節ダシしか使わなかった。そのタレだと辛さはあっても、とろみと甘さが勝るから、江戸っ子にはウケないと伝兵衛は口酸っぱく諭した。それでも赤井は、意志を曲げなかった。
しみじみと伝兵衛が語ると、銀平が湯気を立てる蒲焼きをつまみながら中之島に訊いた。
「へえ、関西じゃノロの蒲焼きが甘ぇんですかい?」
「うむ。まあ、照り焼きっぽいのが関西風の蒲焼ちゅうことや。わしの店の蒲焼きも、どっちかちゅうたら、甘辛なタレや。関西の蒲焼きに合うこの熟成酒、伝兵衛はん、いっぺん飲んでみまへんか」
中之島が新聞包みを開くと、褐色に変化した酒を入れたフロスト仕上げの一升瓶が現れた。明らかに長熟している色合いで、栓を開けると、甘いキャラメル香が漂った。
「いやぁ、せっかくだが、あっしは遠慮しときやす。今夜は、太郎さんが背開きにした江戸風の蒲焼きでやすから。江戸の地酒を熱燗で合わせまさぁ」
酒は辛口が身上の伝兵衛は、ひと口飲んで甘いと感じた酒は二度と口にしない主義である。焼き上がった二枚目の蒲焼きを待つ盃は、千葉の大辛口本醸造で満たされている。
「さよか。まぁ、伝兵衛はんは生粋の江戸っ子やさかいに、クセのある甘い酒は合わへんかもしれんな」
中之島の大ざっぱに外した新聞包みが、伝兵衛の前に広がった。その途端、黄ばんだ記事の写真に伝兵衛が声を上げた。
「うっ! うおっ! こ、こりゃ、赤井の千治じゃねえか!」
「えっ!? そりゃ、さっき元締めがおっしゃってた深川のまむし屋ですかい!」
新聞記事を覗き込んだ銀平が、どうしたわけかと言わんばかりに中之島へ振り返った。
しかし、一番仰天しているのは中之島本人である。記事に目を凝らした中之島は、小刻みに震え出した。
「ま、まさか!? ほんまかいな……わしは今の今まで、その新聞のことなんぞ、まったく気にもかけてなかったで。10年前の今日、読みもせんと包んだだけの新聞やがな。それに赤井はんの載ってる記事には、わしが造ったこの酒と同じ熟成のやり方を本人が書いてるわ! 深川のまむし屋で評判になった酒のことやって」
唖然とする伝兵衛だったが、自分の頬を両手で叩くと気を取り直し、新聞の日付を食い入るように見つめた。
「10年前の7月22日……お、思い出しやした! 千治の奴が亡くなったのは、その翌日。つまり、今日が命日でさ」
今度は、伝兵衛の両手が震えていた。
銀平が背筋をゾクゾクさせながら、問わず語った。
「てぇ、こたあ、元締めが聞き出せなかったまむし屋の謎の酒は、中之島の師匠が造ったその熟成酒と同じってことですかい……こりゃ、おったまげた。千治さん、あの世から中之島の師匠を使って、元締めに教えたわけですか」
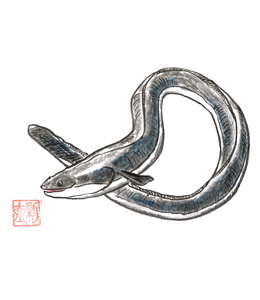
店内の客たちが無言になる中、中之島が棚から冷酒グラスを取って、伝兵衛に土用酒を注いだ。記事を三度も読み返した伝兵衛は、琥珀色の酒にようやく口をつけた。
「うっ、うめぇ! 甘いのに、辛い! それに、ちょいと酸味もある。こいつぁ、蒲焼きの脂にすこぶる合いやすぜ!」
「さすがに、築地の元締めや。ご名答でっせ! わしの土用酒の秘訣は、酸味にもありまんねん。ましてや、昔の鰻は天然物で、極上の脂がのってたはずや……きっと赤井はん、その脂の味を熟成酒で生かすことに、気が付いたんでっしゃろ」
自分も冷酒グラスに土用酒を注いだ中之島は、伝兵衛とグラスを合わせ、互いに赤井千治の命日を偲んだ。
三匹目の蒲焼きを焼く炭火が、パチンと大きく爆ぜた。
「うっ、うへ!」
ビビったまま一尺ほども飛び上がった銀平に、客席から笑い声が巻き起こった。
