中央卸売市場の豊洲への移転がひと月先に近づき、築地周辺では、別れを惜しむかのようにグルメイベントが連日催されていた。鮮魚商にはサケやサンマを焼く煙が立ち込め、精肉商はサシ(脂)がのった米沢牛や松坂牛を炭火で炙っていると、スポーツ新聞は報じている。
その記事をポンバル太郎のカウンター席で読み耽る右近龍二に、やって来たばかりの平 仁兵衛が隣へ座りながら声をかけた。
「私は極上の牛肉より、今夜のおススメメニューにある、“熊本直送の馬刺し”の方が惹かれますねぇ。マリさんの熊本の友人がやっておられる牧場が、送ってくれたそうです。太郎さんの味見じゃ、脂がとろけて、熊本の山廃純米酒にピッタリだとか」
早速にぬる燗の山廃純米酒を注文した平は、カウンターの隅に座っている火野銀平にも笑みを向けた。しかし、銀平は背中を向けたまま、返事もしなかった。よく見ると、向こう隣りに座る小柄な男と難しい顔で話し込んでいる。青く剃った頭が、二人とも似ていた。しかも、まだ酒は口にしていなかった。
「珍しいですねぇ。銀平さんは、いつもマリさんが熊本土産で持って来る馬刺しにぞっこんのはずなんですけどねぇ」
つぶやく平に、龍二が銀平たちへ聞こえないようスポーツ新聞を壁にして、声をひそめた。
「平先生。どうも込み入った話みたいです。だから僕、新聞に集中しているふりをしてるんですけど……よけいに、聞き耳を立てちゃって」
龍二によると、銀平の連れは銀座6丁目にある老舗の寿司店「江戸正」の板前・加藤 清だった。江戸時代から続く有名店の名に平が「ほほう!」と声を上げると、付き出しの小鉢を置きながら太郎が言った。小鉢の中身は馬肉のユッケで、甘い熊本の醤油と卵の黄身で和えている。
「江戸正さんは、仕入れ先の火野屋と長い御縁なんです。それに銀平と加藤君は、同い歳。ところが、加藤君が故郷の熊本へ帰るらしい。それを、銀平が考え直すよう説得してるってわけです」
太郎の言葉が耳に入ったのか、銀平から視線を外した加藤は龍二と平に小さく会釈した。
加藤は火の国出身にしては色白で、人の好さげな愛想笑いを覗かせたが、熱を帯びた銀平の口は一方的に喋り続けている。
「江戸正さんは、銀座でも一、二を争う寿司店でしょう。あそこを辞めてまで故郷へ帰るのは、よほどの理由でしょうねぇ」
平の声が耳に入ったテーブル席の客たちも、「確か、ミシュラン二つ星の店だよな」と頷いた。その時、銀平の声音が高くなった。
「馬鹿じゃねえか、花板が目の前だってのによう、もったいねえ。熊本を元気にするったって、おめえ一人の力じゃ、どうにもならねえだろ。でえいち、おめえの寿司を食わせたからって、熊本の復興が早くなるわけじゃねえよ」
話を蒸し返す銀平は平と龍二へ聞こえよがしにぼやくと、加藤の帰郷理由も吐露した。
熊本の高校を卒業後、地元の寿司店・肥後屋で修業した加藤は、25歳の時に上京。運を天に任せて、一流店の江戸正の門を叩いた。
折よく、一人前の職人になりたての加藤は人手不足の江戸正に格好の人材だった。
加藤が入った頃の江戸正の常連客は接待族を中心にした年配の男性ばかりで、女性客が少なかった。それは、寿司が少し大きいせいだった。だが、ここ10年は銀座の寿司屋も、女性客がカギを握っている。酒も地酒だけでなく、高価なワインやシャンパンも揃えている。そんな時代に合わせて寿司も変わらねばならないと加藤は考え、目にも美しく食材も風変わりな握り寿司を生み出した。
フォアグラやふかひれをネタに使う加藤の創作寿司は、セレブな女性たちに好評で、江戸正の店主はどんどん取り入れたと、銀平は我がことのように自慢した。
聞き入る平と龍二だけでなく、店内の客たちも唾を飲み込んでいた。
「……でも、その原点は熊本駅前の肥後屋。私にとって、忘れちゃいけない創作寿司があるんです。今夜は、それを銀平さんに食べてもらおうと思って、持って来ました」
加藤は紙袋から寿司折を取り出すと、太郎へ詫びを入れて、カウンターの上に開いた。そこには丸い形をした、可愛らしくも食欲をそそる手まり寿司が詰まっていた。鯛や車海老の身を細工したネタは、あたかも京友禅のように美しい。
「ほほう……食べるのが、もったいないですねぇ」
平がため息交じりにつぶやくと、龍二も
「紅白の手まりは、祝い寿司にも見えますね」
と仕上げの見事さに感心した。
「阿蘇の白菜と赤ナスだな。八百甚の誠司が、この前、奨めていた熊本の地野菜だ」
太郎の感嘆を耳にしながら、銀平の目はもう一つの手まり寿司を見つめていた。赤い身に白いサシが光る肉の手まり寿司だった。
「これ……熊本の馬肉か」
銀平が前のめりになった時、いきなり肩越しに童謡が聞こえた。
「あんたがたどこさ、肥後さ、肥後どこさ、熊本さ……これは、あたしがずっと好いちょる肥後屋の手まり寿司“あんたがたどこさ”たい! 熊本民謡の手まり歌が商品名で、あたしは帰省するたび、土産に買うちょった。ばってん、今年の春の熊本地震で肥後屋は倒壊して、つい先日、廃業したと。それが、どげんして、ここにあるとね?」
いつの間に現れたのか、銀座の「BAR手毬」のママ・手越マリだった。
脇から残念そうな表情のマリが折詰めの箱を持ち上げると、銀平がつぶやいた。
「清……おめえ、肥後屋を復活させてえのかよ。だから、帰ぇるつもりだな」
平と龍二もその問いかけに頷いたが、加藤は答えず、マリの熊本弁と土管のような体に不釣り合いな花柄のジャケットに目をみはった。
「あ、あなたは20年前、最初に、あんたがたどこさを買って下さったお客さんでしょ? 確か、銀座でホステスをなさっていて、ご贔屓客のお土産にしてくれました。私、覚えていますよ」
問わず語る加藤は、そのまま立ち上がって律儀なお辞儀をして、今は銀座の江戸正にいると素性を明かした。
マリがじっと加藤を見つめ返すと、太郎たちは
「それって、BAR手毬を開いた頃じゃないの?」
と顔を見合わせた。
はっと顔色を変える銀平の隣へ、馬肉の手まり寿司を愛しげに見つめるマリが座った。
「思い出した……あの時の、肥後屋にいた若い板前さんねぇ? 銀座の江戸正さんにおるとはねぇ。ばってん、これも御縁ばい……あたしが銀座のホステスを卒業して自分のBARを開いた時、手毬の名前を思いついたのは、肥後屋のあんたがたどこさのおかげたい。東京で負けそうになったり、くじけそうになった時、この手まり寿司を食べながら、いつか、故郷へ錦ば飾ると誓うちょった。加藤しゃんの考え出した、あんたがたどこさは、ずっと、あたしの馬力やったばい」
懐かしそうな、それでいて、どこか寂しげなマリの目元に、加藤は複雑な表情で奥歯を噛みしめた。
厨房で煮物を炊く鍋の音が聞こえるほど静かになった店内に、平の声がした。
「マリさんだけじゃなく、この手まり寿司に支えられた熊本人は、たくさんいるんじゃないでしょうか。だから銀平さん。加藤さんが帰郷して、もう一度、あんたがたどこさを復活させることは、大きな力になると思いませんか」
平は嬉しそうに山廃純米酒を飲み干し、太郎へメニューボードの「熊本産直の馬刺し」を目配せした。
意を得たとばかりに、太郎が口を開いた。
「それじゃ、マリさんの肝煎りの馬肉で手まり寿司を作るよ。今夜の馬刺しは俺からお客さんへふるまう、手まり寿司に変更だ。加藤さん、手伝ってくんねえかな。熊本へ帰る、予行演習も含めて」
龍二に背中を押されながらも躊躇している加藤へ、銀平が行けよとばかり、無言で首を振った。途端に、マリの大きな手のひらが、銀平の頭をピシャリと叩いた。
「銀平! いつまでウジウジしちょるとね! 加藤しゃんが熊本に錦を飾るお祝いに、あんたもいっぱい食べるばい」
「い、痛ぇな! 分かってるよ……マリさん、ありがとうよ。あんたの店の名前を手毬にしてくれて。おかげで、俺、腹がくくれたよ」
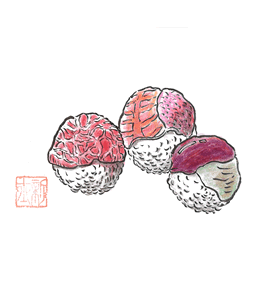 いつになく素直な銀平の目尻が、うっすらと光っていた。
いつになく素直な銀平の目尻が、うっすらと光っていた。
慰めようとする龍二を平の酌が止めると、マリが熊本土産の紙袋から黄色い塊を取り出した。
「ばってん、銀平にはこっちの方がよかね。加藤しゃん、これで、銀平に手まり寿司を作ってくれんね」
ベッタリと黄色い辛子レンコンに店内の客たちがどよめくと、加藤は苦笑しながら
「承知しました、これ、新しいあんたがたどこさのメニューに加えましょう!」
と手早く握って、銀平の前に差し出した。
「ち、ちっくしょう! まったくよう、泣けてくるぜ!」
辛子レンコンの手まり寿司を口に運んでやるマリと、その辛さに涙を誤魔化す銀平へ平がほほ笑んだ。
「熊本が一日も早く、復興して欲しいですねぇ」
加藤の握る鮮やかな手まり寿司が、それに応えるかのように客たちの前へ転がっていた。
