残暑と呼ぶには熱すぎる西日に肌を焼きながら、高野あすかはポンバル太郎に向かっている。はやる気持ちと汗をハンカチで拭いながら、今夜の集まりに誘ってくれた太郎の言葉を思い出していた。
「毎年、九月に入ると常連客だけで催す会があってね。ハル子との約束なんだ……旧き良き酒文化を忘れないためでもある。それに、今年は特別な人も呼ぶしね」
その夜、あすかが閉店時間まで大吟醸をチビチビと舐めていた理由は、誰もいなくなった店内で、初めて太郎と二人きりになれたからだった。いつもより太郎の声を身近に感じ、独り占めできる悦びに酔いながら、特別な人というのはひょっとしたら自分ではないかと、あすかは自惚れてもみた。
そんな密かな期待を胸にポンバル太郎へ着くと、扉には「本日は貸切営業、誠に申し訳ございません」と貼り紙がしてあった。
「おっ、ようやく来ましたか。こっちですよ、あすかちゃん」
扉を開けると呂律のゆるんだ平の声が、カウンター席から飛んで来た。もう、ぬる燗の純米酒に酔っている。
その周りには、銀平や龍二、さらには平と菱田、中之島哲男、手越マリといった常連たちが肩を寄せ合って太郎の大皿料理をつつき、朱色の盃を手にしている。
そして、いつもと雰囲気がちがったのは、その漆塗りの盃だけでなく、はなだ色の生絹をまとった芍薬とした女性がカウンターの真ん中に凛とした姿で佇んでいた。
薄化粧なうりざね顔は、派手に描き上げたマリの丸顔と対照的だった。
あすかは妙齢な女を一瞥しながら、彼女の前に置かれた角樽に視線を奪われ
「あっ、柳樽(やなぎだる)!」
と声を洩らした。
「う~む、さすが蔵元の娘や。角樽とは呼ばへんで、柳樽ときたか」
中之島の感心する声に、女性があすかを見つめて
「じゃあ、あなたには是非、このお酒を飲んで頂きたいですねぇ」
とおもねった。
その馴れ馴れしい言葉にあすかが表情を曇らせるのを、太郎は見逃さなかった。
「そうか! あすかとは、初めてのご対面だな。こちらが、居酒屋マチコの女将さんだよ」
「えっ、あの噂の真知子さんですか!?」
驚きとともに、一瞬、ライター癖が動いて質問を浴びせそうになり、節操がないと常連たちにとがめられるのを気にしたあすかだったが、その一方で、太郎の言った“特別な人”は真知子だったと気持ちが萎えた。
それでも気丈なあすかは、真知子から目をそらさずに訊いた。
「その柳樽、今夜は何かのお祝いですか?」
真知子が困り顔で太郎を見やると、中之島が助け舟を出した。
「今夜のテーマ酒は、“やなぎかげ”や」
「やなぎかげ?」
合点がいかない顔のあすかに、酒のお預けを我慢していた銀平がシビレを切らした。
「あすか、さっさと座れよ! 暑気払いの酒のゲンかつぎが悪くなっちまうじゃねえか。毎年恒例の催しだが、お前は初めて参加してんだから、ちったぁ気を配りやがれ」
ぞんざいな口ぶりにあすかは口ごたえしかけたが、夏ばて気味の銀平をおもんばかり、黙って腰を下ろすと紅い盃を手にした。
店内が静まると、太郎はあらたまって口上を述べた。
「今年もやなぎかげ、つまりは“本直し”の会を迎えました。一年の半分が過ぎて、皆さん、お疲れさまです。本直しってのは、江戸時代から大正時代まで親しまれた酒で、みりんのように甘いんだけど、米焼酎を加えることで味をひきしめて飲みやすくした。いわゆる柱焼酎効果です。この酒を飲みながら塩を舐めることで、当時の庶民は熱中症を予防していたらしい。中之島の師匠がいらっしゃる関西では“やなぎかげ”と呼ばれ、夏ばてや病魔封じにも効くと言われてた。今夜は、その本直しを真知子さんがオリジナルで作って、持参してくださいました」
太郎の紹介で、ほとんどの常連が知っている真知子から簡単に挨拶があり、さっそく朱色の柳樽が封切られた。
ゆっくりと真知子から各人の盃に注がれる酒は少し褐色を帯びて、あすかは、きな臭くて甘ったるい香りが漂うのを感じた。
「あの……失礼ですが、これってヒネてませんか?」
「そう。だからこそ、柱焼酎を加えるの」
真知子は酒を注ぐ白い手を止めると、目尻の細いシワをほころばせた。
「当時は冷蔵庫がなくて、生酒を売ることが難しいから、火入れしなければいけなかった。それでも、火落ち菌のせいで腐造してヒネる酒やみりんが多かった。だから柱焼酎を加えて酒のアルコール度を高め、味とキレを直したの」
酒造技術が進化すると、清酒の普及とともに、みりんは晩酌の座を譲った。そして、調味酒に使われるようになった。だけど、こうして味わってみると、夏場の気つけや疲労回復には少し甘酸っぱいヒネが理にかなっていると真知子は話した。
「だから、本直しなんですね」
真知子としゃべりたそうにしていた菱田が口を挟むと、やなぎかげを舐める平も言葉をつないだ。
「やなぎかげってのは、その名の如く柳の木陰で、ちびちび飲まれた庶民のお酒だそうですね。どことなく貧乏臭い安酒って印象が、僕は大好きです」
すると、中之島が飲み干した盃を真知子に差し出し、おかわりを求めながら言った。
「それは、いかにもお江戸らしい粋な解釈やな。けど、商売っ気の強い上方のやなぎかげは、ちょっと意味がちがうで。灘や伏見の酒蔵の周囲には木陰を作り、風が抜けやすい樹木を植えとった。その理由は、酒を貯蔵する桶を少しでも涼しい環境に置きたかったからや。つまり、できるだけ酒を腐らせたくなかった。柳の木は、それにピッタリの樹木だったわけや」
真知子は中之島を敬うように両手で酌をしながらも、あすかの表情を探っていた。
すると、目を閉じてやなぎかげを味見していたあすかが、ハッとしてまぶたを開いた。
「……震災で壊れ、更地になった実家の跡に、ご先祖様が植えた柳並木が残っているんです。かつては蔵に引き込んでいた湧き水の堀に沿って、夏になると蔵を囲むように大きく茂ってたの。つい先日、お盆で帰省した時もまだ健在で、夕風に揺れてました」
子どもの頃から見慣れた柳並木だったが、なぜ、それが蔵を囲んでいるのか疑問に思ったことはなかったとあすかは問わず語った。
あすかの内心をおもんばかった常連客たちが黙ると、真知子はあえて口を開いた。
「柳の木は、昔から厄払いに重用されていたの。悠久の時代、中国の長安では旅人に柳の枝を折って手渡し、旅路の無事を祈ったそうです。そして、根や幹がしなやかで粘り強く、簡単には倒れないし、何度でも復活して生え育つの。だから、あの地震にも負けなかったのでしょうね。あすかさんのご実家も、昔は、やなぎかげを造っていたはず……蔵を護っていた柳の精が、あなたに、それを思い出して欲しかったのかも」
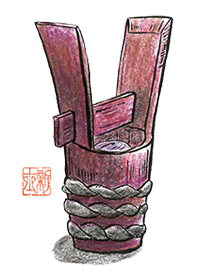
心の琴線に触れるような言葉に、あすかは真知子の人となりを感じつつ自分のまぶたが熱くなるのを感じた。
「柳樽ってのは、“家内喜多留”と当て字するんだ。江戸の人たちは、家の中へ喜びが多く留まるようにと願ってたんだ。あすかのご実家も、まだまだ、これからだぜ」
その太郎の声に菱田がうれしげに頷くと、隣に座るマリがやなぎかげをおかわりしながら言った。
「なるほど。だから今でも、結納や結婚式には柳樽が使われとるとねぇ。それに、柳腰とか柳眉とか、柳って字は女らしい表現がいろいろあって、私は好いとっと」
「ちょっと、ちょっと! マリさんの柳腰って、どこにあるんだよ?」
銀平のツッコミにマリが肉づきのいい太い腰を振ってみせると、ようやく笑い声が起こった。
その心地よい響きの中、太郎の見つめる先に、あすかと真知子がやなぎかげの盃を合わせて、頷き合っていた。
