上りガツオの大群が銚子沖に押し寄せ、先行きの見えない築地市場は久々に明るさを取り戻している。型の揃った上物を人気寿司チェーン店が大量に仕入れても余裕はあるらしく、仲卸の店頭は口の肥えた銀座の料理人たちで連日賑わっている。
創業以来、扱うカツオの数よりも質で勝負する火野屋は、この時期、縁起物での配達に余念がなく、銀平みずから深川や両国の得意先を半被姿で走り回っていた、とりわけ、春の棟上げ式や地鎮祭の御祝儀に上りガツオを奉げるのは古い下町の習わしで、祖父の銀次郎の代から続く馴染み客がいる。
今夜のポンバル太郎に、その一人である大工の棟梁・柾木 貫太郎を銀平は伴って、祝杯を挙げていた。酒は東京の地酒。江戸時代から地廻りしている、多摩の銘酒である。
「棟梁、お疲れさんです。とはいえ、まだまだ、家造りの本番はこれからですね。それにしても、立派な檜造りの注文住宅だ。あんなの、近頃はとんと見かけなくなりやしたね」
「ああ、こっちこそ、いつもながら見事な上りガツオだったぜぇ。近頃の新居は、組み立てキットみてえでよう。一軒建てるのに、ふた月とかかりゃしねえよ。おいらに言わせりゃ、ありゃ、家じゃねえ。模型だ、模型。これも世の流れさね。でぇいち、地鎮祭や棟上げ式を省いちまう時代だからよう、大工どころか、神主さんだって仕事が減っちまってらぁ」
ごま塩頭の貫太郎は歯切れのいい口ぶりで銀平の酌を受けると、熱燗の純米酒を一息に飲み干した。ふぅと吐いた息が、“柾貫”と白く抜いた藍染め印半纏の襟を揺らせた。腰から下は黒い股引に地下足袋を履いた、いなせな姿である。
二人のやりとりをカウンター席で見つめる平 仁兵衛に、隣の高野あすかが
「お互いに、江戸っ子そのものって感じ。今夜の銀平さん、まんざら捨てたもんじゃないな」
と独りごちた。その声も、貫太郎とさしつさされつする銀平には聞こえない。気短な江戸っ子同士の酌が、酔いを早めていた。
「へい、お待ち! メザシの焦がしと、アオヤギの酒蒸しでしたね」
太郎が銀平たちの前へ肴を並べると、貫太郎が鼻をひくつかせて言った。
「おお! このアオヤギは上物だ。木更津辺りの奴かい? それに、純米酒をたっぷり使って蒸してるな。さすが、銀平がベタ褒めする大将だぜぇ。気に入った! これからも寄せてもらうからよ。よろしく頼むぜぇ」
「ありがとうごぜえやす。銀平のお得意様なら、いつでも大歓迎です」
畏まる太郎へ、上機嫌な貫太郎は「まあ、一杯やりねえ」と盃を手渡しながら、お銚子の追加を注文した。
貫太郎の気風に、平が目尻をほころばせて訊ねた。
「棟梁は、今も昔かたぎな仕事をなさっていると銀平さんから聞いてます。使われる大工道具も、長年愛用してるのでしょうねぇ」
骨董好きな平は、古い大工道具にも目がない。陶芸の上り窯にくべる薪や炭も、手斧や鋸で切り落としている。
「そうさね。おいらの祖父さんや親父から受け継いだ道具も、まだありやすよ。だが、本格的に手の込んだ仕事じゃねえと、使わなくなっちまうんでさ。おいら、昨今の安普請の家は苦手なんでね。てぇした腕がなくったって、積み木みてえにポンポンってな具合で仕上げちまう」
年恰好が少し上に見える平をおもんばかって、貫太郎は口調を変えた。呂律は、まだしっかりしている。
ふと、思い出したかのように、貫太郎が足元の風呂敷包みの中を探った。
怪訝な顔の銀平に、貫太郎が煤けたような黒い塊を差し出した。カウンターに酸っぱい匂いが広がった。
「この匂い。懐かしいような、でも古臭い感じ……それ、何ですか?」
あすかが鼻先をつまんで訊ねると、貫太郎が答える前に、平が嬉々とした顔で言った。
「墨壺ですねぇ。しかも、年季の入った彫刻は大黒様ですか。縁起のいい仕立てですねぇ」
物欲しげな平の声音に、銀平が渋い顔で釘を刺した、
「棟梁の宝物ですよ。ねだってもダメですぜ、平先生」
すると、貫太郎は思いがけない言葉を口にした。
「おい、銀平。毎年の上りガツオを目利きしてくれる礼と言っちゃなんだが、おめえ、これをもらってくれねえか。やっちまった後は、好きにしてかまわねえぜ」
「またまたぁ、棟梁。もう、酔っちまったんですかい。ふざけちゃいけませんや」
「ふざけてなんて、いねえよ……いいんだよ、俺の宝物はいろいろあるんでぇ。だから、その一つを、おめえにもらって欲しいんだよ。四の五の言わず、受け取りやがれ」
押し付ける貫太郎へ、銀平は押し返す。束の間それが続くと、あすかが脇から手を伸ばした。
「じゃあ、銀平さんの代わりに私が頂いちゃおうかな!」
と片目をつむるあすかに
「ああ、銀平のダチなら、かまわねえよ。お嬢ちゃんも、物好きだねぇ」
と貫太郎は盃をあおった。
「ば、バッカ野郎! あすかに取られるぐれえなら、俺が大事にしまっときやす!」
銀平が、礼を述べるように両手で貫太郎へ酌をした。それでも、あすかは食い入るように墨壺を凝視して訊いた。
「貫太郎さん。この墨壺って、どうやって使うのですか?」
あすかのしつこさが気に入ったのか、貫太郎は相好を崩した。
「そいつは、大工が木材に直線を引くのに使う道具だ。くぼんだ穴が開いてっだろう。そこに墨汁を染ませた綿を入れるんだ。反対側には、糸巻が付いてっだろう。その糸の瑞は、墨汁を通って穴から出る。その瑞に、猿子(さるこ)って小さな錐(きり)を付ける。これを目印に刺して墨糸を引き出して真っすぐに張り、糸をつまんで弾くと黒い直線がその面に付けられるって寸法よ」
大工が木材に印を付けるのには、鎌倉時代から墨壺を使う。江戸時代まで、大工は朝が早く、暗い内から現場で仕事をしなければならず、物差しと筆じゃ見えにくい。今じゃ鉛筆の方が便利そうに思えるが、木目によっては上手く直線が引けない。だから墨壺は、手間をかけずに狂いの出ないよう知恵を絞った道具なのだ。それに、江戸の大工は墨壺の仕立てで見栄を競った。昼下がりに仕事を終えて一杯引っかける大工は、墨壺を忘れて帰らないように居酒屋の戸口へ並べた。その甲乙しだいで、町の衆からの仕事が決まったと貫太郎は自慢した。
ちゃっかり者のあすかは、雑誌記事のネタしようとスマホで音声を録音している。貫太郎は「なんでぇ、そりゃ?」と眉をしかめながらも、そのまま解説を続けた。
墨壺の材料には欅が多く、糸口は陶器や真鍮製。形もさまざまで、彫刻など意匠を凝らした物が多い。墨汁ではなく紅殻(べんがら)を使えば朱壺(しゅつぼ)と呼ぶが、紅殻は水洗いすると消えるので、主に磨き丸太などの自然木を、木肌を削らずそのまま生かして使う場合に使う。昭和時代までは大工の看板道具だったが、建築の工法が変わったことで、墨壷を使わなくなっていると嘆いた。
「さっき言ったユニット式の組み立て住宅は、その典型だ。大手住宅メーカーの主力商品で、建て方をマニュアル通りに進めりゃ、時間とコストが省けて、熟練した職人がいねえでも仕上がっちまうんだ」
貫太郎が腐すとテーブル席の男性客の一人が
「俺ん家、それなんだけどなぁ……気分悪いや。それでも、30年ローンで買った血と汗の結晶だよ」
と恨めしげに洩らしたが、貫太郎は聞こえないふりで
「東州ハウジングの野郎め……」
とつぶやいた。
その落ち込んだ声が、銀平には引っかかった。
「……東州ハウジングって、あっしより2つ下だった、娘の佐紀ちゃんが嫁いだ先でしょ? お元気なんで? 確か、跡取りのご亭主は専務になったはず」
銀平の問いかけに、平が「墨田区にある、老舗の会社ですねぇ」と頷くと、盃を止める貫太郎の口元がゆがんだ。たるんだ頬は酔いが回ったせいか、火照っている。
「ああ……元気だよ。もっとも、おいらには期待はずれの旦那だがな。佐紀は器量よしだが、こらえ性が強くって損ばかりしてやがる。親馬鹿ながら、そこが“玉に傷”だよ。銀平! おいらぁ、おめえに佐紀をもらって欲しかったんでぇ。ずいぶん前になるがよう、そう銀次郎さんに頼んだことがあったんでぇ」
途端に、グラスのやわらぎ水を口にしていた銀平が吹き出し、太郎は間一髪でよけた。貫太郎らしからぬカミングアウトに、平とあすかだけでなく、テーブル席の客たちも驚き顔を見合わせた。
「じょ、冗談はよしてくんねえ、棟梁! 東州ハウジングは、都内でも知られた会社じゃねえですかい。火野屋とじゃ、比べ物になりませんや」
笑ってはぐらかす銀平の首に、貫太郎が腕をからめた。
「てやんでぇ! あいつは、大工じゃねえ。ユニット住宅ばかりおっ立ててやがんでぇ。現場にゃ、清め酒や祝い酒も奉げねえのが、奴に言わせりゃ当世風なんだとよ。けっ、ふざけんじゃねえよ。てめえが酒に弱え下戸だからじゃねえか……昔おいらがよう、東州ハウジングの下請けをやってたから、佐紀はああなっちまった。あいつの性分なら、畑ちがいでも、魚匠の女将になった方が良かったんでぇ」
雲行きが怪しい二人の会話に客席がざわついた時、玄関の鳴子が響いた。客たちが振り返った先に、三十路半ばとおぼしき女性が清楚な絣の着物をまとっていた。
「お父さん! 今夜は章太郎の就職祝いに、うちで食事会をする約束だったよね。大工仲間に訊いたら、火野屋の銀平さんとこちらに来てるってえじゃない……それに、人様の前でみっともない話をしないでよ」
平が「あの方、佐紀さんでしょう」と察すれば、太郎は「まちがいねえ。目元も口調も瓜二つだ」と唖然としている貫太郎を見つめた。
突然の再会にうろたえながら挨拶する銀平の肩越しに、貫太郎の鬱憤が弾けた。
「なにが、みっともねえんでぇ! おいらぁ、本音をしゃべってるだけでぇ。それに、孫の章太郎は東州ハウジングの関連会社に勤めるってぇじゃねえか。どうせ、今どきの家を建てるんだろ。本物の大工を育てねえ会社なんざ、気に食わねえんだよ!」
すると、佐紀の後ろから若々しい凛としたスーツ姿の男が現れた。その面立ちも、貫太郎によく似ていた。
「お祖父ちゃん、お久しぶりです。僕が勤める東州建材は、国産の材木を目利きする会社です。それには、墨引きとか大工の修業が基本なんだ。来月からの研修では日本檜を仕入れている高知県に単身赴任して、本格的な注文住宅を建てる勉強も始めます。だから今夜は、お祖父ちゃんの大工人生と経験談をじっくり聞きたいんだ……もちろん、僕は大工らしく祝い酒も一緒に飲むよ。飲めないうちの親父の分までね」
成長した章太郎の発言に、貫太郎は声を失くした。ドギマギするだけの銀平を見ていられないあすかは
「お祖父ちゃんに負けずイケメンだけど、肝っ玉の据わり方はそれ以上かもね」
と佐紀親子をカウンター席へいざなった。章太郎は、テーブルの男性客が感心するほどスマートな印象である。
バツが悪そうな貫太郎の隣に座った佐紀が
「まったく、時代遅れの頑固な父で……ご迷惑をかけてすみませんねぇ」
と太郎や平、あすかだけでなく、客席へ向かっても腰を折った。
店内が静まる中、太郎は銀平に目配せをして、三人の前に酒の入った盃を置いた。ガッテンだとばかり、銀平は貫太郎から受け取った墨壺を章太郎の前に置いた。
「棟梁。こいつを受け取るのは、俺じゃねえですよ。章太郎さん、この墨壺は貫太郎さんの魂がこもってる看板道具だ。しっかり、使ってやってくれよ」
つや光る大黒様の肌に章太郎が、「すげえや!」と見惚れた。
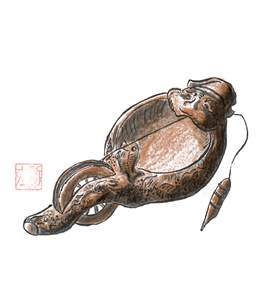 佐紀が貫太郎の肩を揉みながら、頭を下げた。
佐紀が貫太郎の肩を揉みながら、頭を下げた。
「お父さん、ありがとう。跡取りは、大丈夫だよ」
「てやんでぃ……この大将は、しょったことをしやがるぜ」
太郎に向かって貫太郎が赤くなった鼻先を啜り上げると、今しがたなじっていたテーブル席の客が
「注文住宅か……そっちに、乗り換えようかな」
と囁き合った。
福々しい笑顔に謝意を浮かべる佐紀に、銀平は目尻を潤ませて「よかった。本当に、よかったぜぇ」と頷いた。
それを見つめる平に、あすかが耳打ちした。
「銀平さんが逃がした魚は、大きいわねぇ」
ふっと苦笑しながら、平は胸の中でつぶやいた。
「……本当に釣り上げたいのは、誰かさんですよ」
章太郎が満面の笑みで弾く墨壺の糸が、心地よい音を響かせた。
