夕闇に包まれるお台場の沖合で、蛍火のように屋形船の灯りが揺れている。
いよいよ納涼船のシーズン、潮風が運んでいるのは船座敷の宴を楽しむ客たちの歓声だけじゃない。昔から屋形船に欠かせない江戸前のメゴチ、キス、アナゴなどの天麩羅を揚げる、胡麻油の匂いも漂って来る。
そんな屋形船にも、築地の火野屋は魚介類を卸している。今夜の銀平は、売り切れなかった天麩羅のネタになる白身魚や車海老を、年季の入った杉の木桶に入れてポンバル太郎へ持って来た。桶の底が浅いので、ラップをかけたネタはこぼれそうになっている。
「太郎さんよう。どれも上物ばかりだから、火の通りを抑えてサックリ揚げてくんねえか。お客さんにも、振るまってかまわねえよ」
目玉がピカピカのキスや縞模様の色がクッキリしている車エビに、テーブル席の女子会が「わぁ、ラッキー! 天然モノかしら!」と銀平へ拍手を送った。
「あたぼうよう! うちの江戸前の魚は、品川沖の朝網で揚がった一級品だぜぇ。この寿司桶に入れてりゃ、なおさら、うまそうに見えるだろ」
美人揃いの客に褒められ、悦に入る銀平が自画自賛すると、カウンター席の隅に座る中年の男が魚を盛った桶に目を止めた。静かに独酌していた男は、ほろ酔いの目元を見開いている。
太郎が、銀平から桶を受け取りながら腐した。
「まったく……これは、寿司桶じゃねえよ。こんなに縁が高いと、酢飯をこしらえるのに杓文字が引っかかっちまうだろ」
太郎の前で純米酒のぬる燗とズケのマグロを口にする平 仁兵衛も、老眼鏡を鼻先へずらして目を凝らした。
「それにしても、けっこう使い込んでいます。火野屋さんの昔ながらの道具ですか? 江戸時代の魚屋は、こんな浅い桶を盤台(ばんだい)と呼んで、天秤棒で担いで運んでましたからねぇ」
「その通りでぇ! さすが、平先生、よくご存じで。盤台を使っていたのは、あの一新太助みてえな振り売りの魚屋で、こいつはうちの銀次郎祖父さんの代から使ってる物でさ。めったに使わねえが、骨董品じゃねえ。現役の桶なんでさぁ」
一新太助の名前などテーブル席の女子は知る由もないが、飴色を帯びている古桶には興味津々といった面持ちである。
気を良くした銀平の饒舌が、続いた。
「だけど、太郎さん。おもしれえんだよ。この桶に入れた魚は、どうしてだか、時間が経つと旨味がのってくる。祖父さんの頃からお得意先の深川の寿司屋は、いまだに、この木桶の配達でなきゃ承知しねえんだ」
銀平が語ると、女子たちは、そんな馬鹿な、眉唾な話じゃないかと嘲笑したが、太郎は桶の木肌に真顔で見入っている。
ふいに、カウンターの隅から声が聞こえた。
「ひょっとして、その木桶。麹を売る盤台だったんじゃないですか。それに、元々は酒蔵の元摺り桶だと思います。桶の縁に、元を摺り下ろす櫂棒を使った傷がついてませんか?」
酒造りの専門用語を口にした男へ、太郎と平が同時に顔を向けた。女子たちは意味不明なのか、小首をかしげている。
銀平は同世代とおぼしき男に視線を合わせると、感心顔で言った。
「元摺り桶って……確か、昔ながらの生元造りの日本酒に使った、麹と蒸し米を擦り下ろす桶だよな。言われてみりゃ、桶の縁に削ったような跡が残ってんだ。こいつぁ、擦り棒でついた傷か。この桶を目にしたガキの頃から不思議だったが、ようやく納得できたぜ」
銀平の声に太郎が桶の縁へ指先を這わせると、平は頷きながら男へ訊いた。
「ためになるお話ですねぇ。失礼ですが、あなたは醸造業界の方ですか? スーツがお似合いで、ビジネスマン然としてらっしゃるが」
端正な顔立ちの男は、はにかむように表情を崩して答えた。
「ええ、今は発酵食品の会社に勤めています。祖父の代まで、麹屋をやっていたのですが、昭和の代で廃業しまして……子どもの頃、実家には、そんな半切り桶が山積みでしたから、もしかしてと思いましてね」
男は株田 稔と名乗り、実家は江戸時代の半ばから日本橋室町で麹屋を営む老舗「もやし堂」だった。もやしとは、麹菌の旧名である。酒だけでなく味噌や醤油まで、さまざまな麹を扱う商いで、先祖は麹を売る盤台用に酒蔵の元摺り桶を買い取っていた。だが、時代の波とともに発酵食品が自家製でなくなると麹屋は消えていった。“手前味噌”という言葉は各家庭で麹から造る味噌にちなんだ言葉だったと、株田は遠い目をして盃に酒を注いだ。お銚子は、空っぽになった。
テーブル席の女子たちがしんみりすると、株田を気に入ったらしい銀平は太郎へお銚子を注文し、車海老の塩焼きをご馳走させてくれと前置きして問いかけた。
「だけどよう、そんな半切り桶が、どうして、うちみたいな魚屋へ来ちまったんだろう?」
銀平は、長年の疑問を解いた株田へ嬉しげに笑みを浮かべた。
「魚屋と麹屋をつなげる存在とは、何ですかねぇ」
腕を組んで考える平に、太郎も
「塩麹を使うってのは、最近の流行りですからね。もっとも江戸時代には、俺たちの知らない麹を使った調理方法があったのかも知れません」
と桶を厨房へ運ぼうとした。
その時、玄関の鳴子を響かせて、八百甚の誠司が入って来た。遅れたことを銀平に頭を下げて詫びると、木桶の底板を見上げて叫んだ。
「あっ! 八百甚にある古い桶と同じだ!」
誠司の視線が、底板に薄っすらと残っている“室町 もやし堂”の筆書きに刺さっていた。
底板を見上げた銀平と平が、「これ、株さんの桶か!」と口を揃えた。底板が見えない太郎は桶の魚をこぼすわけにいかず、ヤキモキした顔で誠司に言った。
「いってぇ、どういうわけで、八百甚に同じ桶があるんだ。おめえんとこじゃ、何に使うってんだ?」
「へっ、へい。八百甚の先々代。つまりうちの社長のお祖父さんが、もやし堂さんてぇ麹屋がやめちまった時、先方から頂いたらしいんでさ。今は、麹を使ったうちの漬物を配達するのに使ってるぐらいですがね。それが、めっぽう漬物の味がいいそうでさ」
唐突な質問に誠司は戸惑ったが、同じ半切り桶が火野屋にあったと聞いて「いや~、驚きやした!」と目をしばたたいた。ふだんの誠司なら、美人が集うテーブル席に釘付けのはずだった。
それ以上に驚いているのは当人の株田で、唖然としたまま底板を見上げていた。
「思い出しましたよ。祖父の菊蔵は築地市場を徘徊するのが趣味で、仲の良くなった人たちに商品をお裾分けしていました。魚屋には、西京漬けの味噌を。八百屋には漬物用の麹を。それが、いつしか商売につながっていた……嬉しいなぁ。私の手元には一つも残っていませんが、こんなふうに、うちの半切り桶は役に立ってたのか。だけど、どうして魚や漬物の味が良くなるのでしょうか?」
株田の問いに、桶の持ち主である銀平は自信なさげに口をにごした。
「そ、そりゃ……俺にも分からねえけどよう。麹の神様が桶に宿ってんじゃねえか。ねえ、太郎さん!」
答えを振る銀平に誠司が情けないといった表情を浮かべると、太郎は呆れながらも、玄関扉に向かって顎を振った。
「ふっ、おっかねえ教師が来たぜぇ」
涼しい夜風とともに、饒舌な女性の声が聞こえた。人気の酒食ジャーナリストの高野あすかだと分かった女子会メンバーから、歓声が起こった。
「けっ! またタイミング良くやって来やがる」
銀平のしかめっ面にアカンベをしたあすかは、太郎から半切り桶の素性を聞くと、かつてもやし屋だった株田へ尊敬のまなざしを浮かべた。
「菊蔵さんが造っていた麹の酵素が、木桶にしみ込んでいるんじゃないかしら。いつも使ってたら魚の臭いもつくでしょうし、水で洗ってばかりだと酵素の力は消えちゃう。きっと、火野屋も八百甚も時々使って大切にしたから、この半切り桶には食材の旨味を引き出す麹の力が乗り移ったままなのね」
「なるほど、ありがとうございます。きっと祖父の思いが、半切り桶にこもっているのだと思います」
深々とお辞儀する株田にカウンターの面々とテーブル席の女子がいっせいに頷くと、銀平が愚痴った。
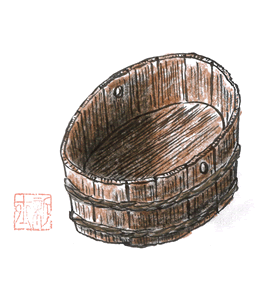 「な、何でぇ! そりゃ俺が言ったのと同じじゃねえかよ」
「な、何でぇ! そりゃ俺が言ったのと同じじゃねえかよ」
「そ、そうでやすよ! 兄貴の答えは、正解ですよ。ついでに教えて欲しいんですが、麹をもやしって呼ぶけど、ありゃ、野菜のもやしとは関係あるんでやすか?」
「うっ……ば、馬鹿野郎。そんなこたぁ……本家本元の株田さんに訊けよ!」
逃げ腰の銀平に女子たちが失笑すると、あすかがいたずらっぽく言った。
「半切り桶って、昔は赤ちゃんの風呂桶にも使われたの。つまり盥(たらい)よ。銀平さんも火野屋に昔からあった、この半切り桶で産湯を浸かれば良かったのにねぇ」
誠司が小首を傾げると、株田は「こりゃ、手厳しいなぁ」と苦笑し、太郎と平は思わず吹き出した。
「ぐぐっ! そりゃ麹の力で、俺がもっとマシな男になれたってことかよ!」
図星だと言わんばかりの爆笑が、店内に巻き起こった。
