新米のコシヒカリの収穫が新潟県で始まり、一番米が都内のデパートにお目見えしている。今年は夏に猛暑が続きながらも、雨量が多かったせいで上々の出来栄え。特A評価のコシヒカリが増えたと、売り場はPRに力を入れていた。
それは全国の酒造好適米にも言えることで、いよいよ新酒の仕込みに入ろうとしている蔵元も、俄然、気合が入っている。
「もう、杜氏さんたちの蔵入りの時期か。吟醸酒用の酒造好適米を開発している地域にとっちゃ、まさに旱天の慈雨でしたが、洪水の被害を受けた蔵元さんには、お見舞いの言葉しかありませんね」
ポンバル太郎へ届いた蔵元からのハガキを手にする太郎が、カウンター席に座ったばかりの平 仁兵衛と菱田祥一に、裏面へ印刷された復興中の写真を見せた。それは7月の集中豪雨で罹災した大分県の蔵元・大友酒造からの便りである。
かつての戦国大名。大友宗麟の血筋を継ぐ名門蔵元だが、築三百年を超えた蔵屋敷は悉く水没していた。
「28byの在庫の酒も流されちゃったんだろ。それに、蔵の中に流れ込んだ土砂も半端じゃない。こんなに環境が変わると、酒の味もおかしくなるんじゃないか?」
菱田は大友酒造の吟醸酒・由布正宗へぞっこんなだけに、気が気じゃない。さっそく、冷蔵ケースに残っている未開封の四合瓶をキープしてくれと太郎へ頼んだ。純米吟醸のレッテルには由布岳と大友宗麟の甲冑が印刷され、昔ながらのレトロな仕立てである。
両手を合わせる菱田のしぐさを止めるかのように、玄関の鳴子が大きく響いた。
「ちょっと待った! 菱田さんだけが、由布正宗のファンじゃねえぜ。俺とジャンケンで勝負だよ」
すでに昨日ハガキを読んだ火野銀平が、鼻息を荒げていた。抜け駆けは許さないという勢いなのは、銀平も由布正宗を独り占めしたいからである。
どっちも引かない顔つきの菱田と銀平に、太郎が首を横に振った。
「残念だがよ、ひと足遅かったな。その四合瓶は、テーブル席のお客さんに売れちまったよ」
拍子抜けした二人の顔がテーブル席に振り向くと、女子会らしきメンバーが気まずそうに上目遣いをした。壁際には長細い革製のケースが立てかけられ、山積みの大きな布袋には、オレンジ色の糸で“大分県剣道連盟”と刺繍されていた。
「おや、皆さんは剣道の選手ですか。凛々しいですねぇ。日本酒を嗜む剣道女子、素敵です」
目尻をほころばせる平が銀平の口から出そうな苦情を制すると、女性たちはホッとした表情を浮かべた。不満げだった菱田が、ハッとして女子会の面々に訊ねた。
「確か、先週から武道館で全国の剣道大会が開催されてるんだよね。君たちは、大分県の選手なの?」
「はい、女子チームのメンバーです。でも、今日の決勝で敗れてしまって……残念ながら準優勝ですけど、打ち上げに来ました。お楽しみにされていた由布正宗を横取りしてしまって、申し訳ありません。私たちも、大好きなんです」
女性の一人が立ち上がって、ポンバル太郎を宿泊している駅前のホテルから紹介されたのだと答えた。ショートヘアに、白いジャージの上下が似合っている。その礼儀正しさと姿勢の良さに、さすが剣道をやっているだけのことはあると、平と菱田だけでなく、斜に構えていた銀平も見入った。
太郎も感心して小芋の皮を剥く手を止めた時、玄関から鳴子の音と高野あすかの声が飛んで来た。
「もしかして、大友麗子さんじゃないかしら? 大友酒造のお嬢さんですよね? 5年ほど前になりますけど、御社を取材させて頂いた高野あすかです……確か、麗子さんは、まだ女子大生で、剣道部で頑張ってらしたわ。今も若々しくって、変わってませんねぇ」
颯爽と登場したあすかに、客席から
「おっ! BS放送に出てる、高野あすかだよ」
と声が上がった。驚いて顔を見合わせる女子たちの中、麗子はあすかに歩み寄ると
「忘れるわけ、ありません。だって、今年の水害の直後に、あすかさんはボランティア活動の情報発信にSNSを使って協力して下さったでしょ。あなたのネームバリューのお陰です。うちの両親にも励ましのお手紙を頂いたことも、ちゃんと知っています」
と両手を握り締めた。そして、大学を卒業した後は大友酒造へ戻って酒造りを修業していたが、その3年目に罹災したとうなだれた。
「へぇ、そうなんだ」と店内から声が洩れると、麗子は気丈に笑顔を見せて、あすかをテーブル席へ誘った。そして、太郎へ頼んだ由布正宗を、カウンター席のメンバーにも飲んでもらいたいと言った。
「そりゃ、ありがてえ! 今夜だけは、あすか様さまだぜ……だけどよう、由布正宗てえ銘柄は、この純米吟醸の香りや味わいにゃ似合わねえ気がするな。ちょいと古臭ぇんじゃねえか」
ご相伴に与りながら、ひと言わせてもらえばと銀平が口を挟んだ。
「でも麗子さんのご先祖は戦国大名の大友家だろ? 何だか強そうな銘柄だし、そう簡単には変えれないだろうなぁ……てかさ、正宗を銘柄にしている蔵元って、けっこう多いんじゃないの?」
由布正宗の純米吟醸を太郎から注がれる菱田が、あすかに訊いた。
聞き耳を立てる客たちから、さまざまな正宗の付く銘柄が挙げられると
「全国に、200銘柄ほどあるわ。ルーツは灘の蔵元が付けた銘柄なんだけど、そもそも武家とか侍みたいなイメージはなかったそうよ。江戸時代の庶民は文字を読めない人が多かったから、意匠だけを描く酒樽が多かったの。つまり、正宗を付けた銘柄は、明治以後に増えたの」
とあすかは菱田の思い込みを否定した。すると、麗子は頷きながらも、壁に立てかけた革袋に手を伸ばした。
「……でも、うちの由布正宗の銘柄は、この刀に由来するんです」
大事そうに麗子が抱える革袋の先から覗いたのは日本刀の柄で、鮫革を張った地肌に藍色の紐を組んでいた。あすかが思い出したかのように、声を発した。
「あっ! それって大友家のお座敷に飾っていた、家宝の日本刀じゃないの?」
その刀は、大友宗麟ゆかりの名刀であることを取材時に知ったとあすかは平たちに教えた。菱田が、飲みかけた由布正宗を吹き出しそうになった。
「うへぇ、それって真剣なのかよ?」
目を丸くする菱田に、麗子は鞘に納まった刀を革袋から取り出した。太郎や平の目に映る刀は魚鱗をかたどった黒漆の鞘を鈍く光らせ、その重厚な趣きが全員を黙らせた。
「ええ、私だけじゃないです。この女子メンバーは、全員、居合い斬りもしますよ」
とほほ笑みながら、麗子は家宝の“由布正宗”の話を始めた。先祖代々が受け継いできた刀は、戦国、江戸、明治、大正、昭和の時代に起こった災難から、大友酒造を事あるごとに守った。そして、火災や空襲などの人災のみならず、天変地異の際にも行方知れずにならず、必ず、蔵元の手に戻って来た。実際、1年前の熊本地震や今年の九州洪水で大友酒造は罹災したが、由布正宗は瓦礫の中から見つかり、蔵元を支えるべく威光を放っている。その力強い存在のお陰で、我が家は代々、生き抜いて来た。だから、復興中の今こそ、由布正宗の銘をおろそかにはしない。この剣道大会の居合試合に家宝の刀を持ち出したのは、蔵元の復活を誓う意味もあったと問わず語った。
由緒ある由布正宗の刀に視線が集まるとともに、店内の声は静まった。
「そんな歴史が、由布正宗の銘にはあるのね。実は、刀を思わせる銘柄って、武士は嫌ったの。あの妖刀・村正は将軍の徳川家康に災いをなす刀だったし、血を吸う刀の銘を酒の名前にするのって悪趣味よね。だけど、由布正宗は、まったくちがうのね」
あすかが刀の鞘に触れながら、ウットリとして冷酒グラスを口にした。
「きっと、どちらの蔵元さんにも、不思議な銘柄の由縁があるのではないでしょうかねぇ。流行や人気ばかりが叫ばれる昨今ですが、やはり、銘酒のルーツや文化も大切にしたいですねぇ」
冷酒グラスを飲み干した平に、テーブルの女子たちだけでなく、ほとんどの客席が相槌を打った。
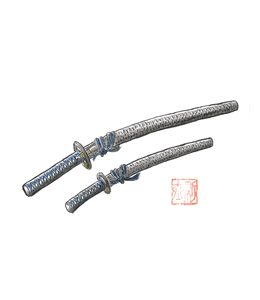 「あ、あのよう、麗子さん。お願えだから、その刀を抜いてみちゃくんねえかい? 名刀てぇのを、ひと目は見ておきたくってよう」
「あ、あのよう、麗子さん。お願えだから、その刀を抜いてみちゃくんねえかい? 名刀てぇのを、ひと目は見ておきたくってよう」
おもねる銀平の禿頭を、あすかが引っぱたいた。
「こんな店の中で真剣を抜くなんて、できるわけないでしょ! それこそ、銃刀法違反よ」
渋い顔の銀平に、麗子がいたずらっぽい口調で耳打ちをした。
「じゃあ、こちらの二階を借りて、お見せしましょうか……ただし、うちの由布正宗には、ちょっと、いわくがあるんです。人柄の良くない相手には、災いが起こるそうなんです」
途端に、太郎だけでなく平と菱田も、破顔一笑して口を揃えた。
「そりゃ、いけねえや! 絶対に、人柄は良くねえから」
イジられてポカンと口を開ける銀平を、店内の笑顔と由布正宗が見つめていた。
