肌寒くなった通りを歩く男たちの誰もが、「あったかい鍋を食いてえな」とつぶやくような夜だった。
その一人である右近龍二がポンバル太郎の玄関に近づくと、粕汁らしき匂いが漂っている。
「おっ! ラッキー。そろそろシーズン到来と思ってたんだ」
手をすり合わせながら龍二が杉の扉を鳴らすと、カウンター席にゆるゆると湯気が立ち昇っていた。その白い移ろいの中で、火野銀平の剃ったばかりの頭が青白く光っている。
銀平の隣に座る白髪の男に、龍二は見覚えがあった。いつか平 仁兵衛とやって来ていた能登杜氏の矢口だった。
二人は酒粕仕立ての鍋を前にして真剣な顔で問答をしているが、鍋の具材がもう煮えているように見えた。
「こんばんは、うまそうな鍋ですねぇ。ひょっとして、矢口杜氏じきじきに搾った酒粕を使ってたりして!」
やにわに首を突っ込んできた龍二へ矢口が驚きながらも会釈すると、会話をさえぎられた銀平が口を荒げた。
「この野郎、今、真剣に矢口さんの話しを聴いてんだから邪魔するんじゃねえよ!」
「で、でも銀平さん、鍋が煮えてます。粕の風味が変わっちゃいますよ」
龍二が鍋を指さすと、銀平が目を丸くして叫んだ。
「わっ、わわ! 煮立ってるじゃねえか!」
矢口もしまったとばかりに白髪の頭を掻いて、龍二に向かってはにかんだ。
すると厨房から出て来た太郎が、眉をしかめて言った。
「銀平! てめえの方が、この野郎だよ! 矢口さん自ら、ひと夏冷蔵保存してくれた酒粕なんだぞ、もっと大事に味わえってんだよ」
抜かったとばかりに銀平はあわてて鍋に追い出汁を足そうとしたが、矢口がその手を止めた。
「大丈夫ですよ。少しばかり火が入ったとしても、この粕は味がしっかりしてコクもあります」
それを聞いた龍二や銀平だけでなく、すでに酒粕鍋を食べているテーブル席の客たちも
納得の表情で頷いた。
すると、玄関先から声が飛んで来た。
「あ~、いいなぁ酒粕鍋。太郎さん、私は一人用の小鍋をお願いしま~す!」
声の主である高野あすかを見るなり、太郎は手招きして矢口に紹介した。
すでに矢口は、あすかが蔵元の娘であることを聞き及んでいた。そして、お互い日本酒と深い関係にある立場と、矢口はあすかに握手を求めた。
手を握る二人を見ながら、銀平が龍二に耳打ちをした。
「おい、龍二……蔵元の娘と名杜氏が語るうまい酒粕ってのを、聞いてみたくねえか」
「それって、俺にそういう流れに仕掛けろってことですか? 銀平さんの目、そう言ってますけど」
「分かってんなら、とっととやれよ」
声をひそめる銀平にせかされ、龍二は咳払いをして矢口に話しかけた。
「矢口さん、ひと口に酒粕と言っても、味わいや形がいろいろなんでしょう? お酒が大吟醸から普通酒まであるように、それを搾った粕だからですか?」
龍二は至極当たり前の質問をしたが、改めて名杜氏からの直言も聞いてみたかった。
それでもテーブル席の新顔の客たちにとって酒粕の話しは初耳らしく、興味津々の面持ちでグラスを傾けている。
「確かに、ひと昔前まで全国で売られている酒粕は“板粕(いたかす)”がほとんどでしたね。平べったい奴です。いわゆる薮田式(やぶたしき)という搾り器の板に貼り付いた粕をはがすから、あんな形になります。さらに塊のような“バラ粕”は、佐瀬式(させしき)と呼ばれる旧来の箱型の搾り器を使った粕。いわゆる、酒船搾りですね。バラ粕は板粕よりも厚みがあってしっとりしてますから、コクや旨味が強いんです。そして、酒袋で吊るして搾る大吟醸や純米大吟醸などの“吟醸粕”は酒が粕にたっぷりと残っている分、香りも高くなります」
「へぇっ、そうなんだ! おもしろいですね」
若いサラリーマン客の一人が声をあげると、あすかの小鍋を準備しながら太郎が口を開いた。
「だから酒粕はいろいろな料理に応じて、使い分けることができるんですよ。例えば、俺は今夜の鍋にはバラ粕を使っています。板粕は炙って裂き、シラスと刻みネギを加えてショウガ醤油で味付けすれば、安くてうまい酒の肴になりますよ。吟醸粕は鯛や鰆の身を一晩それに漬け込めば、贅沢な粕漬けになる。それと、和風ソースにも使える」
感心しきりの客たちを目にする銀平と龍二が、思う壺の表情でほくそ笑んだ。
すると、あすかが口を挟んだ。
「でも、粕はそもそも産業廃棄物だった。昔は、それほど日本酒がたくさん造られてたの。
しだいに酒粕が売れるようになると、全国の小さな蔵元から大きな酒造メーカーが粕を大量に買いつけることもあった。実際、私の実家の酒粕も半分ぐらいはそうしていたもの」
銀平と龍二が盃を口元に止め、あいまいな声で答えた。
「なるほど……酒の桶買いってのは知ってるけど、酒粕まで買い付けていたとはなぁ。ただ考えようによっちゃ、いろいろな蔵元の酒粕をブレンドしてるわけだから、贅沢な味かもな」
「そうでしょうか。僕は、やはり一つの蔵元の酒粕こそが純粋な味だと思いますよ」
銀平の声にテーブル席の若い男たちは頷いたが、カウンター席の隅に座る年配の日本酒ツウは龍二の言葉に拍手を送った。
黙ってなりゆきを見つめていた太郎が、銀平と龍二へ小さくため息を吐いた。
「ふっ……いいじゃねえか。どっちって断言できねえのが、酒粕の魅力なんだよ。それよりも、お前たちが逆立ちしても食べられない幻の鍋が蔵元にはある」
太郎はその語尾を矢口とあすかに投げながら、ほほ笑んだ。
「あっ……あれですね。確かに、あれだけは難しいですねぇ。と言うか、あの鍋は蔵人の特権ですよ」
矢口が繰り返し首を縦に振ると、あすかも思わせぶりな口調を銀平に向けた。
「あの鍋だけは、無理ですよねぇ。私、子どもの頃に杜氏の膝の上に座って、よく食べました」
「ええい、あすか! もったいぶらずに言いやがれ!」
しびれを切らした銀平は、熱い粕汁を飲み込もうとして火傷しかけた。その時、龍二がポツリとつぶやいた。
「泡汁鍋ですね」
「泡? な、なんだ、そりゃ?」
舌を氷水で冷やしながら銀平が視線を向けると、太郎は右手を矢口に差し伸べ、その答えを譲った。
「泡汁鍋は、ずいぶん昔から酒蔵で食べられていた料理ですよ。残り物の野菜を味噌仕立ての鍋にして、そこに酒のモロミから湧き上がった泡を入れるんです。この泡は、酒の発酵中に酵母の菌が集まって盛り上がってきたものです」
その味は酒粕の鍋をいっそうまろやかにして旨味を加えた感じで、身体の芯からぬくもるのが特長だった。かつて自分が若かりし頃は、一晩中モロミのタンクから泡があふれないように“泡番(あわばん)”をしたものだったと矢口は懐かしげに語った。
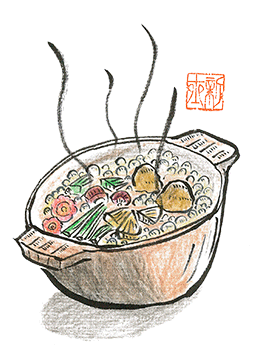
どことなく泡汁鍋のイメージをつかんだらしい客たちに、あすかが言葉をつないだ。
「でも、泡ってすぐに消えちゃうし、酵母だから時間が経つと味が変わっちゃうでしょ。だから、その場ですぐに食べなきゃダメなの」
「なるほど。それで冬場の蔵元でしか食べられない、旬の味ってわけか」
龍二が納得すると、テーブル席の若い客があすかに訊ねた。
「あの、僕たちが酒蔵へ見学に行ったら、食べられますかね?」
その答えを銀平が奪った。
「そりゃ、あんたダメだろ。だってよ、酒の泡が出てるタイミングの見学なんて約束できねえよ。しかし、実は俺も食ってみてえんだよなぁ」
すると間髪入れず、あすかのしっぺ返しが飛んで来た。
「あら、銀平さんなんて、いつも仕事の段取りで泡食ってばかりでしょ?」
思わず粕汁を噴出しそうになる客たちの笑いが、白い湯気に包まれていた。
