まばゆい夏の陽射しに焦がされたアスファルトを、夕立ちが濡らし始めた。大粒の雨が、通りを彩る鉢植えの紫陽花を震わせている。
ポンバル太郎の扉が開くたび蒸した風が入り込み、ほぼ満席の店の熱気を上げた。客席で注文を取っている半被姿の剣は、テーブル席の女性たちにつかまっている。
「かわいいね~。いくつなの? お父さんのお手伝いか、えらいね」
「ねぇ、お姉さんと写真撮ってもらえないかなぁ。ブログとかに載せてもいい?」
近頃は日本酒好きな女性客が増えて、客席のファションも彩りが変わってきた。それを意識してか卓上やカウンターの上には、紫陽花に似た薄紫の花が活けてある。
剣がちやほやされるシーンに、カウンター席の平 仁兵衛は「あやかりたいですねぇ」と目を細めた。その隣で、苦虫をつぶした顔の火野銀平が純米吟醸のグラスを傾けている。
「けっ! ませガキには困ったもんだ。太郎さん、ちゃんと躾けをしとかねえと、ロクな男にならねえよ」
厨房で、ゆず大根の冷製を鉢によそう太郎が、それを鼻であしらった。
「お前に言われたかねえな。まっ、お前よか剣の方が女に接するのは、うわ手だよ」
「銀平ちゃん、ひがまない、ひがまない」
ぬる燗の盃をなめる平も、嬉しそうに銀平をいじくった。
「ひっ、ひがんでなんかねえよ! それとよ、今日のおススメ料理って、大根ばっかじゃねえか。旨いからって、揃えりゃいいてもんじゃねえだろ」
図星を突かれた銀平は、矛先を変えて杉壁のおススメメニューを指さした。白いボードにはブリ大根、大根の田楽ステーキ、大根とエビのごまサラダ、ふろふき大根など八つの献立があった。女性客から「ヘルシーね!」と人気を呼んでるのも、銀平は気に入らない。
ついでとばかり文句を口に出しかけた時、カウンター席の端からつぶやきが聞こえた。
「まったく、お前のためにあるようなメニューだな」
「はは、そうですね。偶然にしては、できすぎです」
低い声に銀平が顔を向けると、半時間前から座っている二人の男がボードを見上げて苦笑していた。二人はようやくお通しのづけマグロを食べ終えたところだったが、すでに顔が赤い。
上司らしき白髪まじりの男はネクタイをゆるめ、若い男に純米酒のお銚子を傾けた。それを盃で受ける三十路がらみの男は今風の黒いスーツ姿で、中間管理職といった印象だった。
「ところで、梶谷。本当に大丈夫なのか……個人農園って、そんなに儲からないだろ?」
「ええ、でも決めたんです。本物の朝採り野菜を、たくさんの人に食べてもらいたいんです。宮瀬部長には本当にお世話になって、感謝しております」
どうやら退職の辛気臭げな話しだったが、“個人農園”と“朝採り野菜”の言葉に銀平と平は興味を引かれた。
聞き耳を立てると、梶谷は練馬の西大泉に先祖代々の農地を持っていた。そこで、自身が今勤めるスーパーマーケットに流通している練馬大根ではない、本当に練馬の土地で作る大根を中心に有機農業を進めたいと言った。
そして、その土地を個人農園としても貸し出し、練馬大根を推奨していきたいと語った。
「うむ……だが有機の土地作りは、そんなに簡単じゃないぞ。どんな方法を考えてるんだ」
「そうですね。兼業農家の父と相談して、昔ながらの干しかを肥料にしようかと思っています」
梶谷が腕組みをする宮瀬に熱く語ると、テーブル席の女性の嬌声をよそに、カウンターの空気が静まった。
ふいに、沈黙する二人の間へ湯気が昇った。太郎がふろふき大根の皿を置いていた。
「よかったら、味見してみませんか。これ、正真正銘の練馬大根です」
そのタイミングの良さに銀平と平が顔を見合わせ、小さく頷いた。
戸惑っている梶谷に宮瀬はふっと笑みを洩らし、「ありがとう、頂きます」と太郎へ会釈した。箸で割った大根はやわらかく、二人の口の中でとろけた。しみ出すダシの旨味と練馬大根の甘さに、赤ら顔の梶谷が唸った。
「これです。この甘味が有機で作った練馬大根の味ですよ。ご主人、この大根はどこで仕入れたんですか?」
「おい梶谷、失礼だよ。ごちそうさまが、まず先だろうが」
先に腰を上げて梶谷をせかし、太郎へ頭を下げる宮瀬の人となりに平が目じりをほころばせた。
銀平が、冷酒グラスを飲み干して言った。
「まったくだ、あんたは礼儀がなってねえ。言っとくけどよ、野菜だろうが魚だろうが生半可な気持ちじゃ、本物なんて扱えねえぜ。この店の大根を作ってる有機農家は、練馬じゃねえ。あきる野市なんだが、苦労して土地を肥やして昔の練馬大根の畑と同じになったんだよ」
途端に梶谷は反応して、銀平の方へ身を乗り出した。
「そっ、それって、どんな工夫をしてるんですか? やっぱり、肥料がちがうんでしょう?」
「おっ、おいおい! 梶谷、落ち着け」
宮瀬が両肩をおさえて座らせると、飽きれて物が言えない銀平に変わって平が口を開いた。
「梶谷さん、焦りなさんな。気が逸るのは分かりますが、結果をすぐに求めるのは今の世間の良くないところですよ。どんな物作りにも、過程が大切です。いろいろな課題を乗り越えてこそ、本物は生まれるのですよ。お聞きしたところ、練馬大根や有機について、梶谷さんの見込みはどうも甘い気がします」
平のたしなめはテーブル席の女性客の耳にも届いたが、憮然とする梶谷とちがって彼女たちは頷きながら大根料理を口にしていた。
調理をひと段落させた太郎が、梶谷の前に立った。右手に持つ土まみれの大根が、青々とした葉をつけている。
「この練馬大根は、そう一朝一夕にできませんよ。有機の畑は、私の友人が営んでいます。三年前まではごく普通の農業でしたが、ある物を土作りに使いました。それは、東京湾で獲れるイワシの頭とワタ、骨を手に入れて、それを発酵させてから土に混ぜるんです」
「なるほど、地産地消ですね。でも、そりゃ大変だ。普通の肥料じゃないから、土に混ぜるのも人手が要りますね」
感心する宮瀬に、声をくぐもらせた梶谷が三度、相槌を打った。いつの間にか、その後ろに剣が立っていた。
「ええ、だからここにいます平先生と銀平、息子の剣、他の常連客の方々と一緒に畑づくりを手伝ったんです。でも、もっと難題があった。梶谷さん、それは何だと思いますか?」
思案顔の梶谷が、はっとして答えた。
「分かった! イワシの頭やワタが手に入りにくいこと」
「いえ、それは築地で魚卸の火野屋をやってるこの銀平に頼めば、知り合いの魚屋から充分なほどもらえます……ただ、それをどこで発酵させるかです」
胸をそらせる銀平を一瞥した太郎は、答えを続けた、イワシの頭やワタ、骨は猛烈な発酵臭を発生させる。ポリバケツやビニール袋などの容器では、ガスがたまって破裂しかねないし、臭いも住民への環境問題を引き起こしてしまう。そこで畑の一画に深い穴を掘り、ガスが少しづつ抜ける巨大な麻袋を埋めて発酵させたと太郎は解説した。
ひとしきり聴き終えた宮瀬が、肩を落としている梶谷の背中を叩いた。
「しっかりしろ! 結果よりもプロセスだって、今、教えて下さっただろ」
その時、梶谷の横に剣が近づいて、カウンター上の紫陽花のような花を指さした。
「これ、練馬大根の花なんだ。普通の農法だともう咲き終わってるけど、その有機農家さんは時間をかけて育てるから、まだ咲いてるんだ。今度、僕たちと一緒にそこへ行ってみませんか」
剣の笑顔と咲きほころぶ大根の花に、梶谷は相好をくずした。
「うん、ありがとう。俺、大根の花も知らないなんてダメですよね……あの、ご主人。またお叱りを受けそうなんですが……」
と梶谷が言いよどむのを、太郎がほほ笑みで制した。
「おっ、おう! 任せときな。その時がくれば、きっちり用意してやるよ」
意気に感じた銀平が胸を叩いて即答すると、テーブル席の女性客から拍手が起こった。
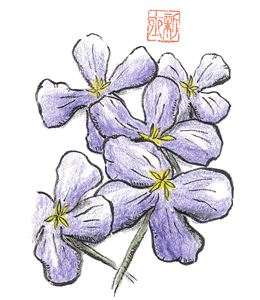
耳まで真っ赤にする銀平の脇腹に剣が肘鉄を入れると、調子に乗ってさらに口走った。
「お嬢さんたち! どんどん注文して、真っ白い大根みたいになってねぇ」
途端に女性たちが表情を曇らせ、平と太郎は情けないとばかり顔を横にふった。
「それって、私たち、大根足ってこと? 失礼しちゃうわ!」
「えっ! あっ! そ、そういう意味じゃなくて、白い肌ってことで……」
たじろぐ銀平に、梶谷と宮瀬が思わず吹き出し、剣がため息まじりにつぶやいた。
「まったく、銀平さんって、本物の大根役者だね」
客たちの笑い声の中で、ほのかな大根の花が揺れていた。
