雨脚がめまぐるしく変わる夜、都内の気温は下がり、湿度も80%まで上がって肌寒さすら感じた。ポンバル太郎のカウンター席では、平 仁兵衛がいつもより温めた上燗の純米酒を傾け、濡れそぼってやって来た火野銀平は鼻水を拭きながら相伴にあずかっている。
「今年はエルニーニョ現象で、ゲリラ豪雨が続くらしいですねぇ」
平の声に、返杯をした火野銀平が手元のスポーツ新聞に指を置いた。その記事は、冷夏の兆しでビールや発泡酒の売れ行きが伸び悩んでいると報道していた。
「先生、もう影響は出てますよ。築地の魚の入りも、おかしくなっちまってる。カツオはガタ落ちだし、イサキやワラサの近海物も安定しねえ。野菜もそうなんじゃねえの、太郎さん?」
銀平は空になったお銚子を振りながら、厨房で肴を盛り付ける太郎に訊いた。
太郎の答えは、菜箸の動きに合わさって返ってきた。
「ああ、五年前のエルニーニョによく似てる。その内、野菜も値段が上がってくるだろ。でも、工夫しだいで安くてうまい肴はできる。こういう時こそ、目で楽しむ旬の味ってのを大事にしなきゃいけねえよ」
太郎の答えに銀平は「もっともだ!」と相槌を打って、火野屋でも得意先の料理屋に、夏バテ予防も兼ねて、イワシを使った梅肉煮など安い肴を提案してると自慢した。
「じゃあ、この冷や奴はどうだ」
太郎はカウンター越しに、緑色の平らな器を手渡した。しつらえていたのは、木綿豆腐の涼しげな肴である。
冷や奴と聞いて肌寒さを感じていた銀平は顔をしかめたが、それを見た途端、視線を釘付けにした。
水滴を肌に浮かせる立派な竹の割り皿に、白い豆腐と柚子皮の黄色が映えていた。豆腐の下にはざらめ氷が敷かれて、新緑のもみじ葉が刺してある。薬味は輪切りした竹筒に、山椒、柚子味噌、葉わさび、梅肉など彩りも豊かに並んでいた。
「う~む、みごとな初夏の風情ですね。これを出されたら、誰だって日本酒を飲みたくなります」
唾を呑んでいる平に、銀平も反応した。
「ざらめ氷が解けても、竹の器の中には冷たい水が残る。最後のひと口まで、うめえ冷や奴が食べられるってわけか……でも、太郎さん。こんな立派な竹の器、いつの間に手に入れたんだよ?」
節回りが銀平の二の腕よりも太い、孟宗竹を使った深い皿だった。
平と銀平が純米酒で舌を湿らせ、箸を手にした時
「それは、私のしわざで~す。こんばんは太郎さん、お連れしましたよ」
と扉の鳴子の音を響かせて、雑誌記者のジョージが現れた。たどたどしい日本語の後ろに、作務衣と雪駄履きの若い男が立っていた。長髪を後ろに束ねた三十歳頃とおぼしき容姿で、アート系の雰囲気に彼を見る平の目尻が細くなった。
「まさかジョージが、この竹を用意したってわけじゃねえよな? ようすからして、そこにいるお客さんってわけか」
銀平の誰何を受けたジョージが、男の背中を押して紹介した。
「イエス! 福島県の取材で知り合った、竹野口 亮さんです」
その名前に銀平は「おいおい、できすぎじゃねえか」と冷やかしたが、平は竹野口に見憶えがあるのか、盃を口元に止めていた。
「お待ちしてましたよ、竹野口さん。銀平、この人を、あなどるんじゃねえぜ。俺が、お招きしたんだ」
と太郎がカウンターから出て竹野口にお辞儀をすると、銀平は視線を泳がせて「す、すいません。失礼しやした」と頭を掻いた。ジョージがしてやったりとばかりに、笑いを噛み殺した。
「いえ、山出しの田舎者ですから。不作法があったらお許しください」
太郎からカウンター席にいざなわれた竹野口は会釈を返し、手に提げた袋から小さな和紙包みと細長い和紙包みを取り出した。
そして厨房に案内されると竈(かまど)の炭火を確かめ、長い和紙包みを開いた。出てきたのは、節二つ分の太い孟宗竹だった。
「な、なんだよ? 竹を焼こうってのかよ? 危なっかしいことをやるじゃねえか」
銀平が怪訝な顔でとがめると、ジョージは対照的に満面の笑みを見せた。
「まぁ、見ていて下さい。サプライズな酒を飲めますから」
竹野口が竈に孟宗竹を差し込むと、チャプリと小さな音が聞こえた。
それを耳にした平は合点がいったのか、カウンターに置かれた小さな和紙包みに手を伸ばした。包みには竹を鋸挽きした盃が入っていて、その肌に「竹慈童(たけじどう)」の銘が刻まれていた。
「やはり、そうでしたか……今夜はまた一つ、いい御縁が頂けそうですね」
竹盃を手にして独りごちる平に、銀平がおもねった。
「せ、先生。もったいぶらずに教えてくださいよ。あの人、有名なんすか?」
竈の竹が、パチンと音を立てた。その余韻を楽しみながら、平が口を開いた。
「あの人は竹を使った器だけじゃなく、竹とともに生きている方です。雅号は竹慈童。阪神淡路大震災の後では神戸の六甲山に育った竹で鎮魂の庵を作り、被災者の心を癒しました。東日本大震災の時は福島や宮城の竹林を訪れ、竹の燈篭を作って亡くなった方たちを弔った。……あれから、ずいぶん歳月が経ちました。世間は、罹災も竹野口さんもしだいに忘れていますねぇ」
今も福島県に留まって創作活動を続けているはずだと、平は純米酒の盃を空にした。
また竹の皮が爆ぜる音がすると、「そろそろです」と竹野口が竈から竹を取り出した。薄い煙を立ち昇らせる孟宗竹には、二つの竹軸で栓がしてあった。
太郎がそこへ錐で穴を開けると、シュッと音がした。とたんに、お燗した酒の匂いと竹の爽やかな香りがもつれ合い、銀平が思わず声を発した。
「いい匂いじゃねえか。爽やかで、落ち着く香りだ」
「はい、私は月を眺めながら、この“かっぽ酒”を味わうのが好きです。……先の震災で陸前高田の松林や神戸の杉並木が倒されましたが、竹は根を張って頑張りました。過去数百年ごとに繰り返された大災害でも竹林は生き残り、その折々に、鮮やかな色で被災した方々を励ました。そして、このかっぽ酒の香りに癒されました。だから、私はこれからもずっと、この竹酒を大切にしていきます」
月と竹は、かぐや姫の逸話からも日本人の心に深く残るモチーフだと、竹野口は語った。
日本文学にのめり込み、中学で竹取物語を学んだ頃、竹に魅せられるようになった。竹野口の姓にも不思議なえにしを感じながら、竹林を散策する旅が趣味になった。そして、奥飛騨の囲炉裏端で知ったのが山里のかっぽ酒だった。
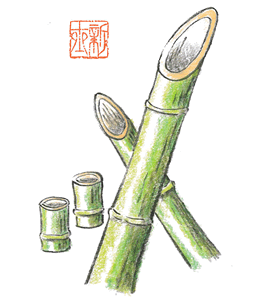
竹野口の話しがひと区切りすると、太郎がかっぽ酒を竹盃に注いだ。
カポッ、カポと心地よい調べに、ジョージが「とても美しい、日本の風情です」とつぶやいた。
「忘れちゃならねえ日本人の心も、注いでくれる酒だな」
「……かぐや姫みたいな女性もそろそろやって来る頃ですし、彼女にかっぽ酒を注いでもらって、癒されましょうかねぇ」
平が竹盃を手にすると、それを待っていたかのように扉の鳴子が鳴って、全員の視線が集まった。
「ハックシュン! 今夜は涼しいですねぇ……あら、それとも私の噂、してました?」
高野あすかの登場にジョージが手を叩いて喜ぶと、銀平はゲンナリした顔で
「俺は癒されるんじゃなくて、いじられちまうよ」
と肩を落とした。
それを苦笑するかのように、竹の中の酒が小さな音を立てた。
