木枯らし一番が、黄金色に染まった外苑の銀杏を揺さぶっていた。都内の街路樹も尖った梢を見せ始め、晩秋の夜風に家路を急ぐ人たちはコートの襟を立てている。
ポンバル太郎の扉を開ける客は、誰もが肩をすくめたまま燗酒を注文した。おかげで太郎は湯煎する手を休める暇もなく、錫のチロリの数は足りない。買い足した辛口本醸造の一升瓶も、今日だけで三本空いていた。
残りわずかな瓶に太郎が舌打ちしていると、空いた玄関扉の隙間から見慣れた顔が覗いた。
「ああ~、寒かねぇ。太郎ちゃん、熱燗とあったかい料理ば、たっぷり作ってもらえんね」
手越マリの声はいつになく弱々しく、かじかんでいた。太めの体形でも、丸まっている背中が今夜は目立っている。
だが、その後ろから現れた巨漢に客たちの視線が貼りついた。カウンター席でほろ酔いの菱田祥一もギョッとした顔で、盃から純米酒をこぼした。
「でっ、でかい! ひょっとして、関取かよ? あっ、まだ髷は結ってねえな」
190㎝近い長身に肩まで伸びた黒髪、胴回りは菱田の二人分以上もある若者が、雪駄に浴衣一枚で立っていた。この寒空の下には、ありえないスタイルだった。
切れ長の目尻がマリによく似ている。
「いいや、まだ十両にも手が届いてなかよ。あたしの甥っ子で、博多出身の中洲錦ばい。中学を去年卒業して、一人で博多から上京して相撲部屋に入ったと。東京にいる親戚は、あたしだけたい」
客席からため息が洩れる中、菱田祥一は中洲錦を見上げたまま椅子を二つ合わせ、隣の席へうながした。椅子がメリメリ音を立てると、鬢づけの椿油の香りがカウンターに漂った。
腕組みする太郎が、中洲錦の体躯を見つめながら訊いた。
「マリさんに、こんな甥子さんいたとはねぇ。でも、何だか顔色が良くねえな。相撲取りのしきたりで薄着はしかたねえにしても、風邪気味じゃなのかい?」
それに答えるかのように、中洲錦は赤っ鼻をハンカチで挟んで大きな音を響かせた。粗忽な鼻のかみ方にテーブル席の客たちが一瞬、唖然とすると、菱田がマリを気遣った。
「こんな夜は、鍋がいいよ。それにマリさんの地元には、精のつく鍋料理があるじゃないか」
「うちの地元ね……九州の精がつく鍋っちゃ、モツ鍋たい。うん、中洲錦ももうすぐ始まる九州場所までに体を治すっちゃ。ニンニクとニラがよう効くばい。太郎ちゃん、お願いできるとね? この子、なかなか成績が伸びんけんねぇ」
無言で頷くだけの中洲錦を見つめるマリの目元が、母親のようにゆがんでいた。
太郎は、中洲錦の気弱さを感じた。相撲取りとしての気迫のようなものが、幼さを残す面ざしに足りない気がした。
「おっ! それなら俺もご相伴に与りたいなぁ」
菱田も、物欲しげに太郎を見返した。だが、太郎は首を横に振り、マリたちへ申し訳なさげに答えた。
「あいにくだが、うちじゃ、モツ鍋はやらねえんだ。どうしてもニンニク、ニラの強さが、日本酒の香りや旨味を消しちまう嫌いがある。唐辛子を入れ過ぎりゃ、舌が麻痺して、なおさらだ」
太郎の断りに中洲錦が肩を落とすと、マリがその横顔を心配そうに見入った。菱田は自分が口火をきったせいだと思い、話しを丸めかけた。
「なるほどなぁ……言われてみりゃ、そうかも。てことは、できる鍋は寄せ鍋、魚ちり、ちゃんこ鍋ってな感じか」
菱田の言葉に、テーブル席の客たちも頷いた。
だが、マリは納得のいかない面持ちで反論した。
「そりゃ、人の好みによるたい! 太郎ちゃんが言ったのは、あっさりした淡白な鍋ばかりやなかと。ばってん、東北には濃い味噌のきりたんぽ鍋があるし、岐阜には八丁味噌の辛い猟師鍋に合うにごり酒があるばい! だったら、モツ鍋に合う日本酒もあってしかりたい!」
興奮するマリに驚く中洲錦の鼻先から、鼻水がしたたった。可愛い甥っ子を思う一心から、マリはやけになって太郎につっかかった。
飛び火するのを避けようとテーブルの客たちが視線をはずすと、太郎が追い打ちをかけるように、きっぱりと答えた。
「にごり酒にしても、清酒にしても、モツ鍋の味を包むほど甘いか、負けないほど辛いかの両極端になる。例えば、辛い酒なら超ドライ系だ。日本酒度が+17~20じゃないと俺は合わないと思う。ただし、そこまで酒度が高くなると米焼酎に似てくる。残念ながら、その手の酒は、うちに置いてねえ」
太郎の断言に菱田が頭を抱えると、マリは椅子から立ち上がって食い下がった。
「うちは中洲錦に元気ばつけたいと! いったい、どんな鍋を食べさせてくれるね!」
不穏なムードに客たちの囁きが洩れた時、玄関から威勢のいい声が響いた。
「マリさん! そいつぁ、俺が答えてやるよ。あらよっと!」
カウンターの内外で対峙している太郎とマリの間に、火野銀平が手に提げる大きなビニール袋を置いた。取り出したのは脂ののった魚の白身で、かなり大きな腹の切り身だった。
魚体はおそらく1メートルを超すにちがいないと、菱田やマリの素人目にも分かった。
「こ、これは、アラたい!」
ずっと口を閉じていた中洲錦の太い声が、店の中に轟いた。割れ鐘のような響きに、銀平は立ちくらみを覚えるほどだった。
「いっててて! 鼓膜が破れちまわ。ちいたぁ、遠慮しろよ。そんなこっちゃ、関取の風格なんて身につかねえぞ……そうだよ、今朝、玄界灘で揚がったアラだよ。これを食えば、あんたも元気になるだろう。下っ端力士じゃ、そうそう口にできねえご馳走だからな。どうでぇ、マリさん。タイミングがいいだろ」
アラを知らないのかキョトンとするテーブル席の男たちへ、聞こえよがしに銀平がウンチクを続けた。
アラは秋から冬にかけてが旬で、中でもアラ鍋は福岡県を中心に鍋料理の王様として珍重されている。千葉や和歌山の海で獲れるクエに似ているが、その旨さは別格と言われていて、脂ののりや食感がすばらしい。玄界灘の潮に揉まれることで、九州のアラは身が抜群にしまるのだと声を高くした。
「銀平、ありがとうねえ。今夜のあんたは最高たい! 太郎さん、さっそく頼むばい。よかとね、中洲錦」
中洲錦の広い背中をさするマリは、銀平へ言葉だけの礼を返した。それを気に入らない太郎がアラの身をマリたちの前にドスンと置いて、語気を強くした。
「そうか。でもよ、クエ鍋を食ったからって、中洲錦の体調が治るかどうかは分からねえよ。問題は、風邪気味なんじゃねえ。マリさん、あんたが中洲錦を可愛いのは分かるが、もう、いっぱいしの男なんだからよ。手を離してやりなよ。過保護は、勝負の世界じゃ仇になるぜ。それは、あんたが生きてる水商売でも同じだろうが」
二度目の諫言に、クエ鍋の話しが台無しとばかりに菱田はカウンターにうつ伏せた。
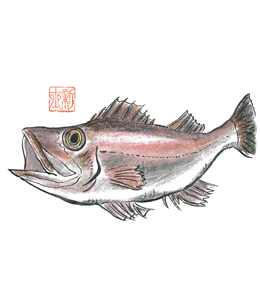
しかし、図星を突かれたマリは反論しなかった。
「そ、その通りばい……よし、これを機会に、あたしはお前としばらく逢わないよ。自分の力で、博多場所を頑張ってみんしゃい。今夜は、壮行会ばい。アラ鍋ば食うて、馬力をつけるたい!」
しおらしくなったマリが福岡の純米酒を頼むと、太郎は中洲錦の座るカウンターに清め塩を盛って、片口に酒をなみなみと注いでやった。
「ごっちゃんです!」
中洲錦がマリにお辞儀する姿に、太郎はほっとした顔でアラ鍋を造り始めた。
銀平と菱田が親指を立て、マリに向かって声を合わせた。
「ついでに、俺たちもごっちゃんです!」
「どすこい! この太っ腹に、まかせるたい!」
関取のようにマリが自分の腹を叩くと、中洲錦の元気な笑い声がポンバル太郎に響いた。
