紅色を忘れたまま朽ち葉を落とすもみじに、通りを過ぎて行くサラリーマンたちから、ため息がもれた。
いい年をしたオヤジにしても、心なしか、寂しさがよぎる晩秋。澤井も公園を一瞥しながら、小さく息を吐いた。
「もうすぐ12月……風情も無いまま、新しい年かよ。まったく、日本はどうなっちまうんだろうねぇ」
独りごちた声に相槌を打つかのように、「カァ~、カァ~」とカラスの声が響いた。
マチコの玄関先に立つと、いつになく静かだった。
「な~んか、今夜はやけに寂しい気配だなぁ」
澤井が気にしつつ格子戸を開けると、予想に反してカウンター席にはズラリと常連客が並んでいた。
「な、何だよ、みんないるのか。お通夜みたいに、静かじゃないの?」
そう問いかけても、松村も、宮部も、軽く会釈を返すだけで、声が無い。
見ると、口いっぱいに何かを入れているらしく、他の客たちも一様に黙っているのだった。
「気持ち悪いな~、どうしたの?それ、何食ってんだよ?」と、澤井が松村の背中を叩いた。途端に、松村はノドに詰まらせたらしく、ドンドンと苦しげに胸を叩き、「みぐ、み、みぐぅ~」と厨房の真知子に唸った。
「いくらせんべい好きだって、そんなに押し込んだら、詰まるわよ。もう、子どもみたい」
「ウェッホン!ゲホッ、ゲホッ!あ~、苦しかった」
松村はコップの水を飲み干すと、涙目になった。
「はぁ?せんべいかよ?しかも、み~んなそうなの?」
澤井の呆れ顔に、いささかゲンナリした表情を返す客もいて、彼らの視線は奥の席に座る若い男を指していた。
見慣れぬ顔だが、どこかで逢ったようなと澤井が眉をしかめれば、「善屋せんべいの若旦那の繁君だよ」と、松村がうざったい顔をした。
善屋せんべいは、駅前の角っこにある手焼きせんべいの店で、誰もが醤油のいい匂いに誘われ、焼き立てを買ってしまう。その店先の炭場に毎日立っている半被姿の男が繁だった。
「あ~、あの、善兵衛さんところの」
思い出した松村が繁に声をかけると、真知子や宮部があわてて「しっ、し~!」と指を口に当てた。と同時に、繁は松村をきっと睨み返し「もう、辞めたんです!」と鼻息を荒げ、冷や酒をグビっとあおるのだった。
「何でも、親爺さんと大喧嘩しちゃって、店、飛び出して来たんだってさ。自分で今日焼いたせんべい、全部、あの席で割っちゃって。捨てるって言い出すわ、真知子さんはもったいないって言うし……それで、みんなで分けてる内に、食べ始めちゃったわけ」
松村の声を聞きつつ、澤井も香ばしい匂いに食欲をそそられ、手を伸ばした。
「何も、今、そんなに食べなくてもいいでしょ」
「でも、まだ温かくて、おいしいし。これ、止められないんだよ」
真知子に食い下がる松村の向こうで、繁が叫んだ。
「いいえっ!絶対、辞めます。辞めてやるんです!」
「まったく、無茶苦茶な会話だなぁ~」
そんな入り乱れる会話に割って入るかのように、ガラガラッ!と威勢よく格子戸が全開した。
「あっ、善兵衛さん!?」と、またも、せんべいくわえた松村が発した。
「この、スットコどっこい!てめえは、大事な商品をどこへ持って行きやがった!?おっ、おおお~!こんなにしちまいやがって!もう、勘弁ならねぇ」
カウンターの割れ砕けたせんべいの山を目にするや、ねじり鉢巻をしたツルツル頭の善兵衛は、やにわに拳を振り上げ、繁に殴りかかろうとした。
すると、その手をはっしと誰かが掴んだ。
「まあ、落ち着きなはれ。ここで暴れたら、他のお客はんに迷惑や」
いつの間にか店に入って来た津田が、善兵衛の皺立った腕をしっかり握っていた。
「う、うむ……そうさな。津田さん、すまねぇ」
時折、せんべいを大阪の土産に買って行く津田は、善兵衛と入魂の仲だった。
ふてくされて黙り込む繁に、善兵衛は呆れ顔でため息しつつ、ここ数日の出来事を客たちに打ち明けた。
繁は、代々続いた「善兵衛」の名を世襲するのをイヤだと言い出し、近頃はインターネットの株式売買に夢中で、夜中までのめり込んでいる。そのせいか、朝がだらしなく、寝ぼけ眼で炭火をいこし、つい今朝も先祖伝来の醤油ダレの壷を危うくひっくり返しそうになった。
そんないきさつをぼやき続ける内、清兵衛はまたもや頭に血が昇ってきたのか、繁を怒鳴りつけた。
「うちは代々、真面目な商売しかできねえ血筋なんだ。大やけどする前に、株なんて止めちまえってんだよ。このトンチキ!」
売り言葉に買い言葉で、繁も負けてはいない。
「本当は証券マンになりたかったのに、無理やり継がせたのは、どこの誰だよ!俺の趣味なんだから、いいじゃないか!ほっといてくれ!」
またも再燃しそうな2人の剣幕を周囲が「まあまあ」と抑えると、津田がタバコの煙を吐き出しつつ、おもむろにつぶやいた。
「まあ、いっぺん気の済むまでやってみるのも、ええかもなぁ……繁はん、“まんじゅう屋長次郎”を知ってるか?」
「ま、まんじゅう屋長次郎、って、誰?」
訝しげな顔をする繁よりも先に、松村が口走った。
「……それって、坂本龍馬の海援隊の隊士ですかね?勘定方って経理担当で、優秀な人物だった。確か、生まれは土佐のまんじゅう屋だった」
宮部がお燗酒をゆっくりとなめながら、答えた。
「その通り。さすが、全国へ出張してる宮さんや。ところが、その長次郎は、金の欲に負けて海援隊を裏切り、切腹させられた。一介のまんじゅう屋やったが才覚に長けて、龍馬の代理として薩摩や長州との商いにも成功したのに、金の魔力に負けてもうたわけや。ほんの一時、世の中を動かすほどの仕事をしたが、非業の死を遂げた。ぼんぼん育ち、肌のきれいな男やったらしい。色白なのは、まんじゅうを食い過ぎたからやと、龍馬も冷やかした。でも、そいつは最期に自分の白い手を見つめながら、『土佐でまんじゅう屋をコツコツやってたら、こんな人生にはならんかった』と悔やんだ……まっ、あんさんがどない思うかは、勝手や」
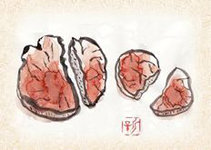 ふと見ると、繁は割ったせんべいを、じっと見つめたままだった。
ふと見ると、繁は割ったせんべいを、じっと見つめたままだった。
善兵衛は手にしていたお銚子を置くと、津田の言葉に何度も小さく頷いていた。
真知子が繁の前に立ち、お銚子を傾けながら言った。
「あなたの手、お醤油の匂いが染みこんでる。いい匂いね」
繁がはっとして、自分の手のひらをみつめた。すると、津田がさりげなく善兵衛の手を持ち上げた。
「繁はんの手も、ええ具合に炭火焼けしてきたやないか……いつか、こんな親父さんみたいな手になるやろなぁ。焼けたてのせんべいみたいに、ええ皺が出てるで」
「皺の数だけ、苦労もあったがね……でも、お客さんが『おいしいね』と言ってくれりゃあ、それで幸せなんだ」
善兵衛の言葉に、みんなが繁にほほ笑みかけ、また、せんべいを食べ始めると、繁もひとかけらを口にした。
「美味しい……やっぱり、止められない」
せんべいを噛む心地良い音が、いつまでもカウンターに響いていた。
