ヒグラシの鳴き声が、つかの間、暑さを忘れさせる頃になった。
お盆の帰省で町も閑散としているせいか、ここ数日はその声がひとしきり心地よい。昼下がりの通りにも、いつもより涼しい風が抜けているような、そんな気がする真知子だった。
郷里の宮崎への帰省は、今年も混雑するこの時期を外すことにした。
かと言って、どこかへ出かけるでもなく、この時とばかり日頃ゆき届かないマチコの掃除や整理を始めていた。
お盆前には、家族旅行に出かけると言う宮地や水野に「誰かいないの?一緒に旅する女友達とか」と呆れられた。帰る田舎を持たない澤井や、妻の由紀が臨月間近のため帰省しない松村からは「俺たち暇だから、手伝おうか?」と持ちかけられた。
「いいの、いいの。まっ、貧乏性だから、しかたないね」と舌を出しておどける真知子だったが、東京に残る理由は他にあった。
2年前、行き倒れて亡くなった近所の老人・島 清吾と妻の千代子の墓参りのためだった。
日頃は清吾の縁者が墓守をしているので、真知子は春と秋の彼岸だけ墓へ参り、二人に香華をたむけていた。
ところが、1週間ほど前に、父親の逸平から不思議な電話があった。
「この頃、うちの墓の草抜きに行くたびサスケが寂しそうに吠くばってん、妙な気持ちじゃ。島さんのお墓は大丈夫か、どげんね?」
サスケは島 清吾の愛犬であったが、故人の遺言から真知子に引き取られ、郷里・宮崎で逸平とともに暮らしているのだった。
胸騒ぎで落ち着かない真知子の所へ、駅前の駄菓子屋の主人・三井たえ子がやって来て、挨拶もそこそこに声をひそめた。
「真知子さん、大変よ。島さんのお墓、ほったらかしになってるみたい」
たえ子の話しによれば、墓地の管理会社に無理を言って確認してもらったところ、朽ち枯れた花と草生した墓石がそのままになっていた。
実は3日前から、毎夜たえ子は島夫妻の夢を見ていた。
「夏になると、買い物帰りに、二人でかき氷を食べに寄ってくれたの。ここ数年、夢に出てくることってなかったのに、毎晩だから……。夢の中で『今年は、特に暑いね』なんて千代さんが言うものだから、何だか気になって管理会社に聞いてみたの。虫の知らせかしらねえ」
墓参りに行きたいところだが、盆はすでに息子夫婦たちと温泉旅行に出かけることになっていると悔やむたえ子に、放っておけない性分の真知子は墓掃除をしようと決めたのだった。
マチコの片付けを終え、花束を手にして電車を乗り継ぎ、現地へついた頃には5時を回っていた。
墓地までの小道沿いの清流には、カジカの声が涼しげに響いている。
閉門時刻まで、小一時間ほどだった。長い陰を落とす墓石の間を急ぎ足で進むと、鬱蒼とした草に取り巻かれる島夫妻の墓があった。
辺りの墓にロウソクの残り火はあったが、誰の人影もなかった。
「こんなになっちゃって……ごめんなさいね。もっと、早く来ればよかった」
真知子の目頭が熱くなった。はらはらと涙があふれ、止まらなかった。
島夫妻の面影が、しばらくの間、真知子の胸で行ったり来たりしたが、はっと気を取り直すと草抜きと墓洗いに取りかかった。
そして、ようやく掃除を終えてみれば、もう薄暮が迫っていた。
水を汲み、花を供え、線香に火を点けようとした時、墓地の小道を覆う茂みがガサリと揺れた。
ドキッとして身構える真知子の耳に「真知子さん、そこにいる?」と聞き慣れた澤井の声がした。
「ここよ、ここ。もう、ビックリするじゃない」
ホッとして胸を撫で下ろす真知子の前に、花を持つ澤井と松村が現れた。
「でも、どうしてここだって、分かったの?みんなには黙ってたのに」
線香の火をあおぎ消しながら訊く真知子に、澤井が答えた。
「たえ子ばあちゃんに聞いたんだ。これが偶然ってか、驚きなんだよ」
新宿で映画を見終わった澤井は、駅で息子夫婦と旅に出たばかりのたえ子に出くわし、おそらく今日は真知子が島夫妻の墓参りに行ってるような気がすると聞いたのだった。
「マチコに電話してもつながらないし、携帯は留守電だし。それで、暇してる俺に澤井さんから電話があって、一緒に追っかけようってことになったわけ。あっ、これ、おばあちゃんからのお供え。島さんたちが大好きだったキンツバだって。駅買いの品物で申し訳ないけど、真知子さんにくれぐれも『ありがとう』って」
松村は小さな菓子折りを真知子に手渡すと、線香を三人の手に分けた。
立ち上る薄い煙の中で、3人は手を合わせた。上品なビャクダンの匂いが、夕景の中で夏草の匂いと混じり合った。
「ありがとう、真知子さん……」と、真知子の耳に聞こえた。
「もういいわよ、和也君」
「へっ?何が」
振り向いた真知子に、松村がポカンとして答えた。
「お礼なんて、何度も言わなくていいの」
「俺?何も言ってないじゃん。ねえ、澤井さん」
松村が自分自身を指差しながら、澤井の同意を求めた。
「……だって、今言ったじゃない。『ありがとう、真知子さん』って」
青ざめる真知子が、今度は澤井に視線を向けた。
「おっ、俺じゃないよ。おいおい……冗談キツイなあ」
澤井の返事とともに三人は口ごもり、足早に墓地を出て行った。
真知子も、澤井も松村も、少し背筋を寒くしながら、小川のほとりを駅に向かっていた。
茜色の空を映すせせらぎの音も、三人の耳には入らないようすだった。
小さな橋を渡りかけた時だった。「うわっ!」と、三人同時に声を上げた。
ゆるやかに流れる水面に、数百もの送り火が浮かんでいた。オレンジ色の小船の群れが、幻想的で幽玄な光景を描いていた。
川岸には、その灯りを映す顔、顔、顔。在りし日の故人を偲ぶ、たくさんの家族が立っていた。
「そうか……お盆は、不思議なことがあっていいのよね。その方が、みんな本当は嬉しいのかもしれないね」
欄干に頬杖を突く真知子の横で、澤井がポケットから小さな瓶を取り出し、その中身を川に注いだ。
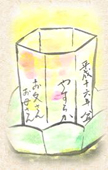 「さっき、供えそびれちまってさ。清吾さんが好きだった、伏見の酒だよ。これも、出かける前にピンと来てね」
「さっき、供えそびれちまってさ。清吾さんが好きだった、伏見の酒だよ。これも、出かける前にピンと来てね」
澤井の言葉に、真知子と松村がコクリと頷いた。
三人は、あらためて、ゆっくりと合掌した。
ゆらゆらと送られる火の中に、清吾と千代子の笑顔が輝いていた。
