日暮れに染まる通りには、春の陽だまりの温かさが残っていた。
そんな空気を楽しみながら、津田は額に汗をにじませてマチコの玄関を開けた。せっかちな津田は、もう麻混じりの背広を着ている。
「こんばんは! ほれ、真っちゃん。お待ちかねの酒と干物、持って来たで」
言うと同時に、津田は緑色の四合瓶と紙包みを大きな手提げ袋から取り出した。 袋の中には、数本の瓶が入っているようだった。
「おっ、待ってました~! 真知子さん、早くグラス、グラス!」
カウンター席の松村は腰を浮かせ、待ちきれないようすで酒の開封をせがんだ。隣の澤井も、さっさと自分の冷酒グラスを飲み干して待っている。
毎年春になると、津田のもとには亡き弟が勤めていた灘の蔵元から、ほどよく熟した酒が送られてくる。マチコへも今まで何度か持参していて、そんな極上酒を、この頃になると皆が待ちわびているのだった。
賑わう常連たちのようすに、カウンターの隅で燗酒を飲んでいる二人の男が目を向けた。白髪混じりの高齢の男は穏やかな表情だったが、若い男は少しやつれて 見えた。
「騒がしくて、すみませんねぇ」
真知子が気を遣うと、男たちは日焼けた顔をわずかに横に振った。
「あれ? おい、あの若い人、日本橋高校の江本監督じゃないか?」
澤井が、松村の腕を突ついて言った。
「日本橋高校って、選抜大会の関東代表校だった? ふーん、そう言えばそうかなあ。でも、関東地区予選で優勝候補って言われてたわりには、ベスト16止まりだっけ」
「しっ! 声がでかいよ」
チラチラと男の顔を見つめる澤井と松村だったが、津田はその隣の高齢の男に視線を止めて、「あの人……確か」とつぶやいていた。
真知子が四合瓶の栓を開くと、澤井が舌なめずりして酒を受けようとした。
「ちょっと、待った! 今日は、常連メンバーは後回しや。たまには、新顔のお客さんへ先にふるまおか。これを機会に、マチコをご贔屓にしてもらわなあかんしな」
津田が澤井の手から瓶を取り上げた。すると、松村は「えっ、そんなぁ。あっ、ああ~」と物欲しげな視線で、その行方を追った。
カウンターの二人の男たちは、そんなやりとりをよそに、静かに会話していた。
「もう一度、考え直してみないか。江本」
高齢の男が、ゆっくりとタバコに火を点けて言った。
「……先生、すみません。いろいろと悩んだ末の結論なんです。自分の能力の無さもそうですが、周囲の声、マスコミの中傷にも、これ以上は我慢できません」
力無げな若い男の声が、高齢の男の吐き出した煙の中に消えていった。 二人の言葉は、途切れながらもしばし続いていた。
その時、テーブル席の団体客に杓を終えた津田が、カウンターの隅に近づいた。
「お久しぶりですな、島はん」
そう言って目じりを綻ばせる津田を、高齢の男は「はて?」と言うような顔で見返した。
「お忘れでっか? 大阪の“ともしび”」
津田は鼻ヒゲと顎ヒゲを手で隠してながら、ぐっと顔をせり出した。
「おっ! おお~、おお。津田さんじゃないかあ。いっやー、驚いちまった! 奇遇だねえ」
高齢の男は、店中に響くほどの大声を発して立ち上がった。その声に、真知子や澤井たちが驚いて振り向いた。
「お元気そうで、何よりですな。風の噂では、まだまだ現役やとか」
「いやあ、お恥ずかしい。家族には、年寄りの冷や水なんて言われちまってるけどね」
旧懐を温めるように、島は津田を隣の席に「まあまあ、どうぞ」と座らせた。タイミング良く、真知子が津田と島、そして江本の前に、冷酒グラスを置いた。
「真っちゃん。この人ね、島監督さんちゅうてな。そうやなあ、今から20年ぐらい前に、夏の甲子園大会で優勝しはった監督さんや」
津田の紹介に、真知子が「どうぞ、よろしくお願いします」とお辞儀した。
「島です。津田さんには、若い頃お世話になって。甲子園大会で大阪市内に泊まった時は、時々ごちそうになりに行きました。私が優勝できたのは、実は、この人の御蔭かもしれません」
ほほ笑む島に、「そら、おおきに。どうでっか、一杯」と津田は酒瓶を傾けた。
「そうだ、紹介します。私の教え子の江本です。今じゃ、もう私より有名ですけどね」
島が、江本の肩を叩いて言った。
「ええ、お顔は存じてまっせ。選抜大会、お疲れさんでしたな。負けはったけど、ほんまにええ試合でしたなあ。久々に、感動させてもらいましたわ」とお辞儀をした。
「えっ……あっ、ありがとうございます」
江本が恐縮しつつ津田の杓を受けると、三人は冷酒グラスを合わせた。
「美味しいなあ。……うん? ひょっとしてこの酒」
島が、グラスを見つめてつぶやいた。
「そうでっせ。あんさんがウチの店に来てくれはった頃の、あの灘の酒と同じもんだす。なあ、江本はん。20年前は島はんも悩んではってねえ。何べん甲子園に来ても勝たれへんで、もう監督辞めたいちゅうて、ウチの店でぼやきますねん。へたれみたいな、元気の無い顔してましてんで。今の江本はんに、そっくりですわ」
「えっ!」と江本は声を発し、島が「津田さん、どうしてそれを……」 と言葉を途切らせた。
「あんさんら二人が渋い顔して語り合うてたら、そんな話やないかと思いますがな。ほれ、江本はんの顔に書いてまっせ。そうちゃいまっか?」
その読みに、しばらく二人の男は黙っていたが、江本は気心よさげな津田に自分の気持ちを語り始めた。
江本はこれまで数校の監督を転々としていた。いずことも、春の選抜や夏の甲子園に出場したが、同じような敗戦を繰り返すばかり。
毎年、激戦だけが評判となり、それを制せない彼の監督能力は周囲の期待を裏切っていた。
津田は江本と、静かに、ゆっくりと言葉を交わした。2杯、3杯と注ぐ内に、江本は心地良く酔っているようだった。
「みんな、同じですねん。人間やから逃げたい時も、しんどい時もありますわ。けどなあ、それを越えた人、耐えたには、神様の褒美がおますねん。あんたの師匠は、それをやりはった。そんなら、あんたもできるはずや。それに、師匠を越えるのは弟子の生き甲斐ちゃいまっか。……江本はん、これしきで諦めたらあきまへん。夏は、きっと優勝できますわ」
その津田の言葉に、島や江本だけでなく、真知子や澤井たちも耳を傾けていた。
「今の言葉……昔、この酒を飲みながら、よく聞かされてな。だから、私にとっては、優勝の味がする酒なんだよ」
島が、懐かしそうな優しい視線で、江本に言った。
「先生……自分は、甘かったです」
江本の瞳が、少しだけ潤んでいた。
その時、真知子が焼きたての香ばしい干物を、島と江本の前に置いた。
「これもまた、懐かしい味……でっしゃろ」と、津田が島に笑った。
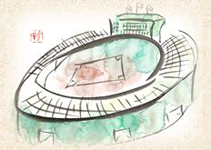 島は、魚に箸をつけ「うむ……甦るよ。あの感覚が」と頷いた。そして、空いた江本のグラスに酒を注いだ。
島は、魚に箸をつけ「うむ……甦るよ。あの感覚が」と頷いた。そして、空いた江本のグラスに酒を注いだ。
「江本、お前も自分の優勝の味を、見つけてみろ」
「はい、先生……きっと」
島と江本は、コツンと冷酒グラスを合わせた。 すると、いつの間にか新しい瓶を開けていた松村と澤井、常連客たち、真知子と津田が、二人へ向かってグラスを上げていた。
冷酒グラスの中で、胴上げされる江本の笑顔が揺れていた。
