カウンターの隅に、赤紫色のれんげが映えている。その小さな鉢植えだけでなく、マチコの“酒の肴”にも初夏を感じる頃になった。
タケノコ煮、焼きアナゴ、菜の花漬けなど、そんな旬味をつまむ男たちが店内のそこかしこで笑い合っている。
注文をテキパキとこなす真知子は、メバルの煮付けに山椒を添え、テーブル席へと運ぼうとしていた。ふっと、木の芽の香りがカウンターに漂い、客たちが口々に「おっ、いい匂い……」とつぶやいた。
今しがた来たばかりの松村が、舌なめずりして言った。
「うっ、うまそう~! やっぱ、初夏はメバルだよなあ」
「和也君。今、注文がたまってるから、しばらくは料理出せないからね」
うっすらと額に汗した真知子が、メバルを運びながら、念を押すように言った。確かに、厨房の中には、各テーブルの伝票のモギリが十数枚ほど貼られている。
「そう……しかたないな。じゃあ、弁当の残り物でもアテにしてよかな」
松村がそう答えると、真知子はやさしい目でうなずいた。
「けど……イマイチなんだよなあ」
一人ごちる松村は、周りの客の視線を気にしつつも、しかたなげに弁当箱の包みを取り出した。
箱の蓋を取ると、緑色のいんげん豆が残っていた。その胡麻和えを見つめる松村の顔は、いかにも「美味しくない」と言うような表情だった。
「おっ、胡麻和えですか。こりゃ、美味しそうですなあ」
ふいに、松村の隣で徳利をかたむけていた高齢の男が声を発した。地味な色のジャケットと白いシャツに、皺だらけの顔が笑っている。
松村は、男があまりにも嬉しそうなので、「あっ、お好きですか。これ? 職場の冷蔵庫に入れてたから、大丈夫ですよ。よかったら、どうぞ」と弁当箱を差し出した。
「いやいや、これは失礼しました。いんげんは好物なので、つい気になっちやってね」
男は、額に垂れた白髪を掻き上げながら、はにかんだ。
「……でもねえ。これ、たぶん美味しくないっすよ。ウチのカミさんの味付けが、ちょっとね」
松村の申し訳なさそうな声を聞きつつ、男は「じゃあ、一つだけ」と箸を伸ばした。
「うむ……なるほどね。そういうことか」
口を細かく動かす男の言葉に、松村は「へっ? どういうこと?」と不思議そうな顔で訊いた。
「この胡麻和えは、かなり胡麻を摺りつぶしてるから、油の味が染みこんでますな。時間が経つと、胡麻の油っ気はしつこくなるんです。だから、作る時は摺らずに和えておいて、食べる時に胡麻を噛むようにすれば、香りも味も新鮮で美味しいですよ」
男は、ぬる燗の酒を口に流し込み、幸せそうな声で答えた。
「へぇ~、詳しいですねえ。あの……ひょっとして料理人の方ですか?」
松村が、目を丸めながら訊ねた。ほかの客たちも「ほお~」と感心しきりである。
「いやいや、素人です。まあ……私もこれなんですよ」と、男はカバンから布包みを取り出した。松村のものより、ひと回り小さな弁当箱だった。
「実は、妻が5年前に亡くなりましてね。やらざるを得なくなってしまって。それに、もっぱら弁当派でしたから昼の外食は苦手で……それで弁当作りするようになったんです。……晩酌もそれなりに、男ヤモメの手料理で楽しんでますよ」
頬を赤らめて苦笑いする男に、周囲の男たちは気を遣っているのか、しばし黙りこんだ。
松村が弁当包みへ縫い込まれた「坂口」の名に気づき、口を開いた。
「あのう、坂口さん。訊きたいんですけど……美味しい弁当の秘訣って、あるんですか?」
名を呼ばれた男は一瞬はっとしたが、むしろ、もっと笑みを見せて答えた。
「まずは、自分でやってみることですなあ。私も、当初は面倒臭くってね。米を砥ぐのも、まともにできなかったんですよ。まったく、60年生きてながら、それすら知らない自分が情けなかった。40年近くもカミさんと暮らしながら、見ていなかったんですなあ。ところが、いざやってみると、これが楽しくなってきた。料理の腕、知識が少しずつ上向いて、まんざらでもなく感じる。こりゃあ、カミさん作ってたのより美味しいぞ、なんてねえ」
坂口はイキイキとした表情で、話し続けた。いつの間にやら、料理を作り終えた真知子も耳を傾けていた。
男の料理の魅力、季節の食材の使い方、塩や味噌のこだわりなど、カウンター客たちは聞き耳を立て、中には手帳へメモを取り始める者もいた。
お終いには、「私も弁当派でして」「実は、僕も」などと皆が弁当箱を見せ出すしまつで、弁当箱の選び方まで坂口なりに語った。
そして、一人また一人と客たちは坂口に礼を言い、帰って行った。坂口は満足げな笑みをこぼしながら、皆を見送った。
松村と坂口だけになったカウンターに、真知子が熱い番茶を置いた。
「坂口さんって、本当にお料理するのが楽しそう。……お上手な奥様の味を知っていたから、上達も早いんでしょうね」
真知子の言葉に、坂口はふっとほほ笑んだ。
「あいつの料理は……美味しかったのか、どうか。ただ、私には合っていましたなあ。いまだに、私はカミさんの味を追いかけてるようです。あの味が、出せないんです。……いつか仏前に供えて、ほら、どうだ!って食わしてやりたいですね」
坂口の目じりの皺が、白い湯気に見え隠れしていた。
「頑張り屋さんね。それに……奥様のその刺繍も、秘訣なんでしょうね」
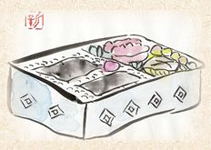 真知子のおだやかな視線が、弁当袋に止まっていた。
真知子のおだやかな視線が、弁当袋に止まっていた。
「あっ!……そうか、なるほど」と、目じりをゆるめた松村が坂口にグラスの酒を手渡した。
「いや……照れますな」
恥ずかしそうに額を撫でながら、坂口は冷酒を傾けた。白い名前の刺繍が、グラスの中で揺れていた。
