マチコの柱時計の鐘が、5時30分を告げた。厨房のやかんは、秋冷えしてきた空気の中で白い湯気を昇らせている。
カウンターに腰かけていた真知子は「あら、もうこんな時間!」と見入っていた便箋から顔を上げた。
ようやく新酒造りの季節を迎えた全国の酒蔵から、“蔵入り”を知らせる手紙が数通届いていた。毎年のことながら、蔵元や杜氏からの丁寧な挨拶に、真知子は嬉しくもあり、ほっと胸を撫で下ろすような気持ちだった。
その時、格子戸がガラリと開いて澤井が入って来た。
「こんばんは~。お、今日は一番乗りだな。あれ? あいつ何やってんだ」
澤井がカウンター席に座りつつ玄関を振り返ると、一緒にやって来たらしい松村が靴の裏を地面に擦りつけていた。
「どうしたの、和也君?」
真知子が問うと、「さっき、公園の通りでぎんなんの実を踏んじゃって。な~んか臭くってさ。せっかく飲むのに、気分悪いじゃん」と和也は苦笑いした。
そのようすに、「ぎんなんか……あっ、しまった。いっけない!」と真知子は椅子から飛び上がった。途端に、厨房からパチッ、パチパチ、パチンと何かが連続して弾ける音がした。
「おっ、おっ、何だ……あつっ、いてて。これ、ぎんなんじゃないの?」
カウンターまで跳んで、澤井の額に当たったのは、熱くなったぎんなんだった。
「あらあら、ごめんね澤井ちゃん。さっき炒り始めたのを、うっかり忘れてたわ」
真知子とが床に散らばるぎんなんを拾うと、松村がそれを手伝いながら言った。
「こうすると香ばしくって、いい匂いなのになあ……とてもじゃないけど、あの臭い実の種とは思えないよね」
「……確かにな。酒の肴にも最高だし、秋を感じる味覚だよなあ」
澤井がニンマリとして、カウンターに転がっている一粒を割り、実を噛んだ。
拾ったぎんなんを見つめながら、真知子がふっと笑みをもらした。それに気づいた松村が「何だよ、真知子さん。思い出し笑い?」と訊いた。
「2年前の秋に会った、多摩の順平君……憶えてる?」
真知子がぎんなんを前掛けのポケットに入れながら、問い返した。
「……あっ、あいつね。そうそう! あいつ、ぎんなん男じゃん」
松村も割れたぎんなんの皮を剥いて、口にほうりこんだ。
「思い出すよなあ……彼が店に入って来た時のスゴイ匂い。どことなく野暮ったくて、小汚い感じだったから、みんな一瞬引いちゃったもんなあ。けど、あの酒は美味しかったよ」
澤井はもう一つぎんなんを割ると「真知子さん、ぬる燗を」と嬉しそうに頼んだ。
「あっ、おれも!」と松村が澤井の横に座ると、順平の思い出話しが始まった。
2年前の秋のある夜、マチコにはいつものメンバーが顔をそろえていた。
そこへ、ヒョッコリと若い坊主頭の男がやって来て、カウンターの隅に座った。男は茶色のジャンパーに擦り切れたジーンズ、汚れたスニーカーという地味な風体だったが、右手に提げたビニール袋は強烈な匂いを発し、思わず常連たちはのけぞった。
「ねえ、お客さん。それ、何なの?」
しかめっ面で鼻をつまむ松村が訊くと、若い男は「あっ、す、すみません。や、やっぱり臭いですか。ご、ごめんなさい。あの、そ、その先の公園に落ちてたぎんなんです。お、お、俺、ぎんなんが大好きで。と、と、特にこれ、粒が揃って美味しそうだから、持って帰ろうと思ったもんで。ぎんなんは、うちの冷やおろしにとっても、あ、合うんです」
恥ずかしいのか、どもり症なのか、男は口を詰まらせながら、真っ赤な顔でビニール袋を足元に隠すようにして答えた。
「ふむ、それは否定しないさ。僕も、ぎんなんは酒の肴にピッタリだと思う。でもさ、うちの冷やおろしって、どういうことなの?」
ほろ酔いで頬を赤くした澤井が続けると、「あ、あの……俺、多摩の蔵元で酒を造ってます」と答え、牧 順平と名乗った。
「うっそだろ、見えねえなあ……それに、酒造りしてる蔵人が、そんな臭いのするもの居酒屋に持って来るかよ。じゃあさ、銘柄って何なの?」
すると、詰問するような松村に、順平はどもらず「多摩泉」と明確に答えた。
「聞いたことねえなあ~。ねえ、宮部さんは知ってます?」
冷酒グラスを飲み干して松村が声高に言うと、宮部が黙ってうなずいた。
「ああ、あるよ。奥多摩の地酒だ。しっかりとした、旨味のある酒だよ……ところで、牧君はどんな仕事を受け持ってるんだい?」
「は、はい、今年は3年目で、ようやく麹造りを教えてもらってるところです」
宮部の問いに順平はどことなく嬉しそうに答え、ひさびさの有給を取りその公園近くに住む友人宅へ遊びに来て、帰りにぎんなんを拾ったと、問わず語った。
松村が「ふーん、そんなに美味しいもんかな」とつぶやいた。
そのようすを厨房から見ていた真知子が、口を開いた。
「宮部さん、今、秋月商店に多摩泉は残ってないかしら。あれば、誰か持って来れないかしら」
真知子に頼まれるや、宮部はピン!ときた顔で携帯電話をかけた。
「純米酒が1本だけあったよ。私がひとっ走りしてきますから、真知子さんは……」と立ち上がった宮部が言いかけるや、真知子は「分かってる!」と片目をつむった。
おずおずとしている順平に、宮部は「待ってな。みんなを驚かそうや」と肩を叩いて出て行った。すると真知子が厨房に入り、しばらくすると、炒り上げられたぎんなんが、カウンターに登場した。
「これは、昨日スーパーで買ったもんだから、公園のぎんなんの実じゃないけどね。でも、大粒で、おいしそうでしょ」
真知子が、順平にぎんなんを盛った皿を差し出すと、同時に宮部が帰ってきた。
さっそく多摩泉の瓶が開けられ、みんなのグラスが満たされた。
焼け上がったばかりの香ばしい実に塩をふり、それをつまみながら酒を飲む男たちから、思わず「うおっ! こりゃ合うよ」
「いいねえ~、これぞ秋の味わいだねえ」とため息まじりの声が聞こえた。
周りから好評が出始めると、宮部が順平に、ほらっとばかり顎をふった。
順平はおもむろに立ち上がると、頭をかきつつ多摩泉の酒の話しを始め、客たちはその丁寧な説明に感心しつつ、耳を傾けていた。
「どう、和也君はお気に召して?」
カウンターに頬杖をついた真知子に、松村が「ちぇ、はいはい、私が悪うござんしたよ」と舌を打てば、「まあ、ぎんなんも牧君も、見かけによらず、中身がイイってことだ。誰かさんと違ってな」と澤井が皮肉った。
その言葉に、松村がジロリと順平をにらんだ。
「あっ、いえ、あの……僕、そんな」
順平が慌ててうつむいたのを見て、「冗談だよ。ちくしょう、ぎんなんは俺にとっちゃ、災難だよ~」と松村はおどけて見せ、その場は笑いに包まれたのだった。
「そろそろ、彼も蔵入りの頃だな。あれから顔を見ないけど、元気にしてるのかなあ」
澤井が真知子の杓を受けつつ、つぶやいた。
「とか言ってると、やって来たりしてね」
そう言って松村が手酌で酒を注いだ時、開けっ放しの玄関から、ただならぬ異臭が漂ってきた。
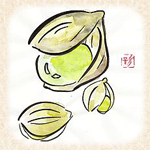 「ぶっ、まっ、まさかあ~!」
「ぶっ、まっ、まさかあ~!」
松村が酒を吹き出すと、真知子と澤井は目を丸め、顔を見合わせた。
「まいど、こんばんは。真っちゃん、公園のぎんなんがうまそうやで~。思わず、拾うてもうたがな」
玄関で、ビニール袋を手にした津田が嬉しそうに笑っていた。
「もう、勘弁してくれよ~」
倒れこむ松村の姿に、真知子と澤井の大爆笑が響いていた。
