寒波の引き起こした風が、赤い提灯を揺らせていた。犬の遠吠えが冷えた空気に響き、マチコの店先で落ち葉がカサカサとつむじを巻いている。それでも店内は温かな湯気と明かりに満ちていたが、カウンターに座る面々はやけに浮かない表情だった。
澤井、松村、宮部のほかに、たまにやって来る近所の商店の主人たちなどが思案顔を繰り返しながら、徳利を傾け合っている。
「けどさあ、町ぐるみで募金活動するとか、何とかならないの? 八百秀の大将」
澤井が、ほとんど禿げ上がった頭にタオルを巻いている八百秀の主人に、酌をしながら肩で突いた。
「そりゃ、俺っちも何とかしてやりてえよ。けどなあ、たとえ募金で持ち直したとしても、今後も富士見湯さんがやってけっかどうかなんだなあ」
腕組む八百秀の言葉に、面倒見が良いことで評判の魚辰の若旦那も、「う~む」と唸ったままだった。
「景気復調なんて言ってるけど、まだまだ中小企業はどこも不景気だし、この町だって同じだよ。富士見湯さんも大変だけどねえ……俺たち自身の不安だって、どっさりあるしなあ」
隼ガソリンスタンドの所長はそう言うと、ブルーの帽子を脱いでため息をついた。
今夜の集まりは、この町にたった一軒だけ残っている銭湯「富士見湯」が、瀬戸際に立たされていることから起こった。
ここ数年、隣町に林立し始めたマンションへ、古い家屋を売って移り住む熟年世帯が増えていた。そのあおりを受けて、富士見湯の客は徐々に減っていった。
さらには、この春にマンション群の住人を目当てにした温泉ランドも誕生し、富士見湯は閑古鳥が鳴く日もあった。時折、ひと風呂浴びてマチコにやって来る澤井や宮部からそんな事情を聞き、真知子にしても、顔見知りの経営者夫婦が「もう、やってけないねえ」と困り果てている顔を思い浮かべた。
何とか手立てはないものかと考える真知子だったが、この町の新参者である彼女が、町内の御れきれきの前にしゃしゃり出ることは難しかった。
そんな中、真知子は「この町の御意見番なら、何とか打つ手を考えてくれるかも」と、毎日野菜を仕入れている八百秀の主人に、ひと肌脱いで欲しいと頼み込んだ。
もともと真知子が大好きな八百秀は「よしきた! ドンと任せときな!」と太った腹を叩いて主だったメンバーを揃えたまでは良かったが、いざ場が開かれるや、当初の威勢もどこへやらであった。
「富士見湯さんは、戦前からあったんでしょ? 俺も2、3度入ったことあるけど、洗い場の奥にツギハギだらけの七色タイルがあるじゃない。あれって、ステキだよねえ」
松村が、顔を赤くしている魚辰の若旦那に訊いた。
「ああ、あれは空襲で焼けちまった瓦礫の中から、富士見湯の先代さんと僕らの祖父たちが引っ張り出した物だ。その後、銭湯の建て直しも手伝ったそうだよ。昭和40年頃は、そりゃ賑やかでね。僕は番台に上って、よく叱られたよ」
若旦那は、懐かしげな目をして冷酒グラスを空けた。
「俺なんぞ、今のカカアは風呂帰りのしるこ屋で見初めたんだ。けどなあ……もう今度ばかりは、復活は無理かもなあ」
意気消沈する商店の男たちに、たまらず真知子は声を高めた。
「ちょっと、ちょっと……皆さん、そんな弱気でどうするのよ。大将、ドンと任せとけ! は誰の言葉だったかしら?」
「う、うん……それはそのう、まあ、八百屋の性分ってヤツでよ」
店の明かりに光る頭を撫でながら、面目なげに八百秀は声を低めた。
「とにかく、何かやらなきゃダメだよ。富士見湯さんへお客さんが入るには、どうすればいいか。できることから考えましょうや」
宮部の声に、スタンドの所長がポンと手を打って「いっそのこと、信用金庫の支店長もメンバーに入れて、融資を頼んで、温泉ランドみたいに改装したらどうだろ」と言った。
「金利は誰が払うの。みんなで持つわけ? そんな考えって、安直すぎる他人事だよ」と澤井が指摘すると、酔ってきた松村が立ち上がって叫んだ。
「あのさぁ~、そもそも販売促進てのは、テーマとかコンセプトってのが必要なのよ。つまり~、今回の目的、条件、対象は何かって…」と口火を切るやいなや、それまで押し黙っていた真知子が立て板に水のようにまくしたてた。
「今さら健康ランドなんて、この町には必要ない。だって、あれは個々人が満足する設備でしょ。富士見湯さんの、銭湯の魅力は、お風呂に来るみんなと心が通うこと。温かい気持ちにもなれる空間なんだと思うの。大きな銭湯画、洗面器のコーンって音、懐かしいタイルの色、蛇口の形、フルーツ牛乳、そこで毎日出会う顔と挨拶。心のぬくもりこそが、銭湯のぬくもりだと、私は思う。そんなぬくもりを求める人は、まだまだたくさんいるはず。“週に一度は銭湯へ!”とかキャンペーンしてさ、富士見湯の存在を教えて、案内することが大事じゃないかしら」
その勢いに、カウンターを囲む男たちは、ポカンと口を開けたままだった。
「あっ……俺の言うこと、何もなくなっちゃった、あはは……はは」
独りごちる松村をほっといて、八百秀がニヤついた顔で言った。
「う~ん、なるほど。銭湯の良さは誰もが家族的なことだなあ。じゃあ、いっそ“月に一度は水着で混浴風呂の日”なんてのはどうだい、真知子さん」
ピント外れの答えに、真知子とその場の一同が「はぁ?」と呆れた途端、ガラリと格子戸が開き「このスケベ親父は、どうしようないね!」とビア樽のような体を揺すって、八百秀の女将が登場した。
「か、か、母ちゃん。何だよ!」
「何もかにも、あったもんじゃないよ! 黙って外で聞いてりゃ、まったくろくでもない会合だねえ。あんた! 仮にも町の御意見番を気取るなら、もうちっとは富士見湯さんを親身に考えてあげるもんだろ! それが、混浴デーだって? 呆れてものが言えないよ。そうだろ、魚辰さん」
気がつけば、八百秀の女将の傍には、魚辰の若旦那の母親である女将が立っていた。
「うちの息子も、まだまだ主張がなくてダメですねえ。分かってて言えないのが、子どもの頃からの悪いクセなんですよ」
「お、お袋……やめてくれよ」
たじろぐ男たちを、二人の女将はジロリと睨むと、その視線をそのまま真知子へ向けた。
真知子はでしゃばったことを指摘されてもしかたないと、神妙な面持ちで、おじぎをした。
「真知子さん、だったわね。私は、このお店は好きじゃなかったから一度も来なかったけど、あんた、なかなか大した人ね。これは、嫌味じゃないよ。もっとも、昨日までは町の男たちが『いい女だよ』って言うたびに、イライラしてたけどね。あんたのさっきの“心のぬくもり”、とっても気に入ったわ」
八百秀の女将の言葉に、「あ、わわ」と大将は目をパチクリさせた。
「八百秀さん、町内の女将を集めて、いろいろ検討しましょ。お買い上げチケット、スタンプカード、ポイントカードとか、資金集めの方法をいろいろ考えてみましょうよ。そんな仕掛けは、隼スタンドさんなんてお手のものじゃないの」
魚辰の女将から話しを振られた隼スタンドの所長は、どぎまぎとしておべっかを返した。
「さすが、女将でありながら主婦ですねえ。俺なんて、油売るしか能がないですから」
すると、暖簾がふわりと揺れて「あんたは、あっちこっちで無駄な油ばっか売ってんじゃない!」と、金切り声が響いた。
「うへぇ!」と帽子を目深にかぶった所長の後ろに、長身の妻が鼻息を荒くして立っていた。
「まあまあ隼さん、もういいじゃないの。それより、真知子さん。どうかしら、こんな頼りない会合は置いといて、私たちで富士見湯さんを助けようじゃないの。これから定期的に、このお店で富士見湯復活の会合を持ってくれない? もちろん、あなたもそのメンバーよ」
八百秀の女将の声に、松村と澤井、宮部の3人が、にっこりと視線を合わせた。
すると、真知子がすっと顔を上げて答えた。
「私……例えば、6,000円以上の飲食には、富士見湯さんの回数券をプレゼントしたり、お風呂上りのご来店には、生ビールを一杯サービスしたりとか、いろいろアイデアを考えたんです。だから、できることから、お金をかけずに心を使って、手作りの支援をしたいんです」
真知子の言葉に3人の女性たちは「異議なし」と、声を合わせた。
「そうと決まれば、今夜は第1回のオープニング会ね。ほらほら、あなたたち。いつまでも飲んでないで、私たちの会の準備をなさい。真知子さんは、大事なメンバーなんですからね」
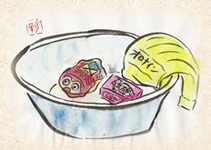 魚辰の女将に言われ、松村、澤井、宮部は、嬉しそうに「よしきた!」と、料理や洗い物をテキパキと始めた。
魚辰の女将に言われ、松村、澤井、宮部は、嬉しそうに「よしきた!」と、料理や洗い物をテキパキと始めた。
「じゃあ……俺たちは、やっぱり」
八百秀の大将がつぶやくと、テーブル席に座った3人の女将がそれぞれに、おいでおいでをしていた。
真知子はそこに、この町のあたたかさを実感し、賑わう富士見湯の光景を想っていた。
