花冷えがゆるみ、春告魚の真鯛が築地市場をにぎわしていると夕刊が報じていた。今年の旬を先取る桜鯛は三重県産の真鯛が値ごろで、志摩半島あたりで大漁と書いている。
その新聞を手にする右近龍二は、ポンバル太郎のメニューにある、まさに「桜鯛の刺身」を食べていた。記事の写真に、目ざとい龍二は剃髪した頭を見つけた。
「あっ! これ、銀平さんじゃないか」
華やかな香りが、龍二の息にまじった。ついさっき龍二が飲み干したグラスの大吟醸は、バラの花酵母で醸していた。
カウンター席に並び桜鯛をつまんでいた高野あすかが、その匂いに惹かれながら紙面を覗き込んだ。しかし、ここ数日のあすかは雑誌の売れ行きが伸びず、いささか機嫌が悪い。
案の定、あすかは銀平の写真をくさした。
「本当だ。大ざっぱな銀平さんが、ちゃんと差配してるじゃない。ということは、この桜鯛は三重県ってわけね」
若い衆に指図してトロ箱の山を仕分ける親方の表情は、ポンバル太郎で酔っぱらっている時の銀平とは別人のようだった。
あすかの言葉へ返事するかのように、玄関から鳴子の音とひねくれた声が聞こえた。
「大ざっぱで悪かったなぁ。だがよ、おめえが食ってる鯛の刺身は、新聞の三重県産とはちょいとちがうぜ。マスコミが書いた“大漁”ってのは、“大量”のまちがいだ。記者が養殖鯛を早とちりして、大漁と書いちまってやがる。でも火野屋が仕入れたのは英虞湾で獲れた、正真正銘の天然物だ。どうでぇ! 親方の時の俺は、大ざっぱな仕事はしねえんだよ」
龍二たちがふり向くと、銀平がトロ箱を提げて店先に立っていた。
毒づかず単刀直入に鯛の素性を話した銀平へ、あすかは文句なく、素直に頷いた。カウンター越しに、太郎がいたからだった。
「その大した親方が、桜鯛に優るとも劣らない魚を持って来てくれたらしいが……それかよ?」
太郎が顎を振ると、トロ箱の中には一尺半(45㎝)を超えてそうなグロテスクな魚が横たわっていた。ビニールの中の岩のようなゴツゴツした体と色合いに、あすかは椅子から飛び上がった。
「キャッ! そ、それ、何よ? そんなの食べられるの?」
「おめえ、酒のこと以外はからっきしだな。これは、オニオコゼ! 見た目とは反対に、めっぽううめえんだよ。オコゼの旬は初夏なんだけどよ、こいつぁ桜鯛の網にかかったてえ、縁起物だ。英虞湾の主みてえな、大物だぜ」
飛び出した目玉と突起のある背びれが特長で、昔は関東ではあまり食べない魚だったが、最近は白身の美味しさに人気が出てきたと銀平は言い、毒針を気にしながら取り出した。
自慢する銀平に太郎も目を丸くし、忘れかけているオコゼのさばき方を思い出していた。
大きなオコゼに嬉しげな龍二が、唾を呑んで言った。
「へぇ、オニオコゼかぁ。高知にいた子どもの頃、おふくろが作った唐揚げをよく食べました。見かけによらず、うまいんですよ。フグもそうだけど、毒がある魚の美味しさは女性に似てるって言うし」
酔いの回った龍二が顔をゆがめているあすかへ、意味ありげに流し目をした。
「ちょっと龍二君! その目つきは、どういう意味よ?」
迂闊にも舌が滑った龍二に、あすかの矛先が向いた。謝る龍二の桜鯛の刺身を、あすかは独り占めしようと皿を奪った。
二人に飽きれる銀平がオコゼを厨房へ運ぼうとした時、太郎が懐かしげな目元を見せた。
「オコゼのさばき方を教わったのは、ハル子だった。あいつ、言ってたよ。おもしろいのは、オコゼって悪食だから、腹にいろんな物が入ってるってんだ。それで実際にさばいてみると、赤や茶色の玉が出て来た。巻貝の破片だって、ハル子は言った。……そういや忘れてたな。あの玉、キレイだったもんで、剣が大事に持ってるよ」
太郎の目尻がほころぶと、銀平もハル子の姿を想うように言った。
「俺は初めてハルちゃんにオコゼをすすめた時、驚いたんでぇ。日本酒の古酒とおぼろ昆布でしめた白身を天麩羅にするてえ方法に、目を丸くしちまった。それってよ、銀座でも名の通った料理長が俺に教えてくれた、秘伝の品だったのさ。ハルちゃんは、それをいとも簡単に考えやがった」
古酒のヒネ香と甘さ、おぼろ昆布の旨味が、たんぱくなオニオコゼの白身に染み込めば、揚げるだけで最高の肴になるのだと、銀平は龍二とあすかに教えた。
「私、オコゼを食べるの、初めてなの……毒もあるのにためらわず、上手に調理してしまうハル子さんって、本当に割烹の女将さんですねぇ。かなわないなぁ」
語末のひと言は聞こえよがしのつもりだったが、そのあすかのつぶやきは太郎の耳に入っていないようだった。
「そうだったのか……じゃあ、俺もいっちょ、やってみるか」
目尻を下げる太郎は出刃包丁を取り出すと、オコゼの毒針を断ってから、はらを裂いた。その時、包丁の切っ先が何かに当たり、太郎が目を凝らした。
はらわたから転がり出たのは、血がにじむ白い玉だった。
「何だ、こりゃ……おいおい、これって真珠じゃねえかよ」
血のりを洗うと、太郎の手のひらに直径7ミリほどの真珠が絹のような輝きをまとっていた。
「豚に真珠……じゃねえ! オコゼに真珠なんて、ありえねえだろ!?」
呆気にとられるあすかの前で、銀平が信じられないといった顔をかしげた。
途端に、龍二が手を打って、叫んだ。
「あっ! 英虞湾って、真珠の養殖イカダがひしめいてる海じゃないですか。てことは、イカダから落ちた真珠貝をオコゼが食べちゃって、真珠を胃袋に残したまま、鯛の網にかかったってわけですか。これは本当に、縁起物ですよ」
真珠はいびつな形で、お多福豆のようだった。それが、かえって珍しさを引き立てた。
「で、太郎さん、この真珠はどうするよ……また、剣のお宝にしておくかい?」
銀平がオコゼの皮剥きを手伝おうと、厨房に入りながら訊いた。真珠は、太郎の手拭いでピカピカに磨かれていた。
「いや……よけりゃあ、あすかにあげるよ。初めてオコゼを食べる記念に、どうだい。もらってくれると、オコゼ好きだったハル子も喜んでくれそうだ」
太郎の声に、あすかが頬を火照らせた。期待しなかったわけではないが、思いがけない言葉だった。
「えっ! 私に? うん、頂きます! 私、ずっと大切にします! これってティファニーのビーンズみたいだから、ネックレスに加工しようかな」
真珠を受け取ったあすかは、げんきんなほど機嫌を直した。そして冷蔵ケースの前に歩み、ガラス窓を鏡にすると、真珠を喉元にあてがった。
そのようすに、龍二は苦笑をもらした。
厨房でオコゼをさばく太郎が、銀平に肩を並べて訊いた。
「ふっ……あすかの元気が出りゃ、オコゼ玉も価値があるってわけだ。それよりお前、どうしてオコゼなんて持って来たんだよ」
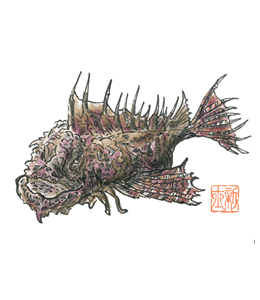
銀平は、太郎が出刃包丁で落としたオコゼの顔を骨せんべい用にさばいた。
「オコゼはよう、うるせえ女を黙らせるのには好都合なんだと、昔、親父に教わってよ。カミさんのことを、ヤマノカミてぇだろ。うちのオフクロの機嫌が悪くなると、親父はいつもオコゼをさばいてた。自分よりもブサイクなオコゼを見てると、オフクロは腹も立たなくなるんだって俺に耳打ちしたのよ。だからよ……ここ数日、虫の居所が悪いあすかも治るんじゃねえかと思ってよ」
ヤマノカミという俗称は、かつて全国の農村でオコゼの干物を山の神への供物にする風習があったことに由来していると、銀平は付け足した。
「じゃあ、オコゼ玉は、思わぬヤマノカミの御利益ってわけか」
「ちげえねえ。ほら、もう上機嫌じゃねえか」
ニヤけっぱなしのあすかの指先で、オコゼ玉が淡い光を放っていた。
