花曇りの空から時おり射す陽射しに、温もりを感じる頃になった。
桜前線が予想され、上野公園や日比谷公園には朱色のぼんぼりが準備されている。もう半月もすれば、東京は春を迎える。
毎年そんな頃になると、ポンバル太郎へやって来る連中がいた。テーブルを囲み、訛り言葉で飲み交わす山出しの男たちだった。
太郎がお久しぶりと、彼らに愛想をすれば
「あいやぁ、マスター。俺たちゃ、渡り鳥みてえなもんだべさぁ」
と恥ずかしげに東北弁を返した。
男たちは、秋田県から建設現場の出稼ぎに来ていた。
東京ではガテン系で働く若者が減って人材不足のせいで仕事は多いと、気のよさげな赤ら顔を見せた。
「もうひと月もすれば、田植えですか。だから皆さん、それぞれのお国へ帰って行くんですねぇ。その前に、一緒に汗した仲間とお疲れさまの酒で別れを惜しむ……いいですねぇ、日本人ですねぇ」
カウンター席から酔っぱらった男たちを見つめる平 仁兵衛は、すこぶる機嫌がいい。
平がうまそうに盃を飲み干すと、横に座る右近龍二が純米酒のお銚子を傾けた。
「毎年、4ヵ月くらいの単身赴任か。僕らのような都会人は慣れっこですが、2世帯同居が多い東北の人たちは精神的にキツイでしょうねぇ」
龍二が問わず語ると、男たちの一人が答えた。中年の男はかなり酔っているらしく、人懐っこい笑顔がこぼれた。
「だどもねぇ、冬場に国さいると金ばっかり使って、ロクなことがねえんだ。パチンコで大負けしちまってよぉ」
すると隣りの白髪の男が、破顔一笑した。
「それだっけぇ、武田。おめえはカアちゃんに追い出されて、東京さ来てるんだべ」
賑やかな笑いに包まれるテーブル席に、龍二たちもつられて吹き出した。
だが、カウンターに一人で座る短髪の男は無口だった。独酌で傾けているのは秋田の本醸造で、テーブルの面々と同じ作業服を着ているが、一人離れてしみじみ飲んでいた。
龍二が短髪の男に目をやると、平も顔をもたげた。男の前へ太郎の置いた鉢が、ハタハタで山盛りになっていた。
二人があっけにとられていると、近寄った太郎もため息をもらした。
「俺も驚いたよ。三人前を鉢に入れてくれってんだ。しかも卵のブリコも、たっぷりって注文だ」
ハタハタは、むろん火野屋から銀平が届けていた。男鹿半島沿岸で獲れた極上物で、卵のブリコも新鮮だった。そろそろシーズンも終わりだが、これを目当てにやって来る客は多い。
男は太郎たちの視線を気にせず、ボリボリと音を立ててブリコにかぶりついた。
「あの食いっぷりは、まちがいなく秋田の人ですなぁ」
盃を持ったまま感心する平の後ろで、武田が言った。
「あの人、佐川さん。男鹿の港町育ちでよぉ。俺たちのほとんどは農家だども、あの人は漁師上がりさ」
「……だから、皆さんとはあまり喋らないってことですか?」
武田は首を小さく横にふると、龍二と平の耳元でささやいた。よく喋る口が、酔うとさらに軽くなる性格らしい。
「2年前に、猟師だった一人息子が冬の海で亡くなってさぁ。息子の敵みてえに、目の色変えてハタハタを食うんだよ。だっけぇ、ああなると、俺たちも佐川さんに近づかねえの」
途端に、武田の丸めた背中に佐川の声が飛んできた。
「別に、俺はハタハタを恨んでなんかねぇべ。息子が獲ったのと同じ男鹿のハタハタだがら、腹いっぺ食いてぇだげだ! なんもおめえに、迷惑はかけてねえべ!」
店内に響いた佐川の太い声に、奥のテーブルに座るビジネスマンたちが目を丸くした。
出稼ぎの男たちが水を打ったように静まると、平が聞こえよがしに口を開いた。
「ハタハタが魚へんに雷って書くのは、冬の稲妻が秋田の海に走る頃に獲れるからと聞きました」
「そんだ。ハタハタが産卵に岸へ押し寄せる。そこを、浅場にしかけた網で獲る。まさに一網打尽だ。だげど、吹雪いて海が荒れると危ねえんだ。俺の息子は、陸からたった50m沖で船がひっくり返って死んじまった」
佐川は噛みつぶしたブリコを喉に流し込むように、秋田の本醸造を飲み干した。
「これは申し訳ない……つまらないことを訊いて、佐川さんに嫌な思いをさせました」
話しをすりかえるつもりが、なおさら暗くした平が佐川に詫びた。
佐川は手酌でお銚子を傾けたが、空だった。
「どうってこたねえ、平気だ。ただ俺のような漁師には、農家の奴らとはちがって“板子一枚、下は地獄”ってのがついてまわる。土の上で生きてる奴らに、俺や息子の気持ちなんて分かるわけねえんだ」
少しずつ声音が荒くなっている佐川に、出稼ぎの男たちから愚痴や文句がもれ始めた。
気まずい雰囲気に、龍二が空いている佐川の盃に酒を注ごうとした時、太郎がカウンター越しに立った。手には朱塗りの片口を持ち、燗酒の湯気が立っている。
「これ、おもしろい燗酒です。いかがですか、サービスですよ」
佐川は右手の箸でブリコをつまみながら、左手を横にふった。
「そんな、気を遣うことはねぇべ。大っきな声を出して悪かったなぁ、もう俺は黙ってるからよぉ。それに、俺は男鹿の酒しか飲まねえ」
ぞんざいに返事する佐川に、今しがたの仕返しとばかり武田がからんだ。
「けっ、男鹿の酒よりうめえ酒は、秋田にはいっぺだ!」
ほかの面々も、小さい頷きを繰り返した。
顔色を変える佐川に、太郎は隙を与えず片口を差し出した。
「これは、佐川さんにも武田さんにも美味しいと言わせる酒です。二人とも、騙されたと思って飲んでみて下さいよ」
渋々、盃に注がれた酒を口にした佐川だったが、「うぉ!」と唸ったまま太郎の顔を見返した。
怪訝な顔で盃を差し出した武田も、口にするなり「うっ、うめえ!」と叫んだ。
二人の豹変ぶりに、酒にうるさい龍二も盃を差し出した。そしてひと口飲むと、「これって……しょっつるの味」とつぶやいた。
片口の湯気をかぐ平が、目尻の皺を広げて驚いた。
「ほう、どうすれば、こんな香ばしくて、磯の香りがするお燗酒にできるんですか……ひょっとして、ハタハタがからんでますかね」
「平先生、正解です。こいつですよ」
太郎が厨房から持ち出した行平鍋には、燗酒の中にハタハタとぶりこが漬かっていた。
「男鹿の魚醤のしょっつるに漬け込んだハタハタとブリコを炭火で少し炙って、白神の山間部の濃厚な純米酒であっためるんです。いわば、海と山の共演の“ハタハタ酒”です。お燗する間に、ハタハタの旨味としょっつるの風味がどっしりと辛い酒にとけ込んで、秋田人好みの変わり酒になる。佐川さんも武田さんも、塩辛いの好きでしょ?」
太郎が見せた行平鍋に二人はお互いの顔を見合わせ、ためらいながらも頷いた。
すると、テーブル席の出稼ぎ者たちが、次々に片口を回し始めた。
「うんめぇ! こりゃ、いける」
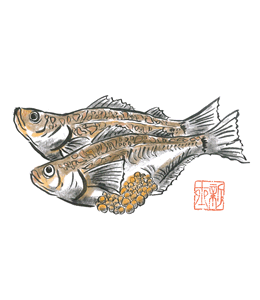
「ああ、うちさ帰えったら、さっそく、かあちゃんと飲むべ!」
「あんれぇ、おめえは嫁さ、大嫌いじゃねがったか?」
テーブルにようやく会話と笑い声が戻ると、佐川が言った。
「……俺も男鹿へ戻ったら、息子の位牌と飲むべ。きっとあいつも、うめえって言う。こんだな飲み方、知らなかったてなぁ」
目頭をおさえる佐川に武田が走り寄って、そっと肩に手を置いた。秋田人同士の純朴さに、龍二は胸の中で拍手していた。
出稼ぎの男たちを見つめる平が、ハタハタ酒を飲みながらつぶやいた。
「よかったですねぇ。また皆さんいっしょに、ポンバル太郎へ来て欲しいですねぇ」
「ええ、来年はきっと佐川さん、ハタハタ酒にいい気分で酔っぱらってますよ」
お燗酒の湯気の中で、男たちの笑顔が揺れていた。
