ぎらつく陽射しが、青山や原宿に半袖スタイルの若者たちを呼んでいた。竹下通りでは、夏まで待てないタンクトップ姿の店員たちが声高に売り込みをかけている。
ギャルたちに視線を奪われているのは、やっと東京に慣れつつある新入社員だろうか、垢抜けない格好の青年も目立つ。
そんな昼下がりの日曜日、ポンバル太郎は珍しく店を開け、カウンター席の火野銀平が冷酒グラスをなめている。
「うへへ、休日の昼酒ってのは贅沢だぜぇ。それにしてもよう、中之島の師匠様々だ。アグー豚と海ぶどうなんて、めったと口にできねえや」
脂がのってるアグー豚に合わせるつもりで、もう銀平は冷蔵ケースから加賀の山廃純米酒を取り置きしている。
「まったく、こらえ性のねえ野郎だな……まぁ、それぐらい食い意地が張ってねえと、築地じゃ勤まらねぇか」
たしなめる太郎だが、その喉も海ぶどうに期待して、唾を飲み込んでばかりである。
昨日、那覇を旅している中之島から、極上の食材を手に入れたので、このまま東京へ飛ぶと太郎へ電話があった。けっこうな量だから、休みにすまないが常連たちを集めておいてくれと、沖縄の陽気のように高笑いした。
「太郎さん。海ぶどうに合う酒って、どれだよ?」
気もそぞろな銀平が、二番目の酒を物色した。それを差し止めるかのように、勢いよく開いた玄関から赤いタンクトップ姿の高野あすかがが飛び込んで来た。
「あ~、いやらしいわね。その山廃純米酒、私も狙ってたのにぃ~」
銀平の顔が、真っ赤に染まった。大きく揺れるあすかの胸に見惚れ、下心を見透かされたと勘違いした。
「な、な、なんでぇ! 今日は特別営業だから、早い物勝ちなんだよ」
たじろぐ銀平にあすかが食ってかかろうとした時、開けっ放しの玄関扉から声が聞こえた。
「あのう、ランチとかやってますか?」
真ん丸の目と濃い眉毛の印象的な青年が、浅黒い顔を覗かせていた。どことなく九州の訛りを感じたのはあすかだけでなく、偶然に青年の後ろからやって来た手越マリも同じだった。
「あんた、奄美か沖縄の人やなかね。顔つきも濃いばってん、すぐに分かると」
ぶっきらぼうなマリの目尻がほころぶと、青年は嬉しげに声を弾ませた。
「あ、そ、そうですかぁ! おばさんは、南九州ですか?」
「おっ、おばさん!? これぇ、なんば言いよっとね、この子は」
ふくれっ面するマリの目元は、どことなく青年と似ていた。
太郎がランチはやってないと答えるのも忘れて吹き出すと、銀平はつられて口をすべらせた。
「だけどよう、“お姉さん”はちょいと無理じゃねえかぁ……あっ、いけねぇ!」
「銀平! もいっぺん、言うてみんしゃい!」
マリは邪魔だとばかりに青年を突き飛ばし、カウンター席へ詰め寄った。転びそうになる青年を支えたのは、ようやく着いた中之島だった。
「昼間っから、できあがってるなぁ。まあ、それぐらい盛り上がってくれんと、わしの土産も値打ちがないわ」
寄りかかった中之島の腕に、青年の目が釘づけになった。海ぶどうの包みを目にした青年は、ふいに体の力が抜けたようにくずおれた。一瞬、気を失いかけたようだった。
「おいっ、大丈夫か。銀平とマリさん、もめてる場合やないがな。この兄ちゃんを、早うテーブル席に運んでくれ」
途端に全員が立ち上がり、長椅子の上へ青年を横たえた。銀平が氷水のグラスを手にすると、太郎はおろしワサビを箸でつまんだ。
「気つけ薬だよ。おい、大丈夫か」
鼻先に本わさびを近づけられた青年は、小さく唸りながら薄目を開けた。
「う、海ぶどう……さっきのは、本場の沖縄の海ぶどうでしょ」
つぶやく青年の前に中之島が包みを差し出すと、両目から涙がこぼれた。ワサビのせいではないようだった。
「あんた、沖縄から出て来たばっかりやなかね……ばってん、東京ばまだ知らんけん、寂しかやろ。最初は、食べ物も口に合わんけんねぇ」
同情するマリが、銀平に逆立てたばかりの目尻を垂らした。マリの南国人の勘に、中之島やあすかも頷いた。
銀平から水を受け取った青年は島袋正雄と名乗り、まだ二十歳だった。
ポンバル太郎の一筋裏にあるアパートに暮らしていると言い、太いちぢれっ毛の頭を掻きながら起き上ると、中之島が手に提げるもう一つのアグー豚の包みに目を丸くした。
「そうかぁ、しゃあないな。太郎ちゃん、島袋君に特別ランチを作ってあげようやないか」
中之島の声に指をくわえていた銀平が「ええ~、そんなぁ」とぼやくと、マリは「あんたは黙りんしゃい!」と釘を刺した。
太郎が動かす包丁と菜箸が、見る間に海ぶどうのサラダ、アグー豚の塩焼きを作り上げた。そのうまそうな香りに、あすかやマリも鼻をひくつかせた。
おあずけを食って口惜しげな銀平に、島袋は気を遣って「お先にどうぞ」と皿を差し出した。山廃純米酒を握ったままの銀平の手が、島袋は気になっていた。
しかし、銀平は首を横にふった。
「おめえが先に箸をつけなきゃ、俺たちは口にしねえ。それが、この店の暗黙の了解みてえなもんでよ。どうでぇ、この酒もひと口やってみねぇか」
江戸っ子の銀平のおしつけが、人懐っこい島袋には嬉しかった。思えば、上京して二か月、これほど優しい面々はいなかったが、島袋はもどかしげに答えた。
「あっ……すみません、僕は日本酒を飲んだことがなくて。泡盛なら、大丈夫なんですが」
島袋の申し訳なさげな視線は、何度もマリに注がれている。九州人への親しみが、そうさせていた。
銀平が情けないと言いたげに鼻を鳴らすと、太郎も素っ気なく答えた。
「悪いが、うちは日本酒の専門店だから泡盛は置いてねえんだ」
わざとらしい二人の態度に気づいたあすかがマリへ片目をつぶり、島袋に言った。
「せっかく東京へ来たんだから、日本酒に慣れた方がいいわよ。でも、泡盛はアルコール度数が高いしドライな米焼酎だから、同じタイプの日本酒ってないなぁ」
あすかの声は、マリの方へ流れていた。それを追うかのように、島袋がマリに訊ねた。
「あの……オバさんが好きな日本酒なら、僕にも合いそうです。選んでくれませんか?」
銀平が顔をしかめて、つぶやいた。
「あっ! バカ野郎、またオバさんって……」
しかし、マリはおだやかな目元で冷蔵ケースの前に立ち、島袋を手招きした。マリが取り出した“アルコール30度”の四合瓶に、島袋が小首をかしげた。
「酒粕焼酎。これは日本酒を搾った酒粕から造っとると。でも、れっきとした焼酎たい。あんたの好きな泡盛も米で造るけん、似とるとよ。まずは、これに慣れてから、日本酒を飲めばよか」
相好をくずしたマリの顔にほころぶ島袋の目元は、親子のようだった。
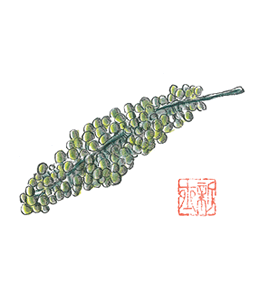
カウンター席の真ん中に、海ぶどうとアグー豚、それに酒粕焼酎のグラスが並ぶと、島袋は両手を合わせてつぶやいた。
「ゆいま~る……皆さん、ありがとうございます」
太郎たちの不思議そうな顔に、中之島が口を開いた。
「沖縄言葉の“ゆい”は結いちゅう意味で、助け合いの心。“ま~る”でそれを仲間と回し合うっちゅうことや。島袋君、ここは大都会の東京やけど、いつでも助け合える人が集まる店なんや」
海ぶどうをつまみ食いする太郎が、満足げに言った。
「東京にだって、“ゆいま~る”みてえな人情はあるぜ。この界隈の下町は、江戸時代から裏長屋の共同生活が長くってな。今でも、ご近所付き合いは厚いもんだ。遠慮してちゃ、いけねえよ。まあ、気の合うマリさんに甘えてみるこった」
その隙に海ぶどうへ指を伸ばす銀平から、マリが皿を取り上げた。
またもひと悶着起こると、酒粕焼酎のグラスに島袋の嬉しげな顔が揺れていた。
