薄暮の隅田川に、屋形船の火影が揺れる頃になった。暮れなずむお台場へそよぐ風は、もう夏の潮の匂いをかがよわせている。
そんな東京湾べりの夕涼みが外国人観光客に好評なのだと、テーブル席の客たちが噂をしていた。
純米吟醸を飲みながら、男たちの駄弁をカウンター席で聞き流している高野あすかがつぶやいた。
「近頃は船頭さんに外国人の男性もいるし、何だか江戸の粋も混沌としてますねぇ」
隣りに座る中之島哲男が、青森の純米酒のぬる燗の盃をなめながら
「大阪も似たようなもんや。犬も歩けば、外国人に当たるてな感じや。まあ、ぎょうさんお金を使うてくれるよって、しゃあないわ。電化製品も爆買いしとるしなぁ。この青森のマグロかて、せり落とすのは中国の寿司屋の経営者らしいやないか」
と皿に盛られた大ぶりの赤い切り身を見つめた。
ポンバル太郎の壁に貼られた今日のオススメには、青森産 黒マグロの刺身と赤字で書かれている。
それに気づいたあすかが、目をしばたたいた。
「太郎さん、珍しいですね? 値段が高いから、青森の大間産は取らないって言ってたのに。あっ、ひょっとして銀平さんのゴリ押し?」
厨房へ投げられた声に、太郎が朱色の椀を手にして現れた。薄白く濁ったダシの中には、オレンジ色の塊が透けている。
「ああ、大間じゃなくて、八戸沖で獲れた値頃な黒マグロが手に入ったから、試してくれってよ。実はこれも、同じ八戸のバフンウニを使った料理だ。中之島の師匠、ちょいと味見してくれませんか」
あすかと中之島の前に置かれた椀の湯気は、強い磯の香りを漂わせた。その料理を初めて目にしたらしいあすかが眉をゆがめた。
ほろ酔い顔の中之島は、ひと目見て即答した。
「ほう! “いちご煮”かいな……わし、若い頃にいっぺんだけ八戸へ行ったことがあってな。地元の食堂の奥さんに、本場のいちご煮を作ってもろたことがあんねん」
太郎が中之島の知見に、さすがと言いたげに頷いた。
「火野屋に、かなり目利きのできる新人が入ったらしいです。今夜、銀平がその人を連れて来るんですよ。その前に、みんなに味をみてもらいてぇって頼まれましてね」
いちご煮の呼び名に、あすかが椀の中を食い入るように見つめた。
「確かに、大きなウニの身がいちごのように粒立って見える……でも、アワビの薄切りも入ってるし、これだってポンバル太郎にしては、けっこうなお値段になるんじゃないですか?」
「それがなぁ……」と太郎が笑いかけた時、玄関の鳴子が音を立てた。
荒っぽい開け方に火野銀平とあすかは分かったが、後ろに立つ白髪の老人が気になった。
「……へぇ、新人てぇから若い奴かと思ったら、ずいぶんと御年配だ」
太郎が声を低くすると、あすかは呆気にとられたままだが、中之島は一瞬、老人に目を細めた。
「お待たせ! この人、青森から最近、東京に引っ越して来た石津健吉さん。元は、八戸の漁師でさ。今日の黒マグロも石津さんが直接、八戸の古い仲間から仕入れたんだ。これからも石津さんのおかげで、安く手に入るぜ」
銀平によると、健吉は八戸の実家を引き払い、東京住まいの息子と同居を始めたばかりだった。興味があった築地市場を見学する内、火野屋の人材募集の貼り紙を目に止めたのだった。
あすかの横に立つ銀平の自慢げな声に、テーブル席の客も「へぇ! そりゃ、いいや」と酔った口を揃えた。
恥ずかしげに縮こまる健吉だが、胸回りは若い頃を髣髴とさせるほど厚く、日焼けした皺深い顔が赤面するというよりも褐色になった。太い手首には、火傷のようなシミがくっきりと残っていた。
「そ、そうなんだ。じゃあ、熟練の漁師さんだったんですねぇ」
健吉の人となりを聞いたあすかが、カウンター席へ誘った。うつむきかげんに座る健吉の横顔を、中之島は黙って見つめていた。
「ところでよ。マグロの味は当然、太鼓判だけどよ。どうでぇ、バフンウニは? 中之島の師匠、まだ食ってねえんですかい?」
せかす銀平に、はっとする中之島が「ああ、今からや」と生返事を返した。待ちきれないあすかは、いちご煮を口に運んでいた。
「ウニが、あっま~い! アワビのダシが効いてるのね」
あすかの感想に、銀平が満足げに胸をそらした。だが、いちご煮の匂いをかいだ健吉は肩を落としていた。
ひと口、ダシを含んだ中之島が無表情で言った。
「……ほんまもんのいちご煮とは、ちがうわ」
小さく相槌を打つ健吉のようすを目にした太郎は、中之島に問いかけた。顔を見合わす銀平とあすかが耳をそばだてた。
「何が、ちがいますか? 青森特有のサバ節のダシでしょうか?」
「いいや、まったくちがう物……ショウガや」
中之島の声に、健吉が打たれたように顔を上げた。驚く健吉の表情を、まばたき一つしない中之島が真っ直ぐ見返していた。
「しょ、ショウガ? それだと、磯の風味やダシの旨味もずいぶん変わっちゃうわ」
あすかが太郎へ訴えるように言ったが、健吉と中之島の耳には入っていなかった。身動きしない二人を、銀平は、「えっ……いったい、どうしたんでぇ?」と見比べた。
中之島が先に口を開いた。健吉が寡黙なのは、青森人の性質である。
「ほんまにお久しぶりやな、健吉はん」
ようやく合点がいったのか、健吉が「あっ、ああっ」と洩らして立ち上がった。そして、人が変わったように声を上ずらせた。
「哲っちゃん。大阪の哲っちゃんかぁ? なんだべぇ、こりゃ、おったまげだぁ」
「ああ、そうや。あんたに命を救われた中之島哲男やがな」
どちらからともなく歩み寄って肩を抱き合う二人を、客の全員が茫然と見つめた。驚きの展開に、あすかは思わず銀平の手を握りしめていた。
静まった店内に、中之島の問わず語りが低く聞こえた。
「八戸の磯には、素もぐりで漁をする“かづき”っちゅう男たちがおってな。いわば、男の海女さんや。その親方が、この健吉はんやった。そやけど、あの頃は石津やのうて、塩田っちゅう名字やったわなぁ」
三十年前の夏、八戸の磯場で釣りを楽しんでいた中之島は高波にさらわれ溺れかけた。それを助けたのが、かづき漁師の健吉で、妻は塩田屋という名の食堂を浜の近くで営んでいた。
塩田屋は獲れたての魚介類を食べさせる店で、ずぶ濡れのまま担ぎ込まれた中之島は、飛び切り熱い八戸の地酒と健吉の妻が作ったショウガ入りのいちご煮に救われたのだと語った。
「健吉はんの右手首の怪我の痕は、わしのせいや……溺れかけたわしに、かづきの命綱を巻きつけて船まで引っ張ってくれた。荒波の中、わしの重さで手首が切れて、皮膚もボロボロになってしもたんや」
中之島は健吉の右手を取ると、目頭を潤ませて頭を下げた。震える中之島の背中を健吉が左手でさすりながら、はにかむように言った。
「八戸は、夏でも風が冷たいっぺよ。かづき漁には、あったけぇ番屋の焚火といちご煮が欠かせねえ。体さ、温もるために、かづき漁師は輪切りにしたショウガを一緒に煮込むのさぁ」
健吉の八戸訛りに、誰もが目尻をほころばせた。
中之島が、思い出したかのように訊ねた。
「あんたのヨメはん、元気かいな?」
「ああ……去年にあの世さ、行っちまった。そうだでぇ、塩田屋の婿養子だった俺は、店をたたんで石津に名字を戻して、東京にいる息子の世話になることにしたのさ。しっかし、東京って町は人がいっぺえいで、俺は溺れそうだぁなや」
おどけるように健吉が答えると、中之島に笑顔が戻った。
「ほんなら今度は、わしがあんたを助ける番やな。これからも八戸の酒と肴で、一杯やりましょうな」
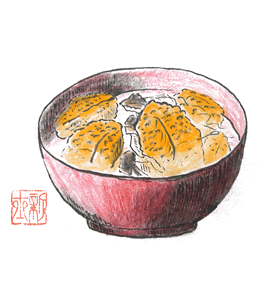
頷き合う二人の鼻先に、ふわりとショウガの匂いがした。
太郎がカウンターの隅に、いちご煮の椀を二つ並べていた。もちろん、作り直したショウガ入りだった。
中之島が打ち明けた過去の傷に、鼻先を赤くしたあすかは感慨深げに言った。
「いちご煮って、私たちにはごちそうに見えるけど、かづき漁師には素朴な料理なんだね」
「ああ。俺にとっちゃ、二人の話しだけでもごちそうだ。それによ、おめえのあったけえ手も、今夜はこちそうさまだねぇ」
鼻の下を伸ばした銀平が、まだ握ったままのあすかの右手を持ち上げた。
「キャア! なにすんのよ」
我にかえったあすかが、銀平の頬をひっぱたいた。
吹き出す中之島と健吉の瞳に、オレンジ色のいちご煮が揺れていた。
