梅雨入りもしていない東京を、今年九つ目の台風がかすめた。足取りの遅い雨風に、新幹線だけでなく羽田や成田の航空便は三日続きで混乱に陥っている。
そのせいで、アメリカへの帰国を伸ばしたジョージの友人たちがポンバル太郎のカウンターに顔を並べていた。
「でも、台風のおかげで美味しい日本酒が今夜も飲めました。しかも、ニューヨークよりもずっと安いです」
流暢な日本語を使うシルバーヘアの男性は、太郎が渡した白磁の平盃の扱いに慣れている。お燗酒の温度も「“日なた燗”でお願いします」と頼んでいた。
「ジムの日本酒好きは、ニューヨークのレストランで有名なんです。ほかのお客さんへメニューと合わせる酒の種類や温度を教えてあげたり、コーディネートもできますよ」
ジョージが褒めそやすと、ジムは色白な目尻に皺を寄せてはにかんだ。歳は三十前後に思えた。
ジムの飲みっぷりに見惚れる右近龍二が、隣りから訊ねた。
「アメリカに温める酒文化ってないけど、お燗酒は広がってるんですか?」
「まだまだです。“Hot Sake”と呼ばれていますが、安い居酒屋ではマグカップでサービスされたりで、日本のような“さしつさされつ”の風情はありません」
盃を飲み干したジムがしなやかな指先で返杯すると、太郎は「サンキュー、でも仕事中だから」と断った。その盃を奪い取る浅黒い手が、ジムの肩越しに伸びた。
「“さしつさされつ”を知ってるたぁ、てえしたもんだ。せっかくだからよう、俺が太郎さんに代わって“お流れ頂戴”いたしやしょう」
江戸言葉を吐く火野銀平に、ジムの顔が嬉々とした。見開いた両目には、銀平の剃った頭が光っている。
「オウ! お流れ頂戴は知っています。あなた、江戸っ子ですね。粋な言葉をもっと聞かせてください。がってんだ! べらぼうめえ!」
興奮したジムがジャケットの内ポケットから手帳を取り出すと、ジョージが飽きれ顔を見せた。ほかの外人客たちも銀平とジムのやり取りに興味津々のようすで、冷酒グラスを口元に止めた。
「なんでぇ、あんたジョージと同じ穴のむじなかい。酒を飲む時ぐれぇ、ペンを置きな」
「お、同じ穴のむじな? って、ホワッツ?」
しかめっ面の銀平へおもねるジムの手帳には、江戸時代の浮世絵をまねた線画が描かれていた。男に酌をする日本髪の美人画に似ている。
「ほう、なかなか上手いじゃないか。そりゃ、吉原の遊女の絵か……おまけに、胸元でお銚子を温めてる。なかなか、粋だねぇ」
カウンター越しに太郎が声を上げると、ジョージは前のめりになって絵を覗いた。
テーブル席の常連客も食い入るように手帳を凝視したが、ジムは浮かない顔でつぶやいた。
「その江戸の粋を、ニューヨークにいる私の彼女のルーシーは分かってくれません。私は、こんな風に“人肌燗”をして欲しいのですが……日本人のおもてなしが、彼女には分からないのです」
ジムが言うには、ルーシーもニューヨーカーで、最近、和食と日本酒のファンになった。しかし、お燗酒をジムが勧めても首を横に振り、太陽の熱で温める日なた燗や体の熱で温める人肌燗はまともじゃないと口を尖らせた。
ジムのぼやきに、カウンター席に座る外人女性から非難が飛んだ。英語まじりの日本語だったが、胸元で酒を温めている遊女をルーシーに重ねるのはまちがいと言うのを太郎も理解できた。
口ごもるジムの盃へ、龍二がなぐさめるように酌をした。
「まあ、確かに江戸時代の人肌燗は、この絵のままなんですけどね……今じゃ、日本でもやりません。古き良き文化とはいえ、そのままやっちゃうのはモラルとして難しいですよ」
それでも承知できないのか、ジムは龍二に食い下がった。めくった手帳に、酒宴の浮世絵がいくつも描かれていた。相当、江戸文化に憧れていると見える。
「でも人肌燗は、江戸のオモテナシの形でしょ。もう一度、やってみればいいじゃないですか」
埒が明かないと両手を挙げるジョージに太郎が苦笑いすると、黙っていた銀平が口を開いた。
「あのよう、勘違いしちゃいけねえぜ。肌で燗をするってのはよう、色っぽい話しじゃねえんだ。火をおこせねえ時に、どうにかしてあったけえ酒を飲ませてやりてえからだ。つまりよ、それほど差し迫った状況ってわけよ。貧しくって炭を買えない家で、女房が主人のためにうまい燗酒を飲ませてえ。病人にもあったけえ酒を飲ませて、体を温めてやりてぇ。だけど、あんまり熱くっちゃいけねえ。体温ぐらいに、ほどほどがいい……そんな情けってのが人肌燗には込められてるんでぇ。だからよう、形だけのお燗酒じゃねえんだ」
キョトンとしているジムや外人客たちに、銀平は「そう言っても、分からねえだろうなぁ」
と龍二に目を向けた。そして視線を、食器棚のブランデーグラスへ移した。
途端に、龍二が声を発した。
「あっ! なるほど。その人肌燗がありましたかぁ」
閃いた龍二は大ぶりの丸いグラスを取ってジムの前に置くと、常温の純米酒を半分ほど注いだ。
ジョージだけでなく、いぶかしげな顔の外人客に向かって、龍二はブランデーグラスを両手で包み、ゆっくりと回した。
「手で温めるんですよ、ジムさん。これならルーシーさんに、日本人のおもてなしの心がスムーズに伝わるでしょ」
目を丸めたままのジムの横で、思わずジョージが頭を抱え込んだ。
「オウ! どうして、こんなシンプルなことが分からなかったのでしょう。僕は日本酒のジャーナリストとして、まだまだダメですね」
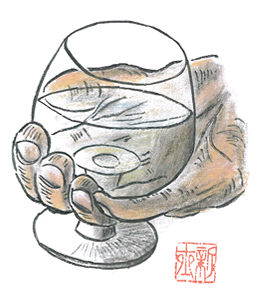
ようやくピンときた面々も、太郎へブランデーグラスを頼んで常温の純米酒を回し始めた。ほのかな香りが広まるカウンター席にテーブル席の常連客たちも、今まで気づかなかったアイデアだと頷いた。
いつしか店内のそこかしこで、手燗のグラスが回っていた。
「何だか、妙な風景だ。でも、まあいいか……クールなSAKEって時代だしな」
太郎のつぶやきに、銀平もぬくもった手燗を口へ傾けた。
「けどよう。俺の本音は、やっぱり胸元の人肌燗がいいねぇ。しかも、ある人の肌が一番あったけぇと思う」
「へぇ~、それって誰ですか?」
にやつく龍二の問いに、ジョージも聞き耳を立てた。
「そいつぁ、俺だけの秘密だよ……実はよ、さっきジムさんへ言った人肌燗の話は、その人から聞いた受け売りだよ」
とぼけた顔で答えると、銀平は誰も気づかない一瞥をハル子の写真を飾っている神棚へ投げた。
太郎も感づかれないよう、小さな感謝を銀平の横顔へ送っていた。
