都心のゲリラ豪雨が、そこかしこで排水溝をあふれさせていた。テレビでは気象予報士が白南風(しらはえ)の文字パネルを手にして、ここ数年の日本から消えてしまった季語だと解説していた。
そんな気象変化の影響なのか天然鰻が少なく、高値を呼んでいるとカウンター席の火野銀平がぼやいた。火野屋が扱う天然物の鰻は築地や深川の老舗を優先し、その次に太郎へ卸すが、今年はまだ鰻の白焼きや蒲焼きがない。
たとえ太郎が手に入れたとしても、メニューは唖然とするほどの値段になりかねない。程度を越えた時価は、割烹じゃないポンバル太郎の流儀に反するのだ。
「土日の多摩川の堰じゃ、天然鰻を獲ろうって奴らが向こう岸まで並んでいるらしいぜ。まったく、鰻もとんだ災難だぜぇ」
銀平は、多摩川産の鰻と飲むはずの福生の酒を渋い顔で飲み干した。
白焼きに目がない平 仁兵衛が、口惜しげに言った。
「昔から浅草辺りじゃ鰻は江戸前に限るって言いますが、今の神田川や隅田川で獲れた天然物じゃあ、臭くって食べれませんねぇ」
太郎は、つき出しの多摩川産の小鮎煮を平の前に置いた。天然鰻が手に入らない詫びの一品である。
「江戸前の鰻ってのは、御城の堀で獲れたのが最高にうまい。そんな言い伝えがありますが、眉唾な話ですね。江戸城の堀で魚を釣るなんてのは死罪になる御法度だから、でっちあげでしょう」
すると銀平が俺の出番とばかりに、太郎の話の腰を折った。
「俺がガキの頃、祖父さんに聞いた記憶じゃ、干潟や浅場が広がっていた戦前の東京湾は年間300トンくれえの鰻が捕れたそうだ。つまり佃島の漁師は、多摩川や荒川から下った鰻を鈎針で引っかけて獲ったんでぇ。それが今じゃ、埋め立てちまったからさっぱりだ。まぁ、うちじゃ扱えねえけど養殖物を広げるしか手はねえ。と言っても、数が減っちまった稚魚すら値が高けぇわけだしよ」
銀平がお銚子のおかわりを頼むと、テーブル席の男客も相槌を打ちながら、久しくランチの鰻重を食ってないとぼやいた。
太郎はお銚子を受け取りつつ、ためらいがちに言った。
「実は、蒲焼きに代用できそうな物が手に入ってよ」
「な、なんでぇ? それって、鰻じゃねえんだろ? じゃあ、ダメだ」
とがめる銀平の目が、冷蔵庫へ伸びた太郎の手元を探った。平も、その塊が何なのかと老眼鏡の奥の目を凝らしている。
「それが、驚くほど似てるんだよ……秩父の長瀞(ながとろ)で獲れた鯰の蒲焼きだ」
途端に、銀平が盃の酒を吹きこぼした。テーブルの客たちも、あんぐりとして太郎へふり向いた。
真空パックの袋の中身は開いた鰻にそっくりな、鯰の蒲焼きだった。
「鯰の白身も柔らかくて、臭わない。それに、蒲焼きのタレが東京とよく似てんだ。だから、おめえが好きな福生の純米酒に合うと思うぜ」
「だ、だけどよう、蒲焼きってのは鰻が当然だろ。鯰なんて、俺は食ったことねえぜ」
腰の引ける銀平を、平がたしなめるように笑った。むしろ、鯰の蒲焼きに興味津々の目つきである。
「おっほっほ。こりゃ、おかしい。海だろうが川だろうが、銀平さんは魚のプロじゃないですか。ここは一つ、騙されたと思って試してみませんか。もちろん、私もご相伴に与りますよ」
おっかなびっくりの銀平をよそに、平が太郎へ鯰の蒲焼きをせかした。その時、玄関の鳴子がカラコロと音を立てた。やって来たのはジョージと右近龍二で、先週末、二人して飛騨高山を旅していた。むろん、地酒の蔵元めぐりも兼ねている。
カウンターへ座るや、ジョージが鞄から土産包みを取り出し、太郎へ披露した。褐色の真空パックに入った塊りに、思わず銀平と平が目をしばたたいた。 「木曽川周辺で食べられている、鯰の蒲焼きなんですよ。これが、飛騨の鬼ころしにピッタリくる味でして。辛くてコクのある八丁味噌や醤油のタレが、鯰の臭いを包んでしまうんですよ。だから、地酒の鬼ころしも、辛くてどっしりしてる。ぜひ、試してもらいたくて、お土産に……あっ、あれ?」
鬼ころしの酒瓶を鞄から取り出す龍二が、太郎の手にある長瀞鯰の蒲焼きに目を丸くした。ジョージも、瓜二つの蒲焼きを何度も見比べている。 「こりゃいいや、鯰が鯰を呼んじまったか。銀平、観念して食わなきゃしかたねえぞ」
二つの蒲焼きを取り分けた皿が、カウンターだけでなくテーブル席の客たちにもふるまわれた。
それでも怪訝な顔の銀平を口説いたのは、ジョージだった。
「アメリカでは、鯰をフライにしてソースで食べます。ニューヨークやカリフォルニアじゃなくて、ミシシッピとかの沼や池の多い町です。でもね、昔から土地のバーボンやビールにとっても合います。だから日本の鯰の蒲焼きも、きっと同じです。秩父の地酒と長瀞の鯰、飛騨の鬼ころしと木曽川の鯰、これって、とても素晴らしい」
銀平からお株を奪うジョージの切り口上に、龍二が手を叩いて喜んだ。
温めた鯰の蒲焼きに、テーブル席の客や平から「うおっ! うまい!」「こりゃ、鰻と変わりませんねぇ」と感嘆の声が上がった。
銀平は、いよいよ箸をつける段になってカミングアウトした。
「あのヌメッとして、ボテッとした鯰が、俺は苦手なんでぇ。鰻なら細くて、大丈夫なんだけどよう」
そんな言い訳にも、カウンター席の面々はいたずらっぽい笑いを浮かべた。
「ええい! ままよ!」
木曽川の鯰を口へ放り込んだ銀平が、呑み込むように鬼ころしを流し込んだ。ゆがんだ顔が、見る間に明るくなった。
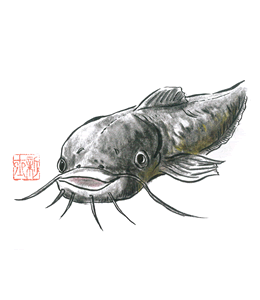
「おっ! おお、イケる! 鰻と変わらねえや。しかも白身が、めっぽうふっくらしてるじゃねえか。太郎さん、うちの鰻が手に入るまで、これなら大丈夫だぜ」
魚匠の銀平の答えに、誰もが自分の舌で味わう鯰の蒲焼きの美味しさを納得した。
一変して箸を動かす銀平に、龍二が水を差した。
「だけど、銀平さんの頭も腹回りも、鯰みたいにヌメッとして、ボテッとしてますけどねぇ」
「うるせえ! まあ、いいや。俺はうまい魚を見分ける舌は持ってんだ。だから、見た目さえ我慢できりゃ、大丈夫ってことよ」
龍二とジョージが飽きれ顔を見せると、鯰の蒲焼きと地酒に満足げな平がつぶやいた。
「これだけ鰻と似てるなら、その内、鯰も獲られていなくなるかも知れませんねぇ。もし、いなくなったら、次はドジョウの蒲焼きを食いましょうかねぇ。私の故郷、石川県の名物ですよ」
むせ返る銀平に、大きな笑い声が巻き起こった。
