浅草寺のほおづき市や入谷の朝顔市が始まり、下町から夏祭りの威勢が聞こえる季節になった。土曜の夜は、ポンバル太郎のテーブル席にも浴衣姿の若者がやって来ている。
仲良く二つの冷酒を分け合うカップルを目にしながら、カウンター席の高野あすかがため息を吐いた。江戸小紋の浴衣を着こなすあすかの隣には、火消しの刺し子半纏に鉢巻きを締めたジョージが座っている。
あすかはジョージから同行を頼まれた、神楽坂ほおずき市の帰りだった。
「あ~あ、いつになったら彼氏と行けるんだろ」
頬杖を突くあすかの視線が、神楽坂の賑わいを太郎へ熱弁するジョージに向いた。道行く人たちから失笑を買ったド派手な格好だが、カウンター奥に座る中年の男は興味深げにジョージを見つめていた。手元には、常温のお銚子を置いている。
興奮気味なジョージの箸は、いっこうに肴へ動かない。その手元を見たあすかが、思わず声を上げた。
「ちょ、ちょっと! ジョージ。その食べ合わせはダメよ」
あすかの声の先に鰻の蒲焼き、ささみの梅肉焼きが冷酒グラスと並んでいた。何の変哲もないメニューに、ジョージが小首をかしげた。
「ワッツ? 食べ合わせって、何ですか?」
「あのね、昔から鰻と梅干は一緒に食べちゃいけないって言われてるの。ましてや冷酒じゃ、いっそうお腹の具合を崩しちゃうわよ」
皿を取り上げようとするあすかに太郎が顔を曇らせると、カウンター席の男が口を開いた。
「お嬢ちゃん。そりゃ、眉唾な話だよ。梅干しの酸味は、脂の消化を助けるんだ。だから、鰻には、むしろオススメなんだよ」
今風のジャージ姿に、ビジネスマンの気配は感じられなかった。歳の頃は、太郎と変わらず四十歳前後に思えた。
見とがめた男にあすかがキョトンとしていると、太郎は感心した顔で会話をつないだ。
「あすかでも、知らねえことがあるんだな。“鰻に梅干し”の食い合わせが悪いってのは、江戸時代に庶民が鰻を食べ過ぎるため、それを防ぐ幕府のデマだったって説もあるんだ」
実際、食べ合わせの何が悪いのか、その根拠をあすかは知らないままで信じていた。
「そうか……考えてみれば分ることよね。それに、ジョージの胃袋なら大丈夫かな。アメリカじゃ、いろんなソースをかけることで何でも一緒に食べちゃうものね。甘い味も辛い味も平気だし、それをビールやワインでガッツリ流し込むんだもん。その点、日本酒と和食はデリケートだな」
思い込みをはぐらかすあすかの言いぐさに、ジョージは不満げに言い返した。
「オウ! 私は、和食なら何でもワインではありません。例えば、イカやタコ。生の刺身は磯の匂いが強くて、醤油やワサビをソースにしても白ワインとは合いません。だけど米で造った冷酒は生臭い風味も包んでしまうから、大丈夫なのですよ」
近頃、ジョージは和食と日本酒の持論を述べるようになってきた。魚の知見は太郎も認めるところで、切り身の見分けができるほどである。
なるほどと頷くあすかに、ジョージは溜飲を下げるように純米酒のグラスを飲み干した。
「そうかい。じゃあ、こいつはどうだい?」
カウンターの奥から、男の手が小さな丸いガラス瓶をすべらせた。あすかとジョージの目前に止まった瓶には、緑色の得体の知れない物が入っていた。ドロリとした塊である。
瓶の鮎のレッテルに太郎が「あっ! 火野屋オススメの……」と洩らし、男はコクリと頷いた。
ジョージだけでなく、あすかも眉をしかめた時、二人の背中に威勢のいい声が聞こえた。
「そいつぁ、火野屋が夏を告げる珍味“鮎のうるか”だぜ。信州は千曲川漁師の手造りでよ。いやぁ、うめぇのなんの! その川漁師こそが、戸隠佑作さんだよ」
のっけから鮎のうるかを褒めちぎる銀平が、カウンター席の男を指さした。
中腰で会釈する戸隠に、テーブル席のカップルたちが首を伸ばした。鮎のうるかなど口にしたことがない世代は、希少な職人だろうと思った。
ジョージは太郎から鮎のうるかの正体を聞いたが、川魚のはらわたの塩漬けと知って箸先は気遅れしている。
食通を自負しながら初めて目にしたあすかは、自慢する銀平にいらだった。
「うるさいわよ! これから味見するんだから、黙ってて!」
「うへっ、おっかねえ」
銀平は酒と肴を注文すると、戸隠の隣へ逃げ込んだ。
腹を決めたあすかが、緑色の塊を舌先に運んだ。隣のジョージもつられて、口へ放り込んだ。味わった二人が見せる対照的な表情に、戸隠がほろ酔いの目尻をほころばせた。
「あっ! しょっぱくて苦いけど、草いきれがする! そうか、川の水苔の風味だわ。鮎の内臓を使ってるから、この味なのね」
あすかが言い得た通り、鮎のうるかは青臭さを残す塩辛である。表情を一変させたあすかは、太郎へ木曽の地酒を上燗で頼んだ。見ていた戸隠も「うむ」と深く頷いた。
「了解。じゃあ、ジョージはどんな酒にする?」
太郎の問いに、苦虫を噛みつぶしたような顔のジョージが頑なに答えた。
「私は、やはり冷酒で。木曽の濃い辛口ですね」
自信ありげなジョージに、銀平が思うツボといった顔で笑いを噛み殺した。
ジョージに助言しかけるあすかを、太郎は目顔で止めた。いいから、ジョージの舌で理解させろと言っていた。戸隠は腕組みしたまま、なりゆきを黙視している。
湯気を立てるあすかの上燗とジョージの冷酒グラスが並ぶと、浴衣姿の客たちもカウンター席を囲んでいた。
二人は、また同時に鮎のうるかと酒を口にした。
途端にジョージが、しかめっ面を真っ赤にした。鉢巻の下の顔は、今にも泣き出しそうである。
「さっきよりも苦い、それに渋い! どうして、こんな肴が美味しいのですか!?」
吹き出した銀平の顔をあすかは指でつねると、ジョージに上燗のお銚子を傾けた。
「それじゃあ、こっちのお酒と食べてみて」
お燗酒より冷酒を好むジョージは一瞬ためらったが、鮎のうるかと上燗を流し込むと青い目を丸くした。驚きの表情に、周囲の客たちが前のめりになった。
「ワオ! これは不思議です! 苦さと渋さが消えています。太郎さん、どうしてですか?」
魔法にかかったようなジョージが問うと、太郎が笑顔で戸隠に答えを譲った。
客たちが揃って、聞き耳を立てた。
「鮎のうるかってのは、酒のツウでもなかなか口にしない。ジョージさんが不気味に思うのは無理もないが、食べ慣れると塩辛さだけじゃなくて、苦さと渋さが個性的なんだよ。お燗酒だと、温かさと燗上がりした旨味が、苦さや渋さを包んでくれる。常温や冷酒だと逆に、その個性が強く出て、さらにくどい味になるんだが、うるかツウにとっては最高の合わせ方だ。いわば、俺みたいな鮎漁師にはたまらねえんだ」
戸隠は常温のお銚子をおかわりすると、鮎のうるかを注文した。そして、ジョージに問わず語った。
「甘くて濃いソースの味つけで育ったジョージさんは、まずはお燗酒と食べ合わせるのが一番だろう。だけどよ、あんたみてえな外人さんが千曲川の珍味を食べてくれるなんて、漁師冥利につきるってもんだ。俺もクールジャパンの一員になれっかねぇ」
「イエス! もちろんです! 戸隠さん、これからも私にご指導をお願いします」
おじぎして名刺を差し出すジョージに、戸隠が「こりゃ、ご丁寧に」と返礼した。
酒の飲み方に通じている戸隠をあすかも感心していると、銀平がここぞとばかりに近寄った。
「へへ、どうでぇ! なかなかの男だろ。まぁ、食べ合わせ、飲み合わせに詳しいってのは、俺の指導もあんだけどよ」
あすかが鼻白むと、太郎がため息まじりに言った。
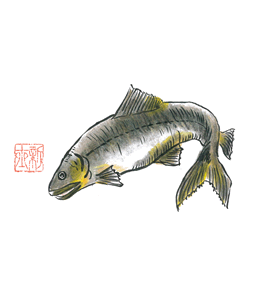
「ふ~ん。それにしちゃ、おめえが食おうとしてるトマトスライスと水ナス漬けって、腹をこわす食べ合わせなんだけどよぉ」
太郎の両手にある皿へ、客たちの苦笑が洩れた。
「うっ! し、しまった。あんまり喉が乾いちまってよう」
「それじゃあ、しょっぱくて苦い鮎のうるかは、食べられないね。残念ねぇ」
あすかの皮肉に歯噛みする銀平へ、珍しくジョージが仕返しとばかりにボケた。
「大丈夫! 何を食べようと、銀平さんのお腹はこわれませんよ。デリケートって言葉は、似合わないです」
「じ、ジョージ! てめえ、ちょっとばかり和食と日本酒をかじったぐれえで、いい気になってんじゃねえ!」
たじろぐ銀平に、太郎はジョージが、また一つ日本人らしくなったようで嬉しかった。
爆笑する客たちの前にも、初めて口にするだろう鮎のうるかが戸隠からふるまわれていた。
