ライトアップされた隅田川に掛かる永代橋は、夜になっても混雑していた。
深川から都心へ戻る人並みが多いのは、富岡八幡宮の祭礼が催されたためである。
神輿を担ぐ人たちに柄杓の水をぶっかけて威勢を上げさせることから、別名「水かけ祭り」と呼ばれ、帰り道では濡れそぼった観衆が奇声を上げていた。
三度の飯よりお祭り好きな火野銀平は、火野屋の半被を誂えて、毎年、社員と神輿を担いでいる。いなせな姿を目にしてポンバル太郎へ戻って来た剣と右近龍二も、生乾きの浴衣から祭りの余韻を発していた。
「いやぁ、僕は初めて富岡八幡宮に行ったんですけど、すごい熱気ですね。水かけどころか、酒までぶっかけられちゃいましたよ」
龍二の浴衣からは酒の残り香も漂い、隣の平 仁兵衛の鼻先をくすぐった。平は目尻をほころばせ、龍二がカウンターに置いた団扇の絵を見つめた。きらびやかな神輿の絵だった。
「富岡八幡宮には、ずいぶんご無沙汰してます。私は、独身の頃に冬木町に住んでましてねぇ。当時は下町っ子の聖地でしたが、今はどうなってますか? 深川も、ずいぶん都会になったようですしねぇ」
かつて祭礼の神輿を担いだこともあるのだと、平は剣に自慢した。
「へぇ、じゃあ平先生も、『わっしょい! わっしょい!』って掛け声を上げてたんですか。ふだんの先生からは、想像つかないなぁ」
厨房から出て来た太郎も富岡八幡の祭りがお気に入りで、江戸っ子の粋を象徴している正統派の掛け声を剣に聞かせてやりたかったのだと言った。
剣から祭りの団扇を配ってもらったテーブル席の客たちも、江戸を自慢する祭りだと相槌を打った。
「今日、僕に掛け声の出し方を教えてくれた、お爺さんがいたんだよ」
スマートフォンを取り出した剣が、平に写真を見せた。そこに、豆しぼりの鉢巻を禿頭に巻く苦み走った老爺が腕組みしていた。藍染めの半被には「門仲寿司」の名が白く抜かれていた。
途端に、細くなっていた平の目が大きく見開かれた。
「おっ、おお! 門仲寿司の松太郎さんじゃないですか! 御達者なようすで、なによりですねぇ」
平は剣のスマートフォンを食い入るように見つめて、いつになく気を昂ぶらせた。偶然にも顔見知りであると知って、剣は松太郎の話しを続けた。
「松太郎さんは昔、お孫さんを亡くして、その子がちょうど僕と同じ年頃だったって。たまたま祭りの御神酒処でお酒をふるまってた松太郎さんに、僕がその酒の銘柄のことを解説したら、ビックリしちゃってさ。『酒を飲めねえガキのくせに、いっぱしの口をきくじゃねえか!』って、えらく気にいられちゃった」
嬉々とする剣に太郎があきれると、龍二が話しを引き継いだ。
「門仲寿司さんは江戸時代末期の創業で、ずっと富岡八幡宮の氏子なんです。ただ、お孫さんが20年前に病気で亡くなってからは、神輿を担ぐ気がしなかった。それが今年の正月に富岡八幡のおみくじを引いて、夏の祭礼に出ればいいことがあると暗示があったそうです。きっと剣君に出逢えたのがそのことだと、松太郎さんは喜んでいましたよ」
浴衣が似合う剣に松太郎の目尻は下がりっぱなしだったと、龍二は気を良くして大吟醸を注文した。
しかし、平は表情を動かさず、胸がつかえているようだった。顔を覗き込む剣に、平はふっと苦笑いを浮かべてた。
「太郎さん……私がここへ置かせてもらっている酒器に、御神輿を描いた盃があったでしょう。あれを、出してもらえませんか」
それは、平が一度も使ったことのない一対の盃だった。酒器棚の奥から取り出した盃には、
金色の御神輿と「病気平癒」の文字が焼きついていた。
感慨深げに盃を手に取る平へ、太郎が黙って純米酒を注いだ。わけありげな盃に龍二と剣も視線を留めた時、玄関の鳴子が賑やかな音を響かせた。疲れて足元のおぼつかない銀平が、似たような禿げ頭の男を連れていた。
「あっ! 松太郎さんだ! ど、どうして、ここが分ったの?」
どぎまぎする剣と龍二に、松太郎もあんぐりとしたまま立っている。
双方を見比べるほろ酔いの銀平が、眉をしかめた。
「おいおい、どうしておめえたちが松太郎さんを知ってんだよ? こちらは深川きっての火野屋の上得意先なんだぜぇ。今日はすこぶる気分がいいってんで、俺のお気に入りのポンバル太郎へ誘ったんだよ……あれ? ひょっとして松太郎さんがさっき言ってた粋のいいガキってのは、この剣のことでしたか。こりゃ、いいや!」
しかし、驚いている松太郎の視線は、剣ではなく平に注がれていた。
先に平が無言で頭を下げると、はっとした松太郎は首に巻いた豆絞りの手拭いを外してカウンター席へ近づいた。
「元気にしてたかい。もう、20年近くなるかね……あんたにゃ、悪いことしちまって、わしはずっと胸に引っかかっててよ」
差し出した松太郎の両手が、詫びるように平の肩を包んだ。そして平が手にする盃に目を留めると、カサついた口元をふるわせた。
「ひょっとしてそいつは、あん時、孫の清太郎の願掛けにこしらえてくれた御神酒用の盃じゃねえのか」
「ええ……あの日からずっと、眠っていました。ですが、今日こうして、偶然にも松太郎さんにお渡しできます。これも、富岡八幡宮の思し召しでしょうねぇ」
松太郎と年恰好の近い平の口元にも、柔和な表情が戻っていた。そのまま平は問わず語った。
不治の病に犯されていた孫の清太郎の平癒に、松太郎は富岡八幡宮で祈祷を繰り返した。当時、門仲寿司の常連客だった平に、寄進する御神酒の盃を頼んだ。だが、松太郎の願いもむなしく、盃の完成を待たずして清太郎は他界した。
松太郎は富岡八幡宮を恨みはしなかったが、爾来、日々の参拝は途絶えた。約束を果たせなかった平も別れを告げる機会を逸して、深川を去っていた。
テーブル席の客が太郎へ肴を注文しかけると、相方の男がカウンター席のなりゆきを見つめながら、それを制した。
「病気が治ったお孫さんと、将来はこの盃で酌み交わしながら神輿を担ぐのが松太郎さんの願いでした」
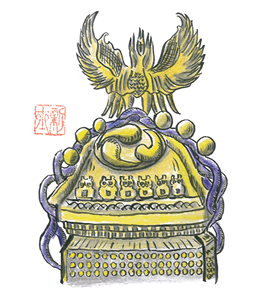
平が、静かにため息を吐いた。その気持ちを汲み取った太郎は、もう一つの盃をカウンターに置いた。
「ありがとうよ……今日、剣君と逢えたのも、ここへ銀平が案内してくれたのも、それに、平さんと再会できたのも、富岡八幡様のおかげだ。全部まとめて、型をつけてくれたよ」
どちらからでもなく、平と松太郎はカウンター席に並んだ。
松太郎の手にしかけた盃に、脇から手が伸びた。剣の手だった。
「じゃあ、僕がお孫さんの代わりに酌み交わしてあげる。これも、富岡八幡宮様のお告げだよ」
松太郎が目を丸くすると、銀平がたしなめた。
「こら剣! おめえは、まだガキなんだからよ。酒は御法度だって、いつも言ってんだろ」
「大丈夫! 水盃ってのがあるじゃん」
冷蔵ケースから取り出した仕込み水の一升瓶に、店内の客たちが「なるほどねぇ」と感心した。
「ちげえねえ。こいつぁ、一本取られちまったぜ」
松太郎の目尻が、うっすらと滲んでいた。神輿を描いた盃の酒に、おだやかな笑みが揺れていた。
