ヒグラシの鳴く街路樹は、陽が暮れるとヒンヤリした風に揺れていた。ようやく関東の残暑も峠を越え、ポンバル太郎の玄関には「冷やおろし、入荷しました」と貼り紙されている。
奇をてらわない剣の素直な筆字に、若い女性客が目を細めていた。
「ようやく、重陽の節句やな。落ち鮎とぬる燗は、最高の癒しや」
カウンター席で、中之島哲男が白磁の盃に口をつけた。臙脂色の作務衣にも、秋を待ち侘びる気持ちが表れている。
型のいいアユは、一昨日、中之島が和歌山の紀ノ川で釣った天然物である。それを目当てにやって来た菱田祥一も、ほろ酔いで舌鼓を打っていた。
太郎が鮎をふるまった客席は、思いがけないサービスに湧いた。おかげで、ぬる燗をつけた錫のチロリが、そこかしこで薄い湯気を揺らした。
鮎の塩焼きを頭ごと平らげた火野銀平は、土佐の純米酒の冷やおろしに四万十川で獲れた手長エビを合わせている。唐揚げされた赤い甲羅は、ひときわ鮮やかな名脇役だった。
「まったく、こんな極上物ばかり持ち込まれちゃ、こちとら商売上がったりだぜ。中之島の師匠の鮎は自前だからいいとしても、手長エビは土佐にいる龍二の親戚からだってえ? あの野郎、そりゃあ行き過ぎだろうて文句をつけてやろうと思ったのに、今日は顔を見せねえな」
やにさがった口ぶりとは反対に、銀平の表情は手長エビの正味の甘さに感心していた。
中之島が黙ってぬる燗を飲み干すと、太郎が「しばらくは、来ねえよ」と意味ありげにつぶやいた。菱田のため息も、その余韻をひきずった。
「な、なんでぇ……やけに、ようすが重たいじゃねえかよ。龍二の奴、どうかしたのかよ?」
銀平の顔が曇ると、菱田が太郎へ問わず語りをした。
「与和瀬、俺の知ってるミラノのレストランじゃ、手長エビは扱わないそうだ……四万十の漁師さんも大変だな。龍二君は、本気で親戚の跡を継ぐ気か?」
今度は、太郎がため息まじりに天井を仰いだ。
それを見つめる銀平の戸惑いを、中之島の低い声があおった。盃を持つ手は、宙に止まったままである。
「うむ……なんぼ和食がブームやちゅうても、いきなり手長エビを海外輸出するんは難しいやろ。それにイタリアンやフレンチは、現地のエビを使うのが常識や。ウナギも日本の蒲焼きみたいに開かずに、あっちはブツ切りにする。しかも見てくれが悪いから、メニューも少ないらしい」
あうんの呼吸で会話する三人を、蚊帳の外の銀平が差し止めた。
「ちょ、ちょっと待ってくれ。もしかして、龍二が土佐に帰っちまうってことかよ? 俺はそんな話し、寝耳に水だぜ! 水くせえじゃねえか!」
鼻息を荒げる銀平が、思わず腰を浮かせた。
語気に驚いたテーブル席の客たちが鮎をつつく手を止めると、菱田は銀平を諌めた。
「ここ数年、四万十川の人気に陰りが見えてね。川漁師をしている龍二君の伯父さんは地元の漁協を束ねてるんだけど、高齢で倒れちまったそうだよ。だけど娘さんしかいなくて、甥っ子の龍二君に白羽の矢が立ったってわけさ」
だが、銀平の怒りは収まらず、尖った視線を太郎へ投げつけている。その肩をなだめようとする中之島の手も、銀平はふり払った。
張りつめるカウンター席の雰囲気に、太郎は土佐の純米酒をグラスに注ぐと一気に飲み干した。客の前で、太郎が初めて口にしたヤケ酒だった。
菱田は唖然としたが、中之島は柔和な目元で見つめていた。
「おめえに相談すればひと肌もふた肌も脱いで、築地に四万十川の魚介類を推してくれることを龍二は百も承知だ。だけど、負担をかけたくないと龍二は言った」
四万十漁師にセリはなく、商品は川漁師から直接、販売者が仕入れる。それだけに、全国流通しない手長エビを火野屋が仕入れれば、運賃も含めてかなり割高になる。一方で川漁師の後継者が少なく、供給量も減っていた。龍二らしからぬ弱音を、太郎は黙って受け止めていた。その翌日、龍二は取るものもとりあえず土佐へ帰省した。
龍二自身が東京で頑張るのは潮時かもと吐いたことを、太郎は憂い顔で銀平へ打ち明けた。
眉根を寄せていた中之島が、突然の音に飛び上った。グラスや小鉢を跳ねるほど、銀平の拳がカウンターを叩いた。
「そうじゃねぇ! あいつの言いわけを鵜呑みにするのは、まちがってらあ! 俺はぜったい、四万十のエビやウナギを仕入れてやるぜ。それに、まだ他に打つ手はあるはずだ!」
銀平は太郎の手からグラスを奪うと、負けじとばかり土佐の純米酒を注いで飲み干した。
対峙するかのような二人に、客席が静まった。
「銀平ちゃん。誰かて、龍二君を土佐へ返しとうはないがな……流通業界の坂本龍馬になるっちゅうて彼は頑張ってきたけど、こればっかりは八方塞がりや」
渋い顔の中之島が手長エビを箸でつまんだ時、玄関の鳴子が鳴った。「あらあら。銀平さん、また暴走してんじゃないのぉ。ひょっとして龍二君のことかしら? だったら、私たちに任せてよ」
高野あすかに続いて、扉から入って来たのはジョージだった。
二人の後ろには、こぎれいなスーツ姿の紳士と若い男が立っている。よく似た顔立ちに、親子だと誰もが察した。息子とおぼしき若者は、長身に青い瞳を覗かせている。
「こちら、ニューヨークとシカゴで日本食レストランを経営している四郎・クリスチャンセンさん。日系三世の方なの。ジョージがニューヨークで行きつけにしてるお店のオーナーで、今度、五番街に土佐料理の居酒屋を出店する計画なんですって。しかも、クリスさんのお祖父様は四万十のご出身。だから、これはぜひ、龍二君を紹介しようって思ったの。まさに瓢箪から駒って感じでしょ!」
あすかの紹介に、ジョージがクリスチャンセンとの間柄を付け足した。彼はジョージに和食文化や食材探しをコーディネイトしてもらいながら、高知産のカツオやマグロだけでなく、四万十川の魚介類を仕入れる取引先を探すために来日していた。
むろん土佐の地酒もいくつか目星をつけていて、太郎がカウンターに置いた純米酒はその一つだった。
土佐っぽの血を受け継ぐクリスチャンセンは浅黒い顔で、流暢な日本語をしゃべった。
「私は、四万十川の手長エビや川海苔を使いたいのです。それで今日、ジョージとあすかさんを通じて右近龍二さんに連絡を取ってもらいました。さっそく明日、四万十漁協へ直販の商談に行きます。そして、彼の伯父さんには私の息子を弟子にしてもらうようにお願いします。しばらく四万十に住ませて、食材の目利きや買い付けの修行をさせます」
息子は不慣れなのか、ぎこちない日本語で「よろしく、お願い、します」と頭を下げた。
太郎たちは狐につままれたように、茫然と立ち尽くしていた。
「へっ!? てことは、龍二君は帰って来るのか?」
菱田は冷蔵ケースの酒瓶に目移りしている息子を一瞥しながら、あすかへ訊ねた。
「ええ……商談が上手くいけばだけど。大丈夫ですよね、クリスさん」
「はい、お任せ下さい。私が新しくニューヨークに出す店の名前は、RYOMA。そして息子の名前も龍馬・クリスチャンセンです。こんな良いご縁を頂いた御礼に、必ず、龍二さんをここへ戻してみせます」
クリスチャンセンが親指を立てると、ようやく中之島は腑に落ちたのか、満面の笑みを見せた。そして龍二を一番失いたくないのは自分だと言わんばかりに、中之島が吠えた。
「よっしゃあ! そうと決まれば、祝杯や! ほら、銀平ちゃん、難しい顔しとる場合やないで。太郎ちゃん、鮎も手長エビも、もっとジャンジャン出してんか。今日はわしのおごりや! 皆さんも景気よう、たっぷり飲んでや!」
すこぶる機嫌を直した中之島はそうぶち上げると、冷蔵ケースの土佐の酒を手にして客席を回り始めた。あたかも土佐流の“献杯返杯”のように、店内の雰囲気が盛り上がった。
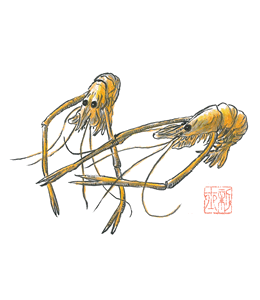
それを目にする銀平が
「まったく、いい気なもんだ。けどよう、おめえたち二人のお手柄だぜ……ありがとうよ」
と腰が折れそうなほど丁寧に頭を下げた。
「オウ! そんな素直な銀平さんは、あなたらしくないですね!」
ジョージが、土佐の純米酒を口にしながら茶化した。
「私だって、たまには名脇役をやらしてもらわなきゃ……この手長エビみたいに」
あすかが赤いエビの唐揚げを口に放り込むと、太郎も無言で深いお辞儀を返した。
目頭を真っ赤にしている太郎に、あすかがつぶやいた。
「ちょっぴり、龍二君が羨ましいな」
あすかの手長エビを噛む心地よい音が、カウンター席に響いていた。
