煌々と光る満月が、スカイツリーのネオンに寄り添っていた。
竹芝沖から流れて来る冷気に、新橋や浜松町の繁華街の居酒屋では熱燗の注文が増えている。シメのラーメン店にも、酔客の行列が並んでいた。
ポンバル太郎では、ひやおろし純米酒の上燗を頼む客が多く、カウンター席の平 仁兵衛は、ようやく自分の季節がやって来たと火野銀平に目尻をほころばせた。平の右隣りでは、五分刈り頭の若者が木枡のひやおろしを口にしていた。
「田沢さん、悪いなぁ。男鹿の海が台風の後にシケて、秋田の魚が築地に届かねえんだよ」
声をかける銀平も見知った仲らしく、若者は「構いませんよ」と薄い笑みを浮かべ、秋田銘酒のロゴを焼きつけた枡を置いた。
「うちへ来てようやく、ひと月ですねぇ。ロクロも上手く回せるようになったし、窯焼きも基本は身につけました。もう三週間ほど頑張れば、秋田へ帰れますよ」
いつになくゆっくりとした平の口調が、物静かな田沢栄一を気遣っていた。
はにかむ田沢の指先は、土汚れを残している。平の工房で、陶器造りを学んでいるせいだった。
半年前、秋田の著名な蔵元社長がポンバル太郎を訪れた際、カウンター席の平と酌み交わした。酒器にこだわる社長は陶芸家の平と意気投合し、ある願いを申し出た。社員の一人を平に学ばせ、蔵元で酒器を手造りすることだった。盃や片口だけでなく、屋号を入れた一升や四合のレトロな大徳利も復活させたいと語った。
会話を耳にしたジョージは日本の陶器はアメリカで大人気だと絶賛し、仕上がれば記事にしたいと申し出た。そんな成り行きで選ばれた蔵人が、弱冠二十五歳の田沢だった。
田沢は東京へ初めてやって来た、根っからの秋田人である。秋田市内の蔵元まで車で1時間半かかる白神山地の僻村育ちで、人見知りするタイプだった。平が初めて連れて来た夜も常連客には笑みを返すだけで、静かに盃を傾けていた。
だが、陶芸を学ぶ姿勢は生真面目で、平の工房に寝泊まりして、外には一歩も出なかった。
「あれが、秋田人の“けっぱれ”魂ですねぇ。内に秘めた闘志と辛抱強さは、東京人なんてかないませんよ」
平は絶賛し、目を細めた。
しかし、田沢は日ごとにやつれていた。具合が悪いのかと訊くと、田沢は「気持ちが、落ち込んで」と小声で答えた。祖父のような平に、田沢は本音をもらした……自分が陶器造りを任されたのは、蔵人に向いてないからだろうか。蔵元は、何のとりえもない自分を見捨てたんじゃないだろうか……平はポンバル太郎の常連たちに、それを打ち明けた。
なかなか弱音を吐かないが、山出しの東北人に東京暮らしはキツイと高野あすかは“癒し”を提案した。それが、今夜のひやおろしの酒座だった。
木桝に二杯目のひやおろしを太郎が注いだ時、玄関の鳴子を響かせ高野あすかが現れた。
赤いカーディガンと長い黒髪を掻き上げるしぐさに、店内の客たちがふり向いた。初めて逢う田沢はどぎまぎとして、頬を赤くした。
「おばんがたっす(こんばんは)、田沢さん。まあ、中休みってわげね。秋田の魚がないのは残念だどもねぇ……でさ、田沢さんのソウルフードって何だべ?」
あすかは、わざと出身地の相馬訛りを使った。驚いた田沢の口元がほころぶと、平は表情をゆるめた。
「はぁ、私は秋田でも山奥の育ちだがら、川の魚が好きでぇ……今でも、家の近所の沢でイワナさ釣って、囲炉裏で焼いてます。田舎味噌をつげるど、うめえっす!」
ふっと遠い目をする田沢だったが、声音は幾分高くなっていた。
「なるほど、天然物のイワナかぁ。そいつぁ、火野屋じゃ扱ってねえなぁ」
申し訳なさげに銀平がうなだれた時、鳴子が大きく叫んだ。右近龍二が、息せき切って飛び込んで来た。「おっ、お待たせしました、太郎さん。あった! ありましたよ!」
額を汗で光らせる龍二は、薄汚れた藁半紙の包みを掲げている。銀平が小首をかしげると、あすかと平も何事かと顔を見合わせた。
「おう! ごくろうさん! さっそく、田沢さんに包みを開けてもらってくれ」
初顔の龍二が手渡すと、田沢は小さく会釈して受け取った。カウンターの面々が注目する中、田沢の手が包みを開くと、その鼻先がヒクヒクと動いた。そして、真っ黒い炭が現れると田沢は目をみはった。
「こ、これは、秋田杉の炭じゃねえですか! この匂いで、すぐに分りました!」
「ええ、白神山地の天然杉で作ってます。合羽橋やらアメ横を徘徊して、ようやく見つけましたよ。でも、そんなに喜んでもらえたら、半日探した甲斐があったな」
答える龍二が営業の仕事をさぼったのは明らかで、それを察したあすかは「いよっ、男前!」と秋田のひやおろしをグラスに注いでやった。
深くて濃い香りを立てる秋田杉の炭に、田沢は顔をうずめるかのように近づけた。鼻から吸い込む息の荒さが、無垢な田沢らしさを伝えた。
「皆さん、ありがどうごぜます。元気が出ました」
ほろ酔いの田沢は赤い頬をほころばせ、体が折れるほどお辞儀をした。その姿に、けがれのない秋田人らしさが滲んでいた。
「礼を言うのは、まだ早いよ……あんたに、届け物が来てるんだ。これも、自分で開けてくれ」
厨房に入った太郎が、クール便の箱を手にしていた。送り主は、田沢の勤める蔵元の社長だった。青ざめる田沢の手が止まると、「しかたなかっぺ」とあすかは代わりに蓋を取った。
箱の中には、冷蔵された天然のイワナが山盛りだった。ピカピカと光る目に、魚匠の銀平も「こりゃ、獲れたてだぜ」と唸った。
「尺イワナで、ねえすか! こんだな物、どうして、うちの社長が?」
田沢の語気の強さに、イワナの山が崩れた。それにつられて、店内の客たちもカウンターを覗き込んだ。
「平先生が、おたくの社長さんに頼んだのさ。田沢さんに一番効く薬は、何かってね」
太郎の答えに、田沢の口元がふるえた。その肩に、しわ深い平の手が置かれた。
「そして、秋田杉の炭でこの白神山地の天然イワナを焼いた骨酒は、あなたが家の囲炉裏端で楽しんでるのと同じ酒……そう言って太郎さんは、龍二君に秋田杉の炭を探させたんです」
匂い立つ炭の香りが平の言葉を包むと、店内の誰もが表情を和ませた。
「なるほどねぇ。けどよう、あすかは今夜の席を提案して、龍二は炭を見つけて……俺だけ、いいとこなしじゃねえか」
ひやおろしの盃を飲み干した銀平が悔しがると、太郎は酒を注ぎながら問わず語った。
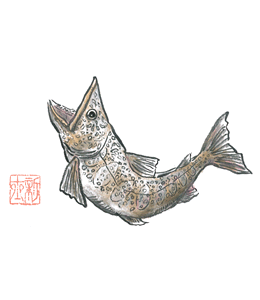
「いや、銀平が秋田杉の炭のことを教えてくれたんだよ。初めて田沢さんがここへ来た日、おめえ、訊いただろ。『あんたの爪の先、やけに真黒だな。何でだよ?』って。そしたら田沢さんは『実家の囲炉裏に使うから、毎日、秋田杉の炭をさわってる』と答えた。だから、分かったんだよ」
その答えに銀平が「あっ!」と声を洩らすと、龍二とあすかは笑顔で頷き合った。
唇を噛んで、瞳を潤ませる田沢に、平がひやおろしのお銚子を傾けた。
「蔵元の社長さんは、あなたをちゃんと見ていますよ。イワナの骨酒が、無口なあなたの好物だってこともね。だから、安心して陶器修行に励みなさい」
「は、はい……ありがどございます」
光を宿した田沢の瞳が、白神のイワナのようにイキイキと輝いていた。
