赤提灯をぶら提げる北千住や小岩界隈の屋台から、もうもうと煙が立ち昇っている。目にしみるほど濃いのは、ヤキトンの煙ではなく、屋台脇の七輪で焼くサンマだった。
今年は、築地に入荷するサンマの脂が極上で、火野銀平も売りさばくトロ箱が足りないとボヤくほどだった。
もちろんポンバル太郎の冷蔵ケースにも、目を光らせる近海物のサンマが並んでいる。
「大変な売れ行きらしいですねぇ。近海物が品薄になってしまう前に食べておかないと、損をしそうです」
焼き上がったばかりのサンマが、平 仁兵衛の声へ返事するかのようにプスプスと音を立てた。平の表情は、ほころびっ放しである。
テーブル席や店奥の客たちも、箸先を光らせて焦げたサンマをつついている。
平は脂ぎった熱い身と、岩手県の辛口本醸造を熱燗にして合わせた。隣りの右近龍二も指を鳴らして、それを真似した。
「これだけ脂があると、やっぱりアル添した本醸造のキレが合いますよね。たっぷり醤油をかけるなら、この辛口酒でしょう。銀平さんも好きそうなペアですよ。早く、やって来ないですかね」
土佐っぽでカツオ、マグロつうの龍二は、冷凍サンマを好まない。それでも毎秋、火野屋の極上サンマだけは見逃さない。とりわけ今年の三陸産はすこぶるつきだと、太郎へ褒めちぎった。
「ところがな、三陸沖のサンマの売れ行きに目をつけて、銀平につきまとってる海産物業者がいるらしい。今夜、その胡散臭い奴を連れて来るそうだ。どうにかして断りてえから、俺にひと芝居手伝ってくれってさ」
厨房から洩れる白い煙が太郎の小声を包み、龍二と平だけに話を聞かせた。
「それは、一興ですね。僕も脇役に加えてもらいたいな」
サンマの骨を上手に取る龍二の箸が、小躍りしている。
「じゃあ私はそれを肴にして、芝居見物としゃれ込みます」
平は銚子の濃口醤油と大根おろしを混ぜたサンマの肝で、熱燗をの盃を飲み干した。
肝の苦みをツマミにするツウな食べ方にテーブル席の若い客が「へぇ! うまそうじゃん」と感心すると、その後ろから銀平の声が飛んで来た。
「ほらよぅ、蝦夷屋さん。いくらオホーツク産でも、おめえん所の冷凍サンマじゃ、あんな肝の食い方できねえだろうがよ」
「いやいや、火野屋さん。うちのサンマは大丈夫ですよ。なんたって現地の船の上で直接取引するし、鮮度は飛び切りなんだからさぁ」
カウンター席の端へ座った銀平に、チョビ髭を生やした小柄な男が揉み手をしている。おもねる風体も、海産物業者らしからぬ派手なスーツ姿だった。
聞こえよがしな銀平の声へ、平が冷凍サンマの肝は食べないとばかりに大きく頷いた。龍二と太郎も、おそらく銀平に話しかける男は業界話に聞いたロシア産のサンマを闇で売りさばく輩だと察した。
太郎と龍二は目を見合わせ、腹を据えた。
いよいよ芝居の幕が切って落とされようとした矢先、玄関の鳴子が小さな音を立てた。
扉から現れたのは七十がらみの老爺で、藍染の刺子半纏を着ている。商店の御仕着せらしく、「葵家」の銘と三つ葉葵の紋所が白く抜かれていた。
白髪と苦みばしった職人面は、いぶし銀の棟梁といった雰囲気である。
「ちょいと邪魔するぜい。銀平、おめえはどういう了見で、この野郎と付き合ってんだい。火野屋の跡取りが、築地の老舗の暖簾に傷をつけようってのか?」
老爺が恰幅のいい体でカウンターへ近寄ると、半纏からキセル煙草の匂いが漂った。
平が懐かしげに鼻先を動かすと、太郎がつぶやいた。
「キセル煙草に、葵の半纏……こりゃ、築地の神様じゃねえか!」
「じゃあ、あの徳川家御用魚を仕切っていた、元・日本橋の魚匠“葵家”。確か、主人の葵 伝兵衛って人は、秋の叙勲を断った変わり者って……あっ、し、失礼しました!」
口をすべらした龍二を伝兵衛は睨みつけることもなく、苦笑いで黙らせた。その風格に、蝦夷屋の髭男だけでなく、店内の客も押し黙った。
伝兵衛が、おもむろに口を開いた。
「おう、蝦夷屋さんよ。確かに、築地は昔とちがって外国の観光客や若けぇ客たちが見物に来て、ようすが変わっちまった。だがよ、商いの心まで変わっちまっちゃ、俺たち江戸っ子はいけねえ。銀平、どうしても蝦夷屋のサンマを扱うてえなら、おめえんちの先代の頃に用立てた残りの一千万円、スッキリ返してくんな。なんなら、蝦夷屋に肩代わりしてもらっちまえば、どうでぇ」
伝兵衛の切り口上に気圧されて、誰もが固唾を呑んでいた。
青ざめる蝦夷屋の隣でキョトンとする銀平に、太郎は片目をつぶって、伝兵衛の芝居だろうと伝えた。銀平の表情に気づいた龍二も、蝦夷屋がどう出るのかとほくそ笑んだ。
素知らぬ顔の平は、ますます面白くなってきたとばかりにサンマをつまみ、熱燗の盃をあおった。
「ひ、火野屋さん。うちは、そんな金の肩代わりなんてしませんからね。と、とにかく、この話はなかったことでお願いします!」
今しがた見せた媚びへつらいは、どこへやら。チョビ髭にかいた冷や汗を拭いながら、蝦夷屋は逃げるように出て行った。途端に、伝兵衛はカウンターに両手を突いて、長いため息を吐いた。
「ふぅ! まったく、胆を冷やしたぜ。銀平、おめえ、まさか本気で仕入れるつもりだったんじゃねえだろうな!」
「あっ、あたぼうよう! てぇかよ、葵の親っさん。ヒヤヒヤしたのは、こっちの方でぇ! 口から出まかせにも、ほどがあらぁ。俺は今夜、ここの太郎さんとひと芝居打って、蝦夷屋の野郎をギャフンと言わせるつもりだったのによう!」
口を尖らせながらも、銀平の目元は明らかに伝兵衛を敬っていると誰もが感じた。築地の仲間の絆を、太郎は羨ましくも思った。
「けっ! 目黒のサンマにゃ練馬の大根がつきものだが、おめえみてぇな大根役者じゃ、うまくねえや。それによ、ロシアのサンマがいくら安くっても、築地の看板を穢すことは俺の目の玉が黒いうちは許さねえ。でえいち、あいつのサンマは目の玉じゃなくて、腹が黒いんでぇ。そんなサンマの肝じゃ、酒もうまかぁねえや。なあ、大将!」
伝兵衛は、うまそうに盃をあおるしぐさを太郎へ向けた。その演技も、落語家のように絶品だった。
「恐れ入りました。じゃあ、さっそく!」
築地の粋を受け取った太郎も、伝兵衛へ焼きサンマと熱燗の用意を始めた。
「いやはや、痛快、愉快です。伝兵衛さんの啖呵には、歌舞伎役者も顔負けですねぇ。ところで“目黒のサンマ”ですが、あれは目黒で将軍様が食べて美味かったからだと聞きましたが、真意のほどは?」
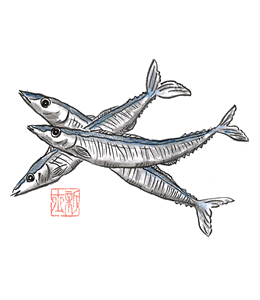
見物していた平は酔いが回り、珍しく饒舌になっている。伝兵衛をよっぽど気に入ったのか、お銚子と盃を持つ両手が隣の席へ誘っていた。
「ありゃ、目の玉が黒いサンマはイキがいいから目黒ってえのが、築地の魚屋の言い分だ。もっとも近頃は、魚よりも魚匠の方に目の曇っちまった奴がいるぜ」
平から注がれる熱燗の湯気の中で、伝兵衛が銀平へほくそ笑んだ。
「おっ、俺じゃねえぞ! よしてくれよ、親っさん。あんたが語ると、みんな本気にしちまうじゃねえかよ」
「それなら、しこたま目黒のサンマを売って、おめえの禿げ頭だけじゃなくて、商いの目ん玉もピカピカに磨くこった!」
爆笑する客たちの中で銀平が真っ赤になると、焼き上がったサンマもジュジュッと音を立てた。
