早まった紅葉に高尾山のもみじ祭りは連日賑わい、週末の奥多摩道路も自転車やバイクが数珠つなぎだった。目にも肌にも、ツーリング愛好家には格好のシーズンである。
右近龍二も運動不足解消にロードレーサーを奮発して購入し、親しいサイクリストと蔵元めぐりへ向かった。都内には十数社の蔵元があるが、その多くは西東京方面に集まっている。
青梅街道を抜けると、沿道には新酒造りを始めた蔵元の幟がはためいていた。だが、自転車の飲酒運転は御法度だったと、龍二は蔵に着いてから口惜しげにつぶやいた。
それほどまで酒好きな龍二に、連れのサイクリストは飽きれた。
「右近君って、実は、肝心な所でヌケてるんすよ。企画のプレゼンでも、たまにやってくれるよなぁ」
ポンバル太郎のカウンター席で、陽に焼けたサイクリストがいたずらっぽい笑顔で隣の龍二を腐した。ツヤ光るイケメン顔や締まった胸板に、テーブル席の女性客が噂をしている。
男の名前は、吉田恵一。マーケッターの龍二が得意先にしている、金属加工会社の研究員である。二人ともいったん自転車を家へ戻し、冷えた純米吟醸で喉を潤している。
吉田の言葉に、火野銀平と太郎は信じられないといった顔で笑った。
「マジかよ! しっかり者のおめえが、そんなトンマな野郎だったとはなぁ」
「所詮、龍ちゃんも人の子か」
腹を抱える銀平と太郎に、龍二は赤面して話をはぐらかした。酒の回りも自転車で走ったせいか、今夜は早かった。
「でも意外と福生市って近いんですよね。僕の中野のマンションからだと蔵元まで約40km、2時間弱で走りましたよ。そうそう、吉田さんの実家も昔は多摩の蔵元だったんですよ」
話しを振られた吉田は、それには答えず、店内のそこかしこに置かれた骨董品に視線を動かした。柿渋を塗ったキツネ桶とタヌキ桶、ギヤマンのデキャンタや長崎チロリなど、ゆかしいオブジェが吉田の瞳の中で揺れた。
「なかなか、酒ロマンがあるでしょ。蔵元出身の吉田さんにふさわしい雰囲気じゃない?」
「いや……うちは、もう小さな酒販店だからね」
冷淡な吉田に、龍二はため息を吐いた。わけありげな吉田の反応に、太郎は話題を変えた。
「40kmだと十里。江戸から遠かった多摩村は玉川上水の源流で、その伏流水は地廻りの酒も仕込んだ名水だ。そこから江戸時代の御府内、つまり山手線の内側まで水路を引いたんだ。ひょっとすると、水流を使った舟で福生や多摩の地酒を運んだかも知れねえ。牛や馬より、よっぽど早いしな」
腕を組んだ太郎は、吉田へ問いかけるように目を向けた。もどかしげだった吉田が、つられるように口を開いた。
「ええ、そうらしいです……実家に昔の古文書が残っていて、多摩村から四谷大木戸までは幕府御用酒とか特別な酒だけ運んだそうです。普段は馬で牽く大八車に酒樽を乗せて、青梅街道を運んだと書いてました」
吉田の答えにテーブル席の女性たちは感心したが、その反応を予想していなかったのか、龍二は言葉を失くしている。
それに気づかない銀平は
「へぇ、さすが蔵元の息子。詳しいじゃねえか。実家が多摩なら近ぇし、いつだって酒の勉強ができて羨ましいぜ」
と褒めそやした。すると、またもや吉田は口を閉ざし、薄い下唇を噛みしめた。
「……なんでぇ、どうかしたかよ?」
銀平の声を制するように、玄関の鳴子が音を立てた。茶革のロングコートに身を包んだ高野あすかが、大きな風呂敷を手にしていた。
かなり重いのか右肩が下がり、額にはうっすらと汗をかいている。
「ちょっと、銀平さん! 黙って見てないで、運ぶの手伝ってよ。まったくもう、気が利かないんだから!」
真顔で八つ当たりするあすかに、銀平はいつもの抗弁を忘れて駆け寄った。思わず素直さを見せる銀平の姿に、龍二と太郎は苦笑した。
「おいおい! こいつぁ、やけに重いじゃねえか。いったい何でぇ?」
驚いた銀平が腹の上に風呂敷を抱えると、あすかは結び目を解いた。
中から現れたのは、漆黒の箱に金箔の家紋を塗った調度品だった。珍しい“月に九曜紋”の脇に、六角形の口栓も覗いている。それを初めて目にしたらしいテーブルの女性たちは、揃って小首をかしげた。
カウンターに、黒い箱が置かれた。
戦国大名の相馬家と同じ紋所に、龍二はあすかの家柄をあらためて実感した。
「うちの実家に残ってた、指し樽(さしだる)。私のひいお祖母ちゃんが嫁いだ大正時代の物で、嫁入りの時に持参した箱型の酒樽なの。うちじゃ持ち腐れするからって、また母が太郎さんに差し上げてって……これ、お邪魔かしら?」
あすかがおもねると、太郎は悩ましげに指し樽を凝視した。
「あすかが苦労して持って来た物を、突っ返せねえよ。大したお宝だけど、実用性はなさそうだな」
考え込む太郎の前へ、吉田が歩み出た。そして、指し樽の肌を愛しげに撫でた。
キョトンとするあすかに龍二は目顔で頷くと、吉田の肩にそっと手を置いた。太郎は、龍二の口にするであろう言葉が読めた。
「吉田さんのご実家にも、こんな指し樽があるでしょ……帰ってみればどうですか、一度」
「ど、どうして、帰ってないと……俺、右近君にひと言も言ったことないぜ」
吉田の素性を銀平があすかへ話すのを耳にしながら、龍二は指し樽を開けた。
「だって、分かりますよ。いつも実家の話しになると、顔が曇っちゃうから。そっちの勘は、僕はヌケてませんよ」
龍二の声に合わせて上部が外されると、中には銅製の箱が組み込まれていた。緑青の錆びついた匂いがした。
太郎が、諦め顔を横に振った。
「う~む、こいつぁ、使い物にならねえ。おまけに、緑青は毒だからな。できれば、これに福島の地酒を入れて売れば、あすかのお母さんに恩返しができるって考えたんだがよ」
相槌を打つ銀平も、顎に手を当てて惜しがった。
「確かによう。これをカウンターに置いてりゃ、誰だって飲みたくなるぜ。百年近く前の、粋な嗜み方だからよう」
その声が終らないうちに、龍二を押しのけるように吉田が覗き込んだ。
指し樽の中や底を見回した吉田は
「大丈夫、修理できます。俺は金属加工が仕事ですから……銅製の中箱や注ぎ口を新品に換えて、木面は漆を塗り直せば大丈夫でしょう。俺、やりますよ」
と自分の腕を生かし、漆塗りは蔵元だった母親に頼んでみると言った。
「吉田さん……どうしたんですか」
「ああ、福島の蔵元だったあすかさんが大切に持って来たんだから、そうしなきゃって、なぜか今思った……俺の実家には、蔵元を廃業した後も埃だらけの菰樽や道具が転がってた。いつまでも蔵をほったらかしの両親に嫌気が差して、木桶や瓶と関係ない金属を扱う仕事を選んだ。もう十年ほど、実家には帰ってないのにね」
自分でも不思議だとつぶやく吉田へあすかが近寄り、指し樽に触れた。
「それって、吉田さんの身勝手な考え。うちのような被災した蔵元には、たとえ古臭い蔵や道具でも宝物なの……でも、あなたは、この指し樽を直さなきゃって思ったんでしょ。それは、あなたの中にある蔵元の血だと思う。だって、子どもの頃から、いつも傍にあった道具なんだもの」
吉田は答えをためらっていたが、ふと、銅箱の底に目を止めると太郎に割り箸をくれと
頼んだ。
錆びついた銅箱の底をこすり始める吉田に、銀平と龍二がいぶかしげに顔を見合わせた。
つかの間、単調な動きを繰り返していた吉田の手が止まった。
「あすかさん……銅箱の底に“高野酒造に栄え在れ”と彫られてます」
吉田が指し樽を押し出すと、あすかが引き寄せられるように中を覗き込んだ。途端に、あすかの瞳が潤んで、緑青のふいた銅箱にしみを落した。
「きっと、ひいお祖母ちゃんの言葉ね」
テーブル席にいた女性の一人があすかを気遣い、ハンカチを差し出した。しんみりする空気の中、太郎が言った。
「それを見つけたってのも、蔵元たる吉田さんの血だよ」
取り巻く面々が頷くと、吉田が長い息を吐いて答えた。
「この指し樽を修理できたら、実家の蔵に眠ったままの指し樽を直します。それを、兄貴の酒屋に飾ってもらおうと思います……できれば、多摩の地酒を指し樽で量り売りしたいですね」
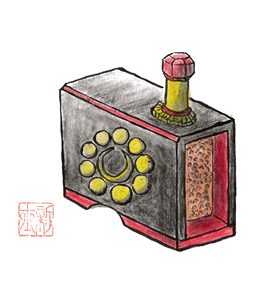
吉田の声音に、今しがたまでの迷いは消えていた。
「おう! それがいいや! 得意のチャリンコで、ひとっ走り、帰ってきなよ」
銀平は威勢のいい声で、湿っぽい雰囲気を変えようとした。だが、全員が吹き出したのは予想外だった。
「あっははは! 銀平さん、チャリンコじゃないですよ。ロードバイク!」
龍二のツッコミに、あすかも続いた。
「まったく、この禿げオヤジの頭の中は、いつまでも錆びついてるわねぇ」
「う、うるせぇ! ガニ又の俺は配達用のチャリンコしか、こげねえんだよ!」
銀平がカミングアウトすると、爆笑の渦が巻いた。
泣き笑いする吉田の顔が、黒漆の指し樽に揺れていた。
