年の瀬のアメ横に人波が押し寄せ、外国人観光客は上野周辺の雑踏に巻き込まれている。
築地市場では歳末の仕入れに業者たちが殺気立ち、多忙な火野銀平は一週間ほどポンバル太郎へ現れていない。太郎も残り二日間の営業のかたわら、限定販売の肴のおせちを造り始めている。
カウンターの向こうには朱塗りの重箱が並んでいるが、それよりも目を引くのは、梁にぶら下がる大きな干物だった。尾っぽを荒縄で縛られ、裂いた腹には割り箸がはまっている。
カッと開いた口には恐ろしげな牙が並び、まるで怪魚のミイラである。
「うっ、うわ! 気っ持ち悪いなぁ……なんだ、鮭かよ」
扉を開けた若い客たちは、誰もが眉をしかめた。その声を聞くたび、干物の下でぬる燗を傾ける平 仁兵衛が独りごちた。
「日本人の食卓を支えてきた鮭に、失礼ですよ」
干物のオレンジ色の腹を平が見上げた時、肩越しに右近龍二の声が弾んだ。
「そうかぁ! 今年の肴おせちには、塩引き鮭が入るんですね! 嬉しいな!……でも、こんな立派な塩引き鮭をどうやって手に入れたんですか?」
塩引き鮭の名前に、テーブル席に座った若い客たちはキョトンとしている。北海道産の荒引き鮭は歳末のお決まり品だが、村上市が本場の塩引き鮭は知る人ぞ知る、冬の新潟の風物詩である。
しかも、吊り下げられた鮭は1mを超える大物。マーケッターの龍二は、1本3万円は下らない高級品と読んだ。
「中之島の師匠からだ。新酒ができた新発田市の蔵元へ行ったついでに、村上市にも寄ったそうだ。村上市は新潟の最北端で、けっこう雪深い。一度行ってみたかった塩引き鮭専門の老舗で、買ってくれたんだよ」
厨房から出た太郎も、惚れ惚れする魚体を見上げた。その表情に、カウンターの端で独酌していた50歳がらみの男がつぶやいた。
「でぎれば、もう一度、夜は外へ吊るして、冷やした方がいい。もっと、うめえなるよ」
訛りのある語尾に、テーブル席から嘲笑が聞こえた。男が飲んでいる冷酒は、新発田の銘柄。肴にしている柳がれいの干物が、新潟人をほのめかしていた。
龍二は男に興味があるのか、隣りへ座った。
「お詳しいですね。ひょっとして、村上のご出身ですか?」
男は一瞬、龍二の顔を見つめると、こぼれそうな笑顔で答えた。
「ああ、岩船って町で水産加工をやってます。先祖は、村上藩の武士でねぇ。だげど、塩引き鮭って、東京じゃ、あまり食わねんだな」
人見知りする新潟気質を感じさせなかったが、どこか寂しげな男に平も声をかけた。お国自慢を語らせれば、元気が出ると思った。
「塩引き鮭の魅力は、何ですかねぇ?」
「そんだねぇ……天然の発酵食品って言うけど、昔から家庭の保存食だっけねぇ。村上じゃ、この季節にはどこの家の軒先にも、塩引き鮭が吊るされんだ。町に来て見れ! ずうっと、塩引き鮭の行列さぁ。塩で漬けこんで、冷てえ水で洗って、雪の降る外へ干して、また塩に漬けてを繰り返すんだ。手間かかるけども、辛抱強い村上らしい郷土食だ」
熱がこもってきた男は斎藤勝治と名乗り、村上市の三面川で代々、秋からの鮭漁を担っていると語った。
村上の鮭漁は遥かな昔、平安時代から伝わり、塩引き鮭は京の宮中にも献上されていた。
延喜式によれば、あまりの美味しさに、帝は村上の人たちに「やたらと塩引き鮭を食べるな」と勅令を下したほどだった。江戸時代の半ばには、村上藩士の青砥武平治(あおと ぶへいじ)が三面川をさかのぼる鮭から卵を取り、稚魚を育て、放流することに成功している。それは、世界で初めての養殖事業だったと斎藤は自慢した。
テーブル席の客たちは斎藤の話しに、打って変わった表情で塩引き鮭を見上げた。
「今も、そのおかげで養殖は続いて、秋の三面川には7万尾の鮭が帰って来る。川が真っ赤に染まるのさ……だげど、東京暮らしの息子は、それを忘れちまってね」
吐き下す斎藤は、白い肌を紅潮させながら冷酒グラスを飲み干した。昂ぶっているせいか、斎藤は息子の素性も口にした。
一人息子の雄一は東京の佃島にある鮮魚会社に勤めて6年、帰省の足が遠のいた。今年も年末まで超多忙で、東京で年を越すとだけメールがあった。
妻は、半月前に手作りの塩引き鮭を送った。しかし、雄一からは、なしのつぶてだった。
斎藤は痺れを切らして上京したが、雄一はここ数日、アパートにも帰っていないようすだった。古いアパートは、ポンバル太郎の裏通りにある。
「まったく、東京の会社ってのは、どこまで人をコキ使うんだ! おめえさん方も、ブラック企業には気をつけなせえよ!」
勢いでクダを巻く斎藤に、テーブル席の客たちはたじろいだ。
龍二がなだめようとした時、玄関の鳴子が音を響かせた。ようやく築地市場の追い込みは山場を越えたのか、銀平が若い男を連れていた。
「ふう! やっと顔を出せたぜ。太郎さん! 年末のご挨拶ついでに、珍しい物を……あ、あれぇ? 塩引き鮭じゃねえかよ」
梁にぶら下がる鮭に目を丸くする銀平の横で、大きな紙包みを提げた若い男が「父ちゃん! どうしてここに?」と奇声を上げた。
唖然とする斎藤の手から落ちる冷酒グラスを、間一髪、龍二がキャッチした。それにも斎藤は気づかない。
「雄一! お、おめえ! アパートにもいねえし、どこさ、行ってた! 心配したんだぞ!
それに、おめえが持ってるのは、母ちゃんの送った塩引き鮭でねえか?」
客たちの視線に雄一がたじろぐと、銀平が
「な、なんでぇ!? いったいどうなってやがる」
と、カウンター席の龍二へ食ってかかった。
「どうなってるじゃねえべ! あんたこそ、うちの息子をこき使いやがって!」
斎藤は銀平に、雄一を使い回している悪党かと言わんばかりに詰め寄った。
あんぐりとする銀平と鼻息を荒げる斎藤の間に、雄一は割って入った。
「と、父ちゃん! ちがうんだよ。火野屋さんは、俺の得意先だ。しかも、この社長さんは俺を明日、村上に帰すために会社へ話をつけて、仕入れを今日までにしてくれたんだ。その御礼に、母ちゃんの塩引き鮭を差し上げたら、ここへ持ち込んで一緒に食べようってことになったんだ。まったく、相変わらずのオッチョコチョイだな」
飽きれ顔の雄一だが、横顔は斎藤に似ていた。早合点して首まで真っ赤になる斎藤に、客たちは苦笑したが、平は憮然として雄一をたしなめた。
「あなたが、そんな口を利くのは20年早いですよ。まずは、御父上にちゃんと事情を説明しなかったことを謝るべきです。村上人は、れっきとした武士の末裔でしょう。これを見て、あらためて反省なさい」
いつになくキツい口調の平が、機敏な動作で吊るされた塩引き鮭を指さした。何の変哲もなく割かれた腹に、客たちはキョトンとしている。だが、雄一は返答に詰まった。
静まる店内に、太郎の声が響いた。
「塩引き鮭の腹が二つ裂きなのは、武士の切腹を思わせないためだ。雄一さん、東京に出て来たって、礼節を重んじる村上武士の血が君には流れてんだろ。それを忘れちゃ、いけねえな」
内臓を取り出すためにパックリと開いた鮭の腹だが、前と後ろの二か所を裂いている。その由来には、人をおもんばかる侍の心がある。
龍二が頷くと、銀平は得心顔で雄一の背中を押した。
「おめえのオフクロさんの塩引き鮭、親父さんと一緒に食べろよ」
斎藤の隣へ腰を下ろした雄一は、おもむろに包みを開いた。
干された半生の塩引き鮭は、濃厚な赤い身が発酵したしょっぱい匂いを放っていた。ふと見ると、二つ裂きの腹の中に淡い汁が滲んでいた。
それへ惹かれるように、雄一が鼻先を近づけた。
「母ちゃんの塩引きの匂いだ……ほんのり甘くて塩臭い、発酵の匂い。これだ、これ! うちの塩引き鮭だよ」
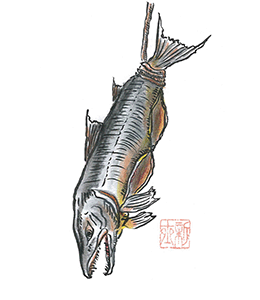
はしゃぐ雄一に、斎藤は平や太郎たちに目顔で礼を伝えると、銀平へ深々と頭を下げて非礼を詫びた。
「誠に、申しわけねえっす」
「親父さん、いいってことでさぁ。雄一は俺の大事な弟分だから、これからも村上人の魂を忘れねえよう、見張っておきますよ」
太郎が塩引き鮭を切り分けると、テーブル席の客たちもカウンター越しに唾を呑み込んだ。
途端に、塩引き鮭の注文が殺到した。
賑わいを見つめながら、明日、能登へ帰省する平が自問自答した。
「クールジャパンもいいですけど、日本人の心を忘れちゃいけませんねぇ。もうすぐ正月……やはり故郷には、見直すべき大切な物があるんです」
梁にぶら下がる塩引き鮭が、いかつい顔で客たちを見下ろしていた。
