上野の不忍池を、冬枯れた蓮の茎が覆っていた。岸辺では越冬する白鳥や鴨が、饅頭のように丸まりながら群れている。
ポンバル太郎で平 仁兵衛が目を通している夕刊は、浅草の仲見世で大寒を前にして外国人観光客が寒さに震えていると報じていた。昨日から、都内は予想だにしない突風が吹き荒れ、JRや私鉄の運休も勃発していた。
夜になってさらに強まった風は、ポンバル太郎の扉と窓を軋ませている。時おりゴオッと唸るとポンバル太郎の店舗がグラグラ揺れた。神棚の榊が落っこちて、テーブル席の女性客が「キャッ!」と悲鳴を洩らした。動じていないのは、熱燗の盃をなめている平だけである。
二度目の突風で、転がるように火野銀平が飛び込んで来た。
「うへぇ! 吹き飛ばされちまうぜ。これじゃ、海は大シケだ。明日の魚は、高値を呼びそうだな」
禿頭をマフラーの中にすくめていた火野銀平が視線を上げると、テーブル席から立ち上がった客に太郎が詫びていた。
「落ち着けなくて、すみませんね。店の建てつけは悪くないんですが、この風の強さはどうにもなりません」
大風の揺れで今夜は客足が遠のき、彼らが帰れば、平とカウンターの隅に座る中年の男だけである。
「落ち着かねえったって……今夜はどこで飲もうが、同じじゃねえか」
銀平が帰り支度する客に口を尖らせると、それを掻き消すほどの風に店はまた揺れた。地鳴りのような音にテーブル席の客たちはとっさに外へ飛び出し、思わず銀平も身構えた。
「うっ、うおっ! や、ヤベえよ、太郎さん。マジで、屋根がふっ飛んじまうんじゃねえだろうな」
うろたえる銀平に、太郎は鼻白んで言った。
「肝っ玉の小さい野郎だな。平先生を見習えよ。いっこうに動じてねえ」
確かに、ノドグロの塩焼きをつまむ平の箸は、止まるでも焦るでもなく、どこ吹く風とばかりに動いている。熱燗にした能登の純米酒も、飲むピッチは変わらない。
「まあ、子どもの頃に暮らした奥能登じゃ、冬の嵐がざらにありましたから。私には、今日の大風は懐かしくもありますよ。それよりも、カウンターにいらっしゃるお客さんの方がみごとです。いい飲みっぷりですねぇ」
平が褒めた男はむしろ大風を楽しんでいるかのように、満面の笑みをほころばせた。
「はぁ、私も突風が吹く新潟の寺泊って町に育ちました。冬は特にひどくて、海っぺりに建ってた実家は大揺れしました。でも、それが私の揺りかごで、風の音は子守歌みたいなものでした」
色白の頬をリンゴのように赤くした男は、長岡の地酒を熱燗で楽しんでいた。肴は、柳ガレイの一夜干し。むろん、新潟の名物である。
「その柳ガレイ、ちょっぴり塩をしただけでよ。うちの手作りなんだよ。あんたが合わせるのは、淡麗辛口の純米酒か。正統派の越後人てぇか、職人的な酒と肴だな」
銀平が含み笑いを浮かべると、男は期待に反して、ためらい顔を覗かせた。“職人的”の言葉に翳りが覗き、横に置いたバッグへ視線を泳がせた。
盃を持つ平の手が止まった。
「そのバッグ、あなたの作品が入っているんでしょ。良かったら、お見せ願えませんか。私も、陶器職人の端くれです」
平が自作の素朴な盃を、男に掲げた。何の変哲もない素焼きの器だが、男はその風合いに見惚れ、しばらくするとバッグを開けた。覗き込む銀平の鼻先に、杉のいい匂いが漂った。
「やはり、曲げわっぱでしたか。寺泊と聞いて、おそらくそうじゃないかと思ったのです。それに、この屋号。“小川安兵衛商店”といえば、代々続く、わっぱ師の家柄です」
平の声に、男は照れくさげにうつむいた。男が手にする曲げわっぱの弁当箱に、銀平が目をしばたたいた。
「ふぇ~! この木目や形の仕上げって、超精巧じゃないの。それに、わっぱって手で曲げるんだろ? あんた、立派な職人じゃないか」
しかし、男は弁当箱をカウンターへ転がすと首を横に振った。
「私は、十代目の小川安兵衛です。でも、既存の曲げわっぱじゃもう売れないと、得意先からダメだしを食らってます。例えば、カラフルな曲げわっぱを海外向けに出したいとも……でも、それは正統派の曲げわっぱじゃない気がするんです」
悩んだ末に、曲げわっぱの厚みや大きさを変えた新シリーズを今日、上京して提案したが、あっけなく得意先に一蹴された。外国人を魅了するインパクトのある商品が欲しいと、得意先は譲らなかった。
小川安兵衛商店の曲げわっぱは、杉の木目の美しさが命だった。先祖代々、その美しさときめ細かな仕事が料理人にも愛され、杉の防腐効果は食材の保存にも使われた。
「奇をてらうような曲げわっぱは、小川安兵衛の作品ではありません……ですが、売れなければ困る。そのジレンマに、悩み続けています」
小川が純米酒の盃を飲み干した時、ゴゴゥ! と突風がポンバル太郎を襲った。うるさいほど響く扉の鳴子に銀平はビビッたが、小川は愛しげにつぶやいた。
「寺泊の海風に似ています……今は“波の華”が舞い飛ぶ季節です」
太郎が、はたと手を打った。
「そ、それだ! 強い海風こそが、小川安兵衛の曲げわっぱを物語る存在だろ。あんたの子守唄じゃねえか。だったら、波の華が舞い飛ぶ風景を曲げわっぱに描くってのはどうだい?」
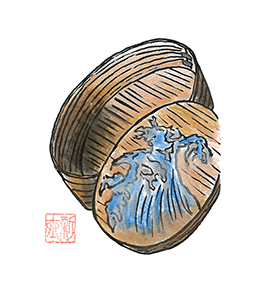
突拍子もない太郎の提案に小川が唖然としていると、平も頷いて追従した。
「なるほどねぇ。錦絵風か近世画か、どちらがいいでしょうかねぇ。まあ、どっちにしても、外国人へのインパクトはありますなぁ」
意表を突かれた小川は「あっ! そうか!」と転んでいる曲げわっぱを手に取り、やにわに蓋へ下絵を描き始めた。
「おっほほほ。やはり職人の血が、騒ぎ始めましたねぇ。ちなみに、その第一号“波の華わっぱ”、私が買いますよ。怒涛と突風で育ったお仲間ですしねぇ」
平が小川の下絵を覗き込みながら、熱燗の盃をあおった。平の耳奥にも、能登の海風が甦っていた。
「波の華わっぱ。うん、粋な名前じゃねえか!」
銀平は太郎と顔を見合わせ、大きく頷いた。
冬の突風が小川の手を後押しするように、ポンバル太郎を激しく揺さぶった。
