桃の節句を迎えたばかりなのに、都心のネオンボードは江戸時代から続く人形の老舗が倒産したと伝えていた。
「冷え込んでるのは、気温だけじゃないよなぁ」
寒いつぶやきが、銀座や六本木の交差点で洩れ聞こえた。この時期の繁華街は、春先の歓送迎会を前にして人波もまばらである。
ポンバル太郎へ着いた火野銀平も、いつになく閑散としている通りに白いため息を吐いた。凍てついた夜気は、扉の窓をビッシリ結露させていた。
「三寒四温はしかたねえけどよう、春が遅ぇなぁ……正月にゃ、あんなに暖冬だったてえのによ」
だが扉を開けると、寒さにすくんでいた銀平の首が、華やいだ雰囲気のカウンターに伸び上がった。視線の先には、桃の花を活けた花瓶を見つめる平 仁兵衛と右近龍二。その前には、紅い十二単衣を纏った雛人形が金襴の座布団の上へ飾られていた。
年季が入った雛人形は、高野あすかが2年前に太郎へ譲った実家の大正雛である。肌や着物の色はくすんでいるが、両手で朱盃を持った珍しい作風だった。
「おっ! そうか! 今年も甘酒の季節か!」
鼻先をくすぐる麹米の香ばしい匂いに、銀平が手を打った。大正雛は、毎年、太郎が客たちにふるまう甘酒のマスコットである。カウンターの端に座っている白髪まじりの男も、朱色の盃に白い酒を満たしていた。
「あれ? 大黒屋の賢太郎さんじゃねえすか? ここんとこ、よくいらしてますね」
銀平の声がけに50歳前後の男は小さく会釈し、翳りのある笑みを返した。甘酒は、太郎が日本酒を仕入れている台東区の老舗酒屋「大黒屋」が手造りしていた。
銀平も見知った賢太郎の父親で、大黒屋の主人である老齢な黒田 貫太郎は、わざわざ麹米だけを蔵元から仕入れて甘酒を仕込んだ。酒粕は使わず、いわゆるノンアルコール飲料なので手軽に造れて、客たちから栄養ドリンクとして重宝がられた。
学生時代まで店を手伝っていた賢太郎だが、昭和ヒトケタの父親とは酒の売り方でそりが合わず、跡継ぎはせずに平凡なサラリーマンを選んだ。明治期から四代続いた大黒屋も、貫太郎の代で終わることになっていた。
賢太郎と同様、平や龍二も飲み干した朱盃を手にして、浮かない顔だった。
「な、なんでぇ……みんなして、御通夜みてえじゃねえの? 今年も長生きして頑張ってる貫太郎さんにあやかろうってえ、甘酒だろう。おう龍二、シケた面してんじゃねえよ」
席に座るなり朱色の盃を龍二から奪った銀平に、太郎が腕組みしてつぶやいた。
「貫太郎さんが、倒れちまったんだよ」
「ええっ! いつだよ! マジっすか、賢太郎さん?」
うわずった声に、店内の客たちが甘酒を飲む手を止めた。全員、大黒屋の甘酒を飲み疲れの特効薬にしている面々だった。
水を打ったように静まる店へ、賢太郎の低い声が響いた。
「半月前に、心臓発作と脳梗塞を併発してね。手術はかなり難しくて、長時間かかったよ。どうにか、命は取り留めた……ただ、手術と入院の費用が高くってねぇ。うちの親父、あの気性だから、生命保険とかまったく入ってなくて。請求書を見て茫然としたんだけど……昨日、大黒屋の郵便受けに、これが入っていた。どうすべきか、太郎ちゃんへ相談に来たのさ」
賢太郎がカウンターにある茶封筒から取り出したのは、銀行の小切手だった。
「ゲッ! 300万円じゃねえすか! いってえ、誰なんで?」
銀平の大声に、客たちが一気に立ち上がった。平は客席へ振り返ると「まあまあ、落ち着いて」と動揺を抑えた。
「それが、目星はついてんだけどよ。どこにいるのか、本人と連絡の取りようがねえんだよ」
太郎は、半月前に貫太郎を見舞った後、賢太郎がポンバル太郎へやって来た夜の出来事を問わず語った。
今夜と同じく、平や龍二もカウンター席にいた。端っこに独りだけ、聡明そうな40代とおぼしき男が座っていた。
男の背中からふっと漂った消毒液の匂いに
「失礼ですが、お医者様ですかねぇ。匂いだけでなく、身なりも清潔ですねぇ」
と平が声をかけた時、賢太郎が現れ、突然と父親の病状、施術内容を打ち明けた。
男と平の会話は、そのまま途切れた。
ひとしきり説明した賢太郎に、常連たちは声を失って黙り込んでいた。
「太郎さん、今年の甘酒は、もう親父が仕込んで冷蔵してるよ。だけど、来年から大黒屋の甘酒はなくなるだろうな……それどころか、酒屋も閉めることになりそうだよ」
賢太郎の声に、厨房でクツクツ煮えるおでんの音がしみ込んだ。
「麹米だけの甘酒って、疲れた体によく効きますね。あれは“飲む点滴”って言っても、過言じゃないです」
ふいに隅の男が、誰とはなく口を開いた。そして、賢太郎へ向かって訊ねた。
「大黒屋さんってのは、帝釈天近くの古い酒屋さんですか? 確か、昭和の頃はアパートやバラック小屋も、近所にあったと思うのですが」
「あ、ああ……近くのアパートには、苦学生がけっこういたっけ。俺が就職した頃、飲まず食わずの学生がうちの前で倒れてた。親父がそいつを介抱して、病院に行かそうとしたんだけど、金がないって拒んだ。それで、あんたが言うように親父の甘酒をしこたま飲ませたんだよ。まさに点滴だった。そいつ、翌朝にはケロッとして帰ってった……もう30年くらい前の話しだけどな」
賢太郎が横顔に諦めの色を浮かべると、束の間、男は口をつぐんだ。そして静かに立ち上がると、太郎へお勘定を頼んだ。
誰から見ても、男は貫太郎の病気の話しを煩わしく思っているようだった。
大黒屋に届いた小切手には、10日前、ポンバル太郎にいた客であり、30年前に貫太郎の甘酒で救われた学生は自分だったと告げる手紙が添えられていた。
そして、あの甘酒のおかげで命拾いし、医師になれた。その恩返しを、ようやく今、できると記されていた。
小切手の名前は、古田一郎となっていた。
「これを使うべきか、どうか。困っちまってるのが、賢太郎さんの心境だ」
太郎も同情するかのように、小切手の金額に目を丸くした。
良くも悪くも囁き合う店内の客たちへ、龍二は聞こえよがしに声を発した。
「僕が思うに、前途有望だった若者の命を救った甘酒の値段なら、安いもんじゃないですかね」
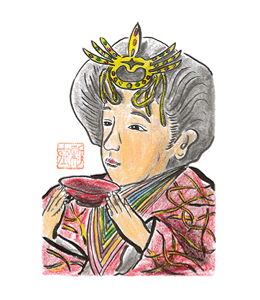
「おう! あたぼうよ! 貫太郎さんを助けるためになら、全部、使っちまいなせえ! それによ、その古川って医者なら俺が探し出しますよ。こう見えても、築地界隈じゃ聞こえた情報通だからよう」
銀平は胸を張りつつ、賢太郎の背中も叩いた。その気っ風に、太郎が嬉しげに同調した。
「別に築地は関係ねえけど、古川先生を捜すのは、おめえに任せたぜ。てえことで賢太郎さん。心置きなく使わせてもらえば、いいじゃないですか」
賢太郎が小切手を茶封筒にしまい、深くお辞儀すると、あらためて貫太郎の甘酒が客席にふるまわれた。
盃を手にした雛人形に、平がつぶやいた。
「ひょっとすると、貫太郎さんへのお雛様の御礼かもしれませんねぇ。長い間、いつも美味しい甘酒を造ってくれて、ありがとうってねぇ」
賢太郎には、雛人形の頬が、ほんのりと赤らんだように思えた。
