隅田川や荒川の堤防を、菜の花が黄色に変えている。丸ノ内の陽だまりでは、寒雀の群れに変わって鳩が遊び始めた。
もうすぐ春一番と期待しているのか、家路を急ぐOLたちの足取りは軽やかに見える。
ポンバル太郎の冷蔵ケースも、春の兆しを覗かせていた。テーブル席から、その魚介類を高野あすかが連れの女性と物色している。実は、ジョージの友人のシェフが日本酒に合うフレンチを遅れて持参するとあって、あすかたちは心待ちにしている。
ここ数日は、火野銀平が納める初ガツオに辛口の土佐酒が好評で、右近龍二の表情は故郷の酒肴の売れ行きにまんざらでもない。平 仁兵衛も、高知の本醸造の熱燗に太郎自家製の酒盗を合わせている。
「やはり春が来ると、太平洋や瀬戸内海の魚が欲しくなりますねぇ。冬の旬は日本海の魚ですが、ようやくバトンタッチですねぇ」
確かに、寒ブリやズワイガニといった冬の肴の王者は、寒流に身の締まった日本海産がほとんどで、そろそろシーズンオフである。太郎自身も、銀平に口酸っぱく旬の先取りを命じている。
「3月半ば、酒造りは最終段階です。去年の暮れに搾った上撰や本醸造の新酒はようやく味がのって旨くなる頃だから、魚も脂ののった赤味のマグロ、カツオ、サバに変わりますよ」
大鉢に盛ったカツオやマグロのヅケを、太郎が厨房から持ち出した。「おお!」っと歓声が上がると、カウンター席の真ん中に座る銀平は胸をそらした。
「昔から築地の春は、カツオから始まるんでぇ! キレのいい灘の酒と銚子の醤油ヅケにしたカツオこそ、江戸っ子の春の酒肴だよ」
我れ先に菜箸をつけようとする銀平を、玄関から飛んで来た関西弁が止めた。
「けどなあ、関西人はちょっとちゃうでぇ。なんちゅうても、春はサワラや。白身魚を甘い酒粕入りの白味噌で漬けた西京漬けは、伏見の甘うて優しい酒に合う。平さんが言うように、春の関西の魚介類は、山陰の日本海産から播磨灘の明石産に変わるっちゅうても過言やないわ」
中之島哲男が右手に提げている折箱は、春先、必ず上京する手土産にしている京都の西京漬けだった。テーブル席で女性客と飲んでいた高野あすかが、「あっ! あの包装紙、京都の老舗料亭よ!」と声を洩らした。
またもや「ほうっ! 京都のねえ」と客席が賑わった時、カウンターの隅から不機嫌そうな声が聞こえた。
「おめさんたち、知らねえだろうが。日本海にだって、“カネタタキ”って春先にうめえ魚があるだよ」
黒いブルゾン姿の中年男が発した東北訛りに、あすかの連れの女性がクスリと笑った。胸には建設会社の名前が刺繍され、出稼ぎ者の雰囲気を漂わせていた。
「カネタタキ? 耳にしない魚ですね」
龍二は魚匠である銀平に顔を向けたが、「俺も、知らねえなぁ」と首を傾げた。
二人の視線は東北出身のあすかに止まったが、「私だって、聞いたことないわよ」と首を横に振った。
すると、盃を飲み干した平が問わず語った。
「カネタタキは、山形県の酒田辺りの方言ですね。私の故郷の能登では、“モンダイ“と呼びます。いわゆる、マトウダイですねぇ。白身の魚で、北陸から東北にかけては刺身で食べますよ。淡白ですが旨味があって、煮物にも合います……でも、東京の料理屋では扱わないでしょうねぇ。さばくのが面倒で、見てくれも不細工ですから」
能登人の平へ男はふっと笑みを浮かべたが、締め括りの言葉には露骨に顔をしかめた。純情無垢な田舎者らしい反応だった。
「う~ん、ハッカクとかホウボウもそうだけどよう。どうも馴染みのねえ東北の魚は、動かしにくくってよう。ひょっとして、あんた、東北から来たばっかりかい?」
同年代とおぼしき男へ銀平が訊ねると、「ああ、そんだ。2月に酒田から上京して駅前のホテル工事で働いてる、本間 五朗ってんだ」
本間は、オリンピック景気を狙うホテル建設の現場で働いていた。
ようやくこの町に慣れて、美味しい山形の酒を飲めると噂で聞いたポンバル太郎へやって来たと答えた。だが、今しがたの日本海の魚から乗り換えるような話題に、いささか腹が立ったと付け足した。
「カネタタキは、ぜってえ、旨ぇ魚だべ」
本間の声はさらに聞き取りにくい酒田弁で終わり、
「確かに、マトウダイは見た目とちがって、淡白で美味しいんです。だから、故郷の自慢を腐されたようで、おもしろくないですねぇ」
と平が同調した。
腕を組んだ太郎が銀平へ、どうにかして手に入れろと目顔で伝えた。
「けどよう。酒田産のマトウダイなんざ、名指しじゃ、無理だぜ。そう簡単に手に入らねえよ」
「明石市のうおんたな市場に行ったら、あるかも知れんが、瀬戸内産のマトウダイでは意味がないしなぁ」
中之島も腕組みをした。
常連たちのやり取りに、いつしか店内の客たちも惹き込まれ、あすかと連れの女性もマトウダイをスマホで検索していた。その時、二人の鼻先をバジルとバターの匂いがくすぐった。
振り向いた玄関には、ジョージと茶色い瞳を持った外国人が立っていた。いい匂いは、男の手にする紙袋から漂っていた。
「お待たせしました! あすかさん。彼は、ロサンゼルスから和食の修行に来ているベンです。今日は珍しい魚を使ったフレンチで、サンピエールのムニエルです。これが、日本酒の山廃純米酒にバッチリ合います!」
カウンターへ座るなり自慢するジョージに、あすかと連れの女性は腰を浮かせたが、本間の表情はさらに険しくなった。
空気を読めとばかり龍二はジョージに咳払いしたが、隣りのベンもお構いなしに料理の包みを開けた。
大ぶりのタッパーの中で、見かけない魚が香草とバターの脂に光っている。
「あっ! それ、マトウダイじゃないか?」
覗きこむ太郎の声に、常連だけでなく、客たちがいっせいにカウンターへ集まった。キョトンとしたままの本間が、
「えっ? フランス料理に、カネタタキさ、使ってるべか?」
と人垣を押し分けた。
そこには40cmものマトウダイが、塩・コショウと小麦粉をつけてこんがりと焼かれ、香草とバターを加え、輪切りしたレモンも乗っていた。
「これはブール・ノワゼットという、ムニエル料理。フレンチでサンピエールと呼ぶマトウダイは、ムニエルの定番ですよ」
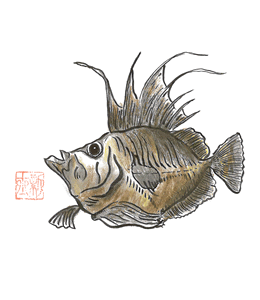
日本語を流暢にこなすベンへ、あすかたちがウットリして近寄った。たが、ベンはさっきの本間の訛りに気づくと
「どうぞ、召し上がってみて。あなた、東北の方ですね。このマトウダイは、山形で獲れました」と先に箸を勧めた。その脇から、山形の純米酒を右近龍二が差し出した。
「う、うむ。いただきます……旨い、カネタタキのこんな食べ方、おらぁ初めてだべ」
箸がマトウダイの白い身に動くと、強張っていた本間の相好がくずれて、素朴な笑みを満面にほころばせた。
ジョージとベンが本間の手を取って喜ぶと、客席からも自然に拍手が起こった。
「予期せぬ出逢いから、また一つ、ポンバル太郎に春の新しいメニューができましたねぇ。本当に、日本酒がつなぐ縁は不思議ですねぇ」
平の箸先も、ゆるりとマトウダイの身をほぐした。
「フレンチかぁ。その手があったか。いっちょ、仕入先を探してみるか」
銀平の嬉しげな声に、マトウダイのバターがツヤツヤと光った。
