丸の内オフィス街の植え込みに、赤い霧島ツツジが咲きほころんでいた。汗ばむほどの毎日で、咲くのはひと月早い。その花弁を、都心では珍しく蜜蜂がせわしなく探っている。
夕暮れになっても、アスファルトの余熱に、帰宅するビジネスマンたちは額に汗を浮かせていた。今日の最高気温も、28℃。爽春を通り越して、真夏並みの気温だった。
ここ数日、ポンバル太郎には、日本酒の飲み方を新入社員へ教える上司とおぼしき男たちが目立つ。学生の頃は缶チューハイや発泡酒を飲んでばかりの若者だけに、盃を持つ手つきがぎこちない。ましてや、お銚子の熱燗など手痛い洗礼を受けるようなものである。
「ほほう、一時はさしつさされつの姿なんて、もはや消えるだけと思っていましたが。なかなか、日本の企業も捨てたものじゃありませんねぇ。外資系だ、世界基準だと言っても、日本人の心を忘れちゃいないんですねぇ。見直しましたよ」
江戸切子のグラスをなめている平 仁兵衛が、カウンター席の端から三人並んでいるグループに目を細めた。四十半ばと見える男は多摩の地酒を飲みながら、二人の若者へ熱弁をふるっている。
平へ灘の生貯蔵酒を注ぐ火野銀平は、彼らに一瞥をくれながら声を低くした。
「さぁて、どうだかねぇ。奴ら、腹の中じゃ、ウザい! 迷惑千万! ってとこじゃねえですかい」
銀平の左に座る右近龍二も、「今の新人は、冷めてますからねぇ」と冷酒グラスを飲み干して頷いた。
不審げな銀平たちを平がとがめようとした時、カウンター席の上司の男が立ち上がった。その背中が手洗いに消えると、若い二人は辟易した顔で愚痴った。
「まったく、ツマラない上司の下に付いちゃったな。俺たち、一応、エリートとしてこの会社へ受かったのにさ。カスみたいな新卒と同じように精神論を聞かされちゃ、たまんないよ」
「ああ、よりによって漁師の話なんてさ。板子一枚、下は地獄の海で魚を獲って生きている漁師に比べりゃ、サラリーマンは保障された人生。だから、死ぬ気で頑張れだって。バカじゃねえの。噂で聞いたんだけどさ、湊川係長の実家って、竹芝の漁師なんだろ? だったら、今の会社辞めちゃって、漁業やればいいじゃん。そうそう! 最近、ネットで“漁師になりませんか”って求人活動が評判らしいぜ」
せせら笑う二人に、太郎が厨房からしかめっ面を覗かせた。むろん平の表情も一変していたが、指をポキポキと鳴らす銀平の比ではなかった。
漁師を蔑むような物言いに、銀平は真っ赤な形相で二人に近づいた。
「よさねえか! 銀平!」
太郎の大声と同時に、銀平と二人の間へ湊川の右肩が割って入った。こわばりながらも部下を守ろうとする湊川は、銀平と鼻先を突き合せた。
一触即発の雰囲気に、店内はにわかにざわめいた。途端に、玄関から鶴の一声が飛んだ。
「やい銀平! 酒の席で人様に迷惑かけるんじゃないよ! どんな理由があっても、酒場の喧嘩は両成敗だ。そっちの兄さんも、揉める気なら出てっておくれ。ほかのお客さんの迷惑だからね!」
ポンバル太郎の玄関に、ド派手な半被を羽織った銀平の叔母で屋形船を取り仕切る松子が腕組みして立っていた。
茶渋色の結城紬を覆う半被には青い波が砕け、巨大な鯛も見え隠れしていた。絵柄の隅には、「次郎丸」の銘が染め抜かれている。そのいなせな格好に、松子のひさしに結った銀髪が似合っていた。手にするのは屋形船の宣伝チラシで、都内の知り合いの居酒屋へ配っている最中のようだった。
セリフを奪われた太郎だが、啖呵を切った松子の気配りに深くおじぎを返した。
相変わらずな松子の威勢に耳の痛い銀平は「ちっ!」と舌打ちしたが、湊川は気おされたのか、愕然とした表情で立っていた。部下の二人は蒼ざめて、ピクリとも動かない。
店内の空気がピンと張り詰めると、平は両手を打ってほぐした。
「はいはい、皆さん、飲み直しましょう……そちらは、湊川さんでしたねぇ。まあ、気分直しに一献いかがですか」
平は生貯蔵酒の500ml瓶を、柔和な表情で差し出した。だが、湊川はグラスを手にすることもなく、松子を見つめたままである。
「な、なんだい!? あたしの顔に、何か付いてるかい? それとも、この年寄りに喧嘩を売ろうってのかい!」
結城紬を腕まくりする松子に客席がどよめくと、気を静めた銀平が立ちふさがった。
「お、おいおい、叔母さん。よしてくれよ! それじゃあ、アベコベじゃねえか。まったくよう、火野家の人間は気が短かくていけねえや」
ところが、松子の声に湊川の頬はみるみる上気した。そして鞄の中をまさぐると、一枚の写真を取り出した。
「こ、これ、あなたでしょう? 四十年くらい前の写真ですが、隣にいるのは私の父です」
湊川が差し出した色褪せた白黒写真には、大漁旗を背にする恰幅のいい中年男と妙齢の女が寄り添っていた。
かなり老眼のキツい松子がやぶ睨みすると、銀平も同時に写真を覗き込んだ。
「おっ! こりゃ、松子叔母さんだぜ。まちがいねえや。だってよ、火野屋の半被を着てんじゃねえか」
当時の松子は船宿を切り盛りしながら、銀平の祖父であり、自分の父である銀次郎の築地の店も手伝っていた。もっとも銀平は、まだヨチヨチ歩きの鼻たれ小僧である。しかし、もっと驚いたのは、今夜の松子が着ている派手な半被とソックリな、写真の大漁旗の絵柄だった。
半被と写真を何度も見比べる銀平に、松子が飽きれ顔を返した。
「いつまでジロジロやってんだい! そうだよ。この半被はね、大漁旗で仕立てたんだよ……あんた、次郎丸さんの息子かい?」
松子の視線が、グレースーツの湊川の足元から頭までゆっくり動いた。
「はい。あなたは、火野松子さんですよね。父の漁船が夕刻の東京湾で難破したのを、あなたの屋形船が助けてくれた。亡くなった父に、子供の頃、この多摩の地酒に酔うとその話を聞かされました……父は御礼をしようにも、我が家は貧しかった。それでも、何も受け取ろうとしないあなたへ、この大漁旗を渡した」
湊川の震える口元を、部下たちは固唾を呑んで見つめていた。そのようすに、平と龍二は笑みを見合わせた。
松子はカウンター席へ腰を下ろし、半被を脱いだ。白檀の香の匂いが、冷酒グラスを前に置く太郎の鼻先をくすぐった。
「漁師にとっちゃ、命の次に大事な大漁旗だからねぇ。あたしゃ女だけど、あんたのお父さんの男気を受け取ったのさ。それが縁で、火野屋には、湊川 次郎丸さんの獲った江戸前の魚が入るようになったんだけどねぇ。いつの間にか見なくなったのは、そうかい、次郎丸さんは亡くなったのかい」
ふだんなら松子を煙たがる銀平が、いつにない神妙な面持ちで耳を傾けた。湊川の部下も、耳を澄ました。
「ええ、私が中学一年生の時に、二月の東京湾でシケに遭いまして……二度目の難破でした」
「残念だねぇ……あたしの屋形船は、真冬には出さないことにしてるんだ。横波を食らったら、東京湾ったって、ひとたまりもないからねぇ。板子一枚、下は地獄だよ。だから、あたしゃ、次郎丸さんの大漁旗を半被に変えてお守りにしてきたんだ……あたしが、次郎丸さんの運をもらっちまったのかねぇ。ごめんよう」
詫びる松子は、たたんだ半被を湊川の胸元へ押しやった。
「これからは、あんたに着てもらいたいの。顔立ちも気風も、次郎丸さんと似てる。漁師じゃないけど、命がけで仕事をやってそうだねぇ」
湊川と部下たちの雰囲気を一瞬で察したのも、松子のただならぬ眼力だった。
たじろぐ部下たちに、龍二がおもむろにお銚子を差し出した。
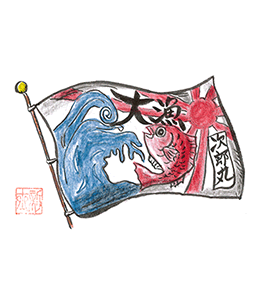
「まあ、ウザい上司も上手く使えば、大漁の仕事を揚げる手段ですよ。そのあたりのコツ、これから伝授してあげるからさ」
「おう! まかせときな! 湊川さんと火野屋の縁もあることだし、俺もひと肌脱ぐぜ!」
銀平が火野屋のTシャツを腕まくりすると、松子の平手打ちが禿頭にピシャリと飛んだ。
「調子に乗ってんじゃないよ! お前みたいないいかげんな奴に、湊川さんの大事な部下の舵取りを任せたら、それこそ沈没しちまうじゃないか。太郎さん、龍二さん、頼んだよ。 もちろん、ご意見番は平さんに任せるからね。ほら、銀平! 明日も築地は早いんだろ! とっとと、あたしと帰るんだよ!」
耳を引っ張られる銀平に、平が苦笑しながら言った。
「確かに、火野屋さんは代々、気が短いようですねぇ」
やり合う松子と銀平に顔をほころばせる湊川の隣で、部下の一人が嬉しげに大漁旗の半被に袖を通していた。
