隅田川をさかのぼる潮の香りが、日増しに濃くなっていた。浅草の三社祭、湯島天神の大祭と続く東京の春祭りに、日本人よりも外国人観光客の方が色めき立っているとスポーツ新聞が報じていた。
確かに、強い日差しと鰻のぼりの気温のせいか、Tシャツにショートパンツといったスタイルの欧米人も多い。5月を前にして、連日30℃近い異常な暑さである。
ポンバル太郎の客たちは、ぬる燗派の平 仁兵衛を除いて、全員が冷酒を口にしていた。
「毎年、全国新酒鑑評会が近くなると、大吟醸ファンが店に増えますねぇ。でも、ずっと大吟醸や純米吟醸ばかりじゃ、せっかくの美味しい魚介類が惜しいですねぇ」
鰆の西京焼きをつまむ平は、満杯の冷蔵ケースを覗き込んでつぶやいた。目玉も鱗もピカピカに光らせたアジやサバ、脂がのったハマチの片身、隅には分厚いアワビや大ハマグリが転がっている。もちろん、火野銀平が目利きした上物ばかり。
「これを生で食べるだけじゃ、野暮だぜ。アワビは竈で塩焼きするとうめえ! サバは生醤油だけで煮つけて辛口の本醸造と。アジは竜田揚げ、合わせるのは純米酒だな。ハマチは、バターソティが山廃仕込みに合うと思うぜ!」
胸を反らせて自慢する銀平を信じ、太郎は今夜の献立にそのまま使った。すると効果テキメンで、客席から注文が続いている。そんな声の中、カウンター端に座る二人の男のつぶやきが耳に引っかかった。
「おっ! あのサザエ。勝浦産だぜ……へぇ、1個500円もするのかよ」
「先週、俺たちが潜って獲ったのと同じぐらいのサイズだな」
引き締まった体格の男たちが目を凝らす冷蔵ケースには、殻に角のあるサザエを盛っていた。陽に焼けた二人の顔と腕回りに、太郎はウェットスーツを着込んでの密漁かと勘ぐった。同じように察した平は、男たちの歳を35歳前後と見た。ただ、不思議に思ったのは、二人とも首筋の同じ所に、よく似た赤い痣が浮いていた。
「じゃあ、俺たちが獲ったのは10万円分か!」
高笑いする二人がお互いに冷酒グラスを翳した時、平の肩越しに女の高い声が響いた。
高野あすかが、手帳を開いて平の後ろに立っていた。
「それって、漁師にとっては許せない話ね。私、記者の端くれなんだけど、詳しく聞かせてもらおうかしら」
虫の居所が悪いのか、今夜のあすかは口ぶりが荒っぽい。おまけに、密漁の講釈まで始めた。
今は日本全国、どこの海でも漁業権で守られている。関東では、都内から近い神奈川県の密漁者が多くて問題になり、ほとんどの場所で磯遊びすら禁止になっている。
地方では魚を突く漁は許されていても、貝類はほとんど禁止で、そんな場所じゃ泳いでるだけで漁師が船で飛んで来て警察に突き出される羽目になる。テレビ番組で「獲ったど~」なんてやってるのは、ちゃんと許可を取っているからなのだ。それを承知で、密漁をやっているのか。
一瞬、店内は静まり、糾問された二人の男に視線が集まった。途端に一人の男はうつむいたが、傍らの大柄な男が立ち上がり、頬をひくつかせながら、あすかへ詰め寄った。後ずさるあすかの表情が、春めいた水色のパンツスーツの中で蒼ざめた。
「お客さん、やめてくれ」と太郎が厨房から叫ぶと同時に、いつになく平が敏捷に腰を上げた。しかし、小柄な痩せ老人の平では、たくましい男に弾き飛ばされそうである。
その時、玄関の鳴子が暴れて、銀平が飛び込んで来た。
「おうおう! ちょいと待ちねえ。俺の大事な妹分をどうしようてんだ」
扉のガラスから覗き見たようすに、銀平は血相を変えていた。
出っ腹の銀平と締まった逆三角形の男が対峙すると、店内から失笑が漏れた。だが、銀平は貫禄負けしていない。
隠れるように銀平の背中へ回ったあすかが、その場の事情を耳打ちした。若い男は、銀平のTシャツに染められた「築地魚匠 火野屋」のロゴを睨みつけるように、仁王立ちしている。
「まずい。こいつぁ、火に油を注いじまう」
太郎がそう漏らした理由は、むろん魚匠の銀平にとって密漁は天下の御法度。漁師を泣かせる許しがたい悪事だけに、怒りは怒髪天を衝くにちがいなかった。
あすかの声に頷く銀平は、目の前の男だけでなく、カウンターでおとなしくなっている男も凝視した。そして、あすかの口が止まると、いよいよ銀平の大爆発かと客たちは固唾を飲んで見守った。
だが、太郎と平が止めに入る寸前、銀平は思いがけない言葉を口にした。
「久しぶりだな……赤井兄弟。お前は弟の次郎で、そっちは兄貴の一郎だろ。俺だよ俺、素潜り兄弟の銀平だよ」
照れ臭げに赤面する銀平の顔は、さらにほころんだ。途端に、男が銀平の顔を両の手のひらで挟んだ。
「や、やっぱり! 銀ちゃんかよう! そのロゴマーク、気になったんだよ。懐かしいなあ。おい兄やん、小学校の頃、東京から夏休みに遊びに来てた火野の銀ちゃんだ」
声を弾ませる次郎に、一郎は豹変して「ええ! マジかよ!」と声を張り上げたが、太郎や平、あすかも含め、誰もがハトが豆鉄砲をくらったように唖然としていた。
店内の雰囲気を察した銀平は、咳払いをして言った。
「すまねえ。こいつら、俺の幼なじみでよ。あの首の赤い痣で、ピンときた。俺は中学の頃、夏休みは親戚の漁師がいた勝浦にひと月ばかり世話になって、毎日、素潜りで魚やサザエを獲ってた。この赤井兄弟は、近所の漁師の息子でよ。潜り方や獲り方を教えてもらったんでぇ」
25年ぶりの偶然の再会に、テーブル席の客たちはどよめいた。
「なるほど、道理で二人ともいい体をしてるわけですねぇ」
平はやれやれといった表情で、カウンター席へ腰を戻した。
「ということは、漁業権を持ってるわけぇ? もう、それを早く言ってよね。どう聞いても、さっきは密漁の自慢話みたいだったわよ」
恥をかいたあすかは所在なさげに赤井兄弟の脇へ座り、詫びを入れた。
「けっ! そりゃ、おめえの早とちりじゃねえかよ。そんなので、よくジャーナリストてぇ名乗れたもんだな」
今しがたの張り詰めたムードはどこへやら、いつもの銀平とあすかのすったもんだが始まると、太郎も包丁と俎板の音を軽快に走らせた。
すると、赤井次郎が口を開いた。
「ポンバル太郎へやって来たのは、都内のデパート催事で勝浦の魚介類を販売していた時、ジョージって名乗る外国人からサザエに合う日本酒を教えろって訊かれたからだ。その酒は千葉県の超辛口な純米酒で、特に熱燗はサザエの肝の苦みにバッチリ。でも、都内で置いている料理店は少ないだろうって念押しした。ところがジョージは、余裕しゃくしゃくで『ポンバル太郎に、あります!』」と答えたのさ」
興奮気味な次郎に、口数の少ない一郎が身を乗り出すようにして続けた。
「それに、まさか、この店で銀ちゃんと逢えるなんて……憶えてるかい? 子どもの頃、獲ったサザエを浜で焼きながら、指切りした約束を」
「な、なんでぇ、そいつぁ?」
動揺している銀平に、平がぬる燗の盃を飲み干して
「災い転じて、福となす……いい話になってきましたねぇ」
とつぶやいた。
ふっと一郎が表情を和ませると、あすかは耳をそばだてた。
「大人になったら、勝浦のサザエで美味しい酒を三人一緒に飲もうぜって約束だよ。あの時は、麦茶で乾杯だった。だから今日、その約束を果たそう」
一郎の声とともに、店内の客たちは誰もが嬉しげに頷いた。もう厨房からは、香ばしいサザエの匂いが漂っている。太郎の気遣いに、赤井兄弟だけでなく、銀平も胸が熱くなった。
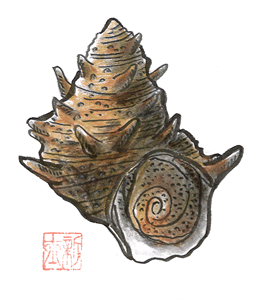
日本酒度+12の辛い純米酒の熱燗は、すこぶるうまいサザエのつぼ焼きにふさわしかった。三人の満足げな声に、店内から注文が殺到した。
次郎から熱燗を注がれたあすかは、ほろ酔い顔で銀平へ八つ当たりした。
「まったく、勘違いして恥かいちゃったじゃない。あっ、それとねぇ。さっき、私のこと妹分とか言ってたけど、そんなの認めてないからね。銀平さんと私は、赤の他人ですからねぇ」
アカンベをするあすかにやり返そうとする銀平を、次郎が酌をして止めた。
「お二人さん、まあ、そう言わず、この赤井兄弟に免じて、仲良く頼むよ! 赤の他人じゃなくて、赤の兄妹ってことで」
「けっ! やい次郎、ダジャレにもなってねえじゃねえか」
それでも、盃を飲み干す銀平の顔は緩みっぱなしだった。
平がサザエの殻を見つめながら、ほほ笑んだ。
「銀平さんの本心は、兄妹以上を望んでいますよねぇ」
