卯の花くたしが5日間降り続き、神宮の森には緑がしたたっていた。
梢の陰では、シジュウカラやヤマガラの巣が騒がしい。もうすぐヒナの巣立つ季節である。ときおりツバメの飛ぶ表参道には、カラフルなレインブーツの女性たちが目立った。
ポンバル太郎にも、それと似たスタイルの高野あすかが登場し、カウンター席で美脚を組んだ。ワインレッドの長靴が、テーブル席の外国人客を魅了した。
「ヘイ! フィリップ。あのレディに、アプローチはNGだよ。あすかさんは、この店のヒロインだからね」
声の主は、ジョージ。彼とテーブルで宮城県のスパークリング純米酒を飲んでいるのは、アメリカから和食修行にやって来たばかりのフィリップである。GIカットのように剃り上げたフィリップの頭は、形良くて清々しい。厨房の太郎も、閉店後に包丁の研ぎ方を教える約束で、彼との会話を楽しみにしている。
「こんばんは、ジョージ。そのスパークリング純米酒に、どんな料理を合わせているの?」
あすかがテーブル席へ笑みを浮かべると、フィリップの鼻の下が伸びた。
「これ、メカジキです! メカジキは、彼のいるマイアミではありきたりなソウルフード。濃厚なバターソース味に料理して、シャンパンと合わせるそうです。だから、このスパークリング純米酒にもいけるはずです」
ジョージの皿では、薄黄色のメカジキの身がバターソースとからんでいる。確かに、活性した純米酒の口当たりは、バター風味をサッパリと流すこともできるとあすかは思った。
だが、今夜のオススメに、その献立は書かれていない。あすかがメニューへ瞳を凝らした時、太郎が厨房から現れた。
「そのメカジキは、フィリップさんが持ち込んだ冷凍物だ。だから、うちのメニューにはないよ。バターソティにしてみたけど、ちょいと油っこい気がするんだ。メカジキ自体、けっこう脂が多いからな」
太郎の声にあすかが「な~るほど!」と頷くと、ジョージにそれを訳されたフィリップが眉をしかめた。
「オウ! このSwordfish(ソードフィッシュ ・剣魚)のバターソティは、白ワインにピッタリです。だから、日本酒にも合うはずです」
もどかしげに身振り手振りでフィリップが伝えた時、玄関の鳴子が大きく響いた。
トロ箱を担いだ雨合羽姿の火野銀平が、肩で息をしていた。したたる雨粒が、黒い長靴を濡らしている。
「まったくよう。今すぐ極上のマカジキ持って来いなんて、太郎さん、無茶言ってくれるぜぇ。この時期は“桜カジキ”つってよう、値が張るんでぇ。葵屋の伝兵衛さんに、また義理ができちまったよ」
銀平は、小一時間前にいきなり太郎から入った電話の頼みを愚痴った。品薄で高価なマカジキの切り身を、築地の親方である葵屋の伝兵衛に頼んで回してもらったと言う。
「すまねえな、銀平。だけど、メカジキよりも日本酒に合うマカジキを、フィリップさんに食わしたくってな」
光る柳葉包丁を手にする太郎がフィリップに目を向けると、ジョージが日本の食べ方を自慢げに披露した。
「マカジキはBillFish(ビルフィッシュ・嘴魚)と言って、特に大きいカジキですね。日本では、赤身のお刺身が一番でしょ!」
むろん、それを口にできるんだろうと舌なめずりするジョージに、フィリップが気おされている間、あすかは銀平へ事のしだいを耳打ちした。
「はは~ん、今食ってるのはメカジキか。そりゃアメリカじゃ、巻き網や延縄で一網打尽に獲っちまうから、ストレスや脂がメカジキの体に回っちまうんだよ。ところがどっこい、日本のマカジキ漁は“突きん棒漁”だ。こいつは、職人芸の筆頭でよ。ヤンキーから見りゃ効率が悪くて滑稽かもしれねえが、活けジメって獲り方だ。日本の漁師の魂。つまり、ソウルが生んだ伝統漁法だ」
またもジョージの通訳に耳を傾けるフィリップが、興奮の色を浮かべた。そして銀平に歩み寄ると、早く見せろとばかりトロ箱を指さした。
「へいへい、分かりやした。これは昨日、土佐沖で突いた180kgのマカジキの赤身だ。値段は1キロ8千円てえ、すこぶるつきの上物だよ」
太郎も目を丸くするトロ箱の中の切り身は、淡紅色で赤みが強かった。銀平は、マカジキは料亭や高級寿司屋などが多く使い、脂分は少ないが、旨みが強いとジョージに教えて訳させた。
「プリーズ……突きん棒漁、教えてください」
たどたどしいフィリップの言葉に、漁のやり方までは知らないと銀平が苦笑した時、またもや玄関の鳴子が揺れた。
「それは、僕にお任せを! なんせ、土佐っぽぜよ」
と飛び込んで来た右近龍二が胸を叩いた。そして、土佐のマカジキなら、土佐の酒だと冷蔵ケースから一升瓶を取り出し、フィリップの隣へ座った。初対面ながら屈託ない龍二の人柄をフィリップは気に入ったらしく、「教えて、教えて」と急かした。
龍二はダブレット端末をバッグから取り出すと、「突きん棒漁」を検索して、画像を並べた。荒海の中、船のへさきに作られた突き台に立つ老練な漁師。彼が持つモリは、5メートルを超え、それを泳ぐマカジキめがけて投げつける写真にフィリップだけでなく、ジョージも息を呑んでいた。
「突きん棒漁は、3日やったらやめられないと、土佐の漁師は言うそうです。でも、今は後継者が減って、ずいぶんとマカジキも獲れなくなった。海水温の影響もあって、マカジキが土佐湾へ寄って来ない年もあるんですよ……そうそう、銀平さん、知ってます? カジキは漢字で「梶木」、「加敷」。それは、船底の両側に取り付ける棚板なんです。カジキは槍のように尖った長い上顎で棚板を突き破るから、そう呼ばれるようになったんですよ」
嬉々として話す龍二の前へ、さばいたマカジキの皿を太郎が置いた。
「土佐の本醸造をやりながらしゃべった方が、舌もなめらかになるんじゃねえか。何たって、龍ちゃんのソウルフードだろ」
龍二は親指を立てると、土佐の献杯や返杯の話もからめながら、フィリップを日本の酒食文化へ惹き込んでいった。ますます磨きのかかっている龍二の博識にあすかは感心したが、銀平はおもしろくなさげに、ふてくされていた。
龍二の話がひと区切りすると、突然、フィリップが銀平の隣へ席を移した。そして、ジョージへ通訳を頼みながら、銀平の足元を指さした。
「フィリップは、こう言ってます。今夜のことは、すべて銀平さんの持って来たマカジキのおかげです。それにしても、その黒いレインブーツには、銀平さんのソウルが入ってそうですね」
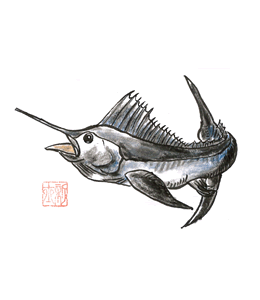
「まあな、こいつで築地を走り回ってるからよう。あすかの長靴と比べりゃ、くたびれてこきたねえけど、俺に取っちゃ魂の一つかもしれねえな」
気を良くする銀平に、あすかが水を差した。
「まっ、そこは百歩譲っても、銀平さんがマカジキみたいな一級品だとは、認めないからね」
マカジキの分厚い刺身を口にしつつ、あすかがほくそ笑んだ。
「ぐっ、くっそう! カジキのくちばしみてえに高いその鼻、いつかへし折ってやっからな!」
茹でタコのごとく真っ赤になる銀平を、龍二がキンキンに冷えた生貯蔵酒を注ぎながら諫めた。
「あんまり怒ると、ストレスと脂が体に回っちゃいますよぉ」
マカジキの刺身を土佐の本醸造でうまそうに食べるフィリップが、ジョージの通訳を耳にして爆笑した。
