長良川の清流に、新緑と鮎の姿がまばゆい。岐阜の水辺は、もう初夏の光景を映している。
川沿いを走る路線バスからそれに魅入っている太郎と剣は、遅い連休を使っての家族旅行…とは少しちがって、車窓を眺めているのは、高野あすかと中之島哲男の四人連れである。
昨日岐阜入りした一行は、美濃加茂、飛騨高山、大垣と三つの蔵元をめぐった。
新酒が貯蔵されてようやく半年、そのできばえを確かめに行かないかと誘ったのは、中之島だった。
全国新酒鑑評会の決審発表を数日後に控え、蔵元は気もそぞろ。杜氏や蔵人は落ち着かないようすだった。
「岐阜県の蔵元は、最近、よう頑張っとるからな。三社とも、金賞を獲って欲しいなぁ。これまで岐阜の地酒は、県外への進出が遅れとった。それを取り返すレベルの高い吟醸酒も出てきよった」
バスの騒音に負けない中之島の地声が、車内に響いた。口元がほんのりと赤いのは、手にする飛騨のカップ酒のせいである。
揺れてこぼれそうな酒に冷や冷やしているあすかが、声音を高くした。
「高山もそうだけど、観光地が多いから、昔はお土産需要が中心だったんですよね。それに、ほうば味噌や八丁味噌とか、山国の味噌に合う濃厚でゴツい味の晩酌酒が多いでしょ。かつてタンパク源は鰻、鯰、鯉、山鳥、鹿や猪とクセのある食材だから、その匂いを味噌で隠したんです。吟醸造りはここ数年、酒造好適米の“ひだほまれ”で力を入れ出した感じですよね」
あすかたちの後ろに座る剣が、背もたれの間から口を挟んだ。
「蔵元の息子さんが家業を継ぐ“蔵元杜氏”も、少しずつ増えてるんだってさ」
下調べしたのか、ノートをめくっている剣に中之島が
「ほう! 剣ちゃん、よう調べたな。お父ちゃんも顔負けやで」
と感心すると、太郎が苦笑いして長良川の流れに目を向けた。
蛇行していた水面が一気に広くなり、小船の上で長い手綱を操っている人影が見えた。
「おおっ、鵜匠や! もう、そんな季節かいな」
中之島の声に剣が背伸びすると、後列の客たちもそれに続いたが、太郎たちと通路を挟んだ右側に座る若い女は無関心なようすで、眠っているのか目を閉じていた。しかし、髪を束ねた美貌の中で、薄い唇だけが歪んでいる。二人掛けのシートには、大きなボストンバックが置いてあった。
女の表情を見つめる太郎の気を削ごうと、あすかは問いかけた。
「太郎さん。鮎料理って、塩焼きや背ごしにしても、岐阜のゴツい酒に合わない気がしませんか?」
「あ? ああ……そうだな」
ふいに訊かれて生返事する太郎に、女の目が開いた。長良川のように青く澄んだ瞳に、太郎だけでなく中之島も吸い寄せられていた。
「長良川の鮎は、滋味が濃いんです。奥美濃の山紫水明、神々しい深山幽谷から下る水のおかげ。それは人間よりも、私の使っていた鵜たちが一番知っているわ」
どことなく挑戦的な口調を、女はあすかへ向けていた。
女の横顔とノートに挟んだガイドブックを見比べる剣が、声をうわずらせた。
「あっ! この人、長良川の鵜匠・加茂めぐみさんだ! ほら、ここに載ってるよ」
指さす剣の写真は、篝火の傍で藍色の鵜飼い装束をまとった女が鵜に鮎を吐きださせる瞬間を切り取っていた。剣の声に、バスの運転手がバックミラーでめぐみの顔をチラ見していた。
「ほう! こりゃ、勇ましい。失礼やけど、そんな男勝りには見えへんけどな」
目を丸くする中之島に太郎も頷いたが、あすかだけは記者の目つきになって、めぐみの素性を剣のガイドブックの記事から探っている。
だが、めぐみは長良川の流れに視線を落とし、短いため息を吐いた。
「その本、5年前の記事のままですから……私は、もう鵜匠じゃない。この夏からは、料理店のスタッフです」
意味深な答えに、バスの運転手がブレーキを踏んだ。ノッキングの揺れに剣の手からガイドブックがすべり、めぐみの足元へ落ちた。開かれたままの紙面を、めぐみはしばらく見つめると、ゆっくり拾い上げた。
「この鵜は、ナギー。羽化したヒナの頃から、私が世話をした子。長良川で生まれ育ったから、その名前を付けたんです。でも……去年の鵜飼いで死んでしまった。私のミスで、7羽が手綱にからまった。野生から戻した鵜じゃないナギーは気が弱くて、仲間に押され溺れてしまったんです」
めぐみは、手縄は鵜匠と鵜を結び付けるもので、手縄本体とツモソ・腹がけ・首結(くびゆ)に分かれている。その中でも、首結いの締め具合で漁の多少が決まる。そのかげんを誤った自分が鵜たちの動きをさばけず、ナギーは死んでしまったと述懐した。
それからは手綱を持つのが怖くなり、鵜どころか、鮎を見るのも辛い日々だったと吐露し、ガイドブックを剣に返した。
「5年目か……まあ、慣れた頃が何でも一番怖い。ミスに陥りやすい時期や」
飲み干したカップ酒をホルダーに戻した中之島が、腕組みをしてつぶやいた。
それに否定も頷きもしないめぐみが、口早に答えた。
「だから、これからは鮎料理のお店で、サーバーとして働くことにしたんです。長良川の鮎に合う、岐阜の地酒をオススメするお店です」
渋滞につかまったバスのエンジンは静まり、車内の誰もが耳も澄ませていた。めぐみに見覚えがある地元の乗客たちは、今しがたまであからさまな岐阜弁を交わしていたが、赤裸々な告白に口をつぐんでいる。
気まずい雰囲気になるとダンマリを決め込むのは、どこの地方も同じかと太郎は座席の年配者たちを見回した。途端に、ギョッとするようなあすかの声が耳を突いた。
「それで、荷物をまとめて逃げ出したわけ。溺れたナギーは、天国でも浮かばれないわね。長良川の鮎を一番知っているのが鵜なら、それを育てる鵜匠は、もっと知ってなきゃダメなんじゃない。あなたは滋味って言うけど、料理の味付けしだいで、岐阜の銘酒をいろいろセレクトできなきゃダメ。淡白なせごしに対して、甘露煮は濃厚でしょ? 前者は吟醸酒が合うけど、後者には鬼ころしのような骨太い本醸造でなきゃ難しい。その見極めや感覚を自慢するわけじゃないけど、私だって5年近く酒と食のジャーナリストを続けて、やっと身に付けたわけ。もちろん今だって、まだ半人前。だからさ、鵜匠を諦めるのは早いわよ、めぐみさん」
竹を割ったようなあすかの口ぶりが徐々に穏やかになると、中之島と太郎は目顔で笑った。剣はガイドブックを開いて、何やら手を動かし始めた。
あすかの直言に、めぐみは目尻に滲む涙を拭おうともせず、唇を噛み締めていた。
すると、バスの後部座席から岐阜訛りが飛んで来た。
「ちゃっと、鵜匠に戻って来てや!」「もう一回、頑張りな!」
思いがけない激励を盛り上げる拍手まで沸き起こると、太郎たちは驚き顔を見合わせた。
今度は、ドライバー席から大きな声が発せられた。
「お客さん。岐阜人って、本音は熱いんですよぅ!」
バックミラーの中に、運転手の笑顔がほころんでいた。
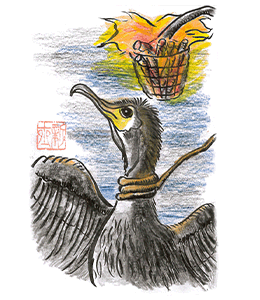
ハンカチを差し出したあすかの右手に、意地を張っていためぐみがすがった。
「ありがとう……ございます。私にもう一度、できるでしょうか」
深く頷くあすかの後ろから、ニュッと剣の右手が伸びた。その指が、ガイドブックからハサミで切り抜いたナギーの写真を握っていた。
「めぐみお姉ちゃん。ナギーは、ずっと一緒だよ」
涙を拭いためぐみの笑顔に、初夏の陽射しが車窓から注いだ。
「よっしゃ! ほんなら、カップ酒で乾杯や!」
もう一つのカップ酒へ手を伸ばす中之島に、あすかが釘を刺した。
「ちょっと、オヤジ! 朝っぱらから、調子に乗ってんじゃないの!」
運転手の鳴らすクラクションが、心地よさげに長良川へ響きわたっていた。
