暖かな黄昏に染まる新橋駅日比谷口は、ワイシャツ姿のビジネスマンが目立つ。
6時を過ぎても、サインボードの気温は26度。SL前には、オープンしたばかりのビアガーデンへ向かうグループが待ち合わせている。
ポンバル太郎でも、エアコンの冷風にひとごこちをついた客たちは「冷酒!」と注文した。生ビールよりも冷酒を頼むのは、本日の先付が“のぼりガツオの冷やしズケ”だからである。
「へへっ! どうでぇ、俺の読みが当たっただろ?」
ほろ酔いで自慢する火野銀平の右肩が、隣で冷やしヅケをつまむ右近龍二の左肩を突いた。
「土佐でもカツオの群れが来て、数年ぶりに活況しているそうですよ。この時期、脂のノリは少ないけど、身がしまった若いカツオはゴリって呼ばれて、地元じゃ辛口本醸造の冷やでやるんです」
その酒のグラスを、龍二だけでなく、カウンター席の平 仁兵衛も傾けている。
「江戸時代は、立ち食い寿司のズケやネギマ鍋に使っていたそうですねぇ。刺身だと硬い身ですが、縁起をかつぐ江戸っ子は初ガツオを食べなきゃ気が納まらなかったようです。どうやら、現代も同じようですねぇ」
平が目じりをほころばせる店奥では、「まずは、カツオの塩たたきだろ」とか「カツオの柚子胡椒ステーキもいいな」とグループ客がさわいでいる。
「おお! いいね、いいね! なあ太郎さん、俺がみつくろった通り、もう5kgほど仕入れた方がよかったんじゃねえの?」
「ちげえねえ。このまま注文が増えりゃ、9時頃には品切れしちまうかもな」
赤ら顔で溜飲を下げる銀平に、しくじったとばかり太郎が舌打ちした時、着流し姿に雪駄履きの二人の老爺が店へ入って来た。
「予約はしてねぇが、二人、いいかね」
太った男が太郎へ訊くと、痩せた方は酒の枡を使った扉の鳴子に感心していた。
「カウンターの隅でよろしければ、どうぞ」
太郎の返事に、初顔の70歳代とおぼしき二人はカウンター席へ白髪を並べた。お互いの体形は対照的だが、下町のご隠居らしい落ち着いた格好である。
「あの人たち、絶対、縁起かつぎにカツオを食わなきゃって年代ですね」
ほくそ笑む龍二に平が相槌を打つと、銀平は嬉しげに老爺へ声をかけた。
「今夜は、初ガツオがオススメですぜ! 新鮮な上物でやすから、栄養もつきまさぁ!」
聞こえよがしな魚河岸の口っぷりは、調子に乗り始めた銀平のサインである。
二人の老爺は素っ気ない顔を見合わせたが、銀平が着た火野屋Tシャツへ気づくとヤブにらみを返した。その表情に銀平が戸惑っていると、厨房から太郎の声が飛んだ。
「銀平、出過ぎたまねをするんじゃねえ。お客様、申し訳ございません。どうぞお好きな物を選んでください」
銀平が「す、すいやせん」と詫びると、痩せた方の男は「いいってことよ。気にしなさんな」と渋い声を返した。腰の据わった江戸っ子らしさが、銀平の気を引いた。
「ネギマ鍋かぁ……三郎の奴ぁ、ネギマも好物だったから、これにしておくか」
メニューボードを見上げながら太い男がつぶやくと、痩せた男も
「しかたあるめえ。ドジョウなんざ、専門の店じゃねえと置いてねえさ」
と灰色になっている顎鬚をさすった。どちらも、いぶし銀のような表情を曇らせている。
銀平の耳に、ドジョウの言葉がひっかかった。
「あのう……ドジョウって、柳川鍋のことですかい? それなら、ウナギの柳川ができます。味は保証しますぜ。うちが納めた、江戸前の鰻でさぁ」
またぞろ銀平がでしゃばり、火野屋Tシャツのロゴマークを引っ張った。しびれを切らせた太郎が厨房から顔を突き出した時、おしぼりで手を拭く太い男が口を開いた。
「おめえさん、火野屋の銀次郎さんの孫だろ? よく似てきたな」
「まったくだ。その剃った頭のハチ回りは、お祖父さん譲りだぜ」
青々としている銀平の頭に、痩せた男も懐かしげに言った。
「へ?……うちの祖父さんをご存じなんで? そ、そりゃ、ご無礼しやした」
酔い覚めしたかのように銀平が目をしばたたくと、太郎も龍二や平と顔を見合わせた。驚く銀平たちに、太い男が名乗った。
「俺は、深川で魚屋をやってる山下 勇、こっちは俺が魚を納めてる寿司屋の金子 源治てぇんだ。どっちも今は店を息子に任せる身だがよ、昔、銀次郎さんに教えを乞うた者同士だよ」
じみじみと告げる山下に、金子が頷きながら続けた。
「銀平さん、憶えてないかね。子どもの頃、深川のどぜう鍋を銀次郎さんといっしょに食べたこと。山下と俺も、その場にいた。あんたはドジョウの水槽にかぶりついて、目ん玉をクルクル動かしてたな」
先付の冷やしヅケを差し出す太郎へ、金子がほころんだ目元を移した。
ドギマギとする銀平が、はっとして叫んだ。
「あっ! 思い出した! 柳橋に近い“どぜう三郎”だ。祖父さんが贔屓にして、確か、店主は芝 三郎さんでした」
「ああ、その通りだよ……おい、源治。こりゃ偶然にしちゃ、できすぎだぜ」
「まったくだ。三郎が、ここへ俺たちを呼んだのかねぇ」
茫然としている銀平に、山下が問わず語った。
「その芝 三郎てえのも、銀次郎さんの弟子だった。残念だが3月に亡くなっちまって、昨日が49日だ。その喪明けにここへフラリと立ち寄ったら、おめえさんにバッタリてぇわけだ。もう三郎のどぜう鍋は食えなくなっちまったのに、皮肉なもんだな」
山下は短いため息の後、目の前の冷やしヅケを箸で口に運ぶと「うむ、いいカツオだ」と銀平にほほ笑んだ。
にぎやかな奥のテーブル席をよそにして、カウンター席の面々は静まっていた。
龍二が小声で、平へ耳打ちした。
「ど、ドジョウって、銀平さん、ここに納めてましたっけ?」
「いやいや、さすがにドジョウは、私もポンバル太郎でお目にかかったことはありませんねぇ」
平も声をくぐもらせたが、歳のわりに地獄耳らしい金子が答えた。
「銀次郎さんは『ウナギ一匹は、ドジョウ一匹』が口癖でよ。ドジョウはウナギよりも小せえが、負けねえくれえ栄養があると言ってた。銀次郎さんがいた頃、火野屋はすこぶるつきな天然のドジョウを扱ってたよ。そのほとんどを、三郎は仕入れた……銀次郎さんが亡くなってからは、養殖ドジョウで辛抱しなきゃならねえとボヤイいてたよ」
「憶えてやす。祖父さんが扱うドジョウは、多摩の農家が田んぼで獲ってた天然物でした。店先の杉桶に井戸水を張って、3日ほど泥を吐かせてから出荷してた。でも、平成になってからはドジョウを食べる江戸っ子も、どぜう鍋を食わせる店も減っちまったと愚痴ってたなぁ。面目ねえけど、俺の代になってドジョウは扱わなくなっちまったし……それでも三郎さんが店を続けてたってえのは、スゲエじゃねえですか」
銀平は自分の盃を飲み干すと山下に手渡し、お銚子を傾けた。祖父の縁の感謝と三郎を偲ぶ山下たちを斟酌する気持ちに、龍二や平も相槌を打った。
それを見つめていた太郎は、無言で厨房へ戻った。
飲み干した盃を山下から回された金子が、おもむろに口を開いた。
「“どぜう三郎”が続いた理由は、銀次郎さんの知恵があったからだよ……江戸の地酒が大好きだった銀次郎さんらしい発想だった」
金子の目が、冷蔵ケースの多摩の地酒を見つめた。腰の強い、旨みとコクのある本醸造で、ぬる燗派の平が好む銘柄だった。
「日本酒……をうちの祖父さんが、どぜう鍋に生かしたってんですかい? いったい、どんな方法だったんで?」
興奮して前のめりになる銀平に山下と金子が目尻をほころばせた時、太郎が
「そいつぁ、俺が教えてやるってよ」
とスマートフォンを銀平に差し出した。通話中の相手は、築地市場で親方と慕われている葵 伝兵衛だった。伝兵衛は、天然ドジョウの泥臭さを抜くには井戸水だけじゃなく、仕上げに日本酒で泳がせるのがコツ。酔ってのたうつ間に、しみこんだ酒が匂いを取り、なおかつ旨みが増して、身も柔らかくなる。それは江戸時代からドジョウを売っていた火野屋の先祖が祖父の銀次郎へ口伝てした方法で、銀平には教えてないはず。今から、葵屋の水槽にいる天然ドジョウをポンバル太郎へ届けるから、そこにいる俺の仲間にふるまってやれ。酒で泥臭さを抜くのは太郎さんに任せたと、気風のいい声を弾ませた。
スマホのやりとりを耳にする山下が「なんだぁ! 葵屋の伝兵衛も、この店の常連だったか。こりゃ、まいったぜぇ」
と満面に笑みをたたえた。
太郎は、厨房から伝兵衛へ電話してドジョウを手配していた。銀平に祖父が紡いできた老練な男たちとの縁を引き継がせ、再び、天然ドジョウを火野屋で扱わせたいと思った。そして太郎自身も、江戸伝統のどぜう鍋を店のメニューに加えたくなった。
その温かな思いを、龍二や平も察していた。
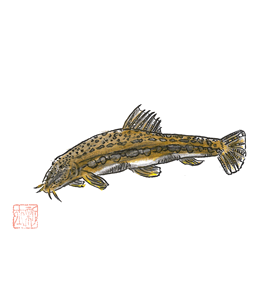
金子が空けた盃を銀平に戻しながら、多摩の酒の一升瓶を冷蔵ケースから取り出した。
「丸鍋と呼ばれる江戸前の“どぜう鍋”は、とき卵でとじる柳川鍋とちがって、生きたドジョウを酒に入れてすぐ蓋をするんだ。そこへ甘辛いワリシタを注いで、炭火で煮込む。ネギを大量にのっけたら、山椒をかけて食べる。それをもっと旨くするために、下ごしらえから酒で工夫するのが三郎流。銀次郎さん直伝のアイデアだった……孫のおめえさんも、やってみな」
気づくと銀平の前に、丼用の手鍋が置かれていた。あれなら丸鍋の代用になると、龍二が太郎へ助言していた。
「銀平さん、初ガツオならぬ、初ドジョウですね。こりゃ春から、縁起がいいや!」
龍二に背中を押された銀平は山下と金子に深くお辞儀して、腕をまくった。
ほほ笑む太郎の指先が、メニューの隅に“江戸前 どぜう鍋”と書き加えた。
