千鳥ヶ淵の堀端を、紫や薄紅色の紫陽花が染めている。梅雨入りは宣言されていないものの、ここ数日は悪天候で、帰宅するビジネスマンたちはゲリラ豪雨にうんざり顔である。
ポンバル太郎には、傘が役に立たないくらい濡れそぼった客たちも駆け込んだ。
「こりゃ、お湿りなんてぇ悠長な雨足じゃねえぜ。梅雨も待たずに、台風並みの雨じゃねえかよ」
雨粒を青剃りの頭からしたたらせる火野銀平が、火野屋のロゴ入りタオルでしかめっ面を拭いた。
カウンターの隣に座っている平 仁兵衛が、窓ガラスを叩く横殴りの雨につぶやいた。
「小糠雨なんて情緒のある言葉、もう使えなくなってきましたねぇ」
平がぬる燗の純米酒で飲みくだした嘆きに、カウンターの隅で渋い低音の声が相槌を打った。
「まったくだ。私は“篠つく雨”ってのが、日本の梅雨と思ってたのに。これじゃ詐欺だよ。カリフォルニアのスコールよりも、ひどいな」
シルバーグレイの頭をキッチリと七三分けにした40歳頃の男が、冷酒グラスを口にしていた。初めて来日したかのような口調のその男はハーフのような高い鼻梁の下で、灰色の髭の端が少し吊り上がっている。
そして「カリフォルニア」や「スコール」はネイティブな発音で、常連のジョージが口にする流暢な英語と変わらなかった。
「まあ、いい……この店には、私の憧れてる本来の日本酒と肴が揃ってたからね。この季節は、やはり生貯蔵のような爽酒(そうしゅ)が一番だ。合わせる料理をここのシェフに任せたら、まさにピッタリの肴が出されて、驚いたね。私の経営するロスの寿司BARには、このセンスを分かる奴が足りない」
頬杖を突く男は日本人離れした彫りの深い表情を崩すと、太郎の作った明石ダコの湯引きを口にした。
梅雨前に獲れる播磨灘の真ダコは最高の味だと、中之島哲男が明石漁協から太郎へ直送してくれた活けダコだった。魚匠の銀平も舌を巻くほどの上物で、半生で透明な薄い切り身に梅肉と刻んだ大葉が添えてあり、太郎はキレのいい辛口の生貯蔵酒と合わせている。
「もしかして、ロサンゼルスの寿司職人の方ですかい?」
訊ねた銀平の目は、箸を持つ男の右手の人さし指を見つめていた。柔らかそうな血色のいい手だが、指の腹には包丁コブができている。
「ほう! よく分かりましたねえ。ビバリーヒルズで竹寿司を経営してる、エディ・K・武田と言います」
男が嬉しげに銀平へ名刺を差し出すと、即座にテーブル席の客たちから
「あっ、知ってるよ! ロサンゼルスで人気の寿司BARだ」
「確か、日系三世のオーナーだろ」
と漏れ聞こえた。それを耳にした銀平が、相手に取って不足はないとばかりに切り返した。
「俺は築地の魚屋なんでね。江戸前の寿司屋が、もっぱらの得意先でさぁ。だから、腕利きの寿司職人の手をいつも見てる。酢飯を握るから柔らかくて血色がいいけど、包丁ダコは消えねえ」
自慢げな銀平に武田が得心して、「一献、どうだね」と生貯蔵酒のデキャンタを差し出した。遠慮なくグラスを差し出す銀平に酒を注いだ武田は、平にもデキャンタを向けた。
だが平は盃を持たず、武田を微に入り細に穿つように見つめていた。
「もしかして、武田さんは能登の輪島ご出身でしょうか? 家は入り江の傍にあって、御父上はウニ獲りの漁師じゃないですか?」
唐突な平の問いに、武田の柔和な表情が一気に蒼ざめた。
「ば、バカな……私はサンフランシスコに生まれて、ロスで育ったんだ。あ、あなた、誰かと勘違いしてるよ」
動揺する武田は、明らかに視線が泳いでいた。
銀平が不審げな表情を浮かべた時、玄関の鳴子がカラコロと音を立てた。
「わしも、平さんと同じ質問をするでぇ。その漁師っちゅうのは、ウニ獲り名人と呼ばれた武田勘吉やろ? あんたは、その次男の武田和男。日系三世やなんて、嘘ついたらあかんわ。わしを忘れたとは、言わせへんで」
中之島哲男のしゃがれた声に、武田が玄関を藪睨みした。そして束の間、中之島を凝視すると「あっ! もしかして、中之島の哲男さん」と口走った。自ら墓穴を掘る発言だった。
客たちが、武田へ冷たい視線を送った。
顔色を失くした武田がうつむくと、隣に座る中之島は興奮気味に声を高くした。
「25年ぶりやなぁ……勘吉はんの元へ、ようやく戻って来たか。先月、勘吉はんが亡くなった時、偶然にお互いの知り合いやったこの平先生も、一緒に能登の葬式へ参ったんや。それにしても、能登湾で素潜りして勘吉のウニ漁を手伝うてた少年が、こないに大きゅうなったか。おまはんが15歳で家を出た時、勘吉はんは『一介のウニ漁師を捨てて、一旗揚げると出て行きよった』と吐き捨てたが、アメリカで成功してるとはなぁ……竹寿司は、ウニの軍艦巻きで売れた店やろ。わしかて、噂は耳にしとる。そのウニはカリフォルニア産やが、なかなかの上物で、竹寿司のオーナーの目利きが素晴らしいと聞いた……蛙の子は蛙やな」
料理人の中之島は武田和男の父・勘吉の獲る能登湾のウニがお気に入りで、無二の親友だった。そして平の能登の実家は代々、勘吉の家からウニを買っていて、和男の面影に気づいていた。
中之島の暴露に、和男の日系三世の詐称はもはや疑いなかった。
声を顰めていた客席から、非難が飛んだ。
「ふんっ! 詐欺はお前じゃねえかよ」
「竹寿司の人気も、ウソなんじゃない?」
ますます所在を失くす武田に銀平はいかんともしがたい顔だが、中之島は客席の声を物ともせずに言った。
「まあ、西海岸のロサンゼルスやサンフランシスコにいてるわしの弟子たちも、最初は日系人社会に入り込まんと、飲食事業は成功しにくいと言うてた。そのための詐称だったんやろ。ほんなら、今から撤回して、謝罪したらええ。また、やり直したらええんや。それより、ユダヤ人社会で人気を得んことには、和食は成功せえへんと聞いたが、和男君、おまはんは、そこを上手くつかんだらしいな」
助け舟を出す中之島と武田の前に、ふいに太郎がブリの照り焼きを置いた。
ただ、タレの香りがちがっていることや、ブリの身に赤や緑のこま切れがふりかかっていることに中之島は眉根を寄せた。
「な、なんじゃい? これは、バジルにローズマリー?」
小鉢の匂いに鼻先をひくつかせた中之島は、さらに照り焼きのタレをなめて
「太郎ちゃん! チキンスープで仕込んでるやないか?」
と目を丸くした。隣へ座る武田の表情が、にわかに明るくなった。
「さすが、師匠。正解ですよ。ジョージから聞いた受け売りなんですけど、このスタイルが、ロサンゼルスの和食レストランではスタンダードなんだそうです。ねぇ、武田さん。そうなんでしょ?」
太郎の問いに深く頷いた武田が、重たげな口を開いた。
「ユダヤ人は元々、海産物の料理を口にしなかったし、昆布や鰹節といったダシは生臭くて性に合わないんです。だから、私もアレンジしなきゃいけないと、渡米した20年前に気づきました」
武田は、ようやく鰹節や醤油が海外でも受け入れられているが、まだまだ裾野は広がっていない。例えば、カリフォルニアのウニは能登の紫ウニと味がそっくりだが、軍艦巻きにはライムやオレンジを搾って食べるのが好評である。日本じゃ考えられないスタイルだ。日本酒の楽しみ方も同じで、アメリカらしいカクテルスタイルを竹寿司では提案していると語った。
レモンやピーチの生ジュースを使ったSAKEカクテルが、アボガドロールの巻き寿司にピッタリと言う武田に、客席の男たちはゲンナリした。
「なるほど、セレブなビバリーヒルズには独自の日本酒スタイルも必要でしょうねぇ。だけど、本筋がブレてはいけないと思いますよ。あなたのウニを選ぶ眼力も同じでしょう」
諭す平は、能登の海水で洗って食べる武田の父が獲った生ウニは酒肴の正道だったと称えた。
ようやく懐かしい平の顔を思い出したのか、和男はひと呼吸して答えた。
「……図星ですね。実は、少し自信がなくなっていたんです。あまりにも、クールジャパンなテイストを意識しすぎて、奇抜で突飛なレシピを出し過ぎていた。それで、一度日本へ帰って、改めて本来の日本酒と肴を学ぼうと思いました。もちろん、親父にも訊いてみようと……その矢先に、逝ってしまいました」
中之島はブリの照り焼きをひと口つまむと、短いため息を吐いて箸を置いた。
「流行のスタイルちゅうもんは、いずれ廃れる。だけど、王道は消えへんもんや。ビバリーヒルズにあっても、自分の中から能登を消さへんことが、ブレない竹寿司の基本ちゃうか。親父さんの供養にもなると思うで……おまはんの本名もな」
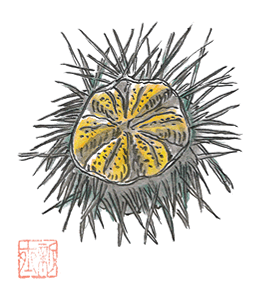
中之島が銀平の前に置かれたエディ・K・武田の名刺をおもむろに破ると、和男がつぶやいた。
「でも、能登のウニはどうにか空輸できても、さすがに海水は手に入りません」
すると、厨房へ戻った太郎が盃を手にして現れ、飲めとばかりに和男へ差し出した。
「し、しょっぱい! ……だが、この味。能登の風味がする」
「この塩水は、奥能登の塩田村で作っている揚げ浜式の天然塩を使ってます。だから、アメリカでも純水に戻せば、きっと能登の海水っぽくなるんじゃないかな」
太郎が手渡す天然塩の袋を、和男は震える手で受け取った。
「勘吉はんも、きっと喜ぶで」
中之島の声に平が目じりをほころばせると、銀平がすっくと立ち上がった。
「おっし! ひとっ走り、知り合いの寿司屋へ走って、能登の紫ウニを手に入れてくらぁ!」
ようやく店内に、和男を励ます拍手が響いた。
